住宅ローン控除の確定申告をe-Taxでするなら?手順や注意点を徹底解説

そこで本記事では、初めて住宅ローン控除の申請をする方や、e-Taxを使って住宅ローン控除の申請をするか迷っている方に向けて、その手順や申請時のポイント、メリットを解説します。さらにe-Taxで申請する時につまずきがちなことなども解説します。
記事の目次
確定申告でおこなう住宅ローン控除の概要は?

住宅を購入する時、多くの方は住宅ローンを組むでしょう。住宅ローンがあると確定申告して住宅ローン控除を受けられます。住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した個人や世帯が、支払う住宅ローン残高に応じて所得税から控除できる税制優遇措置です。
以前は控除率1%、控除期間は10年間でしたが、2022年の改正後に控除率は0.7%、控除期間は13年間になりました。ただし、中古住宅(既存住宅)と増改築は控除期間が10年間です。
控除されるのは所得税ですが、所得税だけで控除しきれなかった場合は住民税からも控除されます。ただし、その年に納める予定の税金以上の金額は控除されません。また、住民税からの控除額は、最大で9.75万円と決まっています。
また、適用される住宅ローン残高には上限が設けられており、住宅の性能によって分けられています。住宅ごとの最大控除額は以下のとおりです。
| 住宅の種類 | 居住 開始年 |
借入 限度額 |
控除率 | 控除 期間 |
最大控除額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間 | 控除期間合計 | ||||||
| 新築住宅・買取再販 | 長期優良住宅・低炭素住宅 | 2022年~2023年 | 5,000万円 | 0.70% | 13年 | 35万円 | 455万円 |
| 2024年~2025年 | 4,500万円 | 31.5万円 | 409.5万円 | ||||
| ZEH水準省エネ住宅 | 2022年~2023年 | 4,500万円 | 31.5万円 | 409.5万円 | |||
| 2024年~2025年 | 3,500万円 | 24.5万円 | 318.5万円 | ||||
| 省エネ基準適合住宅 | 2022年~2023年 | 4,000万円 | 28万円 | 364万円 | |||
| 2024年~2025年 | 3,000万円 | 21万円 | 273万円 | ||||
| その他の住宅 | 2022年~2023年 | 3,000万円 | 21万円 | 273万円 | |||
| 2024年~2025年 | 住宅ローン控除適用なし ※2023年12月31日までに建築確認を受けたもの、または2024年6月30日までに建築されたものは2,000万円を上限として、10年間の控除が受けられる |
14万円 | 140万円 | ||||
| 既存 住宅 |
長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅 | 2022年~2025年 | 3,000万円 | 0.70% | 10年 | 21万円 | 210万円 |
| その他の住宅 | 2,000万円 | 14万円 | 140万円 | ||||
| リフォーム | 2,000万円 | 14万円 | 140万円 | ||||
出典:国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
国税庁 No.1211-3 中古住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)
住宅ローン控除の確定申告をe-Taxでする方法は?

住宅ローン控除を受けるには、確定申告をする必要があります。給与所得の方も、事業所得の方も住宅を取得して一年目は、自分で確定申告をしなければなりません。
住宅ローン控除の確定申告は、税務署の窓口に行く方法や、郵送、e-Taxが利用できます。e-Taxを利用した電子申請をすれば、簡単に住宅ローン控除手続きが完了します。では、どのように手続きをすればよいのか、順番に解説していきます。
e-Taxとは
e-Taxとは2004年に導入された国税電子申請納税システムで、パソコンやスマートフォンを使って納税の手続きができます。
e-Taxを利用する際には、以下が必要になります。
- マイナンバーカード
- マイナンバーカードリーダー、もしくはマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン
- 収入や控除証明書(源泉徴収票や生命保険料控除証明書など)
- 住宅ローン控除関連書類(売買契約書・登記事項証明書・年末残高証明書など)
- 利用者識別番号(マイナンバーカードがあれば、アカウント登録時に発行される)
e-Taxを使用した確定申告書の作成(登録)
e-Taxを使うには、あらかじめ登録が必要です。マイナンバーカードがある場合とない場合で操作方法が異なります。
マイナンバーカードがある場合
マイナンバーカードを持っている方は、マイナンバーカードを手元に用意したうえで、ICカード読み取り機能付きのスマートフォンか、ICカードリーダーを準備しておきます。
ご自身のスマートフォンにマイナンバーカードの読み取り機能があるか否かは、以下の一覧で確認できます。
公的個人認証サービスポータルサイト マイナンバーカード対応一覧
マイナンバーカードの読み取り機能があるスマートフォンに、「マイナポータルアプリ」をインストールします。画面の指示にしたがってマイナンバーカードを読み取り、完了すると書類作成ができる状態になります。
Google playデジタル庁提供 マイナポータルアプリ
App storeデジタル庁提供 マイナポータルアプリ
マイナンバーカードがない場合
マイナンバーカードがない状態で確定申告をe-Taxでおこなう場合には、IDとパスワードを事前に発行してもらうため税務署に行く必要があります。税務署へ行き対面で本人確認をおこなってIDとパスワードを取得しましょう。
その際は写真付きの身分証が必要で、本人が直接行かなければなりません。この方法は、マイナンバーカードが普及するまでの対応策としておこなっています。
e-Taxを使用した確定申告書の作成・送信
利用者登録ができたら、確定申告書を作成します。国税庁ホームページ 確定申告書等作成コーナーから作成できます。ここで作成する書類は、確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。作成方法は、操作画面で案内してくれます。
操作は、パソコン・スマートフォンのどちらからでも可能です。サイトの指示にしたがって、先述したe-Taxを利用する際に集める書類を用いて、ローンの残高や住宅の取得金額などを入力していきましょう。
入力が済んだら、作成した申告書や必要書類などをスキャンしてe-Taxで送信すれば完了です。
e-Taxを使用して住宅ローン控除の申請をするポイント
初年度からマイナンバーカードを使用してe-Taxを利用すると、住宅ローン控除の申請が楽になります。2年目以降は、税務署から毎年10月頃、住宅ローン控除の証明書データが送付されてきます。なお、手続きの期間は、住宅を取得し居住した翌年1月から確定申告の期限の3月15日までです。
もし、マイナンバーカードを利用して確定申告をしなかった場合、2年目以降の手続きで「証明書データ」の取り込みが利用できなくなります。その場合は毎回、自分で入力や計算をしなければなりません。マイナンバーカードを持っている方は、使用してe-Taxでの申請をおすすめします。もし取得していないのであれば、マイナンバーカードを取得しておいたほうがよいでしょう。
住宅ローン控除の確定申告をe-Taxでおこなうメリットは?
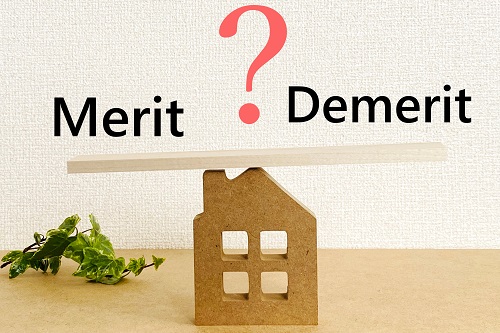
住宅ローン控除の確定申告でe-Taxを利用するとどのようなメリットがあるのでしょうか。以下に代表的なメリットを解説します。
税務署に出向かずオンライン上で手続きできる
e-Taxで確定申告をすると、場所も時間も気にせず、必要な書類とインターネット環境があれば手続きができます。書類での提出の場合、書類を取得したり提出するのに、税務署に行かなければなりません。窓口で手続きするには時間内に行く必要がありますが、会社に勤めている場合、平日の日中に出向くのは難しいでしょう。オンライン上で手続きできれば、窓口が開いていない時間でも都合のいいタイミングで、いつでも提出でき便利です。
提出・訂正など簡単にできる
e-Taxを利用すると、提出期間内はいつでも修正ができ、上書き保存もできます。社会保険料控除や生命保険控除証明書等関係書類の提出を省略してよいと認められているのも便利なポイント。e-Tax用のソフトを利用すれば、作ったデータを取り込んで申請に使うこともできます。書類の用意、修正・保存、提出などが簡単なのがメリットです。
確定申告の提出は郵送でもでき、税務署に出向かなくても手続きできます。しかし、手書きの書類を用意して郵送するのは手間のかかる作業です。人によっては、たくさんの添付書類を用意しなければなりません。修正や不備があった時には再度、直して郵送するのもひと苦労です。従来のこのような苦労をしなくてよいのが、e-Tax申請のメリットといえるでしょう。
入金処理が早い
電子申請した場合は、還付金の入金処理も窓口申請より早くなります。従来の方法で書類を提出した場合は、還付金が入金されるまでに1カ月から1カ月半かかっていました。e-Tax申請だと、2~3週間で入金が完了します。確定申告を受け付ける期間も、窓口の受付より早い1月から開始されます。手続きを早く始められるのも便利な点です。
e-Taxで住宅ローン控除の確定申告をしづらい理由は?

住宅ローン控除の確定申告の際に便利なe-Taxですが、使いにくいと感じる方もいるようです。どのような点でe-Taxが使いづらいと感じるのでしょうか。
事前準備が面倒
e-Taxを使って確定申告をするには、事前登録が必須。登録にはマイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応のスマートフォンが必要です。もしマイナンバーカードの読み取りに対応していないスマートフォンを使用する場合には、カードリーダーを用意することになります。
マイナンバーカードを持っていないと登録が不便
マイナンバーカードは身分証や健康保険証として利用するようになってきているため、申請をしようと考えている方も多くなってきたと思います。一方で、まだマイナンバーカードを利用していない方もいらっしゃるでしょう。
e-Taxを利用するのに、マイナンバーカードを持っていない場合、事前に税務署へ行き利用登録をするか、マイナンバーカードの取得が必要です。税務署に行く手間を省いて電子申請したいと思っていても、登録に行かなければならないのは、かなりの手間だと感じるでしょう。
入力画面やシステムなどがわかりづらい
e-Taxのメリットでは、申請内容が訂正しやすかったり、保存ができたり、書類の提出が省略できるなどの点で、スムーズに確定申告が可能と先に説明しました。しかし、入力画面やシステムの操作がわかりづらいと感じることも。
e-Taxは国税庁が運営するシステムやスマホアプリ上で手続きをします。税金の計算や、税務処理に関してなど入力していく内容が特殊なので、普段アプリを使っている人でもわからないこともあるようです。特に初めて申請をする人や高齢で機械操作が不慣れな人は、使いづらいと感じるでしょう。
国税庁の公式ホームページなどで、操作の手順を説明していたりしますが、読むだけではわかりづらいかもしれません。所定の相談窓口に問い合わせたり、操作が詳しい人や申告をしたことがある詳しい人などに聞いてみて対策する必要がありそうです。
この記事のQ&A
Q:確定申告でおこなう住宅ローン控除の概要は?
A:住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用して住宅を購入した個人や世帯が、支払う住宅ローン残高に応じて所得税から控除できる税制優遇措置です。2022年の改正後控除率は0.7%、控除期間は13年間になりました。ただし、中古住宅(既存住宅)と増改築は控除期間が10年間です。
控除されるのは所得税ですが、所得税だけで控除しきれなかった場合は住民税からも控除されます。ただし、その年に納める予定の税金以上の金額は控除されません。また、住民税からの控除額は、最大で9.75万円と決まっています。適用される住宅ローン残高には上限が設けられており、住宅の性能によって分けられています。
Q:住宅ローン控除の確定申告をe-Taxでする方法は?
A:e-Taxとは2004年に導入された国税電子申請納税システムで、パソコンやスマートフォンを使って納税の手続きができます。手続きには、マイナンバーカードやマイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン、住宅ローン残高のわかる書類などが必要です。
実際に確定申告をおこなうときは利用者登録をし、確定申告書を作成します。書類は、国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナーから作成可能。作成する書類は、確定申告書と住宅借入金等特別控除額の計算明細書です。作成方法は、操作画面で案内してくれます。操作は、パソコン・スマートフォンのどちらからでも可能です。
Q:住宅ローン控除の確定申告をe-Taxでおこなうメリットは?
A:税務署に出向かなくても、時間と場所を気にせずオンライン上で手続きできるのがメリットです。また、提出・訂正などが簡単にできるうえ、還付金の入金処理が早いのもメリットといえます。
Q:e-Taxで住宅ローン控除の確定申告をしづらい理由は?
A:e-Taxを使って確定申告をするには、事前の登録が必要です。わざわざ登録するのが面倒に感じる方もいらっしゃるでしょう。また、登録にはマイナンバーカードとカード読み取り機能があるスマートフォンが必要で、もし持っていないと税務署に出向いて登録しなければなりません。
e-Taxを利用すると、申告内容を訂正しやすかったり、保存ができたり、書類の提出が省略できるなどの利点がありますが、一方で、入力画面やシステムの操作がわかりづらい難点があります。確定申告に特殊な内容の入力など、普段機会を使っている人も使いづらいと感じるようです。
まとめ
本記事では、初めて住宅ローン控除の申請をする方や、e-Taxを使って住宅ローン控除の申請をするか迷っている方に向けて、その手順や申請時のポイント、メリットを解説しました。さらにe-Taxで申請する時につまずきがちなことなども解説しました。これから確定申告の時期になるので、この記事がお役に立てば幸いです。
物件を探す

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ






