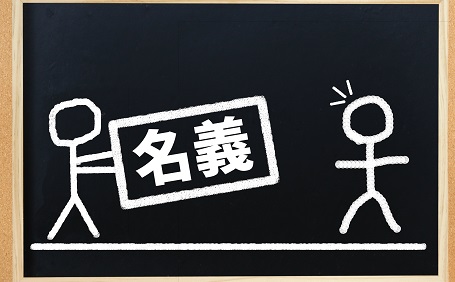夫婦で住宅ローンを組む方法とは?負担割合で注意すべき事項もわかりやすく解説!

本記事では、夫婦で住宅ローンを組む際の適切な負担割合や注意すべき事項をわかりやすく解説します。さらには、負担割合の決定だけでなく、夫婦間で起こる緊急事態に備えた対策も。住まいづくりの大切な第一歩に向けた、具体的な方法をご紹介していきます。
記事の目次
夫婦で組む住宅ローンにはどのような種類がある?

夫婦で協力して組む住宅ローンの種類は3つあります。
- ペアローン
- 連帯債務型の収入合算
- 連帯保証型の収入合算
以下、3つの方法を詳しく見ていきましょう。
ペアローン
ペアローンとは、同じ物件に対し夫婦それぞれ住宅ローン契約を結ぶ方法です。具体的には、物件を購入するために夫婦それぞれが別々に住宅ローンを契約し、その際に互いが連帯保証人となります。この方式では、両者が個別に契約者となるため、それぞれが住宅ローン審査の対象となります。契約手続きでは、勤務先や収入、勤続年数などの情報が確認され、また、個人信用情報機関に登録されている信用情報も照会されます。
返済の義務は夫婦両方にかかるため、片方の返済が遅れると、もう片方は連帯保証人として返済の責任を負うことになります。この仕組みは、貸し手のリスクを軽減するために設けられていますが、同時に夫婦間の協力と責任が求められるものでもあります。
ペアローンのメリット
- 借入期間や返済方式、金利タイプや団体信用生命保険(団信)の選択などそれぞれの契約をそれぞれが自由に設定できる
- 夫婦それぞれが団信に加入できる
- 夫婦それぞれ住宅ローン控除が受けられる
ペアローンのデメリット
- 契約本数が2本になり、手数料も2倍必要になる
- 団信が適用されるのはローン名義人分の残債のみであり、遺族側のローンはそのまま支払い続けなければならない
連帯債務型の収入合算
連帯債務型の収入合算とは、夫婦がお互いの収入を合算して住宅ローンを申し込み、一つのローン契約を結ぶ仕組みです。この方式では、主たる債務者と従たる債務者と呼ばれる二人が連名で住宅ローンを契約します。
二人の収入を合計してローンに申し込むため、より大きな借り入れが可能になることがあります。主たる債務者と従たる債務者はともに債務を負うため、返済の責任も共同で担います。ペアローンと似ていますが、ペアローンでは別々にローン契約を結ぶのに対し、連帯債務型の収入合算では一つの契約となります。
収入や信用情報などの審査は、主たる債務者と従たる債務者の両方が対象になります。これにより、両者の収入や信用情報の良し悪しによって、融資の可否や金利が決まります。
この仕組みは、夫婦が協力して一つの住宅ローンを組む際の一つの方法です。しかし、返済の責任をともに負うため、将来の変化やリスクにも注意が必要です。
連帯債務型の収入合算のメリット
- 単独で借りるよりも借入可能額が多くなる
- 主たる債務者だけでなく従たる債務者も住宅ローン控除を受けられる
- 契約が1つなので、諸費用が1本で済む
連帯債務型の収入合算のデメリット
- 従たる債務者が病気やケガなどで収入が減っても、返済は免除されない
- 従たる債務者は団信に加入できない可能性がある
連帯保証型の収入合算
収入合算の連帯保証型は、夫婦が共同で住宅ローンを契約し、お互いの収入を合算して返済能力を高める仕組みです。この方法では、主たる債務者と連帯保証人の役割があります。
主たる債務者は、実際に住宅ローンを契約する主要な借り手で、収入や信用情報が評価されます。連帯保証人は、ローン返済が滞った場合に備えて、返済を支援する責任を負う存在です。夫婦の場合、通常は主たる債務者が収入をもたらす一方、連帯保証人はそのサポート役を担います。
連帯保証型の収入合算のメリット
- 契約が1つなので、諸費用が1本で済む
- 単独で借りるよりも借入可能額が多くなる
連帯保証型の収入合算のデメリット
- 不動産の名義は主たる債務者の名義となり、保証人に持分はない
- 住宅ローン控除を利用できるのは、主たる債務者のみ
住宅ローンを夫婦で組む割合の適正値は?

返済比率の適正値
住宅ローンを夫婦で組む場合、一つの物件に対して共同で返済をしていくことになります。共同で住宅ローンを返済する分、一人で組むよりも返済比率を多くできるのか、あるいは安全にしたほうがよいのかと、迷う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
返済比率の適正値は年収だけでなく家庭の状況によっても変動します。そのため、適正値には幅がありますが、一般的には返済比率で20%以内が適切とされています。この範囲を超えると生活に支障が生じやすくなるといわれています。
負担割合の適正値
住宅ローンを夫婦で協力して組む場合、二人の負担するローン割合はどのように決めればよいのでしょうか。基本的には、収入に応じて案分するのがよいでしょう。例えば、物件価格が6,000万円、夫と妻の収入がどちらも600万円だったとします。この場合は、夫も妻もローンの負担は同じ3,000万円とします。仮に、夫と妻の収入に差があった場合はそれに合わせます。例えば、物件価格:6,000万円で、夫の収入が800万円、妻の収入が400万円だったとすると、夫のローン負担額は4,000万円、妻のローン負担額は2,000万円にするのが適当でしょう。もちろん、家計の状況によって前後しますが、ローン負担額は収入に応じて案分するのが一般的です。
夫婦で住宅ローンを組む時の注意点は?

夫婦で住宅ローンを組む時に注意すべき点は、支出割合と持分割合に差を付けないことです。もし差があると、贈与税の対象になってしまいます。以下、どのような仕組みでそうなるのかを解説します。
持分割合とは
どのようなしくみで贈与税の対象になるかを説明するうえでまず、持分割合を説明します。持分割合とは、不動産を共有する際に、それぞれ所有者が何割ずつの権益を持つかを示す割合のことです。
夫婦で組む住宅ローンは、夫婦共同で不動産(住宅や土地など)の返済をしていきます。物件を所有するにはまず、物件登記をおこないます。登記で、夫婦がそれぞれ不動産に対して何割ずつの権益を持つかを示します。
持分割合と支出割合に差があるとどうなるか
住宅ローンを夫婦で協力して組む場合、二人の負担するローン割合は前項にもあるとおり、収入に応じて案分するのが多いでしょう。
例えば、夫の収入が600万円で妻の収入が400万円の家庭があったとして、5,000万円の住宅を購入するためにローンを組んだとします。この時、夫のローンは3,000万円、妻のローンは2,000万円のように分けたとします。この時の支出割合は、住宅価格5,000万円に対し、夫が3,000万円で60%、妻が2,000万円で40%となっています。この場合、持分割合も夫60%、妻40%になるのが一般的です。
しかし、実は、持分割合は自由に決めることもできます。仮に持分割合を「夫婦で平等にしたい」として夫50%、妻50%と登記しようと思えば可能です。
しかしこうすると、夫から妻へ共有持分の10%(500万円)の贈与があったとみなされてしまいます。持分割合は、自由に決めることができますが、意図しない贈与税が発生する可能性があります。住宅ローンを夫婦で組む時は、ローン負担割合と持分割合が同じになるよう注意しましょう。
住宅ローンを夫婦で組む前に考えておきたい変化は?

住宅ローンを夫婦で組むと、さまざまなメリットがあるのは確かです。しかし、夫婦で協力する形をとるからこそ、起こりうる影響があります。この章では、住宅ローンを夫婦で組む前に考えておきたい変化を解説します。
働き方の変化
住宅ローンを組む際、働き方が変化する可能性があると考えるのは重要です。共働きの夫婦でも、子どもが生まれたりすると、どちらかが家事や育児に専念する可能性があります。この状況下では、元々の収入が変わるため、住宅ローン返済にも影響が出るかもしれません。以前は二人分の収入で返済できていた住宅ローンでも、収入が一方のみになれば、家計が厳しくなるケースが考えられます。
また、どちらかが他方の名義の住宅ローンを返済する場合、前述のように贈与税の課税対象になる可能性があります。さらに、仕事を辞めたことで所得税や住民税がゼロになると、住宅ローン減税の対象から外れる可能性があります。
これらの事態を考慮して、住宅購入時にライフプランを綿密に考慮し、将来の変化に対する準備をしておきましょう。もし住宅ローン返済が難しくなる予感がした場合、金融機関に早めに相談し、返済期間の延長や返済額の調整を検討するのも一つの手段です。将来に備えた計画立案と、柔軟な対応が重要です。
夫婦関係の変化
将来的に夫婦関係が変化し、離婚する可能性もゼロではありません。ペアローンや連帯債務(収入合算)型の住宅ローンでも、離婚したからといって返済義務がなくなるわけではありません。
例えば離婚後、元夫が購入した家を出ることになった場合でも、家のために借りたお金を返済しなければならない状況が考えられます。離婚によって生活状況が大きく変わっても、返済は続くのを考慮して返済計画を立てておくべきです。さらに、住宅ローンの条件には対象の家に住む前提があります。離婚によって家を出た側が条件を満たさなくなると、一括返済を求められる可能性があります。
離婚時の住宅ローン問題には、いくつかの対処法があります。1つ目は住宅を売却し、住宅ローンを一括返済する方法です。2つ目は、連帯保証人や連帯債務者を第三者に変更する方法、三つ目は、ペアローンを住み続ける側に一本化する方法です。
住宅ローンを夫婦で組む時に、離婚に備えて計画を立てている人はいないかもしれません。実際に離婚はしないにせよ、可能性として考慮し対処法を知っておくのは何かの役に立つかもしれません。
死別による変化
住宅ローンを夫婦で組む際には、パートナーと死別する可能性も考慮が必要です。
ペアローンを選ぶ場合、夫婦はそれぞれが個別に住宅ローンを組み、団体信用生命保険(団信)にも個別に加入しています。片方が死亡すると、住宅ローンの残債は消えますが、生存している人のローンはそのまま残ります。両者のローン残高をゼロにするためには、生命保険への加入が別途必要となります。
連帯債務型の収入合算の住宅ローンを選んだ場合、団信は通常、主債務者に対してのみ適用されます。主債務者の死亡時には残債がゼロになるものの、連帯債務者の死亡時にはローン残高は減少しません。連帯債務者の死亡にも対応したい場合、夫婦連生団信に加入できる住宅ローンを選択するか、別途、生命保険に加入しなければなりません。
死別時のローン問題には、いくつかの選択肢が考えられます。1つ目は、夫婦連生団信に加入できる住宅ローンを選び、連帯債務者の死亡にも対応する方法です。2つ目は、別途、生命保険に加入する方法です。どの方法を選ぶにせよ、適切な保障を考えながら、住宅ローンの組みかたを検討するようにしましょう。
記事のおさらい
Q:夫婦で組む住宅ローンの種類にはどのようなものがありますか?
A:夫婦で協力して組む住宅ローンの種類は、ペアローン、収入合算の連帯債務型と、連帯保証型で3つあります。
Q:住宅ローンを夫婦で組む割合の適正値はどのくらいですか?
A:返済比率の適正値は、年収の20%の範囲とされています。この範囲を超えると生活に支障が生じやすくなるといわれています。住宅ローンの負担割合は、収入に応じて案分するのが一般的です。
Q:夫婦で住宅ローンを組む時の注意点は何ですか?
A:夫婦で住宅ローンを組む時の注意点は、支出割合と持分割合に差を付けないことです。もし差があると、贈与税の対象になってしまうので注意です。
Q:住宅ローンを夫婦で組む前に考えておきたい変化とはどのようなことですか?
A:夫婦で協力する形をとるからこそ、起こりうる変化に備えておく必要があります。例えば、働きかたが変わったり、夫婦関係が変化したり、パートナーと死別したりする可能性もあります。住宅ローンを夫婦で組む際には、将来起こりうる変化に対しての準備が必要です。
まとめ
本記事では、夫婦で住宅ローンを組む際の適切な負担割合や注意すべき事項をわかりやすく解説しました。さらに、負担割合の決定だけでなく、夫婦間で起こる緊急事態に備えた対策も紹介しました。なかには、離婚や死別など想定したくないこともありますが、一つの可能性として考える機会を持つのも重要なのではないでしょうか。
物件を探す

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ