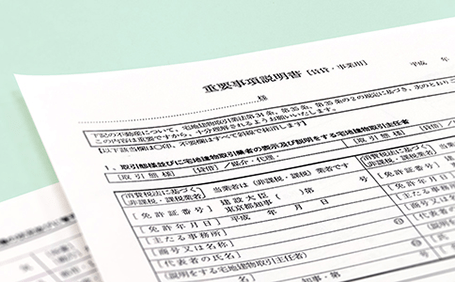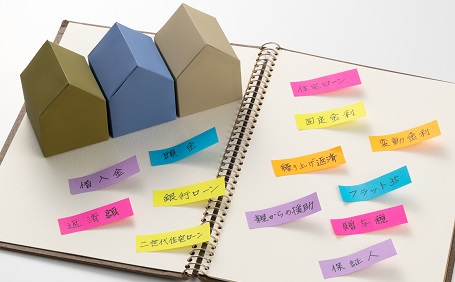新築マンション購入の注意点は?購入前に知っておきたいポイントを徹底解説!

マンションは大きな買いものです。選ぶのに失敗し、購入してから後悔をしないためにも、この記事の内容をチェックしながら購入の計画を立て、実行しましょう。
記事の目次
新築マンションを購入する時の注意点は4つ
新築マンションを購入する際に注意することは、次の4点です。
- 購入時の初期費用、月々の住宅ローン返済額、購入後に必要な費用など、お金がどのくらいかかるのかを把握したうえで、購入の予算を立てること
- 専有部分や共用部分の希望条件を決めておくこと
- 立地や場所、周辺の環境、将来売却する場合売りやすい立地かなどを確認すること
- 物件探しや契約の際に注意する内容を確認すること
それでは4つのポイントを詳しく説明します。
お金に関する注意点
新築マンションを購入するためには、頭金や毎月のローンの返済金、管理費、修繕積立金など、マンションの価格に加えて、さまざまな支払いが発生します。
物件を探しはじめる前に、入居前後にどのくらいお金がかかるのか考慮して、購入予算を決めるようにしましょう。
無理のない資金計画か確認する
先に説明したように、新築マンションの購入、維持にはさまざまな支払いが発生します。
マンションの価格のほかに、諸費用としてローン事務手数料や登記費用なども必要です。また、月々の支払いは、ローンの返済額や管理費などを含めていくらまで支払うことができるのか、事前に計画を立てましょう。
無理のない資金計画を立てるうえで、確認しておく項目は次のとおりです。
住宅ローンの返済額を確認する
どのくらいの金額のマンションを購入できるかは、自分で用意できるお金(頭金)と住宅ローンの借入金の合計額で決まります。
金融機関で組める住宅ローンの額は、その人の年収や勤務先、勤続年数などをベースに決めているため、無理なく返済できる額とは限りません。
一般的な年間のローン返済額は、住宅ローンおよび他のローンも含めて税込年収の35%以内ですが、実際の返済可能額は世帯の事情によって異なります。
例えば子どもがいる世帯では、教育費を考慮する必要があります。個々の事情に合わせて無理のない範囲で返済できるような借入額を設定しましょう。
「どのくらいの価格のマンションを購入できるか」を確認したい場合、下記の記事で年収ごとの借入可能額や返済額のシミュレーションを紹介しています。一度参考にしてみてはいかがでしょう。
新築マンション購入には「諸費用」がかかる
マンション購入には、物件価格以外に諸費用がかかります。諸費用は新築マンションの場合、物件価格の3%から5%が目安で、頭金とは別に現金で用意しなければなりません。
諸費用は、登記費用や住宅ローンの融資を受ける際に必要な経費などがあります。
また、新築マンションの場合は、大規模な修繕費用に充当する修繕積立基金、マンションの管理組合発足の経費に充当する管理準備金も諸費用に含まれます。
維持費がかかる
マンション購入後、月々の支払費用として、住宅ローン返済の他に修繕積立金や管理費などの維持費がかかります。また物件によっては駐車場代や駐輪場代、トランクルーム代など各種施設の使用料が必要な場合も。さらに年に1回支払う税金(固定資産税、都市計画税)も必要です。
住宅ローンの返済額を設定する時は、維持費の額も考慮して決めましょう。
専有部分・共用部分に関する注意点

実際にマンションを購入する予算が決まったら、具体的に物件探しや内覧をおこないますが、その際に次のことを確認しましょう。
優先する条件を決めておく
専有面積、部屋の間取り、部屋の向き、階数、防音など住まいに求める条件を整理し、希望する条件に優先順位をつけましょう。同じマンションでも専有面積や階数、北向きか南向きかなどの条件の違いによって販売価格が異なります。もし希望条件にあう物件が予算オーバーの場合、どの条件を取捨選択するかの目安になります。
新築マンションは内覧できない物件がある
新築マンションは、販売時に物件が完成していないことも多いです。その場合、実際の建物や部屋の中を確認できません。しかし、マンションの建設予定地の近隣にモデルルームが設けられており、そこで内覧をすることが可能です。モデルルームを内覧することで部屋の作りや動線などを確認できます。
モデルルームとして用意されていない部屋でも、販売会社の担当者の話を聞いたり、資料をもらったりすることで、物件について詳しく知ることが可能です。
実際にモデルルームを内覧する時に注意するポイントを紹介していきます。
モデルルームは事前予約をする
予約なしでも利用できる場合がありますが、モデルルームが定休日で閉まっていたり、説明する担当者がいない、すでに先客がいて時間がかかるなど、スムーズに内覧できないことがあります。また、予約をしないと内覧できないモデルルームもあるため、事前に予約をするようにしましょう。
モデルルームは標準仕様と異なる
モデルルームに備え付けてある家具や設備、部屋の仕様などが標準仕様と異なる場合があります。内覧して部屋の雰囲気や備え付けてある設備を気に入っても、有料オプションの可能性も。これらの設備や仕様が標準仕様なのかオプション商品なのかを販売担当者から説明を受ける、もしくは資料をもらうなどして確認しましょう。
完成した物件はオプションが付けられない可能性がある
完成済みの物件は、購入希望の部屋を見学して実際の間取りや動線、仕様を確認することができます。ただし、床や建具の色など、有料オプションの種類によっては申し込み期限が過ぎているため、追加や変更ができない可能性があります。
共用部分の設備を確認する
マンションの共用部分の設備や仕様も確認しましょう。宅配ボックスの有無、ポストの仕様、エレベーターの基数や購入希望の部屋からの距離、オートロックなど気になる箇所を確認しましょう。また、大規模マンションではゲストルームやラウンジ、トレーニングジムやキッズスペースなど物件ごとに、いろいろな共用施設を設けてあることも。あると便利な共用施設ですが、別途維持のために管理費が割高になったり、使用料がかかることもあります。維持費用を負担し続けることは可能か、あわせて検討が必要です。
完成前の物件で、実物を確認できない場合は、モデルルームで販売会社の担当者に質問をする、またはマンションの公式ホームページやチラシなどで確認しましょう。
近隣の住人を確認できない
新築マンションは完成前に購入を決めることが多く、どのような人が住んでいるのかを事前に確認することは困難です。
ただ、マンションの公式ホームページやチラシの内容から、マンション販売のターゲット層がわかるため、ファミリー層向け、一人~二人暮らし向けなど、おおまかな予測は可能です。
周辺環境に関する注意点

災害リスクや駅までの道のり、近隣にスーパーはあるかなど、実際に生活する際にマンションの周辺の環境も重要となります。マンションが立地している周辺環境で注意する点を確認しておきましょう。
災害リスクがないか確認する
水害、地震、土砂災害などの災害リスクについて、必ず事前に調べておきましょう。ハザード情報は国土交通省や自治体のホームページに掲載されています。事前に災害リスクについて知ることで、リスクの低い場所に立地している物件なら安心要素になりますし、逆にリスクの高い場所に立地している物件であれば、対策を考えることができます。
また、購入契約時に売主から説明される重要事項のなかに、水害リスクに関することが含まれています。内容を確認し納得してから購入を決めるようにしましょう。
参考:ハザードマップポータルサイト(国土交通省)
確認する災害の種類
次にあげる災害リスクは特に発生頻度が高く、希望する物件の立地が該当しているか確認が必要です。
水害(洪水、浸水、高潮)
洪水は大雨などで川の水が増えることで堤防が壊れたり、堤防を越えて川の水が外に溢れ出したりすることです。
浸水は大雨や洪水などにより建物の床下や床上まで水が入ってくること、高潮は台風などの影響で海面の水位が上昇することをいいます。
これらの水害は、海岸に近いゼロメートル地帯や湾奥、河川敷、沖積地などの河川付近に建てられたマンションで発生するリスクがあります。
地震災害(津波、液状化)
津波は海で地震が発生した際に、海底が大きく揺れることによって発生するものです。海岸付近の海抜が低い土地に建てたマンションは、被害にあう可能性があります。
液状化現象は、地震が発生した時に地盤が液状化することをいいます。地盤がゆるくなるので、建物が傾いたり沈んだりします。埋め立て地に建てられたマンションは液状化現象が起こる可能性があります。
土砂災害
土砂災害は山や崖が崩れたり、崩れた土砂が雨水や川の水と混ざって流れ出てくることで建物が押しつぶされたり、道路が閉鎖されたりします。
丘を切り崩した造成地、山のふもとにある扇状地などに建設したマンションの土砂災害リスクの有無は地盤の強度や過去の災害履歴で確認できます。
必要な施設の優先順位を決める
マンションの周辺環境は、ライフスタイルによって求める条件が異なります。最寄り駅からの距離や道のり(平坦か坂があるか)について実際に歩いてみましょう。また、スーパーやコンビニ、ドラッグストアなどが便利な場所にあるか、子育て世帯の場合は学校や保育園、幼稚園が近くにあるかなど、生活するうえで必要な施設を確認し、優先順位を決めておきましょう。
立地や資産価値を考える
将来的に転勤やライフスタイルの変化などによりマンションを売却して住み替えたり、賃貸に出したりする可能性があります。その時に売却や賃貸しやすいように、需要が高い場所、物件の資産価値が落ちにくい場所に立地したマンションを選ぶこともポイントです。
資産価値が落ちにくい立地の例としては、駅から徒歩10分以内で、都心など地域の中心地へのアクセスがよいこと、近隣にスーパーや学校、病院など生活に必要な施設があることなどがあげられます。
物件探し・契約に関する注意点
実際に物件を探したり、新築マンションの購入時の契約に関して注意する点を紹介していきます。
不動産会社を自分で選べないことが多い
賃貸や中古物件を購入する場合、購入者が自分で不動産会社を選んで依頼できます。しかし新築マンションの購入は、ほとんどが売主の代理として販売代理店や販売提携店を通じておこないます。そのため、以前対応してもらったことがある不動産会社や、依頼したい不動産会社を利用できません。
一方で、販売代理店・販売提携店は大手企業が運営していることが多く、購入の手続き面で比較的安心できます。また仲介会社が入らず、売主と購入者が直接売買できるため、仲介手数料がかからないメリットもあります。
重要事項説明書を確認する
マンションの購入を決めたあと、売買契約を結ぶまでの間に、売主から購入物件に関する重要事項説明書を渡されます(前もって渡される場合もあります)。そして、宅地建物取引士の資格を持った担当者から、重要事項説明書の内容について説明を受けます。
重要事項説明書は、物件に関する事項、売買契約に関する事項などが書かれている書類です。記載内容に間違いがないかよく確認し、不明点や疑問点があれば説明時に質問しましょう。
重要事項の説明を受け、納得したら説明書(売買契約書と一緒になっている場合が多い)の署名欄に署名と押印をすることで、すべての内容を理解した意思表示になります。
引き渡しまで時間がかかる場合がある
マンションが完成していない状態で購入した場合、物件の引き渡しは完成後になるため、すぐには入居できません。特に購入から引き渡しまでの期間が長期の場合、当初の計画より完成が遅れるケースもあります。子どもの就学など、ライフイベントに合わせて引越しを計画している場合は注意が必要です。
マンション購入から引き渡しまでの期間は、売買契約を結んだ時に物件が完成している場合は、約1カ月から3カ月後です。また、物件が完成していない場合は完成後になります。完成までの期間は物件によって違い、半年から1年以上になるケースもあります。
新築マンションを購入する時の流れ

ここまで、新築マンションを探す際に知っておきたいポイントについて説明してきましたが、実際にマンションを購入する時の流れを説明します。
資金計画を立てる
マンションを購入するのに、いくらまでなら資金を出せるのか、次の順序に沿って予算を立てましょう。
-
STEP 1自己資金(現金)がいくら用意できるかを調べます。
自己資金は貯蓄の他に親などからの資金援助があればその額も加えます。 -
STEP 2購入する物件価格の予算をおおまかに決めましょう。
予算を決めることで立地エリアや部屋の間取りなどの購入可能条件がはっきりします。 - STEP 3購入する時に必要な諸費用を計算します。(目安は購入価格の5%)
-
STEP 4住宅ローンの借入額を計算します。
借入額の計算式は、(購入価格+諸費用)-自己資金=借入額
例えば購入物件の価格が5,000万円、自己資金が500万円の場合
(5,000万円+諸費用250万円)-500万円=住宅ローンの借入額は4,750万円になります。
物件探し・内覧をする
物件を探す時には、不動産情報サイトを利用することで、自分のライフスタイルや好みに合った条件の新築マンションに関する情報を集められます。気になる物件があれば売主に問い合わせや内覧予約も可能です。またファミリー向け特集・駅徒歩5分圏内の物件特集などさまざまな特集があるので、希望する条件の物件を簡単に見つけられますよ。
申し込み・契約
マンションの購入申し込みから契約までは、次の手順ですすみます。事前に手順を確認して、契約に関するスケジュール感を把握しておきましょう。
- STEP 1マンションの購入を希望する場合、売主に購入申込書を提出します。売主が申込書に記載された内容で了承すれば、マンションの売買契約に移ります。
- STEP 2マンション購入に住宅ローンを利用する予定がある場合は、売買契約を結ぶ前に住宅ローンの事前審査(仮審査)を、住宅ローンを組む予定の金融機関に申し込みます。事前審査の結果は、金融機関にもよりますが最短で審査申込日の翌日、おおむね3日前後でわかるところが多いです。審査に通過すれば、売買契約をおこないます。
- STEP 3売買契約時に重要事項説明書と売買契約書の説明があります、内容に問題がなければ売主と購入者とで売買契約を結びます。
- STEP 4売買契約が締結したら、すぐに事前審査に通った金融機関に住宅ローン本審査の申し込みをします。金融機関にもよりますが申し込み後およそ2週間で結果が通知されます。
- STEP 5住宅ローンの本審査が通過したら金融機関と金銭消費賃貸契約を結びます。
内覧会・引き渡し
内覧会とは、マンションの完成後購入予定の住宅の引き渡し前に、購入者の立会いのもとおこなわれる建物の確認をいいます。この時に契約したとおりの建物、室内になっているか、オプションの設置は依頼したとおりになっているか、部屋に傷や汚れがないかどうかなど入念にチェックします。もし不具合や気になる点があれば担当者に話し、対処してもらいましょう。
内覧会が終わったら、売主へ物件の購入代金を支払い、物件の鍵を受け取ることで引き渡しが完了します。購入代金の支払い完了後、法務局で所有権移転登記の申請手続きをおこない、書類が受理されたあと、物件の持ち主が売主から購入者に変わります。所有権移転登記の申請手続きは購入者がすることも可能ですが、住宅ローンを利用する場合は、抵当権を設定する関係上、金融機関と契約している司法書士に依頼するケースが多いでしょう。
まとめ
販売会社の案内ホームページやパンフレットなど新築マンションの広告は、イラストを多用した豪華な作りになっていたり、魅力的なキャッチコピーや紹介文が載っていたり、どれがよいのか迷ってしまいますよね。新築マンションの上手な物件探しをおこなうには、不動産情報サイトの活用がおすすめです。より多くの物件を調べることで、立地や建物の仕様などによる価格相場の情報が手に入ります。さらに不動産情報サイトを活用することで効率よく希望に合った物件を見つけられるでしょう。この記事で紹介した購入前に知っておきたいポイントを参考にして、新築マンションを探してみてくださいね。
物件を探す