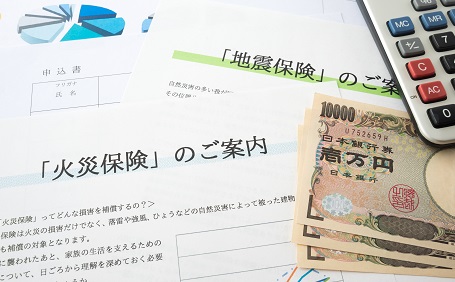マンション火災にどう備える?自分でできる対策と避難方法を徹底解説

そこで、本記事ではマンション火災にどう備えるか、自分でできる対策と避難方法を徹底解説します。マンション住民にとって知っておくべき情報を参考に、マンション火災に備えて安全な暮らしを守りましょう。
記事の目次
マンション火災はどのくらい発生している?

マンションは火災に強い構造となっていますが、それでも火災が起きているのが現実です。火災の原因はさまざまですが、一般的な戸建住宅では、ひとたび火災が発生すると全焼するケースが多いでしょう。しかし、マンション火災では火災が発生した部屋のみの被害で済むことがほとんどで、マンションが全焼することはほぼありません。
以下、消防庁のデータから、2023年(1~3月)の共同住宅(マンション)の火災発生件数や死者数をまとめてみました。
| 火災件数 | 1,063件(全体の17.9%) |
|---|---|
| 負傷者数 | 295人(全体の21.1%) |
| 死者数 | 77人(全体の13.8%) |
また、東京消防庁のデータから2012年~2021年までの、11階以上の高層マンションの火災件数を整理すると、次のような件数になっています。
| 発生年 | 件数 |
|---|---|
| 平成24年 | 106件 |
| 平成25年 | 83件 |
| 平成26年 | 90件 |
| 平成27年 | 110件 |
| 平成28年 | 91件 |
| 平成29年 | 118件 |
| 平成30年 | 102件 |
| 令和元年 | 144件 |
| 令和2年 | 123件 |
| 令和3年 | 107件 |
これを見ると、11階以上の高層マンションでも火災が起き、増減しながらも近年では100件を超える件数が続いていることがわかります。
マンションでは「耐火構造」が義務付けられている
マンションが火災に強い大きな理由に、「耐火構造」が義務付けられていることがあります。耐火構造とは通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために、当該建築物の部分に必要とされる性能のことです。
技術的な基準としては、各構造部分の種類や建物の階数に応じて定められる一定時間(おおむね1~3時間)の間、火熱を加えても各構造部分が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであることなどの要件が定められています。
鉄筋コンクリート造や鉄骨造などの耐火性能の高いマンションでも、火災が起こらないわけではありません。「天ぷら火災」などは、一戸建てやマンション問わず火災が起きる大きな原因となります。
また、先の消防庁のデータでも死者をともなう火災の原因として、放火を除くと「たばこ」や「ストーブ」が上位になっています。つまり、住人の不注意によって耐火構造のマンションであっても火災は起きてしまうのです。
特に高層階のマンションの場合、火災が起きると避難が困難になりやすい傾向があります。そのため、初期消火に有効な消火器などの備えが重要です。また、火災が起きた際にどのように避難するかのシミュレーションや、マンションの管理組合が開催する避難訓練などには積極的に参加するようにしましょう。
マンション火災で発生しうるリスク

マンション火災では、さまざまなリスクが発生します。逃げ遅れや一酸化炭素中毒では、死亡するリスクも高くなるでしょう。ここでは、マンション火災で発生しうるリスクについて解説します。
逃げ遅れ
マンションが高層かつ大規模であればあるほど、逃げるのに時間がかかるため逃げ遅れのリスクが伴います。マンション火災は火元の部屋だけでなく、廊下や階段などの共用部分にも煙や熱が広がります。そのため、火災発生時には速やかに消防に通報し、避難経路を確認して安全な場所に逃げることが重要です。
逃げ遅れると、煙や熱で窒息したり、火傷を負ったりする危険性が高まります。また、窓から飛び降りるなどの危険な行動は避けてください。マンション火災の逃げ遅れを防ぐためには、日頃から防火対策を心がけることが必要です。例えば、火気の使用後は必ず消す、延長コードの使用を控える、煙感知器や消火器を設置するなど。
マンション火災は予測できませんが、予防と対策でリスクを減らすことができます。
一酸化炭素中毒や酸欠
マンションは気密性が高いため、火災の際には一酸化炭素中毒や酸欠のリスクが高まります。一酸化炭素は無色無臭のガスで、吸い込むと血液中の酸素を奪います。酸欠は空気中の酸素濃度が低下して起こり、どちらも意識障害や死亡に至る危険性があります。火災報知器や一酸化炭素検知器を設置して、早期発見・避難に努めましょう。
消火活動による水損
マンション火災の消火活動による水損リスクとは、消防隊が火災を鎮火する際に使用する水が、建物や家財に被害を与える可能性のことです。水損リスクは火災の規模や消火方法、建物の構造や設備、家財の種類や配置などによって異なります。水損リスクを低減するためには、火災保険や家財保険に加入し、経済的な損失を補償してもらいましょう。
エレベーターの停止
マンション火災の際にエレベーターを利用すると、途中で停止し閉じ込められる危険性が高まります。エレベーターは電気で動いているため、火災によって電源が切れる可能性が高いのです。また、エレベーターは密閉された空間であるため、煙や熱によって窒息ややけどのリスクが高くなります。
さらに、エレベーター利用では、火災現場への救助隊のアクセスを妨げる可能性があります。マンション火災の際は、エレベーターを避けて階段を使うことが安全かつ重要です。
避難経路の閉塞や混乱
マンション火災の際には、避難経路の閉塞や混乱が発生する可能性も考えられます。避難経路上に障害物やゴミが置いてあると避難できないばかりか、避難経路から発火するかもしれません。
また、大勢が非常口に集まると、密集状態になって混乱をきたします。避難経路は火災の際に有効に利用できるよう、日頃から整理しておくことが重要です。そして、避難時には慌てずに住民と協力し、声かけや誘導をおこない避難を促進しましょう。
建物火災の出火原因は?

消防庁の2023年(1~3月)における火災の状況によると、マンションを含む建物火災5,928件中、上位5位の出火原因は次のようになっています。
| 第1位 | コンロ | 705件 |
|---|---|---|
| 第2位 | たばこ | 532件 |
| 第3位 | ストーブ | 495件 |
| 第4位 | 配線器具 | 368件 |
| 第5位 | 電気機器 | 352件 |
2023年(1~3月)に発生した建物火災 5,928 件の出火原因別件数(出典:消防庁 )
火災原因のトップである「コンロ」のほとんどが「天ぷら火災」であり、揚げ物や焼き物をしている際に、人がコンロからが離れて出火し火災にいたっています。ガスコンロでなくIHクッキングヒーターなら、天ぷら火災は起きないと聞いたことがあるかもしれません。しかし、この情報は誤りです。天ぷら用の油が少なかったり、揚げ物モードを使用していなかったりが原因で、IHコンロでも実際に火災が起きています。したがって、どのようなコンロであっても、調理中にコンロから離れてはいけません。
2位の「たばこ」は寝たばこだけでなく、灰皿に多くの吸い殻がある場合に、消したつもりでも時間の経過によって発火し火災を引き起こします。たばこを吸うなら、水を使用して1本ごとに確実に消火しましょう。
3位は「ストーブ」でした。ストーブを使う際には周囲にものを置かないことが重要ですし、ストーブの上で洗濯物を乾かしてはいけません。
4位の「配線」は、たこ足配線による火災が大半を占めます。そのため、不必要にひとつのコンセントから多くの電化製品へ電源供給するのは避けましょう。また、コンセント付近や電源タップにほこりがたまらないよう、普段からきれいに掃除することも重要です。
そして、5位は「電気機器」でした。年式の古い電化製品は要注意です。10年以上も使用している電化製品は、普段から異常がないか確認が求められます。予算に余裕があるなら、古い電化製品を新しく買い替えることで火災を防ぐと同時に、電気代の節約につながるでしょう。
マンションでできる事前の火災対策

先の建物火災の出火原因を見ればわかりますが、建物火災はすべて人的な要因が原因となっていて、マンションも例外ではありません。逆に考えると、マンションの住人ひとりひとりが対策を施すことで、マンション火災を防ぐことが可能となります。ここで、マンションでできる事前の火災対策を解説しましょう。
布製品は防炎タイプにする
防炎タイプの布製品は火が点いても燃え広がりにくく、発煙量や有毒ガスの発生も抑えられます。マンションではカーテンやソファ、ベッドなどの布製品が多く使われていますが、これらが火災の原因になったり被害を拡大させたりする可能性があるでしょう。そのため、防炎タイプの布製品に交換することで、火災の予防や住民の安全を高めることができます。
火災警報器の設置確認・点検を受ける
マンションでできる火災対策として、火災警報器の設置確認・点検を受けることは非常に重要です。火災警報器は火災が発生した際、早期に発見して住民に警告する役割を果たします。火災警報器が正常に機能していないと、火災の拡大や人命の危険が高まります。そのため、マンションの管理者や住民は、定期的に火災警報器の設置場所や種類、電池の残量などを確認し、必要に応じて点検や交換が重要です。
火災警報器の設置確認・点検は、マンションでの安全な暮らしを守るための基本的な対策です。特に2004年以前に建築されたマンションでは、住宅用火災警報器の設置が義務化されていません。そのため、必要な個所にきちんと設置してあるか確認しておきましょう。
避難設備を確認しておく
マンションでできる火災対策として「避難設備を確認しておく」とは、マンションの非常階段や非常口、消火器や消火栓などの場所や使い方を事前に把握しておくことです。火災が発生したときにはパニックになりやすいので、誘導灯や非常用照明、避難器具、スプリンクラーなどの存在を知っておくことが重要です。次に、各避難設備の役割をご紹介します。
誘導灯

誘導灯とは非常時において、避難経路を照らすための照明装置です。火災などで停電が発生した場合でも、バッテリーなどの電源に切り替わり、避難するための廊下や階段など出口に向かう道を示します。誘導灯は定期的に点検や交換をおこなう必要があり、誘導灯の設置場所や数は建築基準法や消防法などの法令によって定められています。
非常用照明

マンションの「非常用照明」とは、停電や火災などの緊急事態に備えて設置された電気設備のことです。非常用照明は、通常の照明とは別にバッテリーや発電機などの電源から供給されるため、停電時にも点灯します。非常用照明の役割は、主に次の2種類です。
- 1:避難経路や出口などを明るく照らして、住民や来客者が安全に避難できるようにする。
- 2:非常用電話や消火器などの重要な設備を見つけやすくする。
非常用照明は、マンションの安全性や快適性を高めるために必要な設備です。定期的に点検やメンテナンスをおこなって、いざという時に機能するようにしておきましょう。
避難器具

マンションの「避難器具」とは、火災などの緊急事態において、住民が安全に避難できるように設置された器具のことです。一般的に避難器具は8種類に分類されていて、避難はしご、緩降機(かんこうき)、すべり台、すべり棒、避難橋、避難用タラップ、救助袋、避難ロープに分かれます。
このなかで多く利用されているのは、マンションのベランダに設置されている避難ハッチと避難はしごでしょう。これらの避難器具は、マンションの管理者や住民が定期的に点検やメンテナンスをおこなう必要があります。
スプリンクラー

スプリンクラーは、火災が発生した時に自動的に水を噴射して消火する装置です。天井に取り付けられたヘッドと、水源との間に配管されたバルブから構成されています。火災が発生すると、ヘッドの温度感知部が高温になり、ガラス管が破裂して水が噴出します。スプリンクラーは火災の拡大を防ぎ、住民の避難や消防隊の到着を待つ時間を稼ぐ役割を果たす装置です。
マンションへのスプリンクラーの設置は、11階以上の高層階には設置義務があります。11階未満の階には設置義務がありません。したがって、マンションによっては設置されている階と、そうでない階が混在するケースもあります。
自室からの避難経路、避難場所を確認しておく
マンションによってフロアごとの共用部分が異なり、独自の形状を持つマンションも存在します。一般的には、各階の共用部分である廊下は1本であることが多いでしょう。このケースなら、ほとんどが廊下の両端に非常口を設置しています。
しかし、高級マンションなどエントランスから各フロアの廊下が建物内にあり、できるだけ隣人と会わないように複雑に設計されているマンションも少なくありません。いずれにしても、マンションは階層や部屋の位置によって避難経路が異なります。そのため、自室から非常口までの避難経路と、マンションから脱出したあとの避難場所の確認は必須です。
避難訓練に参加する
基本的に50人以上の居住者を有するマンションでは、避難訓練については法令上の定めはありません。しかし、年1回程度の定期防災訓練(避難訓練など)が義務付けられています。
また、飲食店が入店している複合型のマンションの場合は、年2回以上の消火訓練および避難訓練が義務付けられています。いずれにしても、入居しているマンションで避難訓練が開催されるなら、積極的に参加しましょう。そうすれば、万が一の火災時の避難に役立ちます。
万が一マンションで火災が発生してしまったら?

万が一、マンションで火災が発生してしまったら、どのような行動をとればよいのでしょうか。一目散に、非常口へ向かって走るのがいいと思われるかもしれません。しかし、マンション火災では自分だけでなく、住民と一緒に避難することが重要です。ここで、マンション火災が発生した際のとるべき行動を解説します。
大声で「火事だ」と叫び周囲に知らせる
マンション内で火災を発見したら、大声で「火事だー!」と叫び、周囲の住民に火災を知らせます。とはいえ、各フロアを回っていると逃げ遅れてしまう危険性があります。該当のフロアだけで構いませんので、叫びながら各部屋のドアを叩いて非常口に向かいましょう。マンション内の火災報知器が正常なら、非常ベルやアラーム、アラートなどでマンション全体に火災を知らせて避難を促します。
消防に通報する
自身の安全を確保しつつ、119番に通報します。火災を発見して冷静になれる方は少なく、ほとんどの方がプチパニックに陥ります。その結果、119番でなく110番に電話してしまうかもしれません。間違って110番に通報してしまっても消防にも連絡が行くので問題ありませんが、「火事が起きたら119番」を忘れないようにしましょう。また、通報の際には住所が必要になるので、慌てず間違うことなく伝えることが重要です。
火災報知器を鳴らす
マンションで火災が起きたなら、火災報知器が自動で作動するはずです。しかし、火災の原因によっては作動しないケースもあります。マンションの廊下には一定区間に火災報知器が設置されていますから、火災を発見したら近くの火災報知器を作動させましょう。
初期消火活動をする
火災報知器のある場所には消火器が設置されています。火災が小規模で初期消火できる状況であれば、消火器で初期消火をおこないましょう。
逃げる場所を確保しつつ、火元に近づいてホースを向けてピンを抜きレバーを握ります。消火器の黄色のピンは、消化場所に着くまで抜いてはいけません。先に抜いてしまうと移動時にレバーを握ってしまい、消火液が噴出してしまうからです。消火訓練などに参加して、消火器の使い方を知っておくと万一の際に有効です。
避難する
もしも炎が天井近くまで上っていれば、初期消火は無理なので素早く避難します。無理に消火しようとすると、逃げ遅れて火災に巻き込まれる可能性が高くなります。あくまでも、自身の安全を一番に考えつつ行動しましょう。
マンションで火災を発見したら、大声で住民に火事であることを知らせることが重要です。しかし、これは誰もができるわけではなく、多くの方が慌ててしまうだけになるでしょう。それでも、近くの火災報知器のボタンを押すことはできるはずです。自分の身の安全を確保しつつ、火災報知器などでマンション全体に火災であることを知らせること。そして、119番に通報することもお忘れなく。
マンションで火災が発生した際の避難方法

マンション火災に遭遇したら、安全に避難しなければいけません。炎や煙がフロアに充満していなければ、非常口まで走って逃げることも可能でしょう。しかし、すでに煙が充満していれば、立姿勢で走るのは避けてください。火災時の鉄則は「煙を吸わないこと」です。ここでは、マンションで火災が発生した際の避難方法について解説します。
鼻と口を覆う
避難する際には煙を吸わないように、鼻と口をタオルやハンカチ、マスクで覆って避難します。自宅の部屋から避難する際には、タオルを水に濡らして鼻と口にあてて避難するとより効果的です。そうではなく、外出中に廊下などで火災を知ったならハンカチを利用します。もしもハンカチがなければ、衣服の袖部分を破いて鼻と口を覆うなど工夫が必要です。
なるべく低姿勢で避難する
煙が充満していれば、できるだけ姿勢を低くして顔を下向きに避難します。特に煙の色が黒い場合は、一酸化炭素が含まれているので吸い込むと命を失くしてしまうかもしれません。這うくらいの低い姿勢で、壁を伝ってできるだけ素早く避難しましょう。
部屋の窓やドアは閉める
マンション火災で部屋から逃げる際には、部屋の窓やドアを閉めてから避難します。その理由は、火元への空気の供給を遮断して、延焼速度を抑える効果があるからです。
また、消火活動による水損を防ぐ意味もあります。そうすることで、自分の部屋を守りつつ、マンション全体の住民が避難する時間を確保できます。
避難ハッチや非常階段を利用する
高層階のマンションなら、火災時に利用できる非常用エレベーターが設置されています。しかし、そうでないマンションの場合は、避難ハッチや非常階段を利用して避難します。エレベーターが作動しているからと、エレベーターを利用しての避難は絶対にやめましょう。途中で止まってしまい逃げ遅れることになったり、火災に巻き込まれたりする可能性が高くなります。
面倒でも怖くても、避難ハッチや非常階段を使用してください。
下階へ降りられない場合は屋上へ避難する
マンション火災の場合、炎や煙は下の階から上に向かってきます。したがって、できるだけ早くマンションの外に逃げることが重要です。
しかし、炎や煙によって下の階に逃げることができない状況もあるでしょう。そんなときは、その階に留まらず屋上を目指して避難します。マンションの高さにもよりますが、屋上からレスキュー隊が救出してくれるケースもありますし、屋上に避難具が設置されていて地上に避難できるケースもあります。
マンション火災に遭遇したら、煙を吸わないことが重要です。特に、煙が黒い場合は一酸化炭素が含まれているため、吸い込むと死亡する確率が高くなります。そのため、できれば濡れたタオルで鼻や口を塞いで、這うような低い姿勢で避難することが望ましいでしょう。外出中であれば、ハンカチやストールなどを使うと有効です。いつ火災に遭うかわからないため、外出時にはハンカチは忘れずに携帯しましょう。
そして、避難する際にはエレベーターの使用は厳禁です。必ず、避難ハッチや非常階段を使用してください。屋上に避難するのは最終手段ですので、できるだけ早くマンションの外に逃げるようにしましょう。
マンションの火災保険を活用しよう

マンションに住んでいると、火災による損害を受ける可能性は低いと思われがちです。しかし、実はそうではありません。マンションの火災は火元の部屋だけでなく、隣り合う自分の部屋にも影響をおよぼすことがあります。その場合、「失火責任法」に基づいて、火元となった部屋の住人への賠償請求は望めません。
放火のように故意に火災を起こした際は重大な過失となり、火元の住人がすべての部屋の賠償をすることとなりますが、ほぼそのようなケースはないと考えた方がよいでしょう。
マンションの管理組合やオーナーが加入する火災保険の適用範囲は、建物の外壁や駐車場、駐輪場、エントランスや廊下など共用部分に限られます。そのため、管理組合やオーナーが加入する火災保険では、自分の部屋や家財の補償はされないので注意しましょう。そこで、万が一に備えて、個人で火災保険に加入しておくことが大切です。
火災保険は、自分の部屋の専有部分や家財などが補償されます。ただし、家財についてはオプションになっていることもあるため、加入する火災保険に家財保証が付帯するか確認しておいてください。
マンションの火災保険は、加入する保険会社によって補償額が異なります。以下に、ある保険会社の新築マンションの火災保険について、具体的な内容をまとめました。
| 立地場所 | 東京都 |
|---|---|
| 構造級別 | M構造(マンション構造) |
| 建築年数 | 新築 |
| 延床面積 | 100平方メートル |
| 火災保険 | 1,000万円 |
| 家財保証 | 500万円 |
| 地震保険 | なし |
| 特約 |
・臨時費用補償特約
・個人賠償責任補償特約
・築浅割引
・証券不発行割引
|
| 火災保険料 | 年間8,210円(税込) |
火災に強いマンションとは?

火災のリスクを踏まえれば、まず火災に強いマンションに住むということも有効です。では、どのようなマンションを選べばよいでしょうか。ここで詳しく解説します。
建築構造が「鉄筋コンクリート造」や「鉄骨鉄筋コンクリート造」
マンションと呼ばれる建物は、ほとんどの建築構造が「鉄筋コンクリート造」や「鉄骨鉄筋コンクリート造」となります。木造の共同住宅をマンションと呼ぶことは、例外はありますがほぼないといってよいでしょう。
これらの建築構造は、鉄筋や鉄骨をコンクリートで覆うことで火災の際に高温になりにくく、耐火性能が高まります。また、鉄筋や鉄骨は強度が高く、火災の影響で変形や崩壊しにくいのです。そのため、火災に強いマンションとして、安全性や信頼性が高いといえます。
周囲の建物と距離が保たれている
周囲の建物と距離が保たれていれば、火災に強いマンションといえるでしょう。周囲の建物と距離が保たれていると、火災の際に火の熱や煙が直接マンションに影響するのを防ぐことができます。また、消防車や救急車などの救助隊が迅速に現場に到着が可能です。
防災設備が整っている
防災設備とは、火災の発生や拡大を防ぐための設備や、火災時に住民の安全を確保するための設備のことです。例えば、自動火災報知器やスプリンクラー、消火器や非常口、避難ハッチ、非常階段などがあります。これらの設備は、マンションの構造や規模に応じて適切に配置されています。
火災に強いマンションは防災設備が充実しており、住民の安心感や快適さを高めています。
高層すぎない
タワマンと呼ばれる高層マンションは、火災の際に避難や消火が困難になる可能性があります。また、地震などの災害にも弱いことが欠点です。そのため、火災に強いマンションは高層すぎず、適度な高さで建設されることが望ましいでしょう。
高層マンションでは、防災設備を充実させるために費用的、構造的に難しい面を持ち合わせているのも事実です。逆に、高層すぎないマンションは火災の発生や拡大を防ぐための設備や対策が十分に整備されており、住民の安全を確保できるメリットがあります。
管理人や防災スタッフが常駐している
マンションに管理人や防災スタッフが常駐していれば、火災に強いマンションといえます。管理人や防災スタッフは、火災の発生や延焼を早期に察知し、消火や避難の指示を効果的におこなうことが可能です。また、定期的に消防設備の点検やメンテナンスをおこない、火災の予防にも努めます。
これらのサービスは、住民の安全と安心を高めるだけでなく、火災保険の料金を安くする可能性もあるでしょう。
この記事のまとめ
最後に、マンション火災について改めて、重要事項を確認しておきましょう。
マンションでも火災は発生する?
マンションは火災に強い建物ですが、それでも火災は起きています。令和に入っても11階以上の高層マンションにて、100件以上の火災が発生しています。
マンションの火災で発生しうるリスクは?
マンション火災で発生するリスクは、主に逃げ遅れや一酸化炭素中毒が挙げられます。できるだけ早く火災を認識し素早い避難が重要です。
マンションでできる火災対策は?
マンションでの火災対策は、部屋のなかの布製品を防炎タイプにすることや、火災警報器の設置が重要です。また、避難経路の確認も普段からおこなっておくとよいでしょう。
マンション火災にどう備えるのか、自分でできる対策と避難方法を解説しました。マンションに住むなら、火災に強いマンションに住むことをおすすめします。また、万が一のマンション火災に備えて個人での火災保険や家財保険への加入も重要です。本記事の内容を参考にしていただき、安全で安心なマンションライフを楽しみましょう。
物件を探す