物置に固定資産税はかかる?課税対象の条件とかからないケース、減税措置を解説

この記事では、固定資産税がかかる物置とそうでない物置の違いや課税対象となる条件、税額の目安を紹介します。物置選びで後悔したくない方は、ぜひ最後までご覧ください。
記事の目次
物置に固定資産税はかかる?
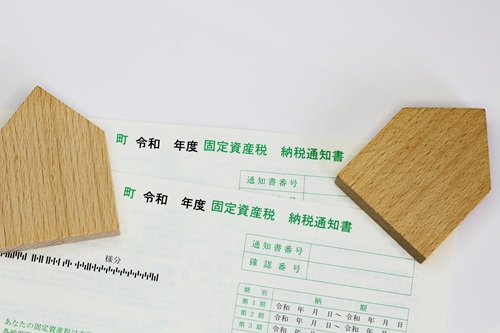
物置に対して固定資産税は、かかる場合とかからない場合があります。そもそも固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地や家屋などの固定資産の所有者に課される税金です。そのため、設置した物置が法律で定める家屋の条件を満たす場合にのみ、課税対象となります。
例えば、基礎工事で地面にしっかり固定した頑丈な物置は、家屋と判断されて課税される可能性が高いでしょう。一方で、コンクリートブロックのうえにただ置いただけのような簡易的な設置であれば、家屋とはみなされず固定資産税は発生しません。
このように、課税されるかどうかは物置の仕様や設置方法に左右されます。「知らなかった」と、あとから慌てないためにも、物置を設置する前に課税対象となる条件や固定資産税を正しく理解しておきましょう。
固定資産税の基本知識や計算方法、減税ポイントを詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてください。
物置が固定資産税の対象となる条件

物置が固定資産税の対象になるかは、先述のとおり不動産登記法で定められた家屋の認定要件を満たすかどうかで判断されます。具体的には、土地への定着性・外気遮断性・用途性の3つです。それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
土地への定着性
土地への定着性とは、物置が基礎工事などで地面にしっかり固定されている状態を指します。例えば、コンクリートで基礎を造り、アンカーボルト(コンクリートの基礎に固定するために使われる特殊なボルト)で物置本体を固定している場合は「定着性あり」と判断されます。
一方で、コンクリートブロックのうえにただ置いただけの状態や、転倒防止のワイヤーで簡易的に留めているだけの設置方法は「定着性なし」と判断されるのが一般的です。
外気遮断性
外気遮断性とは、屋根と3方向以上の壁によって、雨風などをしのげる構造であるかどうかを指します。つまり、物置の内部が外部の気候から遮断されている状態です。
具体的には、四方が壁で囲まれ、出入り口に扉が付いている一般的なスチール物置は、外気遮断性を満たします。逆に、屋根はあっても壁が二方向以下しかないカーポートのような構造は、雨風が吹き込んでしまうため外気遮断性はないと見なされます。すなわち、固定資産税の対象にはなりません。
用途性
用途性とは、設置された物置が、その目的(居住、作業、収納など)のために利用できる状態であるかどうかを指します。物置として、あるいは作業場や居住空間として使える状態であれば、用途性があると判断されます。
例えば、荷物を収納する目的で建てた物置の中が空っぽでも、収納スペースとして機能する状態であれば用途性は満たされます。そのため、一般的に物置として販売されている製品を設置した場合は、用途性の条件を満たすと考えて問題ないでしょう。
物置に固定資産税がかからないケース

物置が固定資産税の課税対象になる条件を紹介しましたが、一方で具体的にどのようなケースであれば、物置に固定資産税がかからないのでしょうか。ここからは、固定資産税がかからない物置の具体的なケースを紹介します。
基礎工事がされていない
基礎工事がされていない物置は、固定資産税がかからない可能性が高いでしょう。これは、課税の条件である「土地への定着性」がないと判断されるためです。
具体的には、地面に直接コンクリートブロックをいくつか置き、そのうえに物置本体を載せるだけの設置方法がこれにあたります。この方法で設置した物置は土地に固着していないため、いつでも簡単に移動できる状態と見なされます。
恒久的に設置しない
恒久的に設置しない物置も、固定資産税の対象外と判断される場合があります。これも「土地への定着性」に関わっており、恒久的ではなく一時的な利用を目的とした物置は、土地に定着していないと考えられるためです。
例えば、地域のイベントで数日間だけ使うテントや、建築工事の期間中のみ設置する現場事務所などがこれに当たります。家庭で物置を設置する場合も、近い将来に移動させる明確な計画があり、簡単に動かせる状態で設置していれば、恒久的な設置ではないと主張できる可能性があります。
電気設備が付いていない
電気設備が付いていない物置も家屋として認定されにくく、固定資産税の課税対象外になる可能性が高いでしょう。照明やコンセントなどの電気設備があると、単なる収納スペースとしてだけでなく、作業場や居住空間としての用途性が高いと判断されます。
例えば、母屋から電気配線を引き込み、物置の内部で照明や電動工具が使えるようにした場合、建物としてみなされ、課税対象になる可能性が高まるでしょう。物置を収納専用と割り切り、電気を引き込まないようにすれば、課税リスクを抑えられます。
床面積が4平方メートル以下
床面積が4平方メートル(約2.4畳)以下の小型物置は、固定資産税の対象外となるケースが多く見られます。
ホームセンターでよく販売されているコンパクトなサイズの物置は、簡易的な設置方法であるものが多いため、課税対象外になる傾向にあります。ただし、これはあくまで課税されにくい目安です。面積の大小よりも、家屋の3要件を満たすかどうかが本来の判断基準であることを覚えておきましょう。
物置の固定資産税はいくら?計算方法・税金の目安

課税対象の物置を設置した場合、実際にいくらの固定資産税を支払うのでしょうか。ここでは、具体的な固定資産税の計算方法と、物置の価格に応じた年間の税額の目安を解説します。
計算方法
物置の固定資産税は「課税標準額 ✕ 税率1.4%」の式で計算します。課税標準額とは、市町村が決定する物置の評価額のことです。
この評価額は一般的に物置の購入価格を基準に算出され、自治体の判断によっては、実際の購入価格よりも低い金額(購入価格の70%~80%程度)で評価される場合もあります。
例えば30万円の物置を設置し、評価額が同じ30万円だった場合の固定資産税は、年間4,200円(30万円 ✕ 1.4%)です。このように、固定資産税の計算自体はシンプルですが、実際の税額は自治体が決定する評価額によって変動します。
支払う税金の目安
ここでは、支払う固定資産税の目安を、物置の価格別に一覧で紹介します。以下の表を参考に、検討している物置の価格と照らし合わせて、おおよその税額を把握しましょう。また、設置場所が市街化区域内の場合は、固定資産税に加えて都市計画税(税率0.3%)が課税されます。
| 物置の購入価格 | 固定資産税 (年額) |
都市計画税 (年額) |
|---|---|---|
| 10万円 | 1,400円 | 300円 |
| 20万円 | 2,800円 | 600円 |
| 30万円 | 4,200円 | 900円 |
| 50万円 | 7,000円 | 1,500円 |
| 80万円 | 11,200円 | 2,400円 |
| 100万円 | 14,000円 | 3,000円 |
ただし、自治体が決定する評価額によって固定資産税は変動するため、この表はあくまで目安として参考にしてください。
物置を設置するときに建築確認申請の手続きが必要なケース

固定資産税の課税対象となるような物置を設置する際に、建築確認申請の手続きが必要になる場合があります。建築確認申請とは、工事の前に建築物が建築基準法に適合しているかを確認する手続きのことです。
建築確認申請を怠ると法律違反になる可能性もあるため、どのケースで申請が必要かしっかりと把握しておきましょう。
床面積が10平方メートルを超えるケース
床面積が10平方メートル(約6畳)を超える物置を設置する場合は、原則として建築確認申請が必要です。ある程度の規模を持つ建築物は、安全性などを法律に沿って事前にチェックする必要があるためです。
ただし、これはあくまで建築物として扱われる場合の話です。コンクリートブロックのうえに置いただけのような、土地に定着していない物置であれば、たとえ10平方メートルを超えても建築物とは見なされず、建築確認申請は不要となります。
防火地域または準防火地域に設置するケース
防火地域または準防火地域に物置を設置する場合は、面積に関わらず建築確認申請が必要です。防火地域・準防火地域は、駅周辺の市街地や幹線道路沿いなど、火災のリスクが高いエリアに指定されており、万が一の火災時に被害が拡大しないよう、建築物に厳しい防火性能が求められます。
そのため、たとえ床面積が10平方メートル以下の小さな物置でも、法律に適合した燃えにくい構造であるかを事前に審査しなければなりません。防火地域・準防火地域が指定されているエリアは、自治体のホームページや都市計画課などの窓口で確認できます。
以下の記事では、建築確認申請の流れや必要なタイミング、通知書を紛失した場合の対処法を解説しています。詳しく知りたい方は参考にしてください。
物置の固定資産税に対する減税措置

物置が固定資産税の課税対象になった場合でも、減税措置が用意されています。ここでは、代表的な2つの減税措置を紹介します。
新築住宅に対する減税
新築住宅に対する減税とは、住宅を新築してから一定期間、家屋の固定資産税が2分の1に減額される制度です。新築住宅を建てた際、物置が「住宅に付属した建物」と見なされた場合に、この減税措置が受けられます。
減税期間は一般的な住宅で3年間、長期優良住宅の場合は5年間です。家を新築するタイミングで物置の設置を考えているのであれば、この制度を活用できないか施工会社に確認してみましょう。
出典:国土交通省「認定長期優良住宅に対する税の特例(所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税)」
免税点以下の小屋
免税点以下の小屋、つまり評価額が低い物置は、固定資産税が課税されません。固定資産税には、免税点の制度があります。同じ市町村内に所有する固定資産の課税標準額の合計が一定額に満たない場合、税金がかからない仕組みになっています。
家屋の場合、この免税点は20万円です。つまり、物置の評価額が20万円未満で、かつ同じ市町村内に他の家屋を所有していない場合は、固定資産税は発生しません。家屋を所有しておらず、固定資産税の支払いを避けたい場合は、免税点以下の物置を購入するとよいでしょう。
物置をこっそり設置してもばれる?固定資産税はどうなる?

課税対象となる物置を申告せずに設置しても、いずれ発覚する可能性は高いでしょう。自治体は、固定資産税を正しく課税するために、職員による現地調査や航空写真を定期的に確認して、新しく建てられた建物を常に把握しています。
もし無申告が発覚した場合、物置を設置した年にさかのぼって固定資産税を請求されます。例えば、5年後に見つかると5年分の税金をまとめて支払わなければなりません。さらに、本来の納付期限を過ぎているため、ペナルティとして延滞金も上乗せされます。
結局、本来より多くの税金を払うことになるため、課税対象の物置は正しく申告しましょう。
まとめ
最後に、物置にかかる固定資産税についてポイントをおさらいしましょう。
物置に固定資産税はかかるの?
物置に固定資産税は、かかる場合とかからない場合があります。設置した物置が法律で定める家屋の条件を満たすケースでのみ、課税対象となります。
例えば、コンクリートで基礎を造り、アンカーボルトで物置本体を固定している場合は課税対象となる可能性が高いでしょう。このように、課税されるかどうかは物置の仕様や設置方法によって異なります。
物置が固定資産税の対象となる条件とは?
物置が課税対象となる条件は、次の3つを満たした場合です。
- 土地への定着性
- 外気遮断性
- 用途性
物置が基礎工事などで地面にしっかり固定されていて、中が外部の気候から遮断されている状態で、物置として使える状態であれば、固定資産税の課税対象となります。
物置に固定資産税がかからないケースは?
物置に固定資産税がかからないのは、以下の4つのケースです。
- 基礎工事がされていない
- 恒久的に設置しない
- 電気設備が付いていない
- 床面積が4平方メートル以下
物置が上記のいずれかに当てはまっている場合は、固定資産税の対象外になる可能性が高いでしょう。
物置を設置する際、固定資産税がかかるかどうかの判断が難しく、知らないとペナルティを受けるリスクがあります。しかし、課税される条件をあらかじめ理解しておけば、設置方法を工夫して節税することも可能です。この記事を参考に、自身の状況に合う物置を選びましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる







