【実例あり】注文住宅に防音室を設置するには?防音室のメリット・デメリットと注意点を解説

本記事では防音室を注文住宅に設ける際のメリットやデメリット、注意点、費用などについて、実例を交えて詳しく解説します。
記事の目次
防音室とは?

防音室とは、壁や床に防音材や吸音材を施し、防音性や遮音性を高めた部屋のことです。楽器演奏や映画鑑賞、テレワークなど用途に応じて音響対策をとることで音を低減させられます。
防音室は、予算やライフスタイルに見合った設備を選ぶことが重要です。部屋全体を防音室にするものや組立式の簡易的なものまで、さまざまなタイプがあることを知っておきましょう。
防音室の種類
防音室には大きく分けて2種類あります。それぞれどのような特徴があるのか説明します。
組立式防音室(ユニット式簡易防音室)

「組立式防音室」とは、あらかじめ用意された部品を組み立てて、家の中のスペースに設置するタイプです。「ユニット式簡易防音室」とも呼ばれており、吸音材や遮音材などで構成されています。
狭いスペースでも防音性の高い部屋を作ることができ、短時間で解体や再組立が可能なので、引越し時に移設できるものも存在します。また、工事音が発生しないため、近隣に迷惑をかけずに組み立てられます。自宅での楽器演奏に適しているのはもちろん、テレワークや動画配信などの際にも便利です。
フルオーダー式防音室

フルオーダー式防音室は、1室まるごと防音室にするタイプです。注文住宅の場合、新築時に設置することができます。自由度が高く、使い心地のよい空間を目指せて、デッドスペースを少なくできるのが特徴です。より高い防音性を求めつつ、音の響きをよりよくしたい場合におすすめです。
防音室の設置時に押さえておきたい「遮音等級」とは?

遮音等級とは、建物の遮音性能を表す数値のことで、建物がどのくらいの騒音を遮断できるかを示しており、D値またはDr値といいます。例えばピアノ、ギター、ドラム、シアタールームの音の大きさは、それぞれ90~110dB(デシベル)、80~95dB、100~130dB、90dB~100dBです。90~110dBは地下鉄の騒音と変わらないといわれているので、想像以上に楽器の音は大きいことがわかります。
防音室を設置する際の遮音性能の目安として、ピアノとシアタールームの場合は遮音等級がD-60〜D-65、ギターならD-70 、ドラムならD-85であることが理想です。なお、これらは一般的な数値で、子ども、大人、プロなどによっても多少の違いがあります。
注文住宅を建築する際には、ハウスメーカーや工務店の担当者に相談しながらどのくらいの遮音性能を取り入れるのか検討してみましょう。
| 遮音 等級 |
ピアノ・ステレオ等の大きい音 | TV、会話などの 一般発生音 |
|---|---|---|
| D-65 | 通常では聞こえない | 聞こえない |
| D-60 | ほとんど聞こえない | 聞こえない |
| D-55 | かすかに聞こえる | 通常では聞こえない |
| D-50 | 小さく聞こえる | ほとんど聞こえない |
| D-45 | かなり聞こえる | かすかに聞こえる |
| D-40 | 曲がはっきりわかる | 小さく聞こえる |
| D-35 | よく聞こえる | かなり聞こえる |
| D-30 | 大変よく聞こえる | 話の内容がわかる |
| D-25 | うるさい | はっきり内容がわかる |
| D-20 | かなりうるさい | よく聞こえる |
| D-15 | 大変うるさい | つつぬけ状態 |
表を参考に、必要な遮音等級を検討しましょう。なお、防音室の用途や住宅の周辺環境などによっても、適切な遮音等級は変化するため注意が必要です。
注文住宅に防音室をつくる費用はどのくらい?

注文住宅に防音室を設置するうえでの費用相場は、1坪あたり100万円以上。ただし、部屋の広さや防音性能、使用する素材などによって異なります。組立式防音室なら1坪あたり50万円程度で導入できるため、フルオーダー式は倍以上の費用がかかると考えておきましょう。
以下は、防音室の用途と広さに必要な費用の相場です。
| 4畳 | 5畳 | 7畳 | 9畳 | 10畳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| オーディオ・シアタールーム・ピアノ | 230万円 | 250万円 | 280万円 | 310万円 | 350万円 |
| エレキギター・管楽器 | 316万円 | 351万円 | 380万円 | 393万円 | 432万円 |
| ドラム | 594万円 | 630万円 | 696万円 | 770万円 | 820万円 |
表に記した費用はあくまでも目安です。実際の検討時には、ハウスメーカーや工務店に相談をして見積もりを出してもらうことをおすすめします。
注文住宅の防音室のメリット

注文住宅で防音室を設置すると、さまざまなメリットが得られます。どのようなメリットが存在するのか、以下で具体的に見ていきましょう。
時間帯を気にせず音楽や映画を楽しめる
防音室があれば、時間を気にせず音楽鑑賞や映画鑑賞を楽しめます。例えば、夜中に映画を見たくなってもボリュームを落とさず楽しむことができるので、家族や近隣に迷惑をかけることなく映画に没入できます。自宅に防音室があることによって時間帯問わず、いつでも自分の趣味に没頭できるでしょう。
臨場感がある音を楽しめる
防音室をシアタールームやオーディオルームとして利用すれば、映画館やコンサート会場のような臨場感ある音を味わうことができます。スピーカーの配置など音響にこだわった設計をおこない、家族や友人とコンサート映像を観賞するのもよいでしょう。
近隣トラブルを防げる
しっかりと防音された部屋を設けることで、近隣への音漏れを軽減し、騒音による近隣トラブルを防げます。
騒音などによるご近所トラブルは深刻になるケースもあるため、楽器演奏など大きな音が出ることが予想される場合は、防音室を設置することで安心して暮らせるようになるでしょう。
勉強部屋など用途が幅広い
防音室は、楽器を使うスタジオや映画・音楽鑑賞を楽しむシアタールームとしてだけでなく、勉強やリモートワークはもちろん、配信部屋やゲーム部屋など幅広く活用できます。
音を出す場合に使うイメージが強い防音室ですが、逆に外からの音を防ぐため、仕事や勉強に集中できるスペースとしても使えるでしょう。
また、近年自宅で動画配信やライブストリーミングをおこなう方も増えています。その際、重要になるのが配信環境。このような場合にも防音室が活用できます。
スタジオ費用を節約できる
注文住宅を建てる際に防音室をつくることで、レンタルスタジオを借りる費用や手間も省けるようになります。また、スタジオに行く時間も必要ないので、好きなタイミングで趣味活動やレッスンが実現できるでしょう。
注文住宅の防音室のデメリット

防音室をつくることで、さまざまなメリットを享受できる一方で、次のようなデメリットもあります。きちんとデメリットも把握し、対策を考えておくことが大切です。
土地の広さが必要である
ある程度の土地の広さがないと、注文住宅で防音室をつくる余裕がない可能性があります。土地探しの際は、検討している防音室に対して十分な広さかがあるかどうか、そもそもその土地で注文住宅を建てて防音室を設置できるかなどを確認したほうがよいでしょう。
居住スペースや収納スペースが狭くなる
注文住宅を建てる際に、フルオーダー式で防音室を1部屋つくると、居住スペースや収納場所など生活スペースが狭くなる場合があります。廊下をなくしたりデッドスペースを有効活用したりと、効率のよいアイデアを取り入れることが重要です。
将来使わなくなる可能性がある
フルオーダー式防音室の場合は、将来の使い道も考慮しておきましょう。例えば、子どもの習い事や趣味のために防音室を作った場合、子どもが巣立ったあとに使われなくなることも。柔軟に用途を変更できるよう、将来的に生活スタイルがどのように変化するのか考慮しながら、計画を立てて設計することを意識しましょう。
費用がかかる
防音室の費用相場は仕様によって異なりますが、防音や遮音性を高めれば防音室の設置に必要な費用はその分高額になるでしょう。また、防音室は専用の換気システムや空調などの設備費もかかります。
防音室を設置する目的や用途、予算に合わせてしっかりと検討しましょう。
注文住宅に防音室をつくる時の注意点

注文住宅に防音室をつくるうえで、注意すべきポイントを紹介します。せっかくの注文住宅で失敗を防ぐためのポイントを、事前に確認しておきましょう。
用途を明確にする
防音室の用途や使用時間帯に応じて、必要な防音性能や対策が異なります。そのため、用途を明確にし、音楽鑑賞や楽器演奏、リモートワークなど目的に合った防音設計を考えましょう。また、ライフスタイルの変化も見据えておくことも大切です。
防音室をつくる際に関わる法律がある
防音室の設計や工事においては、建築基準法や消防法などの法令を遵守する必要があります。そのため、希望どおりに造作できない可能性があることを理解し、事前に関連法規を確認しておきましょう。
建築基準法
建築基準法は、住宅やビルなどの建物に必要な基準を定めた法律です。建物の安全を守り、住民や利用者の生命、健康、財産を保護することを目的としています。建築基準法では、居室には採光と換気のための窓を設けなければならないとしています。
防音室が「居室」に該当するかどうかが判断のポイントです。居室とは、「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」を指します。防音室は、音を遮断する目的の部屋であり、窓の設置が必須ではない場合もあります。しかし、楽器演奏や娯楽、集会の目的でも使われる場合は、窓の設置が必要になることを覚えておきましょう。
窓を設置する場合は、開口部があるため防音性能が低くなりやすいため、窓を二重サッシにしたり、ガラスが厚いものを選ぶなど対策をしましょう。
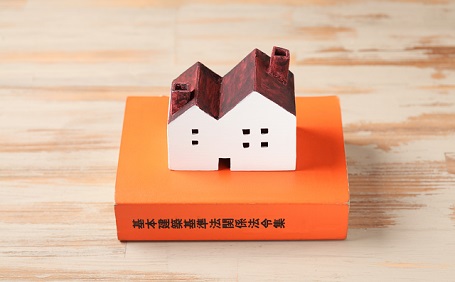
- 2025年の建築基準法改正、変更点と影響は?重要なポイントを解説
- 建物を建築する際には、建築基準法の内容を守らなければなりません。その守るべき法律が、2025年に改正されます。これから家を
続きを読む

消防法
消防法は、火災の予防や被害を最小限に抑えるために必要な対策を定めた法律です。この法律では、建物の防火や消防に関する規制を設け、火災の予防、警戒、鎮圧、そして災害時の傷病者搬送が適切におこなわれることを目指しています。そのため防音室には火災報知器を設置しなければなりません。また、防音室内からは外部の音が聞こえにくいため、警報音に気付きにくい可能性があり、視覚的に警報が鳴っていることがわかる仕様のものを選ぶことをおすすめします。
防音室の実績があるハウスメーカー・工務店を選ぶ
防音室を快適な空間にするためには、防音室の実績があるハウスメーカーや工務店を選ぶことが重要です。
用途ごとに適切な防音対策が異なるため、施工実績がある会社に相談することで、適切なアドバイスや間取りの提案を受けることができるでしょう。
建具も防音性を考慮する
建具によっても防音性の高低に差があります。例えば防音扉は、主に鋼製と木製の2種類です。鋼製の防音扉はより高い防音性能を持ち、外部の音をしっかり遮断したい場合に適しています。一方、木製の扉は鋼製より軽く取り扱いやすいため、設置が比較的簡単です。また、木製はインテリアに溶け込みやすいのも特徴。また、設置する窓の性能によっても防音性が左右されるため、窓の種類や厚さなども検討しましょう。それぞれの特性を考慮して、用途に合った扉を選んでください。
重量と搬入経路を確認する
2階に防音室を設置する場合、床・壁・天井を二重構造にして防音対策を施す必要があります。特に木造の2階では、防音室の重みに耐えられるかどうか、正確な重量計算が求められます。また、グランドピアノなどの重い楽器を置く際はクレーンを使用し搬入することがあるため、搬入経路や費用を事前に確認しておくことが大切です。設計前にしっかりと計画を立てましょう。
開放感や快適性も考慮する

防音室は広さや性能だけでなく、デザイン性や快適な空調にもこだわりましょう。防音室が圧迫感を与えたり、居心地が悪かったりすると、せっかくつくった空間でも使いたくなくなってしまいます。開放感のあるおしゃれなデザインや、音漏れを防ぎながらも十分な換気ができる仕組みを整えることがポイントです。
換気経路を確保する
防音室は密閉された空間になるため、酸欠になる恐れや湿気、においがこもるリスクがあります。そのため、換気システムの設置が必須です。そこで、空気を循環させつつ音が伝わらないようにするために、防音室専用の換気システムを導入しましょう。これにより、快適な環境を保ちながら、音漏れを防げます。
エアコン・火災報知器は必ず設置する
防音室は気密性が高いので、換気システムと同様にエアコンも必須です。特に夏は熱や湿気がこもり、熱中症になる危険性も。また、夏や梅雨時の防音室は、楽器やパソコンなどの保管にも不向きなため、エアコンを設置し適切な室温・湿度管理ができるようにしておきましょう。
また、防音室内ではインターホンや火災報知器の音が聞こえにくいため、通知に気づく仕様のものを導入することも大切です。音での通知だけでなく、視覚的に知らせてくれるランプ点滅なども検討するとよいでしょう。
防音性能は引渡し前に確認する
防音室の防音性能は、必ず引渡し前に確認します。引渡し後は不満や気になる箇所があっても、直してもらえない可能性があるため注意が必要です。
参考にしたい防音室の実例6選
防音室の実例を用途別に6つ紹介します。注文住宅に防音室を設置することを考える際に、ぜひ参考にしてみてください。
防音室のある木造3階建ての家

楽器演奏やワークスペースとして活用できるよう施した、プレミアム仕様の防音室です。子どもの習い事や、リモートワークにも適した防音仕様となっています。遮音性能は50dBで、外部への音漏れを気にせずに演奏したりスピーカー音を上げたりできます。
おうち時間が充実&楽しくなる家

音楽や映画を気兼ねなく楽しめるシンプルな、防音室。防音性のあるドアを採用しているため、より快適な空間を実現しています。また、愛犬の部屋としても防音室を活用することができ、吠えても安心です。
防音スタジオのある家

夜中でも音を出せる空間がコンセプトの、防音性抜群のスタジオです。カラオケやドラム演奏も可能です。機能面だけでなく内装のデザインも趣味や仕事に没頭できるようなシックでシンプルな雰囲気になっています。
【ピアノ教室】心地よい音楽が聞こえてくる住まい【防音】

防音設備を強化したピアノ室の実例。壁は二重構造にして防音シートを施工、さらに空調や吸排気を独立させ、快適にレッスンができる環境を整えました。また、ピアノ室は玄関からアクセスしやすい位置に配置し、生徒がすぐに入れるように配慮されています。
BBQやビリヤード、映画鑑賞など、趣味があつまった部屋

家族や友人などが集まってカラオケを楽しめるカラオケルームです。無垢材の床や空間に合わせて素材から選んだ造作のソファをしつらえた、こだわりの空間になっています。
バーカウンターとライブラリーを実現!趣味人夫妻の住まい

ご主人のためにつくられた、防音性の高い趣味部屋です。以前は賃貸マンション暮らしだったため、音楽スタジオで練習していたそう。しかし、防音室を設けたことで、気兼ねなく楽器演奏ができるようになりました。
まとめ
注文住宅に防音室を設けることは、家庭内の音を外に漏らさず、また外部の音を低減するために非常に効果的な選択肢です。防音室は楽器演奏やテレワーク、配信活動など、さまざまな用途に合わせた音響対策が可能であり、家庭内での快適な空間づくりに役立つでしょう。
ただし、設置にあたっては費用やスペース、法的な要件に注意を払いながら、機能的に設置することが重要です。近隣との騒音トラブルを防ぎたい、家で音楽や映画を存分に楽しみたい場合は、ぜひこの記事を参考に防音室の導入を検討してみてください。
注文住宅を建てる





