旗竿地とは?メリット・デメリット、後悔しないための注意点をわかりやすく解説

本記事では、旗竿地の概要やメリット・デメリット、注意点を詳しく解説します。旗竿地の理解を深めて、理想の住宅計画を立てられるようにしましょう。
記事の目次
旗竿地とは?

旗竿地とは、道路に接する部分が細長い路地になっており、その奥に住宅を建てるための敷地が広がっている土地形状のことです。竿(路地部分)に付けた旗(奥の敷地部分)のような形をしていることから、旗竿地と呼ばれるようになりました。
以下のような別称もあります。
- 旗竿敷地
- 路地状敷地
- 敷地延長
また、旗竿地は不整形地の一つで、住宅が密集しやすい都市部に多く見られるのが特徴です。四角形で平らな土地は整形地とされる一方で、その他は不整形地と呼ばれます。
旗竿地が生まれる理由

旗竿地は整形地と比較すると形状がいびつなため、扱いづらい部分があります。ここでは、なぜ旗竿地が生まれるのかを見ていきましょう。
土地の分筆問題があるため
分筆することが、旗竿地の生まれる理由です。分筆とは、一つの大きな土地を複数の土地に分割し、それぞれ独立した土地として登記する手続きのことをいいます。
大きな土地をそのまま販売すると高額になり購入者が限られるので、分筆によって土地価格を抑えなければなりません。また、土地を縦に分割すると各区画の間口が狭くなって家を建てづらくなるため、一部を旗竿地にする必要があります。
接道義務を守るため
接道義務を守らなければならないことも、旗竿地が生まれる理由です。接道義務とは、幅員4m以上の道路に対して、敷地が2m以上接していなければならない法律のことを指します。
敷地が道路から離れている場合は家を建てられないため、路地を設けて道路に接しておかなければなりません。また、接している部分だけでなく、路地部分すべての幅が2m以上必要です。
旗竿地のメリット

旗竿地は不整形地のために悪いイメージを持つ方もいるかもしれませんが、実際には利点も多く見られます。ここでは、旗竿地のメリットを5つ見ていきましょう。
土地の価格・税金が近隣に比べて安い
旗竿地は四角形で平らな整形地と比較すると、土地価格が安い傾向にあります。旗竿地は不整形地とされ、一般的な整形地よりも評価が低くなりやすいためです。
また、土地の評価額が低い場合は、固定資産税や都市計画税も抑えられます。近隣の土地と比べて安く購入できるのは、旗竿地の最大のメリットではないでしょうか。
道路から離れているためプライバシー性が高い
旗竿地は住宅となる部分が道路と離れているため、プライバシー性が高いのもメリットの一つです。
道路に面していれば、通行人の視線が気になるもの。人通りが多い場合は、カーテンさえも開けられないかもしれません。旗竿地はプライバシー性が高く、落ち着いた生活環境を手に入れやすいでしょう。
騒音や事故の心配が少ない
旗竿地は道路から距離があるため、騒音や交通事故の心配が少ない点もメリットです。車の走行音や通行人の話し声が届きにくくなり、落ち着いた生活環境を得られるでしょう。
また、急に玄関から飛び出しても道路まで距離があるため、事故のリスクが低く、安心できます。子育て世帯にとって、安全な環境で生活できるのはメリットです。
路地部分を活かした間取り・デザインをしやすい
路地部分を有効活用すれば、機能的でおしゃれな空間を作れます。
例えば、駐車スペースとして活用すれば、奥の敷地いっぱいに建物を建てられます。照明や植栽などをうまく使えば、おしゃれなアプローチも作れるでしょう。
延べ床面積が広く取れ、大きな家を建てられる可能性あり
旗竿地に家を建てる場合、延べ床面積を広く取れる可能性があります。建ぺい率や容積率によって、敷地面積に対して建てられる建物の面積は上限が決められています。
例えば、敷地面積が100平方メートルで建ぺい率が60%の場合、建築面積の上限は60平方メートル、容積率が150%の場合は、延床面積の上限が150平方メートルです。
路地部分は敷地面積に含まれるため、奥の敷地と近隣の整形地が同じ面積の場合は、旗竿地のほうが建築面積や延べ床面積の上限が広くなります。その結果、整形地よりも大きな家を建てられる可能性が高まります。
旗竿地のデメリット
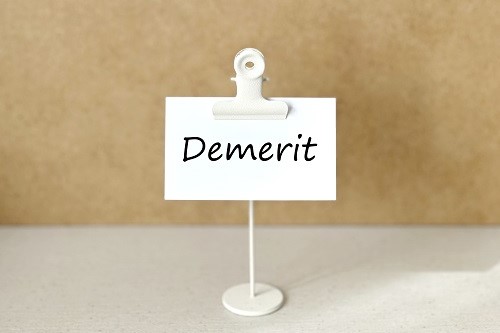
旗竿地を検討する際は、路地部分があることによるデメリットも考慮しておかなければなりません。ここでは、6つのデメリットを解説します。
建築・解体コストが高くなりやすい
旗竿地は、整形地と比較して建築・解体コストが高くなりやすいでしょう。路地部分の工事では、隣家との境界にフェンスを設置したり広範囲のコンクリート工事が必要になったりします。
また、路地が狭ければ大型重機が入れず、建築や解体で人手による作業が増えることでコストアップにつながることもあります。
建築・解体コストが高くなりやすいのは、旗竿地のデメリットです。
日当たり・風通しを確保しづらい
旗竿地は建物に囲まれていることが多いため、日当たりや風通しを確保しづらい傾向にあります。日当たりや風通しが悪ければ夏は熱く冬は寒くなるため、過ごしづらい家になるでしょう。
旗竿地に家を建てる場合は、採光や通風を取り入れられるような間取りにしなければならないため、建築プランが制限されることもデメリットです。
デッドスペースが生まれやすい
路地部分が狭い場合は活用が難しく、デッドスペースが生まれやすくなります。
うまく活用できなければ、玄関までのただの通路になる可能性があります。路地部分の広さによって有効活用ができないのは、旗竿地のデメリットです。
駐車スペースの幅が制限されやすい
路地部分の幅が狭い場合、駐車スペースが制限されやすいでしょう。例えば、路地部分が2mしかない場合、軽自動車でも乗り降りがやっとできるくらいです。
普通車だと幅が1.7m前後あるため、乗り降りは難しいでしょう。また、車が2台以上ある場合は縦列駐車になるため、出し入れに手間がかかるのもデメリットです。
防犯上の不安が生じることも
道路から奥まった場所に家があるためプライバシー性を高められる一方で、空き巣・泥棒など防犯上のリスクもあります。カメラを設置したりインターホン・門扉を道路側に設置したりするなどの防犯対策が必要になるでしょう。
資産価値の評価が低くなる可能性もあり
旗竿地は不整形地として評価されるため、資産価値が低くなる可能性があります。
デッドスペースの多さは、土地の評価を下げる要因の一つです。将来売却を考えている場合は、整形地と比較して価格面で不利になりやすいでしょう。
旗竿地を選んで後悔しないための注意点

旗竿地は価格の安さやプライバシー性の高さが魅力ですが、購入前に土地の寸法などを調べておかなければあとで後悔することもあります。
そこで、ここでは旗竿地を選んで後悔しないための注意点を4つ紹介します。
路地部分の幅・奥行を調べる
旗竿地を購入する前は、路地部分の幅と奥行を調べましょう。
前述のとおり、建築基準法の接道義務によって路地の幅が2mに満たない場合は、家を建てられません。奥行によっては、さらに幅を広くとらなければならないケースもあります。
また、車を駐車する場合は、乗り降りを考慮すると最低でも幅2.5m、可能であれば3m以上は必要です。
2台駐車する場合は、奥行も確認しておきましょう。15mほど確保できれば、縦列駐車でも余裕を持って停められます。
工事の車両・重機が入るスペースがあるか確認する
クレーンやショベルカーなど、工事車両や重機が入るスペースがあるかも確認しておかなければなりません。
重機が入れなければ人手による作業が増えるため、建築費用がかさむ可能性があります。
また、建築資材の搬入経路としても十分な幅が必要なため、工務店やハウスメーカーに相談しながら進めていきましょう。
電気・水道の引き込みの有無をチェックする
電気や水道の引き込みの有無で工事費が大きく違ってくるため、土地を購入する前にチェックしておきましょう。水道の引き込みがない場合、路地部分が長くなるほど費用がかかってしまいます。
また、水道メーターの位置によっても配管の長さが変わるため、引き込みの有無と同時に確認したほうがよいでしょう。
電線や水道管が隣接地を通っていて引き込むのが難しい場合は、敷地内に支柱を立てたり地中に通したりする手間が発生し、工事費が高額になる恐れがあります。
想定外の出費を抑えるためにも、旗竿地を選ぶ際は電気や水道の引き込みの有無を確認しておきましょう。
再建築不可かどうかを確認する
中古物件つきの旗竿地は、再建築不可として販売されているケースがあります。再建築不可の場合、既存の建物を解体しても新たに家を建てられません。
建築基準法ができる前に建てられた住宅は接道義務がなかったので、路地幅が2m未満でも建築が可能でした。現在は接道義務を満たさなければならないため、路地幅が2m未満の旗竿地を購入しても家を建てられません。
建築基準法ができる以前の住宅は再建築不可のケースも少なくないので、購入前に確認しておきましょう。
旗竿地のデメリットを解消する建築プラン例

旗竿地のデメリットは、建築プランで解消できる可能性があります。ここでは、旗竿地におすすめの建築プラン例を3つ紹介するので、ぜひ参考にしてください。
エクステリアアイテムを有効活用する
路地部分に照明や植栽などのエクステリアアイテムを取り入れることで、機能的でおしゃれな空間を演出できます。
例えば、シンボルツリーをスポットライトで照らしたり、アプローチに埋め込み式の照明を設置したり。照明は防犯対策としても有効なため、路地部分に取り入れるのがおすすめです。
中庭・吹き抜け・ベランダで採光・風通しの対策をする
日当たりや風通しを確保しづらい旗竿地では、中庭や吹き抜け、ベランダを活用して対策するのが有効です。
中庭や吹き抜けの高い位置に大きめの窓を設けることで、日当たりを確保できます。ベランダの掃き出し窓も採光対策として有効でしょう。また、空気のとおり道を意識して窓を配置すれば、風通しもよくなります。
路地部分を活かした工夫をする
路地部分を活かした工夫をすれば、整形地よりも快適に過ごせるかもしれません。
例えば、路地の道路側を駐車スペースとして、住宅側を庭として空間を分ければ自宅でアウトドアを楽しめます。また、車が2台ある場合は縦に駐車スペースの確保が可能です。
ほかにも、駐輪スペースとしての使用など生活スタイルに合わせて工夫するとよいでしょう。
旗竿地に関するまとめ
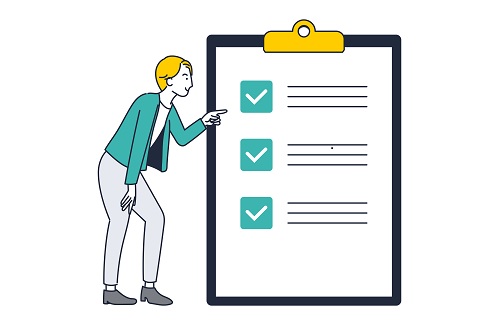
それでは、旗竿地に関してまとめていきます。
旗竿地とは?
道路に接する部分が細長い路地を竿、その奥に広がる敷地を旗として見立てたのが旗竿地です。四角形で平らな敷地は整形地とされる一方で、旗竿地は不整形地と呼ばれ、都市部に多く見られるのが特徴です。
旗竿地のメリット・デメリットは?
旗竿地は土地価格が整形地と比べて安く、道路から離れているためプライバシー性が高さや騒音の少なさなどのメリットがあります。一方で、建築・解体コストが高くなる可能性や日当たりの悪さ、防犯上のリスクなどがデメリットです。
旗竿地を購入する際の注意点は?
工事車両・重機のとおるスペースや駐車スペースを確保できるように、路地部分の幅や奥行を確認しておきましょう。また、想定外の出費を防ぐためにも、電気や水道の引き込みの有無もチェックしておくべきです。中古物件つきの旗竿地は再建築不可の可能性もあるため、接道要件を満たしているかなどの確認が必要です。
旗竿地は価格の安さからデメリットが注視されがちですが、路地部分の有効活用や採光の工夫などができれば心地よい住まいを実現できます。この記事を参考にして、理想の住宅計画を進めていきましょう。
注文住宅を建てる








