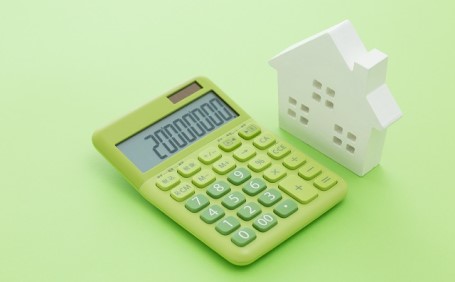土地ありで注文住宅を建てる流れは?相場と相続した土地に建てる注意点を解説

本記事では、土地がある状態で注文住宅を建てる際の基本的な手順、家づくりにかかる費用や注意点について解説します。すでにある土地を活かして注文住宅を建てたいと考えている方や、所有する土地の活用方法に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
記事の目次
土地がある場合の注文住宅を建てる流れ

すでに土地がある場合、土地探しの手順は不要です。エリアや周辺環境、敷地面積など立地条件は変えられないため、その土地に建てる住宅についてしっかり計画を練ることで、家族に合った最適なマイホームを実現できます。ここからは、土地がある場合の注文住宅を建てる一般的な流れを紹介します。主な手順は以下のとおりです。
- STEP 1どんな家にするかイメージする
- STEP 2住宅の予算を決める
- STEP 3ハウスメーカーを決める
- STEP 4住宅の設計プランを決定する
- STEP 5建築工事請負契約を結ぶ
- STEP 6住宅ローンの審査を進める
- STEP 7着工~引き渡し
ステップごとに、注文住宅を建てる流れを見ていきましょう。
STEP1:どんな家にするかイメージする
まずは、その土地にどのような住宅を建てたいのかをイメージすることが大切です。家族で話し合い、希望や条件を決めていきましょう。条件を決める際は、優先順位をつけることをおすすめします。例えば、使用頻度が高い箇所には機能のいい設備を取り入れる、「あったらいいな」と思う設備は必須ではなく後付けにすることを検討しましょう。
間取りにおいては、立地条件によって叶えられないものもあるかもしれません。希望や条件をある程度まとめて、おおまかなイメージを膨らませてから建築会社に相談するとよいでしょう。住宅のイメージがしにくい場合は、複数の建築会社のカタログを見たり、住宅展示場に見学に行ったりするのがおすすめです。
理想の家づくりをするためのポイントについては、以下の関連記事をご参照ください。
STEP2:住宅の予算を決める
おおまかな住宅のイメージができたら、次に予算を決めていきます。自己資金はいくら用意できるのか、両親から受けられる援助はいくらなのか、などを確認しておくことが大切です。また、住宅ローンを組む場合は借入可能額をあらかじめ把握しておくと、予算を決めやすくなります。年収に応じていくら借り入れができるのか、ローンシミュレーションを活用して調べてみましょう。自己資金や住宅ローンの借入金額を合わせたおおまかな予算を割り出し、金融機関や建築会社に相談して検討することをおすすめします。
注文住宅の予算ごとに必要なポイントは、以下の記事を参考にしてください。
STEP3:ハウスメーカーを決める
次に、実際に注文住宅を建ててもらう建築会社を決めなければなりません。建築会社は、全国展開しているハウスメーカーや地域密着型の工務店など豊富な選択肢があります。それぞれの特性を押さえたうえで、建築デザイン・性能や予算がイメージと合っているか、保証内容、担当者の提案力などを考慮し、複数社で比較検討して決めるのがおすすめです。カタログや公式ホームページで施工事例を見たり、口コミを確認したりすることでその会社の実績がわかります。建築会社は家づくりの大部分を担うことになるため、慎重に判断するようにしましょう。
STEP4:住宅の設計プランを決定する
建築会社が決まったら、住宅の設計プランを具体的に決めていきます。土地がすでに決まっている状態でのプラン決めなので、土地探しと同時進行で進めるプラン決めと比べて土地の条件に変更がないためスムーズです。プランを決める際は、建てたい住宅のイメージと予算を担当者に伝えたうえで、その土地で実現できる間取りをつくっていきましょう。希望がすべて叶えられるとは限りませんが、法令制限などによってできないことはあらかじめ担当者が教えてくれます。土地が決まっている分、時間をかけて詳細まで打合せをして、イメージを具現化していきましょう。
STEP5:建築工事請負契約を結ぶ
依頼する建築会社とプラン・金額が決まったら、建築会社と請負契約を締結します。契約時には着手金として建築費の10~20%程度支払うのが一般的です。この手順では、契約と同時にプラン内容に沿って建築確認申請や、後述する住宅ローンの審査をおこなったりします。
なお、請負契約締結後、より詳細なデザインや設備等のプランを決めるための打合せを重ねていきます。プランに変更があった場合は追加費用がかかったり、工期に遅れが出たりする可能性があるため注意が必要です。なかには建築確認の再申請が必要となるケースや、変更が認められないケースも出てくるため、変更可能な範囲をあらかじめ確認しておきましょう。
STEP6:住宅ローンの審査を進める
上述したとおり、建築工事の請負契約を締結したら、住宅ローンの審査を進めていきます。契約締結の前に、1~3日程度で結果が出る事前審査を済ませておくのが一般的です、事前審査が通って請負契約締結後、本審査を進めます。金融機関ごとに借入可能額や借入条件が異なるので、事前審査の結果をもって判断し、希望する金融機関で本審査をおこないましょう。本審査の結果が出るまでの期間は、2週間~1カ月程度が目安です。必要書類を揃えるなど、余裕を持ったスケジュールで進めていくことをおすすめします。
STEP7:着工~引き渡し
住宅ローンの審査に通って金融機関との契約を締結したら、いよいよ着工です。着工から竣工までは3~6カ月程度かかり、大きな音が出たり砂埃が舞ったりするなど近隣に迷惑をかけてしまう可能性があります。工事によるトラブルを避けるためには、事前挨拶を済ませておきましょう。建築会社の担当者だけでおこなってくれるケースもありますが、できるだけ施主も同行することをおすすめします。また、着工前に地鎮祭、工事途中に上棟式をおこなうケースもあるので、あらかじめスケジュールに組み込んでおきましょう。
建物が完成したら、完了検査をしたうえで融資実行と建物の引き渡しをおこないます。
土地がある場合の注文住宅の相場
土地がある場合、注文住宅を建てるのにかかる費用は、実質建築費のみです。以下は「2023年度 フラット35利用者調査」による、建築費のみの融資利用金額の平均です。
| 地域 | 建築費 |
|---|---|
| 全国 | 3,861.1万円 |
| 首都圏 | 4,190.2万円 |
| 近畿圏 | 4,142.1万円 |
| 東海圏 | 3,893.4万円 |
| その他地域 | 3,623.8万円 |
注文住宅を建てる際にかかる建築費は、およそ4,000万円前後であることを表しています。建築費は「本体工事費」「別途工事費」「諸経費」の3つに分けられ、それぞれの費用の詳細は以下のとおりです。
- 本体工事費・・・建築工事費(木工事、仮設工事、基礎工事、内外装工事、設備の設置工事、空調工事など)
- 別途工事費・・・外構工事費、インフラ工事費、設備の取り付け工事費、解体工事費、地盤改良工事費など
- 諸経費・・・印紙代、登記費用、ローン諸費用、保険料、税金など
本体工事費が建築費全体の75%、別途工事費が15%、諸経費が10%程度と考えておくとよいでしょう。注文住宅を建てる際の費用相場の詳細や、予算を決めるポイントなどは以下の関連記事を参考にしてください。
相続した土地に注文住宅を建てる際の注意点

土地を相続した場合、賃貸経営をするためやマイホームを建てるために土地活用するケースがあります。ここでは土地ありで注文住宅を建てるケースにフォーカスし、相続時にどのような点に注意すべきかについて、以下で詳しく解説していきます。
相続登記の手続きが必要
土地を相続した時点では土地の所有者が登記上で被相続人となっているため、相続登記の手続きが必要です。相続人が所有者とならなければ、土地の売買以外にも土地上に建物を建てることもできません。また、相続人が複数いる場合は、相続人全員の合意がなければ手続きを進められないため、円滑な話し合いが必要です。必ずしも全員の合意をスムーズに取れるとは限らないので、相続が発生した早いタイミングから遺産分割の話し合いをおこなうようにしましょう。相続登記の際は、一般的に司法書士に依頼するため登記費用と司法書士報酬が必要です。
贈与税または相続税がかかる
土地を贈与によって譲り受けた場合は贈与税、相続した場合は相続税がかかります。新たな所有者になる前の土地の所有者が生きている間に財産を渡すのか、亡くなってから引き継がれるのかで税金が変わります。それぞれ税額は課税価格×税率で算出されますが、基礎控除の利用が可能です。節税対策を考えて贈与・相続するケースもありますが、一般的にはある程度の税金がかかることを考慮しておくことをおすすめします。条件に応じて税金を安く抑える方法もあるので、あらかじめ調べておきましょう。
建物がある場合、解体費がかかる
注文住宅を建てる土地に古家が残っている場合は、建物の解体費用も予算に入れる必要があります。解体費用は、一般的な木造住宅の広さであれば100万円前後です。古家の築年数の経過が著しいと、地中埋設物がある可能性も考えられます。建物を建築中に埋設物が発見された場合、スケジュールの遅延や追加コストがかかる可能性があるほか、地盤の強度に影響を与える可能性もあります。地盤調査も含め、その土地に建物を建てるのが問題ないかをあらかじめ確認しておくことが大切です。
登記情報や敷地条件を確認する
土地を相続した場合、登記情報や敷地条件を確認しておきましょう。登記情報で確認すべきポイントは以下のとおりです。
- 地目
- 土地面積
- 所有権
- 抵当権設定の有無
- 境界線の明示の有無
次に、敷地条件は以下のポイントを確認する必要があります。
- 接道方位
- 日当たり
- 風通し
- 地盤の安全性
- 隣家の影・視線
- ライフラインの有無
条件次第では希望どおりに仕上がらない可能性があります。住宅を建てるうえで重要な項目ばかりなので、確認してから建築に進めるようにしましょう。
地盤をチェックする
先述のとおり、築年数の古い建物が建っている土地やしばらく使われていなかった土地を相続した場合、安全性のチェックのためにも地盤調査をおこなう必要があります。地盤調査の結果、地盤改良工事が必要となるケースもあるので、追加コストや期間を要することも考慮しておきましょう。地盤調査に加え、同様の土地には隣地との境界線が不明瞭なケースも度々見られます。確認したうえで境界が未確定の場合は、土地家屋調査士に依頼をして早めに境界確定の手続きを進めてもらいましょう。
少しでも安く家を建てたいなら「ローコスト住宅」の選択も

全体の予算を抑えて注文住宅を建てる場合、すでに土地があるのであれば建築費を抑える方法が有効です。しかし、建築費を抑えるには希望条件を妥協したり、延床面積を減らしたりするなど生活環境に大きく影響する方法を選ばざるを得ません。少しでも安く住宅を建てるのであれば、ローコスト住宅の選択も一つの方法です。
ローコスト住宅とは、比較的低い建築コストで建築できる住宅を指します。一般的には坪単価40万円程度で、建築費が全体で1,000万~2,000万円程度に収まります。ローコスト住宅は人件費や材料費、広告費の削減などによってその安さを実現していますが、間取りやデザインの自由度が低くなったり、住宅性能が低くなったりする可能性は否めません。安さだけを重視するのではなく、住宅のどのような点にこだわりがあるのか、アフターサービスなどの保証内容が充実しているか、などをあらかじめ確認して決めるようにしましょう。
まとめ
本記事では、土地がある場合の注文住宅を建てる流れや費用相場、注意点などについて解説しました。注文住宅を検討する中ですでに土地がある場合とない場合は、手順が変わるだけでなく全体にかかる期間やスムーズさも異なります。相続などによって取得した土地がある場合は、注意点も押さえたうえでマイホームづくりを検討してみましょう。
注文住宅を建てる