手すりの高さは何cmがベスト?用途・場所別に徹底解説

本記事では、手すりの一般的な高さや設置すべき場所について解説します。手すりを設置する手順も紹介しますので、記事を参考に効果的な位置に手すりを設置しましょう。
記事の目次
手すりの種類は大きく分けて2種類

手すりは歩行や立ち座りなど日常生活の行動を介助する福祉用具で、大きく以下2つの種類に分けられます。
- 歩行補助手すり
- 動作補助手すり
歩行補助手すり
歩行補助手すりとは、連続した長い手すりです。移動しながら手を滑らせて使えるため、室内でも長距離の移動が必要な場所に設置されます。主に、廊下や階段などに設置される補助用具です。
動作補助手すり
動作補助手すりとは、座る、立つなど一定の動作を補助する手すりです。座る、立つという動作をスムーズにおこなうための補助用具であり、上下運動が必要な場所に設置されます。主に浴室やトイレ、玄関に設置される縦型(I型)やL型の手すりが一般的です。
一般的な手すりの高さは75cm~80cm

一般的な手すりの高さは75cm~80cmです。手すりの高さは使用者の身長や用途によって異なりますが、身長の半分よりやや高い位置に設置します。
ただし、一般的な高さは、不特定多数の人が利用する施設で採用される数値です。特定の人が利用する住宅では、使用者に合わせた高さに調整します。人によって手の長さも異なるため、実際に使いやすい位置を確認しつつ設置することが大切です。
【場所・用途別】手すりの高さ
手すりの高さは、場所や用途によって設置に適した高さが異なります。以下を参考にしましょう。
| 用途 | 適切な高さの 目安 |
備考・ポイント |
|---|---|---|
| 階段 | 75cm~80cm | 子どもや高齢者向けに2段設置も有効 |
| トイレ・浴室 | 20cm~30cm | 座った状態で使いやすい高さ。L字型や縦型の補助バーも併用されることが多い |
| バルコニー・ ベランダ |
110cm~ | 転落防止が目的。手すりというより「柵」の役割が強く、視線や風通しも考慮される |
| 玄関 | 75cm~80cm | 床と垂直に設置する縦手すりは動作時の姿勢を安定させ、床と平行に設置する横手すりは移動を補助する役割 |
それでは、それぞれの場所の手すりの位置について解説します。
階段
階段の手すりは、一般的に75cm~80cmで設置するとよいとされています。手すりを設置する際には、以下のポイントも押さえておくことが大切です。
- 手すりは階段の両側にあるとよい
- 踊り場にも連続して設置する
- 階段の上端と下端も手すりを45cm延長する
- 子ども・高齢者向けに60cm~65cmの高さにも二段で設置する
階段内のすべての部分を手すりでカバーし、下り口や上り口の近くから設置することで、段差が始まる前から体を支えることができます。階段は転倒リスクが高いため、細かな配慮が必要です。
トイレ・浴室

トイレ・浴室の手すりの高さは、20cm~30cmがよいといわれています。手すりをトイレ・浴室に設置する場合は、座った状態からでも利用できるような高さに調整します。横手すりと縦手すりを設置し、座る動作と立つ動作を補助できるよう配慮しましょう。便器や浴槽から近すぎても遠すぎても利用しにくくなるため、便座の位置を基準として手すりの高さを決定します。
また、座ったり立ったりする際には、手すりに全体重がかかります。手すりが外れないよう、設置する場所には補強材を入れて対策しましょう。
バルコニー・ベランダ
バルコニー・ベランダの手すりは、110cm以上に設置します。バルコニーやベランダの手すりの高さが110cm以上としているのは、動作補助ではなく転落防止を目的としているためです。
なお、バルコニー・ベランダの手すりについては建築基準法施行令と品確法によって、一定の基準を満たした場合は必ず設置しなければならないと定めています。例えば、建築基準法施行令には、以下のような定めがあります。
第百二十六条 屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
また、落下防止用の手すりは落下防止だけでなく、通気性の向上や眺望の確保にも役立ちます。手すりを上手に活用して、快適な空間づくりに役立てましょう。
玄関
玄関の手すりの高さは、75cm~80cmが一般的です。ホールに段差がある場合は、段差の部分に上下移動しやすいよう補助の縦手すりを設置します。縦手すりは下端60cm~70cm、上端を110cm~120cmの高さに配置するとよいでしょう。また、玄関とホールとの段差が大きい場合、縦手すりの真下に踏み台を置き、上下移動しやすいように配慮してください。
注文住宅に手すりを付ける際の流れ・手順

注文住宅に手すりを付ける際は、以下の流れ・手順で進めます。
- STEP 1使用者と目的を確認する
- STEP 2設置場所を考える
- STEP 3高さ・長さを決定する
- STEP 4手すりの種類・素材を選ぶ
- STEP 5設計図への反映
- STEP 6施工する
STEP 1. 使用者と目的を確認する
手すりを設置する際は、まず使用者と目的を確認しましょう。使用者によって横移動に抵抗を感じる方もいれば、上下の動きがしづらいと感じる方もおり、手すりを利用する目的はさまざまです。目的を明確にすれば、手すりを設置すべき場所を特定しやすくなります。
STEP 2. 設置場所を考える
使用者と目的を確認した後は、実際に設置場所を考えます。目的が明確になっていれば、使用者の目的を果たせる場所がどこなのか検討します。例えば、転落防止を目的にするのであれば階段に手すりを設置する、座るのが辛いならトイレに設置するなどです。
STEP 3. 高さ・長さを決定する
設置場所を考えた後は、具体的に手すりの高さと長さを決定します。手すりの高さと長さを決定する際は、ハウスメーカーと相談しながら進めましょう。高さと長さは、手すりを効果的に使えるかどうかに直結します。
また、設置する高さや長さに合わせて適切な下地材を入れる必要があります。ハウスメーカーと相談しながら高さや長さを決めておくことで、今後の工事もスムーズに進められるでしょう。
STEP 4. 手すりの種類・素材を選ぶ
高さと長さを決めた後は、手すりの種類・素材を選びましょう。手すりには、以下のように種類や素材があります。
【種類】
| 縦手すり | I型とも呼ばれる手すり 床に垂直に設置する 立ち上がりを補助する |
|---|---|
| 横手すり (水平手すり) |
床と水平もしくは傾斜させて設置する 転倒を防止する 移動を補助する |
| L型手すり | 縦手すりと横手すりを合わせた形状 立ち上がりと移動を補助する |
【素材】
| 木製 | 冷たくなりにくい 水回りでは利用できない |
|---|---|
| プラスチック製 | 水に強い 滑りやすいため滑り止めが必要 |
| ステンレス製 | 頑丈で錆びにくい 熱くなりやすい |
手すりは種類や素材によって、設置に適した場所が異なります。それぞれの特徴を理解し、適切な場所に設置しましょう。
STEP 5. 設計図への反映
手すりの種類と素材を決定した後は、設計図に反映します。決定した手すりの高さや長さ、種類・素材を設計図に正確に反映しておかないと、取り付け時にミスが発生する可能性があります。ミスを防ぐためにも、ハウスメーカーに高さなどの情報をしっかり伝えましょう。
STEP 6. 施工する
決定した内容を設計図に反映した後は、図面どおりに施工してもらいます。手すりは生活に重要な福祉用具であり、設計図どおりに施工されているかどうかを確認しましょう。
引渡し前のチェックでは、図面と実際に設置された手すりを比較してください。図面と異なる箇所があった場合はすぐにハウスメーカーに連絡し、入居前に修正してもらうことが大切です。
取りつけた手すりの高さは変更できる?

取りつけた手すりの高さは変更できます。ビスを外して再度取り付ける工事となるため、手すりの高さは比較的簡単に変更が可能です。
ただし、手すりを再設置する位置に下地材が入っていないと、利用時に外れてしまうため危険です。下地材が入っていない場所に再設置する場合、壁を壊して下地を入れなければなりません。補強が必要な場合、手すり1カ所あたり2万円~10万円程度かかります。補強工事を含めると高額になるため、手すりを付ける場所の周辺にも下地を入れておくとよいでしょう。
注文住宅に手すりを付ける際の注意点

注文住宅に手すりを付ける際の注意点は、以下のとおりです。
- 使用者のニーズに合っているか確認する
- 壁の強度・下地の確認をする
- インテリアと調和しているか考える
- 将来的な変更・追加の可能性を考慮する
- 法令・補助制度の確認をする
- 使用テストをする
使用者のニーズに合っているか確認する
手すりを設置する際は、使用者のニーズに合っているか確認しましょう。使用者によって体格や骨格が異なり、動作に不自由を感じる局面も違います。例えば、足を下げる行動には抵抗を感じないものの、足を上げる時だけに痛みを感じるケースがあるでしょう。このような場合、階段に手すりを設置する効果は高いと言えますが、座る、立つだけのトイレに設置する効果は低くなる可能性もあります。使用者がなぜ手すりを設置したいのか、不自由さを感じる局面はいつなのかを深堀し、必要な箇所、高さに手すりを設置することが大切です。
壁の強度・下地の確認をする
手すりを設置する際は、壁の強度や下地の位置を確認しましょう。壁の素材としてよく使われている石膏ボードには強度がなく、手すりに荷重をかけるだけで簡単に外れてしまいます。ただし、石膏ボードの裏に柱や間柱があれば、下地の代わりとして利用可能です。柱がない場合、プレート状になっている木製の板を下地材として壁の裏に入れたうえで手すりを設置します。
このように、手すりは強度の高い場所にしか設置できません。利用時に外れると危険であるため、設置できる場所を事前に確認しましょう。
インテリアと調和しているか考える
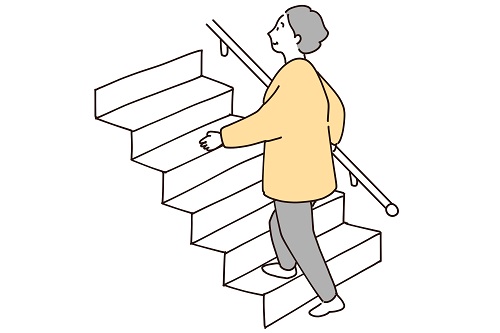
手すりは目立つ福祉用具であり、インテリアと調和しているか考える必要があります。例えば、無垢のフローリングを使った家であれば木製の手すり、モダンな雰囲気の室内ならロートアイアン製の手すりが合うでしょう。
手すりは、白いプラスチック製というイメージがあるかもしれません。しかし、実際には多くの素材やデザインがあります。室内の雰囲気を変える可能性があるため、どのようなデザインの手すりを採用するのかじっくりと検討しましょう。
将来的な変更・追加の可能性を考慮する
将来的な変更や追加の可能性を考慮しておくことで、余計な工事費用を抑えることができます。手すりを設置する場所には、補強材である下地が必要です。下地がない場所に手すりを設置する場合、工事費用が高くなります。将来的な変更や追加を考慮し、あらかじめ必要な場所に下地を入れておけば、手すりを設置する費用のみで工事ができます。老後の生活やケガをしたときのことも想定し、将来的に変更や追加が必要になりそうな場所がないか検討しておくことが大切です。
法令・補助制度の確認をする
手すりの設置には、法令や補助制度が関わります。品確法では住宅性能表示制度を利用する場合、高齢者への配慮に関する事項として、手すりの高さや間隔などを規定しています。規定を守って新築しないと、住宅性能評価を受けられません。
また、手すりを設けてバリアフリー化工事を実施する場合、補助金・助成金を受け取れる補助制度もあります。高齢者住宅改修費用助成制度のような補助制度は国や自治体が実施しており、制度の適用条件が異なります。制度の内容を詳しく知りたい方は、ハウスメーカーに確認しましょう。
使用テストをする
手すりを設置した場合、入居する前に使用テストをしましょう。一般的な目安の位置に設置したとしても、使いやすい場所かどうかは利用者によって異なります。使用テストをおこなっておけば、使いやすい位置かどうかすぐに確認できます。もし、使用テストの結果で使いにくいと感じた場合でも、入居前であれば生活に支障をきたすことなく手すりの再調整が可能です。手すりが使いやすい位置なのかは試してみないとわからないため、入居前に必ず使用テストをおこないましょう。
まとめ
手すりは、日常の動作をサポートする大切な用具です。足腰が弱くなったときや、事故や病気で体が不自由になったときに手すりがあれば、日常生活をサポートしてくれるでしょう。また、手すりを利用して行動することで、転倒によるケガの防止にもつながります。しかし、適切な位置に設置しなければ、手すりの効果を得られなくなるかもしれません。
手すりの効果を最大限に活かすためにも、場所や用途に応じて設置する位置の高さを調整しましょう。適切な位置に設置しておけば、日常生活での負担が軽減されます。
一般的な手すりの高さは?
一般的な手すりの高さは、75cm~80cmです。ただし、設置する場所や用途によって適切な位置が変わります。設置する際は、場所や用途ごとに適切な高さを理解したうえで手すりを付けましょう。
手すりの高さは変えられる?
手すりの高さは変えられます。ただし、手すりの高さを変える際は、設置した部分に補強材を入れる必要があります。設置する場所によっては工事費用が高額になるため注意が必要です。
手すりを付ける際のポイントは?
手すりを付ける際のポイントは、使用者のニーズを確認したり、使用テストしたりすることです。使いやすい位置に手すりを設置しないと、転倒リスクが高まる場合もあります。どの位置が使いやすいかを確認しながら設置することが大切です。
注文住宅を建てる



