注文住宅で予算オーバーになるのはなぜ?原因と費用を削るテクニックを解説

一方で、しっかりと資金計画を考えておかなければ予算オーバーにもなりやすい側面も。例えば土地から購入する場合は、土地の取得費と建築費、それぞれの諸費用を合わせて予算を把握することが必要です。そのため一言で予算オーバーといってもその要因はさまざまでしょう。
そこで本記事では、予算の立て方から予算オーバーの原因、予算が厳しい場合に費用を削る方法を解説します。さらに、あまり予算を削らないほうがよいケースもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
記事の目次
注文住宅の予算の立て方

はじめに注文住宅の予算を立て方の注意点も交えながら解説します。
自己資金の確認
マイホームの資金計画では、まず自己資金をいくら準備できるのか確認が必要です。貯蓄以外にも親からの資金援助や、住み替えにともなう売却収入が得られる場合もあるかもしれません。
しかし、万が一の場合に備えて6カ月程度の生活費や近い将来支出が決まっている費用は、貯蓄として残しておくことも必要です。必要な貯蓄を確保したうえで住宅購入にあてられる自己資金を確認しましょう。
住宅ローンの借り入れ可能金額の把握
次に、住宅ローンでいくら借り入れできるか(借り入れ可能額)を把握する必要があります。
金融機関によって審査基準が異なるため借り入れ可能額も違います。候補となる住宅ローン商品を決めたうえで、事前審査を受けおおよその借り入れ可能額を把握しましょう。
月々の返済可能額の確認
住宅ローンの借り入れ可能額がわかれば、借入期間に応じた月々の返済額を確認できます。このとき注意しなければならないのは、借り入れ可能額と返済可能額は必ずしも同じではないことです。
一般的に、無理のない返済負担率は、年収の20%~25%までといわれています。返済負担率とは、年収に対して住宅ローンその他の返済額が占める割合です。
返済負担率は、利用する住宅ローンの金利水準や返済期間を何年にするかによって変わります。そのため住宅ローンの金利水準や返済計画に合わせて毎月の返済額をシミュレーションし、年収に対して無理のない返済額になっているかの確認が重要です。
土地の購入費用と建築工事費用の配分を決定
自己資金と無理のない住宅ローン借入額の確認ができたら、次は土地の購入費用と建築工事費の配分を決めます。
土地探しで、交通・生活利便性が高い土地ほど取得費は高くなりやすいでしょう。一方建築工事費は、依頼するハウスメーカーや工務店で建築費(坪単価)の相場は変わります。
そのため、土地に求める広さや立地条件、建物の必要な床面積や住宅性能など、何を優先したいかを決めたうえで予算の割振りを考えることが大切です。
注文住宅で予算オーバーになる原因
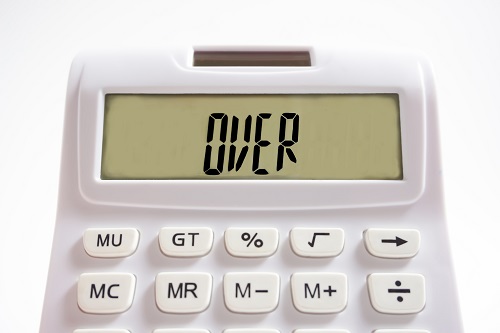
建売住宅や中古住宅と比べて予算オーバーしやすいと言われる注文住宅ですが、何が理由として考えられるのでしょうか。ここでは予算オーバーになる原因を解説します。
予算の設定を誤った
そもそも当初の予算設定を誤っていることが考えられます。
金融機関から借り入れできる金額(借り入れ可能額)だけを基準に決めると、予算設定を誤ってしまう可能性があります。
あくまで借り入れ可能額は、金融機関が融資してもよい金額であり、無理なく返済できる金額とは限りません。利用する住宅ローンの種類によっても借り入れ可能額は変わることを認識しておきましょう。
また、借入金額を判断する基準として返済負担率を紹介しましたが、同じ収入でも家族構成やライフスタイルの違いによって家計支出は異なります。
そのため返済負担率が20%あるいは25%以内でも、家計支出が多い世帯では返済が厳しくなる可能性がある点に注意が必要です。
住宅ローンは長期間の返済を前提としているため、将来の家計の変化も踏まえ無理のない借入金額となっているかを確認することが重要です。
こだわりの優先順位付けが甘かった
注文住宅の予算は、建築面積のほか住宅性能や間取り、仕様、設備など何を選択するかで変わります。そのため優先順位を決めずすべての要望を満たそうとすると、予算オーバーになる可能性が高くなります。
実際の間取りや仕様の打ち合わせのなかで、さまざまなグレードやオプションを見て選択を迷うこともあるでしょう。
このとき建築費にかける予算を踏まえ、優先順位を明確にしながら、こだわるところには予算をかけ、他の箇所では予算を削るなどメリハリをつけることが重要です。
ローンの返済計画が不十分だった
住宅ローンの返済計画の検討が不十分だと、返済負担が大きく予算オーバーと感じる可能性があります。
購入時の年齢によっては、住宅ローンの借入期間を短く設定し、完済年齢を早めたいと考えるかもしれません。
ただし、返済期間を短くした分月々の返済負担は大きくなり、金利上昇した場合の影響も大きくなります。長期間の返済が前提となる住宅ローンでは、毎月の返済負担が大きいと、返済しきれなくなってしまうかもしれません。
そのため住宅ローン契約当初の借入期間は短くし過ぎず、返済期間中、余裕があれば繰り上げ返済を活用するなど無理のない返済計画を立てることが大切です。
想定外の土地購入費や建築費用がかかった
注文住宅の家づくりでは、建物の本体工事以外にもさまざまな付帯工事が必要になる場合も。想定外の土地購入費や建築費用で予算オーバーになることがあります。
以下は、注文住宅建設時に必要になる付帯工事の一例です。
- 地盤改良工事
- 造成・整地工事
- 外構工事
- 給排水管や電気・ガスの引込工事
- 照明器具やカーテン工事 など
地盤調査で地盤改良工事が必要となると、1坪あたり1万円~5万円、工事方法によっては7万円程度の費用がかかることがあります。
また、前面道路に口径が小さい水道管が引き込まれている、あるいは水道管までの距離が長いと給排水工事費が高くなる傾向です。
他にも、駐車場や塀、門扉から玄関までのアプローチなどの外構工事の予算が膨らむこともあります。
これらの付帯工事費も、追加費用がかかることを想定しておくことで予算オーバーを防ぎやすいでしょう。
入居後にかかるコストを考慮していなかった
住宅ローン返済以外の入居後にかかるコストを把握していないと予算オーバーになってしまうことも。入居後に継続的にかかるコストには次のようなものがあります。
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険・地震保険料
- 将来のメンテナンス費用のための積み立て など
通常、返済負担率は、収入に対して住宅ローン返済やその他の借り入れがどれくらい占めるかで判断します。ただし、これらの維持費も含めた住宅コストが家計支出に占める割合が高すぎると、予算オーバーとなる可能性があります。
補助金・助成金制度が利用できることを知らなかった
注文住宅の新築では、国や自治体がさまざまな補助金制度を設けています。補助金を活用し必要資金を抑えることで、結果的に予算内に収まりやすくなるでしょう。
国が実施する補助事業には次のようなものがあります。
- 子育てエコホーム支援事業
- 給湯省エネ2024事業
- ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)事業
- LCCM住宅整備事業 など
また、東京都では都独自の基準の省エネ性能を満たした家を建てると補助金を受け取ることができる「東京ゼロエミ住宅」助成事業を実施しています。
事業者が申請者となる補助金も少なくありませんが、なかには建築主が申請する必要があるものもあります。
自治体が実施する補助事業を含めて、補助事業の給付要件や事業期間などを調べてしっかりと活用しましょう。
注文住宅で予算を削りやすいところは?費用を削るテクニック
注文住宅で予算オーバーしそうな場合、どういった部分で費用を削れるのでしょうか。ここでは費用を削るテクニックを解説します。
土地

まずは土地の費用を削るテクニックです。
エリアの希望を見直す
土地購入費を下げるために、希望エリアを見直す、あるいは対象エリアを広げることが考えられます。
土地の相場は対象とするエリアや駅からの距離によって大きく異なります。予算を抑えやすい要素の一つですので、最寄り駅や利便施設までの距離、住みたいエリアなどこだわりを緩和することも検討してみましょう。
ただし、立地条件は毎日の生活や通勤・通学の利便性に影響します。マイホームに求める条件を踏まえ後悔のない場所を購入することが大切です。
追加工事費のかからない土地を選ぶ
追加工事費がかかりにくい土地を選ぶことも大切です。
土地の購入代金以外にかかる費用として、地盤改良工事費や水道・ガスの引き込み工事、擁壁工事、既存建物の解体工事費などが考えられます。
地盤改良工事の要否は地盤調査によって判明するため、事前の把握は容易ではありません。
ただし、国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」やジャパンホームシールド株式会社の「地盤サポートマップ」などで土地の地歴や特徴、液状化リスクを調べると地盤の強さを一定程度の判断ができるでしょう。
また、土地を購入する前に前面道路に施設されているインフラの位置や口径を確認したり、擁壁工事や解体工事の見積もりを取ることで、追加工事による予算オーバーを防げるかもしれません。
建物

次は建物の費用を削るテクニックです。
延べ床面積を抑える
建築費用は「坪単価×床面積」で決まるため、延べ床面積を抑えることでコストダウンが期待できます。
リビングや各居室に必要な面積を子どもの成長・独立など長期の視点で再検討してもよいでしょう。リビングの広さにはこだわり、寝室や収納部分の面積を減らすなどメリハリをつけることも大切です。
また、間取りを見直し、居室内のデッドスペースや通路部分の面積を減らすことで延べ床面積を抑えられる可能性もあります。
総二階建てにする
建物形状や外観に強いこだわりがなければ総二階建てにすることでコストを抑えやすくなります。
一階と二階の形状が同じ総二階建ての間取りは、外壁の凹凸を減らし、柱を少なくできるため、延べ床面積を減らさずにコストカットできる有効な方法です。
加えて、地震力に対抗しやすい間取りである点もメリットです。
外壁の凹凸を減らす
建物の形状をシンプルにし外壁の凹凸を減らすこともコスト削減につながります。凹凸が多い建物形状は、長方形などの建物形状と比べて同じ建築面積でも外壁や基礎の全長が長くなります。
そのため施工する面積が増え、使用する外内壁材も多くなるため建築コストは高くならざるを得ません。できるだけ凹凸を減らす建物形状にすることでコストを削ることにつながるでしょう。
屋根はシンプルなデザインにする
さまざまな屋根形状がありますが、切妻屋根や片流れ屋根などシンプルなデザインとすることでコストを抑えやすくなります。
形状がシンプルな分施工しやすく使用する材料も減らすことが可能です。また、屋根と外壁の取り合いが少ないため防水処理などの施工手間がかかりにくい特徴があります。
加えてメンテナンス費用もかかりにくいことから、長期的な住宅コストも抑えやすいでしょう。
オープン外構にする
外構工事の費用を抑えたい場合、オープン外構を採用する方法が考えられます。
外構のタイプには、フェンスや塀、門扉などで敷地を囲い住宅と道路、隣地との境界を明確にする「クローズド外構」のほか、必要な場所だけに塀やフェンスを設置する「セミクローズド外構」、塀やフェンスで囲まず外部から見えるようにする「オープン外構」があります。
オープン外構は塀やフェンスを設置しないため、もっとも費用を抑えられます。
プライバシーや安全性の面で考慮しなければならない点はありますが、一つのコストカットの方法として有効です。
間取り・内装

間取り・内装の費用を削るテクニックを紹介します。
窓の数を減らす
コストを削るうえで窓の数を見直すことも一つの方法です。
窓を減らすことで、窓本体の費用や施工費用を抑えられます。
必要以上に窓が設けられている場合、建物の断熱性にも影響する可能性があるため、コスト面も含めて減らせる窓がないか設計士に相談してみるとよいでしょう。
ただし、居室の開口部は、床面積に対して一定の面積を確保しなければなりません。また、採光や風通しも考慮して検討しましょう。
ドアの数を減らす
ドアの数を減らし建物に使用する部品数を抑えることでコストカットを図れます。
例えば、WIC(ウォークインクローゼット)や隣合う子ども部屋、寝室のクローゼットなどの扉を設置せず、建具や工事代を節約することが考えられます。
また、廊下の途中やキッチンなどの収納にあえて扉を設けず見せる収納にする方法もあるでしょう。
洋室のみの構成にする
間取りに和室を取り入れることを検討している方は、洋室のみにすることでコストダウンが図れる可能性があります。
和室の板張り天井や壁材などにどこまでこだわるかで費用は異なりますが、一般的に和室は洋室と比べて費用がかかる傾向にあります。
和室は幅広く使いやすく、畳に使用される「い草」には湿気を吸収する調湿効果があるなどのメリットもありますが、間取りのなかで和室の必要性を検討してみてもよいでしょう。
収納スペースを減らす
収納スペースを減らすのも、コストを抑えられるポイントの一つです。
収納の種類にもよりますが、一カ所の収納にかかる費用相場は、10万~100万円程度。できるだけ高さや奥行を有効利用して、収納スペースを減らすことでコストダウンが図れる可能性があります。
水回りを一カ所にまとめる
水回りの工事費用を削るためには一カ所にまとめることが有効です。
キッチンや洗面、浴室、トイレなどの水回りを集中させることで、設置にあたって必要となる配管工事がシンプルかつ短い距離で済みます。
また、配管は定期的なメンテナンスの際も一カ所に集中しているほうが楽になるでしょう。
カーテンは自分でオーダーする
カーテンをハウスメーカーや工務店が提携している施工会社に依頼した場合、仕上がりはきれいであるものの金額は高くなる傾向にあります。
数量やカーテン、レールのグレードによっても異なりますが、自分でカーテンを設置するより数十万円高くなることも。そのためカーテンは自分でオーダーするとコストカットにつながるでしょう。
こだわりのカーテンを使う部屋とそうでない部屋でメリハリをつけるのもおすすめです。
設備

最後に設備の費用を削るテクニックです。
導入したい設備を再検討する
予算オーバーしそうであれば導入する設備を再度見直すことも考えましょう。
例えば、太陽光発電システムですが、導入には大きなコストがかかります。省エネ設備として補助金が使えることもありますが、初期費用の負担をしっかりと踏まえ検討しましょう。
また、その他にも、天窓やシャッター、ウッドデッキ、ミストサウナ、浴室乾燥機など、建築コストに影響しやすい設備について、必要性を家族で話し合うことも大切です。
設備は標準品を選ぶかグレードを下げる
キッチンやユニットバスなどの設備は、標準品を選ぶかグレードを下げることでコストを抑えられます。
水回りの設備も一定期間を経過すると保証期間がなくなり、いずれは故障します。そのため、定期的な交換を前提にグレードを落とす考え方もあるでしょう。
設備ごとにメリハリをつけ仕様やグレードを検討することで、新築時のコストを下げることにつながります。
照明・エアコンなど自分で手配する
依頼すればエアコンや照明などの電化製品も施工会社が手配してくれますが、量販店やネットで比較的安価なものを自分で手配するとコストを削れます。
また、リビングや玄関の照明やエアコンにはこだわり、子ども部屋や寝室には安価なものを使用するなどメリハリをつけることも大切です。
注文住宅で予算を削らないほうがいいところは?

次に、注文住宅で予算を削らないほうがいいコストを解説します。
屋根・外壁
建築コスト削減のために屋根形状をシンプルにする点も紹介しましたが、屋根や外壁の素材のグレードを落とし過ぎるのはおすすめできません。
なぜなら、屋根や外壁の素材によって耐久性や対候性は異なり、長期の視点でみた時維持管理コストに影響するためです。
また、屋根材であれば、スレート、ガルバリウム鋼板、瓦などさまざまな種類がありますが、耐震性(重量)や断熱性なども異なります。
のちのちメンテナンスの手間やコストで後悔しないよう、それぞれの特徴を踏まえ安心できる材料を選ぶことをおすすめします。
防犯・セキュリティ
防犯・セキュリティに関する費用は削らないほうがよいでしょう。
長く安心して暮らすためには、防犯性の高い玄関ドアや窓を採用することは大切です。
玄関の鍵であれば、ピッキングに強いディンプルキーやスマートキーなどおすすめ。窓は通常のガラスではなく防犯ガラスを選ぶことで防犯性が高まるでしょう。
コストはかかりますが、安全に暮らすためにも必要な支出だと割り切ることも大切です。
耐震性能
地震大国である日本で、一戸建ての耐震性能には予算をかけたいところです。耐震性を判断する基準に耐震等級があります。
最上位の耐震等級3を標準仕様としている住宅会社もありますが、一般的に、使用する材料が増え、設計・施工の手間がかかりやすいことで建築コストが高くなりやすいでしょう。ただし、長く生活するうえで高い耐震性能のもと、安心・安全に暮らせるメリットは大きくなります。
また、耐震性の高い建物は、地震保険料の割引や住宅ローン商品によっては金利優遇を受けられることもあります。
断熱性・気密性
冷暖房費などのランニングコストにも影響する断熱性や気密性にかける費用は削らないほうがよいでしょう。高断熱の住宅は、屋内外の熱の移動を防ぎ一年中快適に過ごせます。
また、居室間の温度差が原因で生じるヒートショックのリスクや結露によるカビやダニの増殖を抑えられるため健康面でのメリットもあります。
これだけは譲れないこだわり
家族のなかで優先順位が高い部分の費用は削らないようにしましょう。
リビングの広さや吹き抜け、家事動線など、ライフスタイルや家族構成にあわせてこだわりたい部分があるはずです。
長く住む家づくりでは、譲れないものを妥協してしまうとのちのち後悔する可能性が高くなります。そのためにもしっかりと優先順位を話し合い、こだわりたい部分を決めておくことが大切です。
注文住宅の予算オーバーに関するまとめ
最後に注文住宅の予算オーバーに関するまとめです。
注文住宅で予算オーバーになる原因は?
無理のない予算や住宅ローンの返済計画を立てられていないことが考えられます。
また、家づくりの予算や優先順位をしっかりと決めていないことで追加費用が生じることもあるでしょう。購入する土地によっては、地盤改良など想定外の付帯工事費用がかかることがあります。
注文住宅で予算を削りやすいところは?
長期の視点で無駄のない延床面積にして、シンプルな建物形状、間取りにすることで建築コストを削ることが可能です。
また、住宅設備のグレードと落とし、水回りを1カ所に集めることで設備工事にかかる費用を抑えられます。カーテンや照明などを部屋ごとにメリハリをつけながら自分で手配するとよいでしょう。
注文住宅で予算を削らないほうがいいところは?
家づくりで後悔しないようにこだわりたい部分の予算は削るべきではありません。
また、断熱性や耐震性、防犯・セキュリティなど、長く住み続けるうえで安全性と快適性に影響する住宅性能については妥協しないほうがよいでしょう。
加えて、メンテナンスコストに影響する屋根や外壁には、しっかり予算をかけることをおすすめします。
注文住宅で予算オーバーとならないためには、まず自己資金や無理なく返済できる借入金額を把握ししっかりと資金計画を立てることが重要でしょう。
そのうえで、地盤改良費や給排水管工事費など購入する土地によっては発生する可能性がある費用を想定しながら予算を考えておくと安心です。
また、建物は、住宅性能から間取り、外観などさまざまなことを決めていきますが、もっとも大切なことは優先順位をつけ予算をかけるところとそれ以外のメリハリをつけることです。
この時、長く生活するうえで大切な快適性や安全性、長期的なコストに影響する部分の予算については、慎重に判断したほうがよいでしょう。
注文住宅を建てる


















