
- 同棲する場合の世帯主は誰?住民票はどうする? 同棲前に確認したい手続きの基本
- 同棲をする際、住民票の世帯主の欄を誰にするのか悩んでしまいますよね。この記事では、同棲・同居をする際の「世帯主」「住民票」について解説しています。同棲を経験した先輩たちの声もぜひ参考にしてください。

同棲を始めるにあたり、「家賃補助はもらえるのか?」「二人分の家賃補助を受け取れるのか?」という疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。一般的に、同棲でも条件を満たせば、家賃補助を受け取ることは可能です。ただし、企業によって支給条件が異なるため、知らずに申請すると思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もゼロではありません。本記事では、同棲を開始したあとに家賃補助を受け取るための条件や注意点、同棲の事実を知られないための方法などを解説します。
記事の目次

家賃補助とはどのような制度でしょうか?
家賃補助とは、従業員の住居費負担を軽減するための法定外福利厚生です。一般的には「月額○万円」「家賃の○%」のような形で、給与に上乗せする形で支給されます。まずは、家賃補助の制度を導入している企業の割合や、平均支給額などを見ていきましょう。
厚生労働省の「令和2年就労条件総合調査の概況」によると、家賃補助や住宅手当の支給を実施している企業の割合は47.2%でした。つまり、約半数の企業が福利厚生の一環として、住居費の支援をおこなっていることがわかります。
なお、支給条件や支給対象者などは、それぞれの企業が独自のルールを定めています。実務上は、賃貸物件に入居している世帯主が、家賃補助の対象となるケースが一般的です。
厚生労働省の同資料によると、家賃補助の1人あたりの平均支給額は月額で約1.8万円でした。年額に換算すると約21.4万円です。なお、企業規模別の平均額は以下のとおりとなっています。
企業規模別の家賃補助平均支給額
| 企業規模 | 平均額 |
|---|---|
| 1,000人以上 | 2万1,300円 |
| 300〜999人 | 1万7,000円 |
| 100〜299人 | 1万6,400円 |
| 30〜99人 | 1万4,200円 |
企業規模が大きくなるほど、支給額が増える傾向にあることがわかるでしょう。
家賃補助は通常の給与の上乗せとして支給されるため、従業員にとっては家計を助けてくれる存在です。支給額は企業が独自にルールを定めており、対象者に対して一律に支給したり、住んでいる地域や通勤時間などを加味したりするケースもあります。

同棲でも家賃補助を受けることができます
同棲でも家賃補助を受けられるかどうかは、企業次第となります。ただし、多くの企業では家賃補助の対象者を以下のように設定しているため、同棲でも受け取れるケースが一般的です。
多くの企業での家賃補助の対象者
| 主な要件 | 備考 |
|---|---|
| 世帯主であること | 住民票で確認される。世帯分離(互いに別世帯主)を求める会社もある |
| 本人が賃貸契約の名義人であること | 連名契約は可否が分かれる。契約者がパートナーだけの場合は対象外になりやすい |
| 重複して受給していないこと | 別々の会社に勤めていても「二重取り」を禁じる企業が多い |
| 証明書類を提出すること | 賃貸借契約書や家賃領収書を定期的に提出させる企業が多い |
就業規則や賃金規程で定めている「世帯主」 や「賃貸借契約の契約者」などの要件に該当すれば、同棲や婚姻などの状況に関係なく、家賃補助を受けられます。ただし、「一人暮らしは支給対象だが同棲は対象外」という企業も存在するため、規則や規程を確認しましょう。
次の章では、家賃補助を受けるための具体的な条件を詳しく解説します。

同棲で家賃補助を受けるためには条件を満たす必要があります
先述のとおり、家賃補助の支給条件として代表的なのは「世帯主であること」「賃貸の契約者であること」「正社員であること」の3つです。以下で、支給対象者となる条件を詳しく解説します。
「世帯主」とは、一般的に住民基本台帳法上の世帯主を指します。住民票に「世帯主」として記載されている場合、家賃補助の対象として判断されるのが一般的です。
ただし、企業によっては、世帯主を「主たる生計者」として定義しているケースもあるので注意してください。具体的には、実際に家賃や住宅ローンを負担している人を支給対象として取り扱います。この仕組みにより、実質的に家賃を支払っていない人へ、手当を支給する事態を防いでいるのです。多くの企業では住民票とあわせて、賃貸借契約書(支払人の箇所)や家賃を支払っていることがわかる証明書類(通帳のコピーや領収書など)の提出が求められるでしょう。
多くの企業では、家賃補助の対象者を「賃貸借契約書の名義人が従業員本人であること」としています。これにより、同一の物件で複数人が住宅手当を受け取る「二重取り」を防いでいるのです。
本人単独名義で実際に家賃を支払っていれば、家賃補助の対象となります。配偶者・パートナーの名義や親名義だと、要件に該当せず家賃補助の対象外となるケースが一般的です。なお、賃貸物件によっては、契約者の名義人を複数設定できる「連名契約」が可能です。連名契約の場合、家賃補助の対象になるかは企業によって判断が分かれるため、勤務先へ相談しましょう。
多くの場合、家賃補助の対象となるのは正社員に限られます。住宅手当は法定外福利厚生であり、企業にとってはコストの一つです。コア人材へのサポートを優先するため、支給対象者を正社員に限定しています。
ただし、企業によっては「無期転換社員」「地域限定正社員」「短時間正社員」なども、支給対象にしている場合があります。契約社員や派遣社員から正社員へ登用された場合、家賃補助のルールを確認しておきましょう。
なお、正社員の種別や勤務地によっては、受け取れる家賃補助に差があるケースがあります。昨今は多様な正社員の形態が生まれているため、規則や規程で対象や支給額を確認しましょう。
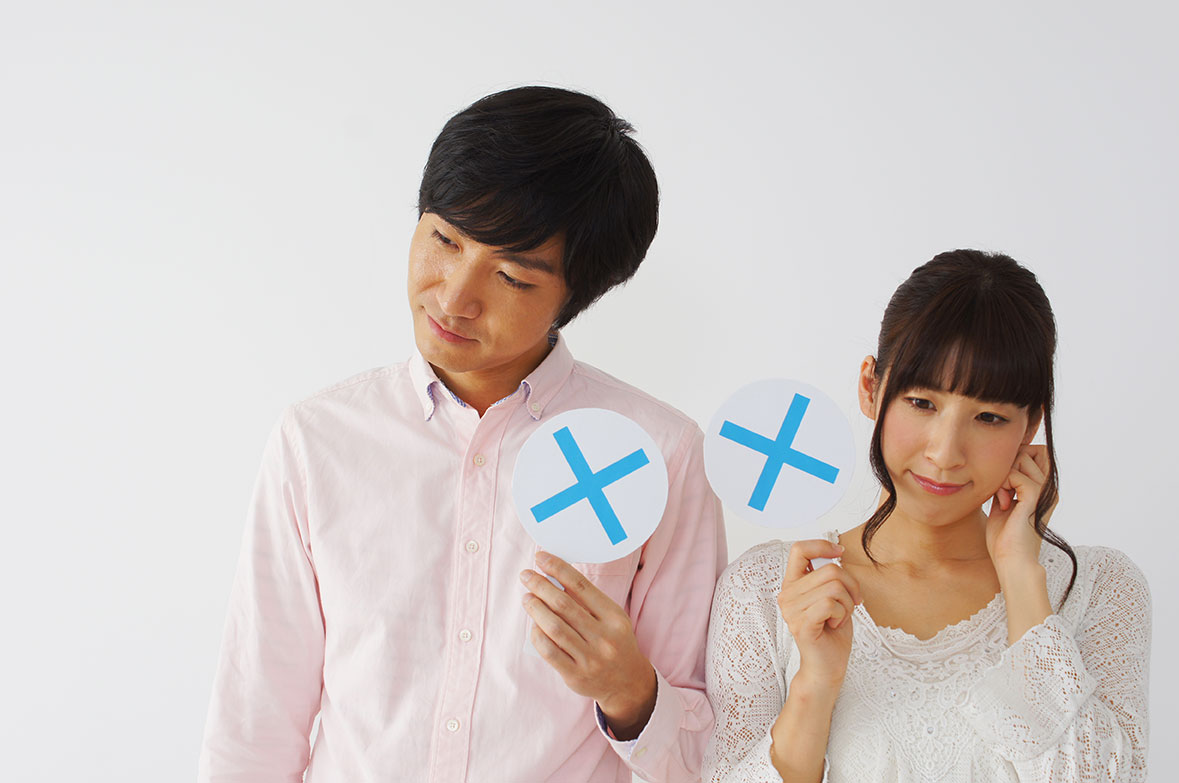
家賃補助の「二重取り」に気を付けましょう
「二重取り」とは、同棲している二人がそれぞれの勤務先から家賃補助を受けることです。多くの企業は、家賃補助を 「一つの住居につき一人(または一世帯)だけに支給する」 という前提で制度設計しているため、基本的に二重取りはできません。
故意か否かに関係なく、本来であれば受給できない手当を受け取っていることが判明したら、その返還を求められるでしょう。もし悪質性が認定されたら、就業規則違反で懲戒処分(戒告や減給など)を受ける可能性もあります。家賃補助の申請をする際には、就業規則や賃金規程などを必ず確認しつつ、判断に迷う場合は人事労務の担当者に相談しましょう。
もし誤って二重取りをしてしまった事実に気づいた場合は、すみやかに担当者へ報告して、自主的に返還手続きを開始しましょう。悪意がないことを示すためにも、発覚後に迅速かつ誠実に対応することが重要です。
そもそも、同棲を開始した事実について、会社に報告する義務はありません。結婚して世帯状況に変化があった場合は所定の届出をする必要がありますが、同棲では特に報告や届出をする必要はないのです。
それぞれが別々に住民票を作成すれば、二人とも世帯主になることができます。何かの拍子に勤務先へ住民票を提出する場面があっても、住民票の情報から同棲の事実を知られるリスクはありません。
ただし、同棲相手が同じ会社に勤務している場合、バレてしまう可能性は高いでしょう。住所に変更があった場合は届出をする必要があり、「同じ住所に住んでいる=同棲している」という事実が発覚するためです。
また、自分が同棲相手の住居に引越して勤務先に届出をしなかった場合、勤務先からの郵送物が宛先不明で返戻されたことがきっかけで、同棲がバレる可能性があります。あるいは、住民税決定通知書を発行している市区町村と企業で把握している住所が異なることで、発覚するケースも考えられるでしょう。
企業で定められている所定の手続きを怠ると、雇用主からの信頼を失ってしまいます。同棲の開始に伴って住所が変わった場合は、忘れずに勤務先へ届出をしましょう。
企業が従業員の住居費負担を軽減するための制度に、「借り上げ社宅」というものがあります。借り上げ社宅とは、勤務先名義で物件を借りたあとに、その物件を従業員へ転貸する仕組みです。自己負担分の家賃は、給与天引きで支払うケースが多く見られます。以下に、家賃補助と借り上げ社宅の違いをまとめました。
家賃補助と借り上げ社宅の違い
| 家賃補助(住宅手当) | 借り上げ社宅 | |
|---|---|---|
| 支給形態 | 手当を給与に上乗せして支給する | 会社が物件を賃借(または所有)し、従業員に現物で貸与する |
| 税務 | 住宅手当全額が給与所得扱い(所得税・住民税が課税) | 社員が「賃貸料相当額」の50%以上を自己負担すれば 非課税 |
| 社会保険料 | 手当額が標準報酬月額に加算され、保険料に反映される | 影響なし |
| 必要な手続き | 物件の選択と解約は自由 | 会社が契約している物件から選択するケースがある |
| 家賃の支払先 | 大家 | 勤務先(給与天引きが一般的) |
借り上げ社宅は社会保険料が上昇するリスクがありません。コスト削減の観点から、家賃補助ではなく借り上げ社宅を提供している企業があります。
借り上げ社宅の運用方法は、企業によってさまざまです。従業員が自由に物件を選択できたり、あらかじめ企業が提携している候補物件から選択したりする方法があります。借り上げ社宅を利用する際には、詳細について勤務先に確認しましょう。
なお、借り上げ社宅に住んでいる状況で同棲を開始すると、勤務先への報告義務が生じることがあります。社宅規程によっては本人と家族以外の入居を禁止していることもあるため、事前に確認しておきましょう。
家賃補助と借り上げ社宅以外にも、さまざまな住宅に関する手当や補助があります。以下に、代表的な支援制度をまとめました。
住宅に関する手当や補助
| 制度名 | 仕組み |
|---|---|
| 社員寮・社有社宅 | 企業が自前で保有する寮・社宅を低額で貸与する |
| 住宅ローン利子補給 | 持ち家の住宅ローン利息の一部を企業が補助する |
| 住宅資金貸付制度(社内融資・財形転貸) | 企業が低金利で住宅支援資金を貸し付ける |
| 引越し費用補助 | 引越し費用(引越代、梱包資材、鍵交換など)の一部または全部の費用を企業が負担する |
| 転居一時金・転勤支度金 | 転勤時に新生活費用を一時金として支給する |
| 単身赴任手当・二重生活補助 | 家族と別居して二重生活になる従業員に対して、手当を支給する |
企業ごとに、導入している制度や対象者、支援内容などは異なります。住居費は家計のなかでも3割~4割程度を占める大きな支出であるため、負担を軽減できる制度を有効活用しましょう。
同棲でも、「世帯主」かつ「賃貸契約の名義人」であれば、基本的に家賃補助を受け取ることができます。家賃補助の平均支給額は月額約1.8万円で、約半数の企業が導入している制度です。ただし、同棲カップルが両方とも家賃補助を受ける「二重取り」は禁止されており、発覚すると返還や懲戒処分のリスクがある点には注意してください。
同棲を開始したあとに家賃補助を受ける際は、まず勤務先の就業規則や賃金規程を必ず確認しましょう。企業によって支給条件が異なるため、自分が対象になるかどうかを把握することが重要です。
また、家賃補助の申請時だけでなく、定期的な確認のタイミングで住民票や賃貸借契約書などの証明書類を提出する場面があります。本来であれば受給できないのにも関わらず受け取っていることが発覚すると、思わぬトラブルになる可能性があるため注意しましょう。
判断に迷ったときは、人事労務の担当者に相談することをおすすめします。家賃補助を正しく活用して、家計の住居費負担を軽減しましょう。
カップルにおすすめの
お部屋探しアプリ
「アットホームであった!」
情報のシェアやトークができるペアリング・トーク機能
キニナルお部屋を共有したり自由にトークしたり、写真を送りあったり、お部屋探しを楽しく快適に!
2人にとってアクセスのいいエリアを検索エリア設定機能
キニナルお部屋を共有したり自由にトークしたり、写真を送りあったり、お部屋探しを楽しく快適に!
希望する条件と気になるお部屋の合致度が数字でわかる!
キニナルお部屋を共有したり自由にトークしたり、写真を送りあったり、お部屋探しを楽しく快適に!
こだわりに合わせて情報をカスタマイズ「選べる表示ビュー」
キニナルお部屋を共有したり自由にトークしたり、写真を送りあったり、お部屋探しを楽しく快適に!
二人にとってぴったりな住まいが
簡単に見つかるアプリ
「アットホームであった!」
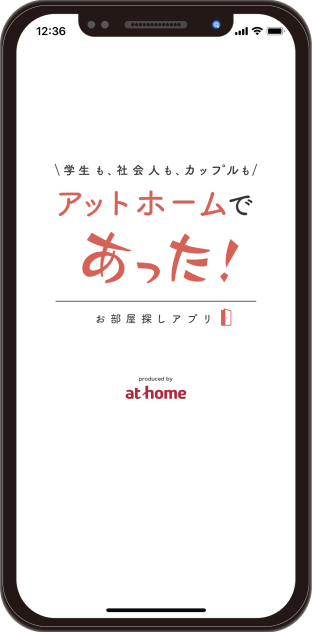
アプリの詳細はこちら
AppleおよびAppleロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。
App Storeは、Apple Inc. のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。