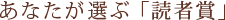ぱらみつぱらみつ
ひきだしのなかにあった、ちいさなビーズ状のものがフローリングの床にこぼれてゆく。
あっというまにじぶんの掌から離れて行って、そのおびただしいほどのビーズは、あちらこちらから楽しそうに弾けていった。
しゃりしゃりっとした音と、かすかなシャボンの匂いを立てながら。
湿気を感じるとそのビーズの色が、桃色に変わる。そういう仕組みらしく、よくみるとフローリングの溝にまで、幾粒かが収まっている。それを回収するには、とても面倒な作業だったのに、しゃがんだ姿勢のままで、ちいさな箒を持って床を掃いているとこっけいで仕方なく、側にいる同僚の月島さんと共に笑い転げていた。
「そっとしずかに、しかもぴったりとドアを閉めるというような習慣が忘れられていく」
ということばが、ふいに事務机の引き出しのクリアファイルの中から透けて見えていた。
そっと、しずかにぴったりと。
かつてその感覚を知っていたような気がする場所から、いまに向けてたしなめられた気分になる。
幼い頃、祖母に習ったようなその習慣も、もう誰も叱る人もいなくなって、無作法なままであることが、あたりまえになってしまった日々が続いていた。生きているとたえず失い続けている気もしてくるし。
その失ったものを掻き集めていったら、何かとてもこころもとない建物でも建ってしまうぐらいのおおきさになってしまうのかもしれないと夢想していた。
会社が資料で取り寄せた「建築は ほほえむ」という書籍の中に〈建築は目地の隙間や継ぎ目をつくることで成り立っている〉という文章があった。
とりわけ〈目地が笑う〉という表現に惹かれた。〈継ぎ目が広がるという意味〉らしく、〈建物が生きているから〉そういう現象が起きるのだとか。
そんなふうに云われてもなにひとつわからないのだけれど、知らない世界に身を任せてみると、いまいる場所からちょうどよい距離でもって逃避させてくれた。
むかし住んでいた浴室のタイルの目地に思いが飛んだ。
そのタイルの目地をずっとずっと俯瞰してゆくと、それはどこかのかつてあった名もない町の路地のようにも見えてくる。
ジオラマを俯瞰してみると見えてくる、もうひとつの世界への入り口にいることを夢想してしまうときに似ていた。
ささやかな目地のことへの関心が、いつのまにか仕事用のコピー資料から引き寄せられていた。
ずっと忘れていた〈風待トンネル〉を抜ける。
車が渋滞しているときの近道は、いつもとは違う古いホテルと郵便局の間を通るのが定番だったけれど、その日のタクシーの運転手さんは、もうひとつのトンネル越えの道を選んだ。
ぱらみつぱらみつ