猫にとって快適な室温は?夏と冬の適温と暑さ・寒さ対策を徹底解説

記事の目次
猫は体温調整が苦手

猫は汗腺が人のように多く存在せず、猫の体の構造上人のように皮膚から汗を放出することができません。汗腺には大きく分けると「エクリン腺」「アポクリン腺」の2種類がありますが、通常汗はエクリン腺より分泌されます。
人の皮膚にはエクリン腺がありますが、猫の場合は肉球と鼻の先端部のごくわずかな部位にしかありません。つまり、汗を人のように効率的に体外へ排出することができないのです。そのため、猫は体温調整が簡易ではなく、生活空間の室温管理が非常に重要になります。
なお、猫は汗をエクリン腺で分泌する他、汗腺からの分泌ほど効果的ではありませんがグルーミング(毛繕い)によって放出しています。これによって、わずかですが多少の体温管理ができます。
猫にとって快適な室温は21~28度前後
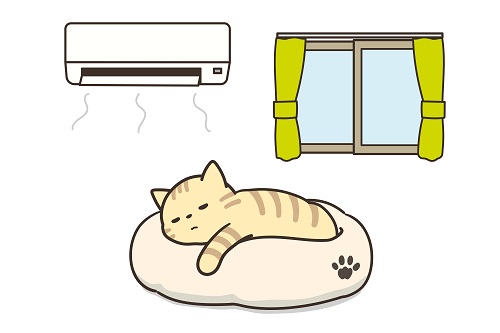
汗を大量に放出できない猫の快適な室温は、21~28度前後だといわれています。ただし、猫の種類や個体差、年齢によって適切な室温は異なるので注意が必要です。
ここで重要なのが、猫の行動を日々よく観察して、室温が適切か判断することです。特に短毛種の猫は、体を丸めたままの体勢で寝たまま長時間動かなくなったり、毛を逆立てたり、水分摂取量が減るようなことがあった場合は、寒いと感じている可能性が高くなります。こうした際には、室温を上げて様子を見てあげるとよいでしょう。寒さが続くと免疫力低下や低体温症、猫風邪を引き起こしてしまうことがあります。
逆に、仰向けで寝ている場合は暑さを感じている可能性があります。暑すぎると食欲低下や体調不良、熱中症等の病気リスクが高まるので、日頃から猫の様子をしっかりと見て、室温の管理を徹底してあげることが必要です。
夏におすすめの室温設定と熱中症対策

猫の熱中症対策として、室温の管理をすることがとても重要になります。その他、必要に応じてエアコンをつける、猫が生活する空間の部屋の間取りを考える、新鮮な水を常に準備しておくといったことが重要です。
夏のエアコン設定温度は21~28度程度
猫にとって快適な室温管理をするために、夏はエアコンの活用をしましょう。設定温度は21~28度程度が目安ですが、実際の設定温度と室温の温度が異なるケースがあります。そのため、猫の生活空間には、室温を計測するための温度計を設置しておくことをおすすめします。
短毛種猫、長毛種猫、ダブルコート、シングルコート、また個体差によって適切な室温は異なります。前述したように猫の寝方を中心に様子を見ながら、個々の猫に適した室温にすることが何より重要です。
エアコンは留守の間もつけておく
夏の暑い時期には、エアコンは留守の間もつけておきましょう。猫も外を見て気分転換ができるため、半分カーテンを閉めておくなど、室温が上がりにくい工夫もするとよいでしょう。
猫が自由に涼しい場所にいける環境にする
夏は特に室温に限らず、猫の生活空間に日陰を確保しておくことも重要です。暑い時には、猫が自由に室温の低い場所に移動できる環境を作ってあげましょう。飼主さんが家にいてそこまで暑くない朝方や夕方は、網戸にして風通しをよくすることも大切です。室温だけでなく、空気の循環に配慮しましょう。
エアコンの風が直接当たらないように工夫する
自由に室内を動くことができる猫なら問題ありませんが、ケージに入れている時や猫が固定位置を好む場合は、エアコンの風が猫に直接当たらないように工夫しましょう。風が嫌いな猫だと精神的ストレスの要因になりやすいですし、体が冷え過ぎてしまうと免疫力低下、下痢や軟便等の消化器系症状を引き起こすリスクが高まります。
エアコンの多くは、風の向きを左右や上下に変更できるようになっています。猫に当たらないよう高さを調整してあげるとよいでしょう。
水飲み場を増やす
夏に限ったことではありませんが、夏の熱中症対策には水分補給が非常に重要になります。猫によっては、自分の口から出たキャットフードで少し水が汚れているだけでも水を飲むのを嫌がったり、水道から流れている水しか飲まなかったりする場合もあります。
最近では、常にきれいな水が流れる自動給水器も販売されています。水飲み場を増やしたり、室温に合わせて水の管理を徹底したりするのも熱中症対策によいでしょう。
猫のためのひんやりグッズを用意する
室温管理以外にも、猫のためのひんやりグッズを用意しておくとよいでしょう。初めて使うアイテムは、猫が破壊したり中身を誤飲したりしないように、しっかりと様子を見てあげてください。
- 冷却ジェルマット
- アルミプレート
- 放熱プレート
- クールマット
- アルミベッド
- ペット用扇風機
猫の熱中症対策に活用できるアイテムは、冷却するためのジェルや温度を冷たい状態に維持しやすいアルミ素材でできているものが多いです。アルミ製の商品も冷却ジェル商品も同様ですが、時間が経過すると猫の体温で冷たさが維持できないことがあるので、定期的に温度確認をしてあげるとよいでしょう。猫の体が冷えすぎないために、ひんやりグッズから自由に猫が移動できるよう工夫して、室温管理にも気を配ってあげてください。
冬におすすめの室温設定と寒さ対策

猫は一般的に、犬よりも寒さに弱い生き物です。体が冷えすぎてしまうと免疫力低下だけでなく、低体温症、尿路結石や膀胱炎を中心とした泌尿器系の疾患を引き起こすリスクがあります。そのため、冬の寒さ対策をおこなうことが大切です。
冬のエアコン設定温度は21~28度程度
冬にエアコンは必須ではありませんが、寒い地域に住んでいる方はエアコンが必要になります。雪が頻繁に降るような地域では、外出時もエアコンをつけておいてあげましょう。設定温度は21~28度程度が目安ですが、室温管理のために温湿度計を設置して、都度室温を確認してあげてください。
なお、エアコンをつけると乾燥しやすくなります。そのため、冬は室温管理だけでなく、湿度も50~60%の間になるように加湿器を導入してあげるとよいでしょう。
こたつやストーブなどの暖房器具に注意
こたつの中に入るのが好きな猫が多く、ストーブ前も猫は好みます。こたつやストーブを使用する時は、いつも猫の様子や室温、こたつの中の温度を気にかけてあげましょう。暑くなりすぎてしまうと、低温やけどや一酸化炭素中毒、熱中症のリスクが生じます。また、こたつの中はやけどの原因になりやすいので、一番低い温度設定にしておくことが大切です。
ストーブを使用する場合は、やけど防止用のストーブガードやヒーターガードを設置しましょう。猫がジャンプしてしまうことを配慮して、屋根付きのペット用サークルを活用するのもおすすめです。
水飲み場を増やす・水の温度を上げる
猫は寒さに弱いため、冬場は冷たい水を避けましょう。一般的に常温の水を好みますが、猫が常温水を飲まない場合は、人肌温度程度の水を準備してあげてください。また、人と同様に寒くて動きが活発でなくなる猫もいるため、猫がよく寝ている定位置にも、水飲み場を増やしてあげることをおすすめします。
日光浴できる場を設ける
冬は室温管理だけでなく、カーテンをあけて自由に日光浴できる場所を設けてあげましょう。冬場は血行が悪くなりやすいですが、愛猫に日光浴をさせてあげることで血液の循環を円滑にすることもできます。
猫のためのあったかグッズを用意する
ここでは、猫のためのあったかグッズをご紹介します。冬の寒さ対策として室温管理も大切ですが、近年はさまざまなペット用のあったかグッズが販売されているため、愛猫が好みそうなものを準備してあげましょう。
- ペット用カーペット
- ドーム型ベッド
- 電気を使用しないホットマットレス
- 猫用寝袋
- ペット用湯たんぽ
電気を使用するものは感電しないよう十分に注意し、定期的に猫が暑くなりすぎていないか確認してあげてください。また、電気不使用で猫の体温で寝床が温まりやすくなる素材のドーム型ベッドや猫用寝袋は、感電リスクがなく安心して使用できるためおすすめです。ペット用の湯たんぽは、安全に配慮した厚手カバーがついているものが多く販売されています。
猫が暑い時・寒い時に見せる仕草

猫の適正室温は21~28度程度と幅が広く、猫種や個体、年齢によって適正室温も大きく異なります。そのため、愛猫に適した室温管理には、猫が見せる仕草で判断することが重要です。
暑い時
- お腹を見せて寝る(軽〜中度)
- グルーミング頻度が増える(軽〜中度)
- 食欲低下(重度)
- 元気喪失(重度)
- パンティング、息が荒くなる(重度で緊急性を要するケースが多い)
また、食欲低下や元気喪失、パンティング※が見られる場合は熱中症になりかけている可能性があるので、動物病院に連絡して獣医師に診てもらうとよいでしょう。
※口を開けて舌を出し、浅く速く呼吸する行動
動物病院の受診を勧められた場合は、車内を涼しくして連れて行きます。また、愛猫の様子次第では、動物病院で熱中症の応急処置案内があるケースがあるので、獣医師の指示に従いましょう。
寒い時
寒さに弱い猫といっても、暑い時と同様に猫の個体差や年齢、猫種や発症している病気の有無、種類によって、その猫にとっての適切な温度は異なります。室温や寒さ対策は、個々の愛猫の様子を見ながら調整してあげましょう。
- 体を丸めて寝ている(軽〜中度)
- 普段以上に飼い主にくっついて寝る(軽〜中度)
- 普段以上に同じ場所から動かない(軽〜中度)
- 猫の体が震えている(中〜重度)
- くしゃみの頻度が高い(中〜重度)
猫は寒いと動きたがらなくなったり、丸くなって寝たり、飼い主から離れないなどの仕草をみせます。体が震えている場合は、早めに室温を高くしてあげましょう。また、くしゃみの頻度が高い場合は猫風邪に注意が必要です。くしゃみに加えて、その他の症状(鼻水が出たり目やにが目立ったりする、食欲低下が見られる場合)が併発している際には、動物病院の受診をおすすめします。
猫の室温調整に関するポイントと注意点

猫の室温調整をする時は、同時に湿度管理と猫の年齢、暖房器具等のつけっぱなしに注意してあげることが大切です。
温度だけでなく湿度にも気を配る
猫のための室温調整は必須ですが、同時に冬場を中心とした乾燥が生じやすい時期は、湿度管理もおこないましょう。猫の適正湿度は50~60%の間が目安です。必要に応じて加湿器を導入してあげるとよいでしょう。梅雨を中心に湿度が高くなりやすい時期には除湿機を設置してあげて、人の体感だけでなく温湿度計で計測してあげると安心です。
子猫・シニア猫は特に注意
猫の室温調整は、年齢によって大きく異なります。子猫やシニア猫に関しては、成猫より免疫力が低下しているケースが多いため、室温目安は25度前後です。
また、生まれたばかりの生後1~2週程度の子猫なら、体がまだ出来上がっていないので室温が命に関わることがあります。室温目安は32~34度程度ですが、このように生まれて間もない猫については、さらにこまめに子猫の様子を見ながら室温管理を徹底してあげることが重要になります。
暖房器具はつけっぱなしに注意
ストーブやヒーター、こたつ等、電気や灯油を使う暖房器具に関しては、猫が温まり過ぎないようつけっぱなしに注意しましょう。つけっぱなしにしてしまうと、室温が上がり過ぎるだけでなく、湿度が下がりやすくなります。感電ややけどにも注意して、定期的に猫の様子や室温チェックをすることが大切です。
まとめ
猫の年齢や個体別の快適な室温、季節ごとの適切な室温や湿度、暑さ・寒さ対策について詳しくご紹介しました。暑さや寒さは、時に猫の命に関わるケースがあります。そのため、本記事を参考にしながら、室温や湿度管理に十分気をつけてあげましょう。
物件を探す






