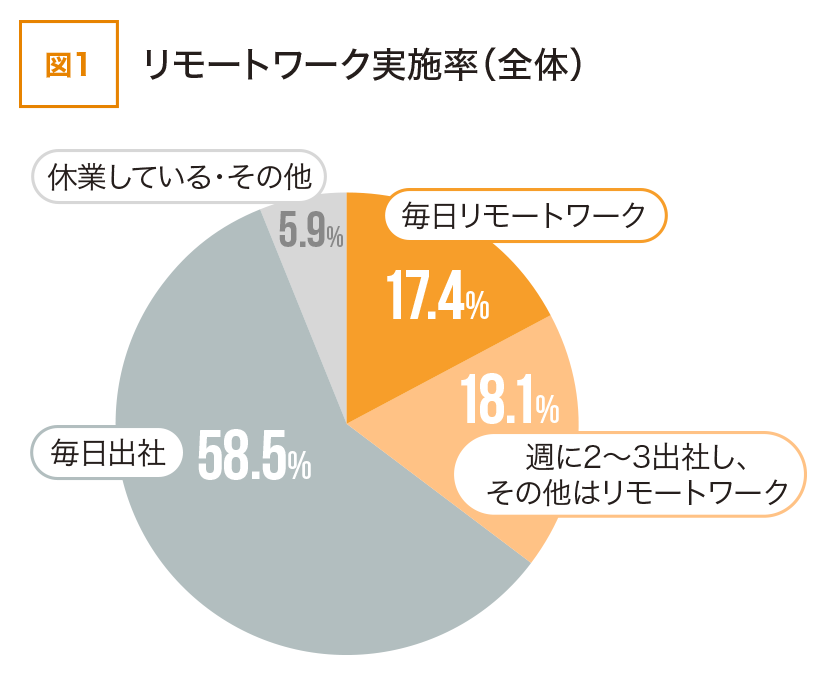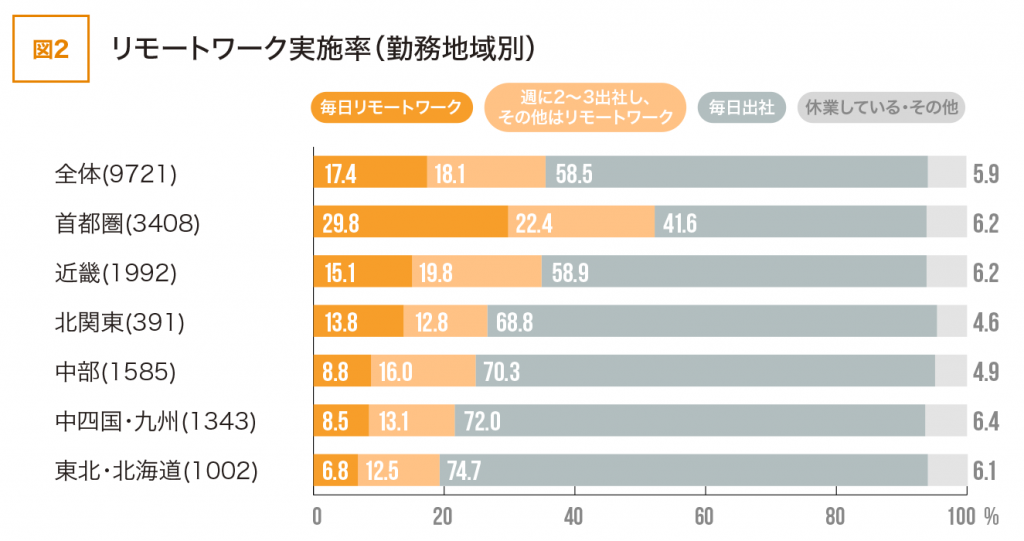新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、テレワークの認知度も高まりましたが、企業や働く人々にとってどのような変化がみられ、今後どのように発展していくのでしょうか?
一般社団法人日本テレワーク協会の専務理事を務める田宮一夫氏にお話を伺いました。
―― 新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、テレワークに対する意識は社会全体で、どのように変わりましたか?
田宮一夫氏(以下、田宮):「テレワーク」という言葉は浸透しましたが、「テレワーク=通勤できない、人と接触できないので在宅勤務」という形であったことが残念です。
本来テレワークは、在宅勤務以外に、モバイルワークやサテライトオフィスでの勤務も含み、柔軟な働き方ができる、ワークライフバランスを実現できる、高齢者や子育て中の就業が促進できるといった、企業にも雇用者にも役立つ便利なものであり、働き方改革にも大きく寄与できるものです。
今後は、スマート社会に向け、本来の意味でのテレワークの発展に寄与したいと考えております。
―― テレワークに対し、若者と中高年ではどのような認識の違いがありますか?
田宮:一般的にですが、ITリテラシーの違いと、これまでテレワークの無い社会を生きてきた長さによる固定観念の度合いが異なるといえます。また、内閣府が2020年6月21日に発表した「新型コロナウイルス感染症の環境下における生活意識と行動変化に関する調査結果(PDF)」
では、地方への移住について「関心が高くなった」と答えた人が全体では15%だったのに対し、20代では22.1%、30代では20%となり、特に東京23区内の20代では35.4%にのぼった点は注目できる点と考えます。
―― 管理職と一般職ではどのような意識の違いがありますか?
田宮:管理職もテレワークを行うことが前提ですが、管理職は利用者としての側面のみでなく、日々の勤務管理や評価、チームとしての業務の進捗や業績など管理上の切り口でも捉える必要があります。評価やコミュニケーションに関する課題が出てきたところも管理職として今後対応していくことが重要なポイントです。
―― 様々な企業がテレワークを導入していますが、求人募集においては、どのような変化が起こっていますか?
田宮:離職防止をはじめ、特に中小企業での採用強化へと繋がりました。さらに労働人口確保、地方創生へと繋がっていると考えています。当協会でコールセンター業務を委託した際も、在宅の方々に対応していただき、コロナ禍でも業務を遂行していただけました。募集する側も応募する側も選択肢が広がり、勤務地の欄が無くなる世界も遠くないと考えます。
また、採用についても、インターネットが普及していく過程において「メール応募」をどこから認めるか、どう評価するかが話題になった時期がありました。WEB面談が同様の状況だとすると、今後において急速にシフトしていくことが想定されます。
―― テレワークを導入してるのはどのような業種が多いですか?
田宮:テレワークは、業種ではなく職種です。昨今では建設業や製造業もテレワークを取り入れるところが増えていますので、どのような業種においても、という世界もそう遠くはないと考えます。
―― どのような人材がテレワーカーに向いていますか?
田宮:一言で申し上げると「時間管理を行える人材」です。働きすぎが課題になっており、メール送付の抑制やシステムへのアクセス制限、テレワークの際の時間外労働の原則的な制限などを検討することが求められています。
―― テレワークのメリットとデメリットを教えてください。
田宮:企業にとってのメリットは、①生産性の向上・優秀な人材確保 ②ダイバーシティ経営(女性・高齢者・障がい者)③事業継続性の確保(BCP対策)④オフィスコストの削減
就業者にとってのメリットは、①ワークライフバランスの向上 ②育児・介護中の仕事(就業)継続 ③通勤時間削減による時間の有効活用 ④多様な働き方の確保
社会にとってのメリットは、①労働力人口減少の緩和 ②高齢者・障がい者・遠方居住者の雇用創出 ③地域活性化 ④環境負荷の軽減
デメリットと申しますか、課題としては、働きすぎ防止とコミュニケーションやテレハラ・リモハラと呼ばれている現象です。テレワークだからこそ過剰に働いてしまう、過剰な管理をしてしまう、干渉が気になるといったところです。
―― 沖縄や北海道、リゾート地に住みながら、東京や大阪の企業にテレワークで働くなんてことも出来ると思うのですが、実際にそのような働き方は行われていますか?また、今後そのような働き方は増えると思いますか?
田宮:「ワーク(仕事)」と「バケーション(休暇)」を組み合わせた「ワーケーション」という言葉で浸透しています。出張先での休暇や旅行先などでの仕事を認める制度で、和歌山県南紀白浜町、長野県塩尻町・軽井沢町、北海道知床斜里などは、サテライトオフィスを設置するなどワーケーションしやすい環境を提供し、県の宿泊料補助制度もあります。
また、企業側では日本航空株式会社(JAL)が、2017年7月から最大5日間、海外を含めた旅先・出張先でのワーケーションを導入しています。
コロナ禍の影響もあり、密を避ける意味でも当然ながらこのような働き方は増えていくと思います。
―― 実際にテレワークを行っている人たちからは、孤独を感じたり、なかなかコミュニケーションがとりにくいという話も聞きますが、どのように回避することができますか?
田宮:朝・夕にチームミーティングを実施する、Web飲み会を開催する、中にはオンラインゲームでコミュニケーションを図るといった事例も出ています。ミーティングの際にはビデオをできるだけオンにし、顔の見えるコミュニケーションを行うことをおすすめします。
―― コワーキングスペースやレンタルスペースなどよく耳にするのですが、どのような違いがあるのですか?また、どのようなときに利用すればいいのでしょうか?
田宮:オフィスと自宅以外の第三の場所(サードワークプレース)には、レンタルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースの他、カフェや、カラオケボックス、ホテル、ロビー等公共スペースなども含まれます。
レンタルオフィスは、デスク・チェア・インターネット回線などのオフィス設備が揃っている貸事務所で、個室になっているため、セキュリティ面でも安心に使えます。
シェアオフィスは、自分だけでなく複数の利用者がフリーアドレス形式で使用し、個室でなく図書館のようなオープンスペースを利用します。
コワーキングスペースは、シェアオフィス同様、複数の利用者とオープンスペースを利用します。利用者同士のコミュニケーションが可能で、お互いの知識や情報などを共有する場として利用されています。また、セミナーや勉強会などで使われることも多いです。
その他、テレワークセンター、フューチャーセンターなどといった呼称もありますが、それぞれのオフィスやスペースによってサービス形態も異なりますので、事前に調べて利用すると良いでしょう。
―― 在宅ワークをする際、仕事のオンオフがつきにくい場合はどうすればいいですか?また、誘惑に負けたり気を散らすことなく仕事の生産性をUPさせるコツを教えてください。
田宮:その日やることを明確にし、上司等と共有する、日単位に進捗報告を行うこと。
また、上司や同僚ときちんとコミュニケーションをとること。自分なりの目標を定め、目標が達成できたご褒美を用意するといった例があげられ、当協会職員も実践しています。