【経験者に聞く】学生結婚のメリット・デメリットは?扶養や必要な手続きもご紹介

そこでこの記事では、実際の経験談も交えつつ、学生結婚のメリット・デメリットや入籍にともなう準備などを解説していきます。
記事の目次
学生結婚とは

学生結婚とは、高校・大学・大学院など、学業を主としている学生期間に結婚することを指します。一般的には20代前半頃までの若いうちに結婚することになり、また就職前であるケースがほとんどでしょう。例えば「子どもができた」「できるだけ早くから身を固めたい」など、学生結婚をする理由はさまざまです。もちろん日本の法律上では正式に認められている行為で、立派な人生の選択肢の一つ。
また国立大学をはじめ、学校によっては結婚して独立生計になった場合など、授業料免除の申請が認められる可能性もあります。厳しい認定基準があるので難しいかもしれませんが、学生結婚を考えているのであれば、覚えておくといいかもしれません。
18歳から結婚できる
現在の日本では民法上の成年年齢は18歳。つまり18歳なら未成年ではないため、たとえ学生であっても、法的には保護者の同意に関わらず結婚できます。
【経験者に聞く】学生結婚ってどう?

では実際のところ、学生結婚をしてみてどうなのか、経験者からのリアルな感想をピックアップしてご紹介。次のように、さまざまな声が挙がりました。
学生結婚をしてよかった人の声
- 体力あるうちに子育てできること。結婚子育てについて深く話し合う機会を設けたので、お互いの考えや子ども、自分の将来についてその都度把握できていること。後悔はないです。(20代/女性)
- 結婚当初の生活が大変だったが、いろいろ乗り越えて今でも仲良く過ごせていますし、子どもにも恵まれたのでよかったと思います。(40代/女性)
- 結婚後すぐに働かなくて、しばらく自由に過ごせたこと。老後まで味わえない自由を先取り。(70代/男性)
学生結婚の場合、社会人を何年か経験してから夫婦になるカップルに比べて、早いうちから二人のライフプランを練りやすい傾向にあります。結婚が早い分、将来設計のすり合わせもしやすく、何歳でどうしたいか柔軟に計画できる面もあるでしょう。
また一緒に長い時間を過ごして、二人でさまざまな経験をし、絆が深まったエピソードも。なかには、学生生活と結婚生活の両立を前向きにとらえて、貴重な体験ができたと感じている人もいるようです。
学生結婚をして後悔している人の声
- 金銭面的に厳しいのと若い時の自由がない。(20代/女性)
- 社会を知らない者同士だとぶつかる。(30代/女性)
- 早過ぎた。(40代/男性)
やはり学生結婚では、若さがゆえに苦労する一面も。学生生活と両立しようと思うと、周りとのギャップや自分自身の未熟さなどを実感して、結婚を後悔してしまうこともあるようです。とはいえ先ほどのコメントにも出てきたように、その厳しさを乗り越えられたら、また感想は変わってくるかもしれません。ですが現実的には、決して学生結婚は甘くはないことも、頭に入れておいたほうがよさそうです。
学生結婚についてどちらともいえない人の声
- 若い親でいられる。金銭面は厳しすぎです。(30代/男性)
- 生活費や家賃の無駄が省け一緒にいたいという欲求は充足できた。アルバイト収入だけでは生活は苦しくいつも切り詰めた暮らしをしていた。若すぎたことは武器にもなったが障害にもなった。自分たちの選択を後悔はしていないが、卒業を待ってから結婚してもよかったと今では思っている。(70代/女性)
なかにはコメントにあるように、「結婚は後悔していないけれど、学生のうちでなくてもよかったかもしれない」との声も挙がっていました。結婚は、必ずしもお互いの絆をつなぐものではありません。最終的に人生のパートナーになるのであれば、社会人になって生活や経済の基盤をつくってから結婚する選択肢もあります。さまざまな可能性が考えられるからこそ、すぐに結婚するのにこだわらなくてもいいのかもしれません。
学生結婚のメリット

ではここまでに見てきた経験談もふまえながら、学生結婚をすることでどのようなメリットがあるのか、以下から詳しく見ていきましょう。
パートナーと長く一緒にいられる
もし学生結婚をして同居するようになれば、早くから二人でずっと長い時間をともにできるメリットがあります。「できるだけ離れたくない!」というカップルにとっては、学生結婚は理想ですよね。学校に行って、アルバイトをして……など何かと忙しい学生のうちは、二人の時間も確保しづらいですが、一緒に生活してしまえばいつでもそばにいられます。
また厚生労働省が発表した「令和6年簡易生命表」によると、男性なら約81歳、女性なら約87歳が日本人の平均寿命です。仮に20代前半までに学生結婚をすれば、少なくとも約60年は人生をともに歩めて、絆を深められる一面も。夫婦の思い出をたくさん増やしていけるのは魅力です。
人生設計を早くから立てられる
学生結婚をして、若いうちから将来的な計画ができるのも利点です。前述にもあるように、早くに結婚すれば二人の時間も長くなるので、夫婦としての選択肢も広がりやすくなります。授かり婚だと難しいですが、いつか子どもがほしいと考えているカップルなら、出産のタイミングも二人で決めることもできます。
例えば20代のうちにマイホームを検討している場合にも、若くから二人で貯金をはじめていれば、早いうちから住宅ローンを開始できる可能性も。二人のライフプランを早めにイメージできるのは、長い人生においてプラスといえるでしょう。
就職先などを家族優先で考えることができる
就職活動の時点で結婚していることになるので、すでに家庭があることを考慮したうえで職場を選べるのはメリットです。
例えば、パートナーと将来設計を相談しながら就職先を探すこともでき、より理想的なライフプランを描きやすくなります。出張や転勤などの可能性も低い仕事を選択すれば、家族との時間も過ごしやすくなります。また夫婦の今後に合わせて、扶養手当や育児支援制度などの福利厚生も確認しておくと、家庭との両立に役立つでしょう。
体力のある時に出産・子育てができる
授かり婚やすぐにでも子どもを考えているカップルなら、若くて体力のある20代のうちに育児ができます。例えば20歳で出産すれば、自分が40歳になる前には子どもが成人するため、子育てが早くに落ち着くのはメリットです。この計算でいけば、30歳頃には小学生くらいになっているので、30代ですでに身軽に動きやすくなります。
育児が若いうちに済んでしまえば、夫婦二人で楽しめる時間も長くなりますし、充実したセカンドライフが過ごしやすいのも大きな利点でしょう。
学生結婚のデメリット

先ほどの経験談でも出てきたように、若くして家庭を持つことは、決して簡単なことではありません。では具体的にどのような注意点があるのか、以下から解説していきます。
自由な時間が少なくなる
結婚ができる18歳を迎えて成人になる頃は、ちょうど誰もが羽を伸ばして遊びたい時期です。そうしたタイミングで結婚や出産をすると、周りの友達たちが自由に時間を過ごすなかで、自分だけ家事や子育てに力を注がなくてはなりません。
すでに家庭を持っているのであれば、やはり家族との時間も大切にする必要があり、自分だけの自由を手にするのは難しい一面も。さらに学業やアルバイトなども並行するとなれば、かなり多忙になることは覚悟しておいたほうがいいかもしれません。
経済的に困難になりやすい
本格的に就職しているわけではないため、やはり収入面での余裕がない場合が多く、経済的には非常に厳しくなることが予想されます。さらに授かり婚となれば、出産や育児に向けた費用も準備する必要があり、産前産後のママさんが働くのは体力的に難しいことも想定しておかなければなりません。もし頼れるなら、親御さんたちの協力も得ながらでないと、学業と両立して学生結婚をするのは難易度が高いでしょう。
例えば親の事業を引継ぐ、自分で事業を立ち上げて収益しているなどの場合は問題ありませんが、学生のアルバイトで生計を立てていくのは、なかなか困難かもしれません。
就職活動で不利になる場合がある
経済的に自立していない状態での結婚に対し、場合によっては「計画性に欠ける」などのマイナスな印象を持たれてしまう可能性もないとはいいきれません。学生結婚はまだまだ珍しいケースなので、なかにはよくないイメージを持つ人もいます。また結婚は、今は子どもがいなくても、出産や育児を想起されやすい一面があります。
例えば「採用してもすぐに育休や時短勤務になってしまうのでは?」と懸念されて、入社を見送られてしまうケースも。とはいえ最近では働き方改革が進み、生き方の価値観も多様化しているため、前向きに受け入れる企業もあります。面接などで自分の将来設計をアピールできれば、反対に学生結婚がプラスな要素につながることも。事前に企業風土などをしっかりと調べて、受け入れてくれそうな就職先なのか見極めることも重要です。
学生結婚を考える時に重要なポイント

学生結婚を考える時に、いくつか知っておきたいポイントがあります。以下から詳しくみてみましょう。
卒業を優先する
結婚後も在籍している学校を中退などはせず、卒業することをおすすめします。仮に中退をしてもさまざまな生き方ができる現代ですが、学歴で希望する職種や企業に就職できなかったり、収入に差が生まれるケースも。将来的に安定して生活するためにも、学校を卒業するのは重要なポイントとなるでしょう。
親の理解・協力を得る
結婚をする際に大切なのが親の承諾です。学業と結婚生活や子育てを両立するのに、夫婦二人だけでは立ち行かなくなることもあるかもしれません。その際に親の協力が得られれば、大きな支えとなるでしょう。学生結婚をする際の親の説得の方法は後述しますので、ぜひお役立てください。
将来設計を具体的にする
学生結婚に限りませんが、結婚前に2人で将来設計を具体的にしておくことも大切です。「子どもは何人ほしいか」、「20年後はどこでどうしていたいか」などを話し合っておくことで、円満な夫婦生活を築けるきっかけになるでしょう。
家での役割分担を決めておく
結婚生活を始める際、事前に家事などの役割分担を決めておくのもおすすめです。曖昧なままにしてしまうと、どちらか一方に負担が偏り、夫婦関係がこじれる原因となってしまうかもしれません。事前にお互いの得意なこと、苦手なことを話し合い、それぞれを補い合えるような役割分担をするとよいでしょう。
以下は同棲するカップル向けの記事ですが、結婚生活に共通することもあるためぜひ合わせてお役立てください。
学生結婚に必要な手続き

では、学生結婚で入籍して、新生活をスタートするにあたり、必要な手続きを確認していきましょう。
婚姻届を提出する
入籍の手続きでは、婚姻届を記載して最寄りの役所に提出します。なお婚姻届を出す際には、本籍地を設定するので、どこにするのか二人で決めておきましょう。夫婦どちらかの現在の本籍地や、二人が同棲している現住所など、特に指定はありません。ただし本籍地の管轄とは異なる地域の役所に提出する場合には、戸籍謄本の添付が求められます。
例えば自分の本籍地がある地域で婚姻届を出すのであれば、パートナーの戸籍謄本が必要です。もし二人ともの現本籍地と違う地域で婚姻を出すなら、双方の戸籍謄本を提出しなければならないため、あらかじめ用意しておきましょう。
扶養者・健康保険変更の手続きをする
学生同士の場合、どちらも保護者の扶養になっているケースが多いでしょう。結婚後も大幅に収入が増えない見込みなら、学生のうちは、それぞれで現状のまま保護者の扶養から抜けない選択も可能です。ただし個々の所得額次第では、扶養から外れる場合もあるので要注意。
例えばアルバイトを増やして、年収額が一定基準を超えるなら、扶養を抜けて自分で所得税や社会保険料も負担しなければなりません。扶養控除や社会保険料については、家族やパートナーとよく相談しながら、手続きを進めていく必要があります。
大学での手続きをする
入籍して夫婦同姓になったら、姓が変わるほうは大学にて名義変更などの手続きをします。また授かり婚で休学する際にも、大学への申請が必要です。なお前述にも出てきたように、学生結婚をして自分たちだけで生計を立てていく場合、低所得世帯として学費免除などが認められるケースも。
こうした学校側の支援制度を活用するのであれば、一度ホームページなどを確認して手続きを進めていきましょう。
一緒に暮らす部屋を探す
結婚して新たに同居するなら、二人で暮らす部屋や引越しの準備も必要です。なお「不動産情報サイト アットホーム」では、新婚カップル向けの賃貸物件も多数掲載しています。ぜひ新生活に向けて、快適な住まいを探してみてくださいね。
親を説得するには?

結婚は二人だけの問題ではなく、それぞれの家族の縁を結ぶもの。双方の親御さんにも納得してもらったうえで、祝福されながら結婚生活を始めるためにも、きちんとした話し合いの場を設けるようにしましょう。
【経験者に聞く】学生結婚をする時、どうやって親を説得した?
実際に学生結婚をした人は、どのように両親の了承を得たのでしょうか。
- 家族ぐるみで仲が良かったので特にない。(10代/女性)
- ありまのままにいう。(20代/男性)
- 将来設計や生活費のことなどを具体的に説明した、納得してもらうまで、何度も通った。(20代/女性)
- 中学生から付き合っていたので反対されなかった。(30代/女性)
- きちんと労働をアピールする。(40代/男性)
- 好きになったことをとくとくと伝えた。(40代/女性)
- 無理は承知で説得を根気よくする。(50代/男性)
将来設計や金銭面などを具体的に説明したという声が多数でした。納得してもらうまで何度も根気よく説得したという人も。なかには、結婚する前から家族ぐるみで仲がよかったり、理解を得ていたりして、スムーズに進んだケースもあるようです。また、「説得はしていない」、「事後報告だった」、「絶縁した」などの声も見られましたが、親の了承を得ないままの結婚はできるだけ避けた方がよいでしょう。
親を説得する時のポイント
実際に親を説得する際、どのようなことに気を付けたらよいでしょうか。抑えておきたいポイントを解説します。
誠意を持って伝える
なぜ社会人になる前に結婚する必要があるのか、今後どのように生計を立てるかなど……。しっかりとした計画性がないまま結婚するのは、親御さんにとっても不安です。今すぐに学生結婚をしなければならない理由や今後の生活など、親御さんにも相談しながら、納得してもらえるようにしましょう。
親の意見もしっかりと聞く
場合によっては、親御さんからの反対を受けてしまう可能性もあります。ただし難色を示している時こそ、感情的にならず冷静に対応することが重要。反対している理由をきちんと聞き、それに対して自分たちはどうしていくつもりなのか、現実的な対処法を提示することで説得できることもあります。お互い頭ごなしに否定するのではなく、それぞれの意見を尊重する姿勢を大切にしましょう。
口論にならないように心がける
話し合いを進めていくうちにヒートアップしてしまい、こじれてしまうケースは少なくありません。言い合いになってしまうと、余計に心証が悪くなってしまい、反対する気持ちを増長させてしまう可能性があります。きちんと承諾が得られるように、自分だけの考えに固執せず、お互いの落としどころを探っていくことも欠かせません。
学生結婚に関するよくある質問

学生結婚のよくある質問をまとめました。
学生結婚とは?
高校・大学・大学院など、学業を主としている学生期間に結婚すること。「子どもができた」「できるだけ早くから身を固めたい」など、学生結婚をする理由はさまざまです。
学生結婚のメリット・デメリットは?
学生結婚には、人生の長い時間を一緒に歩めて、人生設計を立てやすいなどのメリットがあります。一方で、金銭面で困窮しやすかったり、自由な時間とお金が減り、独身の多い同世代の友達と疎遠になってしまったりするデメリットも。実現したいライフプランを具体的に考え、慎重に検討しましょう。
学生結婚で親を説得するには?
結婚をする際に重要となるのが親の承諾です。経済的にも生活面でも自立していないことが多い学生の頃に結婚をするとなれば、社会人の結婚よりも承諾に慎重になるのは自然なことでしょう。経済面や生活面などの将来設計を具体的に話して、理解を得ることが大切です。
まとめ
就職する前の学生結婚は、なかなか見ないレアなケースで、経済的にも時間的にも難易度は高いのが現実です。とはいえ若くに結婚するからこそ、ライフプランが描きやすいなどのメリットもあり、二人の絆が深まりやすい魅力もあります。もし保護者からまだ完全に独立しきれていない状況なら、もちろん親御さんとも相談しながら、結婚に向けて準備していくことが不可欠。
ぜひ本記事を参考に、二人にとって学生結婚がよい選択なのか、じっくり検討してみてくださいね。
【調査概要】
学生結婚をした方に質問です。学生結婚をした理由、よかったこと、後悔したことを教えてください。
調査方法:インターネットリサーチ
回答サンプル数:17人
対象:10代~80代男女(全国)
調査時期:2023年8月
「学生結婚に関するアンケート」
調査方法:インターネットリサーチ
回答サンプル数:10,000人
対象:10代~70代男女(全国)
調査時期:2025年11月
学生におすすめのお部屋探しアプリ「アットホームであった!」
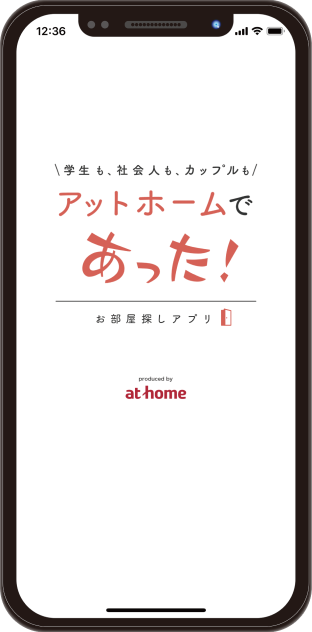
-
point1
簡単な質問に答えるだけ!ぴったりの条件を
自動設定 -
point2
気になるお部屋は
チャットで共有トーク機能 -
point3
先輩たちのアドバイス特集など初心者にうれしい
情報がいっぱい!
学生の一人暮らしにぴったりな住まいが簡単に見つかるアプリ
「アットホームであった!」
学生におすすめのお部屋探しアプリ
「アットホームであった!」
-
point1
簡単な質問に答えるだけ!ぴったりの条件を
自動設定 -
point2
気になるお部屋は
チャットで共有トーク機能 -
point3
先輩たちのアドバイス特集など初心者にうれしい
情報がいっぱい!
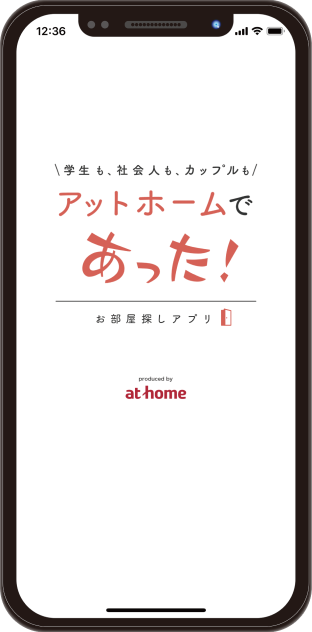
学生の一人暮らしに
ぴったりな住まいが簡単に見つかるアプリ
「アットホームであった!」
AppleおよびAppleロゴは、米国もしくはその他の国や地域におけるApple Inc.の商標です。
App Storeは、Apple Inc. のサービスマークです。
Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。








