引越し後の車庫証明の申請法は?必要なものから書類の書き方までわかりやすく解説
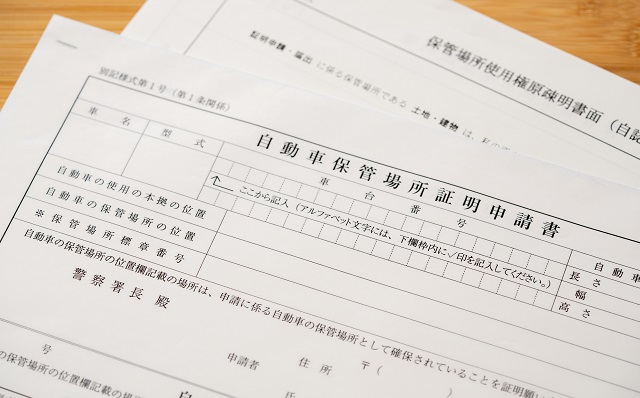
記事の目次
車庫証明とは?

車庫証明とは、自動車の保管場所の確保等に関する法律で定められた、正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれる書類を指します。基本的に普通車を所有する際には、必ず保管場所がある証明をする必要があり、法律で義務付けられた手続きです。ちなみに軽自動車では取り扱いが異なり、自動車保管場所証明書ではなく、「自動車保管場所届出書」の申請をします。
自家用車が普及している現在では、車庫証明によってマイカーの保管場所の確保をルール化することで、スムーズな交通や路上の安全が法的に守られています。仮に車庫の申請をしなかったり、申請とは異なるスペースで保管したりする行為は違法となってしまうため、正しく手続きをするようにしましょう。
車庫証明の交付条件は?
車庫証明では、申請すればどこでも保管場所として許可されるわけではありません。車庫証明を取得するためには、一定の条件を満たす必要があります。以下のすべてに当てはまる駐車スペースを確保しましょう。
- 保管場所が路上ではないこと
(例)敷地内または貸し駐車場、自宅のガレージ、空き地 など - 主に車を使う本拠地(自宅の住所)から直線距離2km以内の場所にあること
- 路上にはみ出すことなく、車体全体が収まる車庫であること
- 車が走ることのできる道路に問題なく出入りできること
- 確保した保管場所の正式な使用権利があること
(例)自身や親族名義の土地、分譲マンションや賃貸物件の敷地内の駐車場、賃貸契約済みの月極駐車場 など
後述で詳しく解説しますが、車庫証明の申請時には、上記の条件を満たす証拠となる書類の提出が求められます。
車庫証明の申請方法は?
車庫証明は、車の保管場所がある地域を管轄する、各地の警察署で申請します。大まかな手続き方法としては、各地域の警察署窓口にて、必要な書類の記入・提出をして完了です。より詳しい申請の流れは、後ほど解説していくので、ぜひ参考にしてみてください。
なお地域によっては、車庫証明が不要とされているケースも。車庫証明の適用除外地域で車を所有する際、車庫証明の手続きは発生しません。また同じく軽自動車でも、自動車保管場所届出書の手続きがない地域があります。車庫証明の適用地域は、自治体ごとに異なるので、各地域の警察署のホームページを確認してみましょう。
車庫証明申請は代行してもらえる?
車を購入した販売店やカーディーラー、行政書士事務所などに依頼して、車庫証明の申請を代行してもらうことも可能です。ただし、代行依頼にともなう手数料がかかってしまうので、コスト面が気になる場合には自分で申請するのがおすすめ。例えば「どうしても引越しでバタバタしていて時間が取れない」など、やむを得ない事情がある時には、代行を検討してみましょう。
車庫証明申請をしないとどうなる?
車庫証明の申請は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第4条で規定された法的義務で、正しい手続きがされていないと違法になってしまいます。場合によっては、法律違反として罰則が科せられる可能性も。例えば虚偽の内容を申請したら20万円以下、届出を出さなかったら10万円以下など、罰金が生じるケースもあります。「転居したのに住所変更を忘れていた」などの場合も、罰則の対象になる恐れがあるため注意しましょう。
引越し後の車庫証明申請はどうすればいい?

引越しをして住所が変わった場合、元の居住地で車庫証明があったとしても、転居先では新たに申請し直す必要があります。引越し先の地域を管轄する警察署にて、車庫証明を新しく取得するのは法律で義務化されているため、忘れずに手続きをしましょう。
引越し後の車庫証明申請に期限はある?
自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第7条では、駐車スペースの位置を変更した場合、15日以内にその旨を申請しなければならないとしています。期限を超えてしまうと違法になってしまい、罰則のペナルティが課せられる可能性も。車庫証明の未申請は、10万円以下の罰金になるリスクがあります。引越し後、さまざまな手続きがあると漏れてしまいがちですが、車庫証明の住所変更は、なるべく優先的に進めるようにしましょう。
車庫の住所が変わらない場合も申請が必要?
例えば「旧住所と転居先が徒歩圏内にある」といった、近隣で引越しをするケースでは、以前と同じ駐車場を使うことも想定されます。そうなると車の保管場所そのものは変わりませんが、使用者の住所が変更になるのであれば、新たに車庫証明は申請し直さなければなりません。先ほども出てきたように、車庫証明の交付を受けるには、「自宅から2km以内」などの条件が設定されています。新たな住所地と保管場所の位置関係が適切であることを証明する必要があり、たとえ同じ駐車場を利用する際も、住所変更の手続きは必須です。
車庫証明申請書の提出に必要なものは?

ここからは、車庫証明の申請にあたり、必要な提出書類や持参品を整理していきます。
車庫証明申請に必要な書類・書き方
まずは車庫証明の交付条件を満たしている証明として、提出が求められる必要書類から見ていきましょう。
【普通車の場合】保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書
「保管場所証明申請書」と「保管場所標章交付申請書」は警察署の窓口で入手するか、もしくは警視庁・各地の警察署の公式ページからダウンロードします。ちなみに上記の「保管場所標章」とは、車体に貼る円形の「車庫ステッカー」を指します。
上記の2つの書類は、用紙としては別々になっていますが、記入項目はほぼ同じです。そのため窓口の備え付けの書類では、保管場所証明申請書(2枚/提出分・控え)・保管場所標章交付申請書(2枚/提出分・控え)の4枚綴りになっています。複写式のため、1枚目に必要事項を記入するだけでOKです。なおダウンロードする際には、それぞれ2枚ずつ出力し、計4枚に必要事項を記入して提出します。
また各書類の主な記入項目としては、以下のとおりです。
- 使用者の氏名、住所(住民票に記載の新住所)、電話番号
- 車名(トヨタやホンダ、日産などのメーカー名)
- 型式、車台番号(車検証に記載)
- 自動車を使用する本拠点の位置(住民票に記載の新住所)
- 自動車の保管場所の位置(駐車場の所在地の住居表示)
- 書類提出左記の警察署名
- 使用者権限欄(車庫の所有者)
- 申請者の連絡先
- 申請区分(新規)
より詳しい記入例は、警視庁の「自動車の保管場所手続きについて」でも公開されているので、ぜひ一度チェックしてみてください。
【軽自動車の場合】保管場所届出・保管場所標章交付申請書
軽自動車の場合、自動車保管場所届出書を提出します。なお記入項目や書き方などは、基本的に先ほどの普通車のケースと同じです。こちらも警視庁の「保管場所届出手続(窓口申請)」から記載例を確認できるので、参考にしてみてください。
保管場所の所在図・配置図
所在図には自宅と駐車場の位置関係、配置図には駐車場そのものの場所を示す、簡単な地図を書きます。ちなみに「駐車場が自宅の敷地内にある」といった、同じ住所内に車庫がある場合などは、所在図のみ省略ができます。ただしいずれにしても、必ず配置図は必要なので、漏れずに提出するようにしましょう。なお所在図と配置図の記載方法は、以下のとおりです。
<所在図>
原則、実際の居住地と駐車場が離れている場合に、必要な記入項目です。自宅と駐車場の位置関係がわかる図を示すもので、周辺マップを紙に印刷して、貼り付ける方法でも問題ありません。また地図の貼り付けで対応する場合も含めて、下記の項目が明確に判断できる図を提出します。
- 自宅と駐車場の場所、それぞれの直線距離
- 自宅と駐車場周辺で目印になる建物(駅、学校、公共施設など)
- 自宅と駐車場付近の道路図
<配置図>
車庫として適切に利用できる土地なのか示すための図で、居住地に駐車場があるケースも含めて、すべての車庫証明で提出しなければなりません。配置図の場合は、下記の項目がわかる図を提出します。
- 駐車スペースの位置
(例)自宅なら敷地内のどこにあるか、月極駐車場なら全体図と借りたスペースの位置 - 駐車スペースの面積(縦○m×横○m)
- 駐車場の出入り口の幅
- 駐車場に面した道路の幅員
- 駐車場周辺で目印になる建物
また所在図・配置図の記載例も、警視庁「保管場所届出手続(窓口申請)2.保管場所の所在図・配置図」にあるので、確認してみてください。
【自己所有の場合】保管場所使用権原疎明書面(自認書)
車を使う本人自身で、駐車スペースとして利用する敷地やガレージを所有している場合、使用する権利がある証明として提出する書類です。用紙に記載された文言に沿って、該当する項目に丸を付けて、窓口となる警察署名・申請年月日・住所・氏名・電話番号を記入して提出します。
こちらも警視庁の「保管場所届出手続(窓口申請)3.保管場所の使用権原を疎明する書類(自認書または保管場所使用承諾書)」にて、記載例が公開されています。
【他者所有の場合】保管場所使用承諾証明書
例えば月極駐車場や分譲マンションの附帯スペースなど、車の使用者以外が所有する土地や車庫を使う場合に、法的な利用権利が与えられている証明として提出する書類が「保管場所使用承諾証明書」です。また親名義の敷地を使う際などにも、土地所有者が車の使用者本人と異なるため、保管場所使用承諾証明書が必要となります。
保管場所使用承諾証明書では、駐車場のオーナー・管理会社・マンション管理組合など所有者の署名欄があるため、早めから準備しておくと安心でしょう。
ちなみに賃貸物件や月極駐車場では、保管場所使用承諾証明書の代わりに、賃貸借契約書の写しの提出でも問題ないケースがあります。ただし保管場所使用承諾証明書の記入要件を満たす内容でないと認めらないので、担当窓口などへの事前確認をしておくのが無難です。
なお保管場所使用承諾証明書の主な記入項目は、以下のようになっています。
- 保管場所の位置(駐車スペースがある土地の住所)
- 車の使用者の新住所、氏名
- 保管場所の契約者(車の使用者本人なら「上記に同じ」)
- 保管場所の試用期間
- 保管場所の所有者や管理者の署名(住所、氏名、電話番号)
こちらも警視庁の公式ページより、詳しい記載例の確認ができます。
車の使用者の住所が確認できるもの
申請内容と、車の使用者の本拠点(引越し先の新住所)が合致している証明として、引越し先の居住地がわかる書類を提示します。具体例としては、運転免許証・国民健康保険証・マイナンバーカードなど。もしくは、新住所の住民票などでも問題ありません。
申請手数料
自治体ごとに異なりますが、車庫証明申請の手数料は、2,000円前後+保管場所標章(車庫ステッカー)の交付料金(500円程度)が一般的です。また、軽自動車における自動車保管場所届出書では、登録料金などは特にかからず、保管場所標章(車庫ステッカー)の交付料金のみです。
車庫証明の住所変更をしたら、正式な自動車保管場所証明書の受け取りをする必要があり、再度警察署の窓口に訪問します。通常であれば申請日より3日~1週間程度で交付通知が届くので、新しい車庫証明書を取得しに行きましょう。
車庫証明の取得時には、まず申請の際に警察署から受け取った、手数料のお知らせ(申請者控え)を窓口にて提示。そして警察署より、車庫証明書(自動車保管場所証明書)・保管場所標章番号通知書・保管場所標章(車庫ステッカー)の3つが交付されます。
引越し後の車庫証明申請の流れは?

ここまでには細かな申請内容を見てきましたが、以下からは手続きの大まかな流れを整理していきます。
- STEP 1車庫証明申請に必要な書類を揃えて記入する
- STEP 2管轄の警察署窓口へ提出する
- STEP 3交付が通知されたら受け取りに行く
引越し後の車庫証明申請で注意したいのが、手続きと交付で計2回、警察署の窓口に行く必要がある点です。新住所になった車庫証明は、取得に何日か時間がかかるので、できるだけ早めから余裕を持って手続きをしましょう。ちなみに車庫証明は、車検証の住所変更にも使う書類です。
いずれにしても、引越し後には車庫証明を取りに行くことになります。
順番としては、車庫証明の申請⇒車庫証明の取得⇒車検証の住所変更、の流れで進めると効率的です。
また車庫証明の申請には、登録手数料2,000円前後+保管場所標章交付料500円程度の用意が必要です。支払いができるように準備しておきましょう。
車庫証明についてよくある質問

引越しにともなう車庫証明の取り扱いについて、よくある疑問をQ&A方式でまとめていきます。
賃貸物件でも車庫証明申請は必要?
原則普通車を所有する場合には、必ず車庫証明の申請が必要です。例えば賃貸物件の敷地や月極駐車場を借りる際にも、車庫証明の手続きはしなればなりません。ただし賃貸物件では、不動産会社が代行で対応してくれるケースもあります。
保管場所標章(車庫ステッカー)を貼る位置は?
保管場所標章は、車の後面ウインドウに貼るのが原則です。ステッカーに記載された表示事項が後方からはっきりと確認できるように、見えやすい位置に貼り付ける必要があります。例えば後面にガラス窓がない・貼り付けが難しい・ステッカー表示が見えづらくなるなどの場合は、車体左側の見えやすい場所に設置します。
なお保管場所標章の貼り付けがなくても特にペナルティはありませんが、場合によっては警察から注意喚起を受ける可能性はあります。
車庫証明がいらない地域がある?
車庫証明の申請には、一部適用除外となる地域もあります。例えば人口が少ない・路上駐車が問題になりにくいなどの地域では、車庫証明が不要となるケースも。もし引越しで適用除外地域に転居した場合、車庫証明の住所変更は必要ありません。なお適用除外地域は、各自治体の警察署のホームページから確認できます。
車庫証明の住所変更は他人にお願いできる?
家族をはじめ、カーディーラーなどの代理人に代行してもらうことが可能です。車庫証明の申請は、原則委任状がなくても、代理人が手続きできることになっています。ただし記入項目に誤りがあった場合など、委任状のない代理人では対応ができないこともあります。もし代理人を立てるのであれば、念のため委任状があると安心でしょう。
まとめ
車庫証明の申請は、引越しをして住所が変わった場合、必ず対応しなければならない手続きです。基本的には警察署の窓口で届出をする必要があり、なんとなく難しく感じるかもしれませんが、整理してみるとさほど複雑ではありません。必要書類の書き方も、基本的には窓口に見本があり、その内容を見ながら作成できます。ただし事前に書類の準備や、申請と交付の2回警察署に訪問する必要があるため、できるだけ早めから優先的に対処するようにしましょう。
物件を探す



