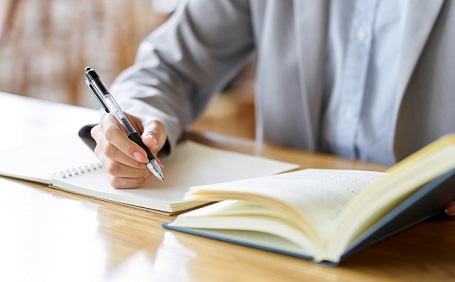賃貸併用住宅が「やめとけ」と言われる理由は?よくある後悔や失敗しないためのポイント

そこで本記事では、賃貸併用住宅が「やめておけ」と言われる理由や、よくある後悔を解説します。また、失敗しないためのポイントも解説するので、賃貸併用住宅を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
記事の目次
賃貸併用住宅が「やめとけ」と言われる理由

賃貸併用住宅の経営は、なぜ「やめておけ」と言われているのでしょうか。本章では、その理由と対策を解説します。
初期費用が高額になる
賃貸併用住宅の経営は「やめておけ」と言われる理由の一つは、初期費用が高額になるためです。賃貸併用住宅を建てるためには、土地・建物ともにそれなりの広さが必要になることから、自分で住むだけの一戸建て住宅と比較して、初期費用が高額になります。
また、賃貸部分の戸数が多ければ、その分のキッチンや浴室、トイレなどの設備も必要になるため、設備投資も高額に。さらに、複雑な設計が必要となることから、設計費用も高くなる傾向があります。これらのことから初期費用が高額になるため、賃貸併用住宅の経営は「やめておけ」と言われる理由になっています。
初期費用が高額になるため、安定した賃貸経営をおこなうことが求められます。安定した賃貸経営をおこなうためには、賃貸需要を調べ、入居者のニーズに合った賃貸併用住宅を作らなければなりません。収益性があると判断されれば、金融機関からの高額な借り入れも可能となります。不動産会社に相談し、周辺地域の賃貸需要や入居者層を確認して「入居したい」と思ってもらえるような賃貸併用住宅を建てましょう。
自宅部分の設計が制限される
自宅部分の設計が制限されることも、賃貸併用住宅の経営は「やめておけ」と言われる理由の一つです。賃貸併用住宅は、自宅部分と賃貸部分を一つの建物内に併設します。プライバシーを確保したり、建物の耐久性を考慮したりするため、注文住宅のように完全に自由に設計できるわけではありません。
しかし、賃貸併用住宅の施工実績が豊富なハウスメーカーであれば、オーナーの希望を叶えつつ、収益性の高い物件を作ることは可能です。例えば、入居者となるべく顔を合わせたくない場合、エントランスを分ける、外部の視線を遮るインナーバルコニーを作るといったことが考えられます。ただし、すべての希望が通るわけではない点を理解しておきましょう。インターネットでさまざまなハウスメーカーの施工例を見られるため、一度調べてみるといいでしょう。
入居者の確保が難しい
賃貸併用住宅は、入居者の確保が難しいことから「やめておけ」と言われています。賃貸併用住宅はオーナーが同じ建物内に住んでいるため、プライバシーを重視する方から敬遠される傾向にあります。入居者が決まらず、空室期間が長期化すると、家賃収入がまったく得られない可能性も。
そのため、「オーナーが同じ建物内に住んでいても入居したい」と思ってもらえるよう、入居者にとって魅力のある物件にしなければなりません。駅から近い、商業施設が充実している場所は、入居者を集めやすくなるでしょう。また、賃貸併用住宅の経営実績のある不動産会社に、入居者の募集を委託することも一つの方法です。
入居者から直接クレームがくる
賃貸併用住宅の経営では、入居者から直接クレームを寄せられることがあるため、「やめておけ」と言われています。オーナーが同じ建物内に住んでいることから、「鍵をなくした」「隣の部屋の生活音がうるさい」などといったクレームが直接寄せられる可能性も。対処法として、管理会社に管理業務を委託することが考えられます。オーナーではなく管理会社が窓口であることを、入居者に周知してもらうといいでしょう。
プライバシーの確保が難しい
プライバシーの確保が難しいことも、賃貸併用住宅の経営を「やめておけ」と言われる理由の一つです。例えば、壁が薄く遮音性が低い物件の場合、オーナーも入居者もお互いに「生活音が響いていないか」を気にしなければならないでしょう。そういった環境で日々を過ごすとなると、ゆっくり落ち着ける場所であるはずの家が、居心地の悪いものになってしまいます。プライバシーが確保できるよう、間取りや動線の設計を工夫してもらいましょう。例えば、マンションの場合、最上階を自宅にして直結のエレベーターを作る、一戸建ての場合は玄関の場所を変えるといったことが考えられます。
売却が難しい
賃貸併用住宅の経営は「やめておけ」と言われる理由の一つとして、売却が難しいことが挙げられます。賃貸併用住宅は、自宅と賃貸部分が併設されている特殊な物件です。そのため、購入希望者が限られます。例えば、持ち家として購入したい方にとって、賃貸部分は必要ありません。また、自宅をすでに所有しているオーナーにとって、賃貸併用住宅の自宅は不要です。これらのことから、賃貸併用住宅は購入希望者が限定されるため、売却が難しくなります。
もし賃貸併用住宅を取り壊す場合、入居者は借地借家法で保護されているため、オーナーの一存で退去させることは難しくなります。退去してもらう必要がある場合には、新しい引越し先を用意したり、引越し費用を負担し、入居者に負担がかからないよう配慮しましょう。
賃貸併用住宅のメリット

前章では、賃貸併用住宅が「やめておけ」といわれる理由を解説しましたが、もちろんメリットもあります。本章では賃貸併用住宅のメリットを4つ解説します。
家賃収入がある
賃貸併用住宅のメリットは、家賃収入を得られること。自宅として住みつつも、一部を賃貸することによって家賃収入が得られるのは賃貸併用住宅の魅力の一つでしょう。
住宅ローンを利用できる場合がある
賃貸併用住宅は、自宅部分を住宅ローン、賃貸部分を投資用ローンで借り入れることが一般的です。しかし、金融機関によって、一定の条件を満たした場合、住宅ローンを利用できる場合があります。例えば、スルガ銀行の「賃貸併用住宅ローン」は、自宅部分が50%以上の場合、住宅ローンとして取り扱われます。投資用ローンより住宅ローンのほうが金利が低く設定されているため、総返済額を抑えることが可能。また、賃貸部分で得た家賃収入を住宅ローンの返済に充てれば、さらに返済負担を軽減できるでしょう。
家賃収入を自宅の住宅ローン返済に充てられる
賃貸部分を貸し出すことで得た家賃収入を、自宅の住宅ローンの返済に充てられることも、賃貸併用住宅のメリットです。オーナー自身の収入からではなく、家賃収入を住宅ローンの返済に充てられれば、経済的な負担が軽減できます。例えば次の条件の場合、返済額がどうなるかシミュレーションしてみましょう。なお、賃貸部分は家賃5万円/戸、4戸とします。
| 条件 | 自宅 | 賃貸併用住宅 |
|---|---|---|
| 借入金額 | 3,000万円 | 5,000万円 |
| 返済期間 | 30年 | 30年 |
| 金利 | 2% | 2% |
| 月々の返済額 | 11万886円 | 18万4,810円 |
| 年間の返済額 | 133万632円 | 221万7,720円 |
| 家賃収入 | ― | 240万円 |
| 家賃収入ー年間の返済額 | ― | 18万2,280円 |
※元利返済式で返済すると仮定
賃貸併用住宅のほうが、借入金額が多くなるため、返済額も多くなります。しかし、家賃収入として240万円を得られるため、すべて住宅ローンの返済に充てたとしても、手元に約18万円残ります。このように住宅ローンの返済負担を軽減できる点は魅力的でしょう。ただし、賃貸経営では、固定資産税や管理委託料などの維持費がかかります。住宅ローンの返済に充てた後の家賃収入もすべてが手元に残るわけではないことを理解しておきましょう。
節税効果が期待できる
賃貸併用住宅は、節税効果が期待できる点もメリットの一つです。主に、相続税と固定資産税で節税効果があります。まず、相続税における節税の仕組みを見ていきましょう。
例えば、現金を相続する場合、相続税を計算する時のもととなる相続税評価額は、額面どおりの金額となります。一方、土地の場合は固定資産税評価額の約70%、建物の場合は固定資産税評価額の約70%です。具体例を挙げて計算してみましょう。
現金8,000万円を相続する場合
→相続税評価額:8,000万円
固定資産税評価額が土地3,000万円、建物5,000万円の場合
→土地の相続税評価額: 2,100万円
建物の相続税評価額:3,500万円
土地と建物の相続税評価額を合わせた額:5,600万円
不動産の場合、現金をそのまま相続するよりも、評価額が低くなるため、相続税も抑えられます。また、賃貸物件の場合、活用方法が限られることから、さらに相続税評価額が下がります。
次に、賃貸併用住宅の固定資産税における節税を見ていきましょう。固定資産税には「住宅用地の特例」があり、適用されると固定資産税が減額されます。具体的には次のとおりです。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分)
固定資産税評価額×1/6×1.4%
一般住宅用地(200平方メートルを超える部分)
固定資産税評価額×1/3×1.4%
なお、アパートやマンションの場合は、戸数×200平方メートル以下の部分が小規模住宅用地となります。
賃貸併用住宅の経営でよくある後悔
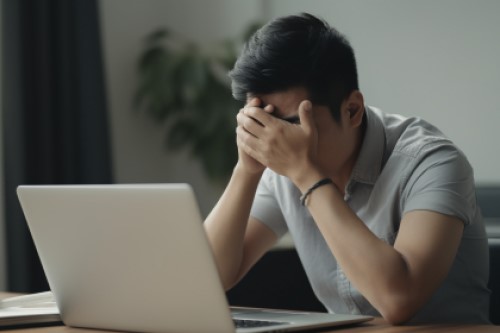
賃貸併用住宅が「やめておけ」と言われるのは、実際に後悔された方がいるからです。しかし、よくある失敗例を知り、ポイントを押さえれば、後悔のない賃貸併用住宅の経営が可能となるでしょう。本章では、賃貸併用住宅の経営でよくある後悔を取り上げます。
自宅が狭くなった
賃貸併用住宅は、賃貸部分と自宅を併設する住宅です。収益性を上げたいがために、賃貸部分を広くすると、その分自宅は狭くなってしまいます。
せっかく購入した自宅が狭いとなると、もう少し広くすればよかったと後悔するかもしれません。自宅と賃貸部分のバランスをよく考えて検討しましょう。何を優先したいのか、希望をすべて挙げ、優先順位を付けることをおすすめします。
思うような収益が得られなかった
賃貸併用住宅のメリットとして、家賃収入を得られることを挙げましたが、必ずしも期待どおりに収益を上げられるとは限りません。先ほどの家賃収入を住宅ローンの返済に充てたシミュレーションは、すべて満室であると仮定したものです。もちろん理想は常に満室であることですが、空室になったり、家賃を滞納されてしまう可能性もあります。
また、建物が古くなれば、修繕費もかかるようになるでしょう。さらに、もともと賃貸併用住宅は、入居者が集まりにくい傾向にあるため、賃貸経営は難しくなります。賃貸需要の高い場所に建てるだけでなく、賃貸併用住宅の経営実績がある管理会社に委託する必要があるでしょう。
入居者との関係が悪化した
賃貸併用住宅は、オーナーと入居者が同じ建物内で生活するため、トラブルが発生しやすくなります。例えば、生活時間や生活習慣の違いから、トラブルが起こることも。オーナーが賃貸部分に頻繁に出入りすることに、嫌悪感を抱く入居者もいるでしょう。入居者とオーナーの動線を分けるなどして、なるべく顔を合わせないようにする工夫が必要です。また、入居者から直接オーナーにクレームが寄せられることもあります。入居者との関係が悪化すれば、退去につながる可能性も。管理業務は管理会社に委託し、オーナー自身が窓口にならないようにしましょう。
賃貸併用住宅で後悔しないためのポイント

賃貸併用住宅の経営でよくある後悔を解説しましたが、事前に対策をすることも可能です。そこで本章では、賃貸併用住宅の経営で後悔しないためのポイントを解説します。
賃貸需要がある土地を選ぶ
賃貸併用住宅に限った話ではありませんが、賃貸経営を成功させるためには、賃貸需要の高い土地を選ぶことが重要です。賃貸需要が高い土地であれば、空室リスクを減らし、安定した家賃収入を見込めます。また、安定した入居率を維持できれば、物件の価値も下がりにくくなります。ターゲットとなる入居者のニーズを把握し、賃貸需要の高い土地を選びましょう。具体的には、次のポイントを確認しましょう。
- 駅からの距離が近いか
- 生活利便施設が充実しているか
- 再開発計画があるか
駅からの距離が近い場所は、賃貸需要が高い傾向にあります。また、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの生活利便施設の充実度も、入居者のニーズを満たすポイントです。他にも、再開発計画が予定されている場合には、インフラが整い、人の流れが増えるため、賃貸需要が高くなります。賃貸併用住宅を経営する際には、賃貸需要が高い土地を選びましょう。
賃貸部分の管理を管理会社に委託する
賃貸併用住宅の経営をおこなう際には、賃貸部分の管理を管理会社に委託しましょう。先述したように、賃貸併用住宅は入居者からのクレームが直接オーナーに寄せられる可能性があります。管理業務は、入居者の募集や賃貸契約、建物の管理など多岐に渡るもの。ノウハウや実績のある管理会社に委託すると、オーナーの負担を軽減でき、安定した賃貸経営が可能です。
入居者の審査をしっかりおこなう
賃貸併用住宅の経営では、入居者の審査をしっかりおこないましょう。入居者の審査を怠ると、トラブルが発生する可能性があります。例えば、家賃を滞納する入居者がいると、家賃収入が減り、経済的な負担がかかるかもしれません。また、近隣住民とトラブルを起こし、他の入居者に迷惑をかける可能性も。そのため、入居者の審査をおこない、信用度の高い方に入居してもらうことが大切です。管理会社に委託する場合は、審査の際にどのような基準があるのかを確認しておくとよいでしょう。
複数のハウスメーカーのプランを比較検討する
賃貸併用住宅の経営で後悔しないために、複数のハウスメーカーのプランを比較検討しましょう。複数のハウスメーカーを比較することで、さまざまな間取りや設備、デザインから選び、理想の賃貸併用住宅を建てられます。また、各ハウスメーカーの施工実績やアフターフォローなどを比較することで、より信頼できる会社を選択できるでしょう。さらに、賃貸併用住宅の借り入れは高額になるため、金融機関を紹介してくれる会社であれば、手続きもスムーズに進めやすいでしょう。
収支シミュレーションをおこなう
収支シミュレーションをおこなうことも、賃貸併用住宅の経営で後悔しないために重要なポイントです。賃貸経営では、空室になったり、設備が故障したりなど、さまざまなリスクがあります。また、固定資産税や管理会社への委託手数料などの維持費も必要です。これらを考慮せずシミュレーションをすると、万一の場合に破綻してしまうおそれも。家賃収入ばかりに目を向けるのではなく、リスクや維持費も考慮し、収支シミュレーションをおこないましょう。ファイナンシャルプランナーや不動産会社などの専門家に相談すると、適切なアドバイスを受けられます。
まとめ
本記事では、賃貸併用住宅の経営は「やめておけ」と言われる理由を解説しました。持ち家と違い、賃貸部分を併設するため、ある程度の広さが必要になることから、初期費用が高額になります。また、入居者と同じ建物内に住むため、プライバシーの確保が難しくなることも理由の一つです。しかし、賃貸併用住宅の施工実績が豊富なハウスメーカーに依頼すれば、間取りや動線を工夫してくれ、プライバシーを確保できます。また、自宅の広さを保ちつつ、賃貸部分の収益性を高められるでしょう。失敗しないためのポイントを押さえ、安定した賃貸併用住宅の経営をおこないましょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ