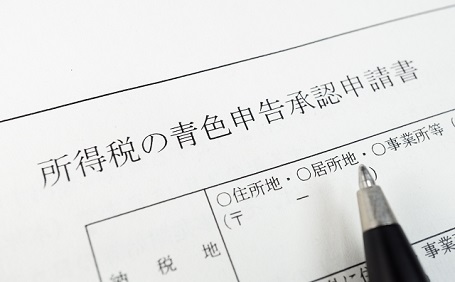家賃収入の確定申告をしないとどうなる?デメリットや対処法を解説

記事の目次
家賃収入がある場合は確定申告が必要

不動産投資で家賃収入がある場合、確定申告が必要となる可能性があります。家賃収入と給与・退職所得以外の所得の合計額が、20万円を超える場合は申告が必要です。ただし、赤字経営の場合は損益通算により、給与所得からの所得税還付が可能となるため、申告をすることでメリットが得られることもあります。
損益通算とは、所得税の総合課税方式により、家賃収入の損失を他の所得と相殺できる仕組みのこと。特に投資初期の段階では、初期費用の影響で赤字になりやすいです。確定申告をすることでメリットが得られる可能性が高いため、申告方法を確認しておきましょう。
相続した不動産で家賃収入を得た場合
相続した不動産からの家賃収入も申告が必要です。相続人は被相続人の死亡翌日以降の収入を申告する義務があります。
また、被相続人の死亡年の収入に関しても、相続開始を知った日から4カ月以内に準確定申告をおこなう必要があります。準確定申告は、被相続人の1月1日から死亡日までの収入が対象。
また相続税と所得税は別の税金で、相続税を納付したからといって、家賃収入に対する所得税の申告が不要になるわけではありません。相続した不動産の管理や収入に関しては、相続人がすべての責任を負うことになります。複数の相続人がいる場合は、各自の持分に応じて申告と納税をおこなう必要があります。
海外赴任中に家賃収入を得た場合
海外赴任中に家賃収入を得た場合も、日本での確定申告が必要です。所有している不動産が日本にある限り、日本の課税対象となります。
海外在住を理由に申告を怠ると、追徴課税のリスクも。さらに、日本に帰国した際に過去の申告漏れが発覚すると、延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があります。
ただし、海外赴任先の国と日本との間で二重課税防止条約が締結されている場合、適切な手続きを踏むことで二重課税を回避できる可能性があります。とはいえ、上記の手続きは複雑な場合が多いため、税理士や会計士などの専門家に相談するといいでしょう。
海外赴任中の確定申告は、e-Taxを利用すれば日本にいなくても手続きができる場合があります。ただし、「日本居住者」に限られます。
例えば、会社員の方で1年以上の海外勤務となった場合は、国内での引越しと同様に市役所に転出届を提出しなければなりません。この届出を提出すると、日本国内の住所が使用できなくなるため、e-Taxに必要な電子証明書が使えなくなります。そのため、海外に移住する前に確定申告を済ませるか、納税管理人の届出をしておきましょう。
家賃収入を確定申告していない場合のペナルティ
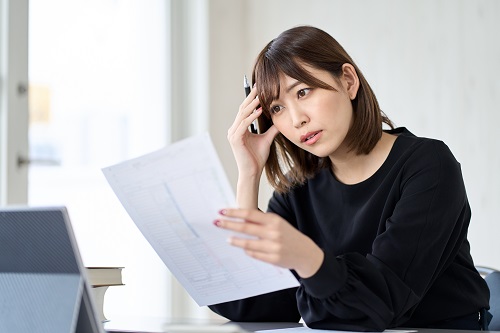
不動産投資による家賃収入がある場合、確定申告は単なる手続きではなく、法的義務です。この義務を怠ると、追徴課税にとどまらず、さまざまなペナルティが課される可能性があります。
ペナルティは、状況の深刻さに合わせて段階的に重くなり、最悪の場合、刑事罰に発展する可能性もあります。
確定申告を適切におこなわないと、金銭的なものだけでなく、社会的信用や将来の事業機会にも影響を及ぼすことも。特に不動産投資は、長期的な視点が必要なビジネスです。一度の申告漏れが将来の資金調達や事業拡大の障害となるかもしれません。
以下では、確定申告をしていないことで課されるペナルティを解説します。
無申告加算税
確定申告期限を過ぎると、無申告加算税が課されます。無申告加算税は、本来納めるべき税額に加えて課される追加の税負担です。具体的には以下のように、段階的な課税率が適用されます。
- 50万円までの部分:15%
- 50万円から300万円までの部分:20%
- 300万円を超える部分:30%
例えば、本来100万円の納税義務があったにもかかわらず、確定申告をしなかった場合の無申告加算税は17万5,000円(50万円 × 15% + 50万円 × 20%)となります。
ただし、税務調査前に自主的に申告をおこなえば、無申告加算税は一律5%に軽減されます。この場合、上記の例でいうと5万円がペナルティです。
また、特定の条件を満たした場合、無申告加算税が免除されることも。例えば、法定期限から1カ月以内に自主申告をおこなったり、過去5年間のペナルティ歴がなかったりなどが、免除の条件に該当します。
万が一期限を過ぎてしまった場合も、できるだけ早く自主申告することで、ペナルティを最小限に抑えられるでしょう。
過少申告加算税
申告額が実際の納税額より少なかった場合、過少申告加算税が課されます。基本的には不足額の10%が課税される点が特徴です。
申告していない金額に対する納税額が、当初の申告額と50万円とのいずれか大きいほうを超える場合、超過分に15%が適用されます。以下で具体的な例を見ていきましょう。
例えば、当初100万円と申告したが、実際の納税額が200万円だった場合。差額の100万円に対して、10万円の過少申告加算税が課されます。
もし当初の申告額が30万円だった場合、差額170万円のうち、50万円までは10%(5万円)、残りの120万円に15%(18万円)が適用され、合計23万円の過少申告加算税となります。
自主的に修正の申告をした場合、過少申告加算税は免除される場合も。そのため、誤りに気付いた際は速やかに修正申告をおこなうことが重要です。
重加算税
意図的な脱税行為には重加算税が適用されます。重加算税は通常の加算税よりも厳しいペナルティで、納税額の35%から最大50%の課税がなされます。特に悪質なケースや再犯の場合、より高い税率が適用されるため、注意が必要です。
例えば、200万円の脱税が発覚した場合、最低でも70万円(35%)の重加算税が課されます。悪質なケースでは100万円(50%)にもなりえます。
重加算税は、単に多額の税金を納めなければならないだけでなく、納税者としての信用を著しく下げてしまうかもしれません。金融機関からの融資や取引先との関係にも悪影響を及ぼす可能性があるため、脱税行為はやめましょう。
延滞税
納税期限を過ぎると自動的に延滞税が発生します。延滞税は申告期限の翌日から計算され、時間の経過とともに増加します。具体的には次のとおりです。
- 納期限の翌日から2カ月を経過する日まで
年「7.3%」と「延滞税特例基準割合 + 1%」のいずれか低い割合※延滞税特例基準割合は年2.4% - 納期限の翌日から2カ月を経過した日以降
年「14.6%」と「延滞税特例基準割合 + 7.3%」のいずれか低い割合※延滞税特例基準割合は年8.7%
上記で考えると、2カ月までは3.4%、2カ月を経過した日以後は14.6%となります。延滞税は時間の経過とともに増加していくため、早期に対応することが重要です。
家賃収入を確定申告していないことで起きるデメリット

確定申告を怠ることで、金銭的なペナルティ以外にもさまざまな不利益が生じる可能性があります。以下で、それぞれのデメリットを詳しく説明します。
国民健康保険料の減免機会を逃す
個人事業主やフリーランスの場合、収入が一定以下であれば国民健康保険料を減額できる可能性があります。しかし、確定申告をしていないと、減免の機会を逃してしまうかもしれません。
例えば、年間収入が300万円以下の場合、保険料が最大で数万円程度軽減される可能性があります。特に賃貸経営が赤字の場合、減免制度は大きな助けとなるでしょう。ただし、確定申告をしていることが条件となります。減免の恩恵を受けられなくなるのは大きな損失になるでしょう。
青色申告ができない
青色申告は、特別控除や損失の繰越しなど、さまざまな税制上の特典があります。しかし、申告期限を2期連続で破ると、青色申告の承認が取り消されてしまいます。
青色申告の大きな特典である最大65万円の特別控除を失うことは、税負担の大幅な増加につながるでしょう。また、赤字の繰越しができなくなることで、将来の税負担にも影響を与える可能性もあります。
金融機関からの信用が低下する
不動産投資では、収益物件購入のための融資が重要です。しかし、確定申告を怠ると、金融機関からの信用を失う原因となります。
金融機関は、融資の判断材料として過去の収入実績を重視します。確定申告書がない場合は、事業の実態や返済能力を示す証拠がないことを意味するのです。
そのため、新規融資が困難になったり、既存の融資条件が悪化したりする可能性があります。金融機関からの信用が低下すると、その後の融資が受けられなくなる可能性があるため、確定申告を速やかにおこなうようにしましょう。
収入を証明できる書類がなくなる
確定申告書の控えは、さまざまな場面で収入証明として使用されます。
例えば、下記のとおりです。
- 住宅ローンの申し込み
- 賃貸契約の締結
- 保育園の入園申請
- クレジットカードの申し込み
上記の手続きで収入を証明できないと、大きな不利益となります。
刑事罰のリスクがある
確定申告をしていないと、最悪の場合、刑事罰の対象となる可能性があります。具体的には、最大10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されるおそれも。
単なる行政処分ではなく、刑事罰であるため、前科として記録されてしまう点が大きなデメリットです。
前科がつくと就職やさまざまな契約で大きな障害となり、生涯にわたって影響を及ぼしてしまうかもしれません。また、社会的信用が低下すると、ビジネスや私生活にも深刻な影響を与えてしまうでしょう。
家賃収入を確定申告していないことが発覚する理由

家賃収入を確定申告しなければ、税務当局の目を逃れられると考える方もいるかもしれません。しかし、この考えは危険です。
国や地方自治体にとって税収は不可欠な財源であるため、公平な納税を実現するためのシステムが整備されています。
確定申告をしていないことが発覚する理由としては、以下の2つが挙げられます。
- マイナンバー制度を通した情報
- 取引企業への税務調査
それぞれ理由を詳しく見ていきましょう。
マイナンバー制度を通した情報
マイナンバー制度は、個人を識別し、さまざまな行政サービスを効率的に管理するためのシステム。マイナンバー制度の主な目的の一つが、「公平で公正な社会の実現」です。
マイナンバー制度により、各個人の収入状況や行政サービスの利用履歴が一元化され、さまざまな政府機関が個人の情報にアクセスできるようになりました。税務署もこの恩恵を受けており、個人の資金の流れを、より正確に把握できるようになっています。
家賃収入も例外ではありません。たとえ確定申告をしていなくても、資金の動きを完全に隠蔽することは極めて困難です。あとからばれて大きなリスクを背負うよりも、確定申告をしっかりおこなったほうが税金の負担を抑えられるでしょう。
取引先企業への税務調査
不動産賃貸業は、多くの関連会社との取引で成り立っています。
例えば、下記のとおりです。
- 収益物件購入時の不動産仲介会社
- 収益物件の管理を委託する管理会社
- 修繕を担当する建設会社
- 融資を提供する金融機関
上記の取引先との金銭のやり取りは、記録として残ります。
たとえ隠蔽を試みても、取引先に税務調査が入れば、取引の存在が明らかになります。税務調査では、個々の取引が詳細にチェックされるため、一つでも取引があれば事業の存在が露呈してしまうのです。
さらに、直接の取引先だけでなく、その先の取引先を通しても情報が漏れる可能性があります。現時点で発覚していないからといって、将来的にも安全な保証はありません。
家賃収入の確定申告をしていないことに気付いた時の対処法

家賃収入の確定申告をしていなければ、大きなリスクを背負うことになります。しかし、自分が確定申告の対象となっていることに気付かず、期限が過ぎてしまうケースもあるでしょう。確定申告をしていないことに気付いた際は、迅速に対処する必要があります。
過去5年分まで遡って申告する
家賃収入の確定申告は、前年分だけでなく過去5年分まで遡っておこなうことが可能です。自主的な申告はペナルティの軽減につながる可能性があるため、発覚したら迅速に手続きをおこなうことが重要です。
また、申告内容に誤りを発見した場合も、速やかに訂正申告をおこないましょう。手順は次のとおりです。
- 申告期限内の場合
訂正した申告書を作成し、再提出します。期限内であればペナルティは課されません。 - 申告期限後の場合
納税額過多の場合:「更正の請求」をおこないます。
納税額不足の場合:「修正申告」をおこないます。
自主的な修正は、加算税の軽減や免除につながる可能性も。ただし、期限後の場合は延滞税の納付は避けられません。税額は日々増加するため、迅速な対応が必要です。
専門家に相談する
確定申告の手続きに不安がある場合、税理士への相談がおすすめです。税務関連の手続きは、事業主本人または税理士以外には認められていないため、家族や友人のアドバイスだけでは適切な確定申告ができない場合もあります。
特に青色申告の場合、必要書類が多いため、作業が複雑です。自分で対応するのが困難な場合は、税理士などの専門家のサポートを受けてみるとよいでしょう。
まとめ
家賃収入の確定申告は、賃貸経営者の義務です。申告を怠ると、追徴課税や加算税などのペナルティを受ける可能性があります。
もし、確定申告をしていないことに気付いた場合は、速やかに修正申告をおこないましょう。わからない場合や不安な点がある場合は、税理士などの専門家に相談するなどして、適切に対応することが大切です。
正しい確定申告をおこなうことで、安心して賃貸経営を続けられるでしょう。

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ