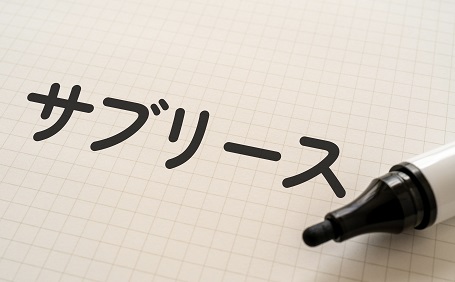サブリースは解約できない?難しい理由や解約が認められる正当事由を解説

本記事では、サブリースの解約が難しい理由や、解約が認められる可能性のあるケースをご紹介します。また、解約する際の手順も解説するため、サブリース契約の解約を検討している方は、ぜひご一読ください。
記事の目次
サブリース契約の基礎知識

まず、サブリース契約とはどういうものか、押さえておきましょう。
サブリース契約とは
サブリース契約とは、オーナーが所有している不動産をサブリース会社が借り上げ、入居者へ貸すものです。サブリース会社が賃貸経営をおこなうため、オーナーに手間がかかりません。また、空室の有無に関わらずサブリース会社が賃料を保証することから、安定した家賃収入が期待できます。
サブリース契約の種類
サブリース契約には「家賃保証型」と「パススルー型」の2種類あります。
-
家賃保証型
オーナーの受け取る賃料が固定されている -
パススルー型
実際の家賃に連動してオーナーが受け取る賃料も変動する
家賃保証型では、実際の家賃が下がってもオーナーが受け取る賃料は変わらないため、安定した収入が期待できます。ただし、一定期間で賃料の見直しがおこなわれます。一方、パススルー型では、入居者が減ればオーナーの受け取る賃料が減少。しかし、入居者が増えればその分受け取れる賃料が増えます。自分が契約しているサブリースはどちらの種類なのか、契約書でよく確認しておきましょう。
サブリース契約のメリット・デメリット
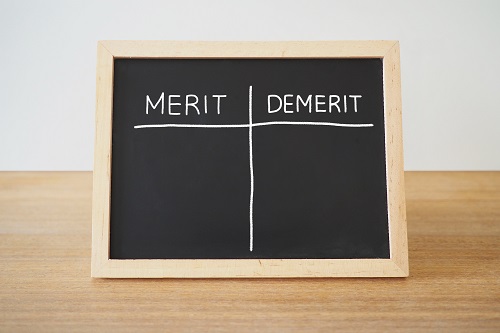
本章では、サブリース契約のメリットとデメリットを解説します。すでに契約をされている方もよく把握しておきましょう。
サブリース契約のメリット
サブリース契約のメリットとして、次の3つが挙げられます。
- 管理の手間がかからない
- 安定した家賃収入が得られる
- 相続税対策になる
先ほども説明したように、サブリース会社が賃貸経営をおこなうため、管理の手間がかかりません。また、空室の有無に関わらず、賃料が保証されることから、安定した家賃収入が期待できます。なぜサブリース契約が相続税対策になるのでしょうか。それは、所有する不動産が「貸家建付地」とみなされるため。「貸家建付地」は、他人に部屋を貸していることから、その分資産価値が低く評価されます。また、サブリース契約ではオーナーがサブリース会社に一棟を貸しているため、満室であると仮定して相続税が計算されます。貸家建付地における相続税評価額の計算式は次のとおり。
貸家建付地の相続税評価額 = 自用地評価額 ×[1ー(借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)]
自用地とは土地の所有者が自分のために使用している宅地のこと。借地権割合とは、自用地評価額に占める借地権の割合です。地域によって異なりますが、60〜70%がほとんど。借家権割合は全国一律で30%とされています。
次の条件の場合、相続税評価額がどうなるか計算してみましょう。
<条件>
自用地評価額:4,000万円
借地権割合:70%
4,000万円 ×[1ー(70% × 30% × 100%)]= 3,160 万円
自分が所有している場合の相続税評価額は4,000万円ですが、サブリース契約している場合は3,160万円となります。
サブリース契約のデメリット
次にサブリース契約のデメリットを見ていきましょう。
- 賃料を減額される可能性がある
- 免責期間がある
- 入居者を選べない
賃料を減額される可能性がある
サブリース契約には2種類ありますが、どちらも賃料の見直しがおこなわれ、減額される可能性があります。例えば、大東建託株式会社の一括借上げでは、借上げ賃料は当初10年間固定されますが、以降は5年ごとに見直し。また賃料の固定期間中であっても、借地借家法第32条1項の規定により、減額する可能性があるとしています。借地借家法については、次章で詳しく解説します。
免責期間がある
サブリース契約では、免責期間が設けられていることがあります。免責期間とは、サブリース会社が責任を免れる期間のこと。入居者が退去してから、次の入居者が見つかるまでの期間は免責期間とされており、この期間は家賃収入が得られません。先ほどご紹介した大東建託株式会社の場合、最大15日間が免責期間となっています。
入居者を選べない
賃貸経営をサブリース会社に任せるため、オーナーは入居者を選べません。そのため、家賃滞納のリスクがある人が入居する可能性や、知らぬ間に別の会社に貸し出される可能性もあります。
サブリース契約は解約できない?難しいとされる理由

サブリース契約の解約が難しいとされる理由は2つあります。
- 借地借家法によりサブリース会社が保護されているから
- 違約金が高額になりやすいから
それぞれ詳しく見ていきましょう。
借地借家法でサブリース会社が保護されているから
「借地借家法」とは、賃貸契約において借主と貸主のルールを定めたもの。借主と貸主の間では、貸主の立場が強くなります。そのため借地借家法によって、借主を保護しています。なお、サブリース契約においてオーナーが貸主、サブリース会社が借主です。実際にどのようなルールがあるのか見ていきましょう。
第28条では、オーナー側から解約する場合には、正当な理由がなければならないと定められています。
“建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。”
引用:e-GOV法令検索|借地借家法第28条
また、デメリットでも取り上げたように、賃料固定期間であっても減額される可能性があります。それは第32条で次のように定められています。
“建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。”
引用:e-GOV法令検索|借地借家法第32条
つまり、不動産市場が変動して不動産の資産価値が下がったり、周辺物件の家賃と比較して高い場合には、契約条件に関わらず、賃料を下げることができるということです。
違約金が高額になりやすい
サブリース会社によっては解約できたとしても、違約金が発生する可能性があります。違約金の相場は家賃の数カ月〜1年分。アパートやマンション1棟分となると、高額になるでしょう。サブリースの契約書に記載がないか、確認してみましょう。
サブリースの解約が認められる正当事由

オーナー側からサブリース契約を解約するためには、正当事由が必要です。本章では、どういうものが正当事由と認められる可能性があるのかを解説します。ここで取り上げるものは、あくまでも「可能性があるものである」です。個別のケースによって違うため、自分のケースが当てはまるか知りたい方は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
物件を取り壊す必要がある時
老朽化や耐震性の問題などで、入居者や近隣住民に危険がおよび、物件を取り壊す必要がある時は、サブリースの解約を認められる可能性があります。日本は地震大国で、いつ地震が起きても不思議ではありません。建物が大地震でも耐えられるよう、建築基準法で満たすべき耐震基準が定められています。1981年5月以前に建築された建物は、旧耐震基準のもので、現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。耐震診断の結果など、物件を取り壊す必要がある客観的な事実を示しましょう。
自分が住む必要がある時
物件に自分が住む必要がある時も、サブリース契約の解約が認められる可能性があります。ただし、なぜその物件でなければならないのか、必要性を示す必要があります。例えば、他に居住する物件がないことを示すなど。さらに、入居者がいる場合には、立ち退き交渉が必要です。場合によっては、立ち退き料や入居者の引越し費用などを負担しなければならないでしょう。
生計維持のために売却する時
生計維持のために物件を売却する時も、サブリース契約の解約が認められる可能性が高いです。過去には物件の売却が必要と判断されたケースで解約が認められた判例があります。実際にどういうケースだったのか見ていきましょう。
このオーナーは老朽化した自宅の補修改築のために、まとまった資金を必要としていました。そのため、サブリース契約を結んでいた物件を空き家状態で売却することを希望。入居者が退去し空き家となったため、サブリース会社に入居者募集をしないこと、半年後の契約更新をしないことを求めていました。しかし、サブリース会社がオーナーに正当な理由がないことを理由に、契約を自動更新。オーナーがサブリース会社に対して、契約の解除と物件の明渡しを求めたものです。
裁判では大きく次の2つの理由から、オーナーの訴えが認められました。
- 物件によって得られるサブリース会社の利益が月額3万3,000円と少なく、経営に影響をおよぼすとは考えられない
- サブリース会社にとって、物件を使用する強い必要性があるわけではない
ただし、正当事由を補完するため、裁判所はオーナーに対して、立ち退き料として50万円をサブリース会社に支払うことを求めました。このように、物件を売却する必要があると判断されれば、サブリース契約を解除できる可能性があります。
公共事業によって立ち退かなければならない時
公共事業などによって立ち退かなければならない時も、正当事由と認められ、サブリース契約を解約できる可能性があります。公共事業の具体例としては、再開発工事や道路の拡張工事など。公共事業で立ち退かなければならない場合、オーナーは不動産を失うという不利益を被るため、補償がおこなわれます。しかしこの際、公共事業をおこなう地方自治体などから、オーナーに相応の補償金を支払われる可能性が高いです。そのため、サブリース会社に対する立ち退き料は、高額になるおそれがあります。
サブリース会社が義務に違反した時
サブリース会社が義務に違反した時も、契約を解除できます。例えば、国土交通省がひな型として提示している「サブリース住宅標準契約書」では、サブリース会社の義務として、次の3つが挙げられています。
- 賃料支払い義務
- 共益費支払い義務
- サブリース会社の故意や過失などで必要となった修繕費の負担義務
賃料支払い義務とは、契約書で定めた賃料をサブリース会社がオーナーに支払う義務のこと。共益費支払い義務とは、共有部分の維持管理に必要な、光熱費や清掃費などに充てる共益費を支払う義務のことです。本来、物件の修繕費を負担するのはオーナーです。しかし、サブリース会社の責に帰すべき事由により修繕が必要となったものは、サブリース会社が負担しなければなりません。また、オーナーの許可を得ることなく、サブリース会社が増改築や移転、模様替えなどをおこなった時も契約違反として、契約を解約できるとしています。
なお、ここで取り上げたものは、オーナーの催告を要件としています。もし催告しているにも関わらず、サブリース会社が義務を履行しない時には、契約を解除することができます。
サブリース契約を解約する際の手順
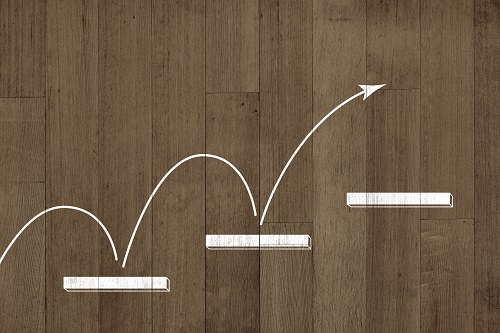
先述したように、サブリース契約を解約するためには、正当事由が必要です。しかし、自分のケースが正当事由として認められるのか、不安な方もいるでしょう。法律が関係しているため、判断が難しくなります。本章では、実際に解約するためにはどうすればいいのか、手順を解説します。
ステップ1.契約書の内容を確認する
まずは契約書の内容を確認しましょう。以下の点が、どのように記載されているかを確認します。
-
解約事由
どのような場合に解約できるのか -
解約予告期間
解約通知をしてから解約が有効になるまでの期間 -
違約金
解約した場合に支払う違約金の金額
契約書によって内容は違うため、よく確かめましょう。
ステップ2.弁護士に相談する
次に弁護士に相談しましょう。サブリースの契約は法律が絡んでおり、複雑なことから、正しい判断が必要となります。また、サブリース会社との交渉において、専門的な知識や経験も必要でしょう。弁護士であれば現在の状況を踏まえ、適切なアドバイスをもらえます。解約交渉がうまくいかない場合、必要に応じて裁判をおこなう可能性も。弁護士がいれば、心強い味方となるでしょう。しかし、どう弁護士を探せばいいのかわからない方もいるでしょう。「法テラス」では、相談窓口の案内や無料相談がおこなわれています。
ステップ3.サブリース会社に解約通知書を送付する
サブリース会社に解約通知書を送付しましょう。口頭ではなく、必ず書面で伝えます。決まった形式はありませんが、一般的に下記の内容を記載します。
- 解約通知日
- サブリース会社名・住所
- オーナーの氏名・住所
- 契約書の解約条項
- 物件の名前・所在地
- サブリースの契約期間・契約終了予定日
すでに弁護士に相談していれば、他に必要な項目はないか確認しておきましょう。なお、送付する際は内容証明郵便で送りましょう。差出日や届いた日、通知した内容などがすべて証明されます。
ステップ4.サブリース会社と解約交渉をおこなう
解約通知書の内容で双方の合意が得られれば、無事解約となります。もし合意が得られない場合は、解約交渉となります。交渉する際には、弁護士を通したほうが、スムーズに進むでしょう。解約する際には、サブリース会社に立ち退き料を支払う必要があります。事前にどれくらいかかるか、弁護士などの専門家に確認しておきましょう。
サブリース契約の解約後にすべきこと
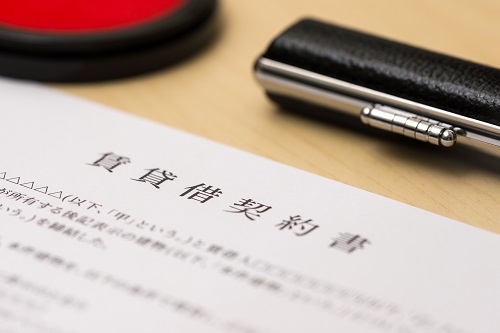
サブリース契約が解約できたあと、何をすべきなのでしょうか。本章では、賃貸経営を続ける場合にすべきことを解説します。
新しい管理会社を探す
物件の管理を自分ではなく、管理会社に任せる場合は、新しい管理会社を探しましょう。管理会社を選ぶ際には、以下のポイントを確認しましょう。
- 賃貸住宅管理業の登録状況
- 口コミ・評判
- サービス内容
- 手数料
200戸以上の賃貸住宅を管理する事業者は、賃貸管理業登録が義務付けられています。登録がされているか、確認しておきましょう。国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で検索できます。また、インターネットで口コミや評判を調べてみましょう。実際に利用したことがある方の意見は参考になるでしょう。管理会社によって、サービス内容や手数料が異なるため、複数の会社を比較検討することが大切です。
入居者と賃貸借契約を締結する
サブリース契約をしていた時は、入居者はサブリース会社と賃貸借契約を結んでいます。しかし、サブリース契約を解約した場合、オーナーと入居者の間で賃貸借契約を結び直さなければなりません。新しい管理会社が決まっていれば、手続きを依頼しましょう。具体的な手続きには、次のようなものがあります。
- 承継通知
- 賃料支払い先の変更
- 契約の更新・満了期の確認
「承継通知」とは、オーナーがサブリース会社の地位を引き継いだことを通知するもの。つまり、貸主が変更になることを入居者に知らせるものです。また、今まで入居者からサブリース会社に支払われていた賃料の支払い先も変更となるため、新しい振込先や切り替わる日なども入居者に伝えましょう。最後に、各入居者の契約期間や賃料などの契約条件を確認します。もし賃料の変更をおこなう場合は、入居者と交渉をおこない、合意を得なければなりません。
空室の賃貸募集をかける
サブリースの契約を解約したあと、空室がある場合は賃貸募集をかけましょう。管理会社が決まっていれば、依頼しましょう。空室がなくなれば、安定した賃料収入を期待できます。信頼や実績がある管理会社であれば、安心して任せられるでしょう。
まとめ
本記事では、サブリース契約の解約が難しい理由や、解約が認められる可能性のある理由を解説しました。借地借家法で借主であるサブリース会社が保護されているため、オーナーからの解約が難しいとされています。もし解約をする際には、正当事由がなければなりません。ケースバイケースであるため、弁護士などの専門家に相談すると、適切なアドバイスがもらえるでしょう。解約後、新たな管理会社に物件管理を依頼する場合は、賃貸住宅管理業者の登録状況や評判などを確認し、信頼できる管理会社を選びましょう。

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ