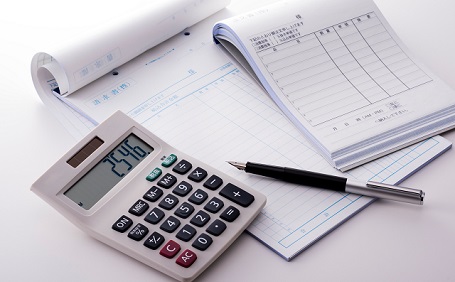不動産投資は個人事業主でもできる?得られるメリットやデメリットも解説

しかし、個人事業主が不動産投資をおこなう際には、さまざまなメリット・デメリットがあります。本記事では、個人事業主が不動産投資をおこなうことで得られるメリットや注意点を解説します。
記事の目次
不動産投資は個人事業主でもできるのか

個人事業主でも不動産投資は可能です。むしろ税制面から見ると、個人事業主は不動産投資に向いているといえるでしょう。ただし、個人事業主が不動産投資を始める際は、いくつかのデメリットや注意点があるため、事前の情報収集が重要です。
個人事業主とは
個人事業主とは、自身で独立して事業を営む方のことを指します。会社員や給与所得者の方は個人事業主には該当しません。
ただ、不動産投資のために開業届を提出すれば、「不動産賃貸業」の個人事業主となります。また、不動産投資は個人事業主でもおこなえますが、法人としておこなうほうがメリットが大きくなる場合もあります。
個人事業主として副業投資する会社員が増えている
近年では、会社員の方で不動産投資の副業を始める方も増えています。開業届を出せば個人事業主として投資できます。安定した収入があるため融資を受けやすく、賃貸収益を経費計上できるのがメリットです。
一方で、一定規模以上になると個人事業税を納める義務が生じたり、青色申告には複式簿記の帳簿付け義務があったりなどのデメリットも存在します。
また、青色申告特別控除を受けるには、一定の「事業規模」が求められるため注意が必要です。
個人事業主が不動産投資をするメリット
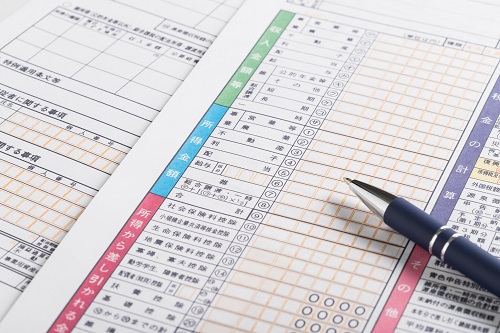
個人事業主が不動産投資をするメリットを詳しく解説します。
青色申告で有利になる
個人事業主は不動産投資に関して、会社員よりも青色申告制度を活用しやすい立場にあります。
事業所得と不動産所得の両方がある場合、条件さえ満たせば、賃貸経営が事業規模でなくても青色申告特別控除(55万円または65万円)を受けられます。
条件は、
- 1.不動産所得または事業所得を得ている
- 2.複式簿記(損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式)で記録する
- 3.貸借対照表および損益計算書と確定申告書に添付して翌年3月15日までに提出する
上記の3点です。
一方、給与所得のみで不動産所得がある場合、不動産投資が「事業規模」でないと特別控除は受けられません。「事業規模」の目安は、以下のとおりです。
- 貸間、アパートなどは、貸与できる独立した室数がおおむね10室以上
- 独立家屋の貸付けは、おおむね5棟以上
つまり、個人事業主として事業所得があれば、賃貸経営の規模に関わらず、会社員よりも青色申告のメリットを得やすくなるのです。
経費を有効活用できる
個人事業主が不動産投資をおこなう大きなメリットの1つが、経費を有効活用できる点です。個人事業主であれば本業に関する経費計上をおこないますが、不動産投資でもさまざまな経費計上が可能です。
具体的には、以下の費用が経費として計上できます。
- 固定資産税や都市計画税、登録免許税など不動産に課される税金
- 入居者募集のための仲介手数料や広告費
- 管理会社へ支払う管理費・修繕積立金
- 火災保険や地震保険などの損害保険料
- 修繕費用
特に注目すべきは、建物の減価償却費です。減価償却費では、建物の購入価格を一定期間で均等に割り振った金額を、実際の支出がなくても経費計上できます。
上記のように実際にお金を払っていなくても経費が認められるケースがあります。経費を多く計上できれば、課税対象となる不動産所得が減少するため、節税効果が得られるでしょう。
本業以外の収入源を確保できる
個人事業主は会社員と比べて、収入が不安定になりがちです。事業の売上げが思わしくない時期など、収入が予期せぬ変動に見舞われるリスクがあります。そのような時に賃貸収入があれば、別の収入源を確保できるメリットがあります。
将来的に別事業を始める際にも始めやすい
将来的に本業とは別の新規事業を立ち上げたい場合も、不動産投資はメリットになります。不動産投資をおこなうためには、収支の記録や確定申告などの会計処理を学ぶ必要があります。
これらの経験を活かせば、新規事業を興した際の会計業務にもスムーズに取り組めるでしょう。
不動産投資を通して得られる会計知識は、個人事業主にとって大きな財産です。本業と賃貸収入の2本立ての収入を確保しつつ、将来の別事業展開に向けて資金を備えられるメリットがあるのです。
個人事業主として不動産投資をするデメリット

個人事業主が不動産投資をおこなう際はデメリットもあります。それぞれのデメリットを詳しく解説します。
融資を受けにくい可能性がある
投資用物件を購入する際は、融資を受ける場合がほとんどです。しかし個人事業主の場合、本業の収益次第では、融資を受けられない可能性があります。
融資を受けるには一般的に、過去3期分の黒字決算書の提出が求められます。事業開始間もない個人事業主や、本業で赤字が続いている場合は条件を満たせず、融資の審査に通らない可能性が高いです。
金融機関によっても審査基準は異なるため、必ずしも融資が受けられないわけではありませんが、会社員に比べると断られる可能性は高くなる傾向にあります。不安な方は金融機関で相談してみるといいでしょう。
確定申告の手間が増える
個人事業主は本業で得た収入に対して毎年確定申告をおこなっていますが、不動産投資を始めるとさらに手間が増えます。
賃貸経営にともなう収支を適切に記録したり、帳簿の作成・決算書を提出したりなど、必要な作業が多くなります。
本業と不動産投資の2つの確定申告をこなさなければならず、手間も時間もかかってしまうでしょう。少しでも確定申告の手間を減らすためには、効率的な記録の付け方や会計ソフトの利用などの工夫が必要です。
不動産投資キャッシュフローが悪化するリスクがある
投資用物件の経営では、空室や滞納などのトラブルが発生すると、不動産投資のキャッシュフローが悪化する恐れがあります。不動産投資のキャッシュフローが悪化すると、個人事業主の方は自身の資産で責任を負わなければなりません。本業の収支が黒字であれば問題ありませんが、経営が行き詰まった場合の備えが必要です。
宣伝活動を広げて物件の入居率を上げたり、滞納を防ぐ対策を講じたりなどして、安定した賃料収入を確保することが大切です。
個人事業主が不動産投資をおこなう際の注意点

個人事業主が不動産投資で失敗しないためには、さまざまな注意点を事前に把握しておく必要があります。具体的にはどのようなことに注意すればいいのか、以下で詳しく解説します。
修繕費用を確実に備える
物件の維持管理には、メンテナンス費用に加え、火災・地震などの自然災害や事故への備えが欠かせません。保険への加入や、大規模修繕に向けた資金計画を立てましょう。
また、築年数の経過とともに大規模修繕が必要になる可能性が高まります。高額になりがちな修繕費用にあらかじめ備えることが大切です。
売却時の黒字確定まで時間がかかる
不動産投資で黒字になるかどうかは、売却時(出口)まで確定しません。運用中は黒字の見込みがあっても、最終的には赤字となるケースも。
購入時から計画を立て、年間キャッシュフローを黒字にすることは可能ですが、あくまでも「黒字見込み」に過ぎません。とはいえ、空室対策や売却価格に余裕を持つなどの対策をとれば最終的な黒字幅を広げることはできます。
長期的な取り組みとなる不動産投資では、一時的な手持ち資金があっても油断は禁物です。返済計画や運用方法、売却のタイミングなどを常にチェックし、無理のないスケジュールを立てる必要があります。
個人事業主が不動産投資に必要な融資を受けるためのポイント

不動産投資の自己資金に余裕がない場合は、融資を活用する選択肢もあります。ここからは、不動産投資の融資を受けるポイントや、融資可能な金融機関を詳しく解説します。
融資を受けるためのポイント
不動産投資の融資を受けるためのポイントを項目ごとに見ていきましょう。
・資金
不動産投資における自己資金の額が、融資審査の際に重要な判断材料となります。口座の残高を確認しておきましょう。自己資金が豊富であれば、返済能力が高いと評価されやすくなります。
・支払いの滞納
クレジットカードやローンの支払い遅延、滞納歴があると、信用度が大きく低下します。過去のデータは一定期間残るため、融資審査に悪影響を及ぼす可能性が高いです。
・所属する会社の規模
会社員が個人事業主となり副業で不動産投資をする場合、勤務先企業の規模が融資審査に影響します。大手優良企業に勤めていれば、安定した収入源があると判断され、融資を受けやすい傾向にあります。
一方でベンチャーや中小企業に勤務している場合は、企業の信用力が問われ、融資が難しくなる可能性もあるので、注意が必要です。
・所属する会社の勤続年数
勤続年数の長さは、「信用度」を判断するうえで大きなポイントです。同じ企業に長年勤務していれば、安定した雇用環境があるとみなされ、高い評価が期待できるでしょう。逆に短期間で転職を繰り返している場合は、収入が不安定と判断される恐れがあります。
融資を受けられる金融機関
次に、不動産投資の融資を受けられる金融機関を解説します。
日本政策金融公庫
日本政策金融公庫は国が出資する政府系金融機関で、個人事業主向けの融資メニューが充実しています。日本政策金融公庫は国民生活の向上を目的としていることから、利益追求のための融資はおこないません。しかし、不動産賃貸事業が目的であれば融資される可能性が高いです。
金利が市中金利より低く設定されており、長期の借入期間が可能な点が大きな特徴です。
一定の要件を満たせば、担保や保証人が不要な融資プランもあります。ただし、申請書類が多く、審査に2〜3週間かかることもあるため、時間に余裕をもった手続きが必要です。
地方銀行
地方銀行には、地域密着型の金融機関として個人事業主への融資実績があります。金利水準は比較的低く、高額の融資も可能です。
ただし、審査が厳しい傾向にあります。基本的には、信用保証協会付きの融資を勧められるでしょう。
信用保証協会とは、個人事業主や中小企業の債務を保証する公的機関のことです。
信用金庫
信用金庫は、地域の中小企業や個人事業主への融資を主な事業としている金融機関です。「地域のお金を地域に還元する」ことを理念に掲げています。
金利は日本政策金融公庫より高めですが、個人の不動産投資向けにも柔軟に対応してくれます。地元に根を張る金融機関ならではの、きめ細かなサポートが期待できるでしょう。
個人事業主が不動産投資のために法人化をおこなう場合の手順と費用

個人事業主の方が不動産投資をしていて、さらに規模を拡大したいと考えることもあるでしょう。本章では、不動産投資のために法人化をおこなう場合の手順と費用を説明します。
法人化するための手続き方法
個人事業主が法人化するには、以下の5つの手続きが必要です。
- STEP 1会社の基本事項(商号、事業内容、資本金など)を決める
- STEP 2定款や設立関係書類の作成
- STEP 3公証人による定款の認証
- STEP 4法務局への登記申請
- STEP 5登記証明書や印鑑証明書の取得
手続きは自身でおこなうか、司法書士に委託するかを選択できます。
法人化にかかる費用
法人化の費用は状況によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。
- 株式会社:約20〜30万円
- 合同会社:約10万円
上記の費用には登録免許税や収入印紙代などが含まれています。自身で手続きをおこなうのか、司法書士に依頼するのかでも費用は変わってきます。
司法書士への報酬は事務所ごとに自由に設定されているため、複数の事務所に見積もりを取り、比較検討するのがおすすめです。
個人事業主が不動産投資で法人化するメリット・デメリット

不動産投資を法人としておこなう場合のメリット・デメリットを見ていきましょう。
法人化のメリット
最大のメリットは、個人よりも融資を受けやすくなる点です。法人は金融機関から信頼されやすく、大型投資や事業拡大に向けた資金調達がしやすくなります。
個人には融資限度額があり、一定以上の規模を求める場合は制約が出てきます。一方、法人として実績を積めば、より大きな融資が可能です。
投資の目標やゴール次第では、初めから法人として不動産投資を始めるのも選択肢のひとつでしょう。
法人化のデメリット
※法人住民税とは、法人事業所のある自治体に納める地方税のこと
さらに設立に向けた諸手続きや定款作成など、個人事業主に比べて負担が重くなります。不動産投資は経費計上で厳しくチェックされる面もあるため、そこまでの規模を追わないのであれば、法人化のデメリットが大きくなる可能性があります。
投資の規模や目標に合わせて、メリット・デメリットをよく検討することが大切です。
不動産投資で個人事業主が法人化するタイミング

不動産投資が軌道に乗り、所得が一定額を超えると、法人化したほうが大きな節税効果を得られる場合があります。
法人化するタイミングの課税所得の目安は、900万円以上です。個人事業と法人では、所得に対する課税体系が異なります。課税所得が900万円を超えたあたりで、個人と法人のどちらが有利になるかを比較し、法人化の検討を始めるとよいでしょう。
まとめ
個人事業主が不動産投資をおこなうことには、メリットとデメリットがあります。メリットとしては、税制面での優遇があること、資産形成や老後の蓄えとなること、融資を受けやすいことなどが挙げられます。一方でデメリットとして挙げられるのは、個人資産へのリスクが高いこと、大規模修繕への備えが必要なこと、売却時まで黒字が確定しないことなどです。
不動産投資にはさまざまなリスクがともないますが、十分な知識を持ち、慎重に検討を重ねれば投資を成功させられるでしょう。自身の事業状況やライフプランに合わせ、メリット・デメリットを踏まえたうえで、不動産投資を始めましょう。

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ