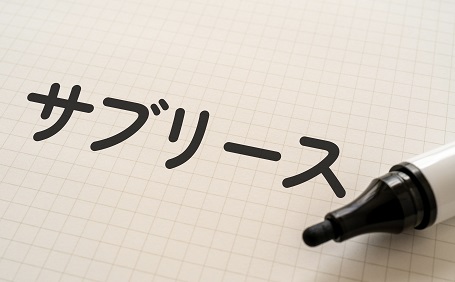不動産投資の勧誘がしつこい時どうする?断り方やよい会社の見分け方を解説!

そこで本記事では、不動産投資の勧誘電話をどのように断るべきか、その具体的な方法を解説します。シンプルで明確な断り方から、法的に対処する手段まで、さまざまな状況に応じた対応策があるので活用してみてください。また、詐欺や不正な会社に引っかからないために、悪質な不動産会社を見分けるポイントも解説しています。
記事の目次
不動産投資の勧誘が電話でくる理由は?

不動産投資の電話勧誘がよくおこなわれるのは、主に不動産会社側の営業効率やコスト面のメリットからです。見込み客と直接コミュニケーションが取れる効率のよさが理由になっています。不動産会社にとって電話での勧誘は、セミナーや訪問、Web広告など他の方法と比べても、時間効率よく成果を得やすいため、営業手法の一つとして欠かせません。結果、電話を通じた不動産投資の営業によく遭遇するでしょう。
電話営業に、特別な調査や複雑なマーケティング戦略は必要ありません。多くの場合、とにかく電話をかけるスタイルで営業しています。もし購入意欲が低い投資家にあたっても、直接対話し商材について詳しく説明できるため、投資家の関心を引き出せる可能性も。不動産会社にとって、他の営業手法と比べて低コストなのも電話営業の魅力です。電話番号のリストさえあればすぐに始められ、特別なスキルや知識は必要ありません。このため、電話営業は一貫して不動産業界で広く利用されています。
電話営業は多くの人が迷惑に感じるかもしれません。しかし、不動産会社にとっては手軽で効率がよい営業手法のため、これからもおこなわれるでしょう。
不動産投資の勧誘の適切な断り方とは?

不動産投資の勧誘で電話が多く利用される理由を解説しましたが、頻繁に勧誘されるとなれば憂鬱に感じてしまう方もいらっしゃるでしょう。できればストレスなく断りたいものですが、どのように断ればよいのでしょうか。そこで本章では、不動産投資勧誘の適切な断り方を紹介します。
シンプルにはっきりと断る
不動産投資の勧誘を断るためにシンプルにはっきりと断ることが重要です。相手に誤解を与えないためにも、曖昧な返答は避け、明確な意思表示をするようにしましょう。「忙しいのであとで」や「今は考えられない」などの言葉は、相手に「タイミングを変えれば話を聞いてもらえるかもしれない」と期待を抱かせてしまうかもしれません。曖昧な返答では、また勧誘の電話がかかってくる可能性があります。
勧誘を断る際には、あくまでシンプルに「興味がありません」「今後もその予定はありません」「電話を含む勧誘は一切不要です」など、明確で短い返答を心がけましょう。理由を詳しく説明する必要はなく、シンプルな断り方が効果的です。相手がしつこく食い下がってくる場合でも、毅然とした態度を保ち、同じ言葉を繰り返しましょう。言葉を変えて断るよりも、一貫した返答を続けたほうが、勧誘を受け入れる可能性がない旨が相手に伝わります。
冷静かつ丁寧に断る
不動産投資の勧誘を断る際は、冷静かつ丁寧な対応を心がけると効果的です。いくら勧誘がしつこくても、感情的になって横柄な態度を取ったり、電話を突然切る「ガチャ切り」などの行動は避けましょう。相手もビジネスとして勧誘をおこなっており、無理に押し付けるわけではなく、興味があれば面談の機会や契約につながる可能性があると考えているだけです。冷静に対応すれば、双方にとって余計なストレスを避け、勧誘がスムーズに終了できます。
横柄な言葉や態度を取ると、かえって相手の感情を刺激し、余計に粘られたり、無用なトラブルを招くかもしれません。電話を途中で切る「ガチャ切り」も、相手に不快感を与えるだけでなく、その後の関係性に悪影響を及ぼす可能性があるため、できるだけ避けましょう。勧誘を断る際には、まず冷静な口調で「興味がありません」「必要ありません」と、丁寧かつ明確に伝えます。相手がしつこく食い下がってくる場合でも、感情を交えずに繰り返し丁寧に対応し続けましょう。冷静で一貫した態度を保つことで、相手も諦めやすくなり、その場のやり取りが円滑に進みます。
法に則って違反行為を指摘する
不動産投資の勧誘がしつこい場合や、違法な手法が取られていると感じた場合、法に基づいて違反行為を指摘することも適切です。不動産投資勧誘のなかには、消費者保護を無視した悪質な手口や、法令を逸脱した営業活動がおこなわれている場合もあります。消費者は、法律で守られる権利があるため、その権利を行使して勧誘を止めましょう。
例えば、日本の「特定商取引法」では、無断での電話営業や過度にしつこい勧誘は禁止です。また、悪質な勧誘や脅したりするような営業は「宅地建物取引業法」でも業法違反とされています。勧誘の違反性を感じたら、「特定商取引法に違反しています」や「宅地建物取引業法に違反しています」と明確に伝えましょう。
「個人情報保護法」に基づき、無断で取得された個人情報の取り扱いに疑念がある場合、その出所や使用方法を確認し、場合によっては削除を要求できます。勧誘をおこなう会社に対して、こうした法的指摘をおこなうと、相手は不正行為を自覚し、違法な勧誘をやめざるをえなくなるでしょう。
法に基づく指摘は、ただ断るだけではなく、勧誘自体が不適切な行為だと示す強力な手段です。しつこい勧誘に対しては、毅然とした態度で法律を根拠に指摘し、相手にそれ以上の勧誘を控えさせるようにうながしましょう。
監督官庁に相談する意思を伝える
不動産投資の勧誘がしつこく、違法や不適切な手法が疑われる場合には、「監督官庁に相談する」と伝えましょう。不動産業界は厳しい規制のもとで運営されており、不動産会社は法的に定められたルールに従わなければなりません。こうした規制を管理するのが、国土交通省や各地方自治体の不動産取引を監督する部門であり、消費者からの苦情や通報が入れば、会社に対して調査や指導がおこなわれ行政指導や最悪の場合、営業停止命令が下されます。
しつこい勧誘に対して、営業担当者に「このまま続けるのであれば監督官庁に相談します」と明言すると、会社は自身の行為が法的に問題視される可能性を自覚し、勧誘を即座にやめるでしょう。特に、法令違反をしている会社は、監督機関からの調査や処罰を恐れるため、こうした言葉には敏感です。
さらに、消費者庁や全国の消費生活センターに相談する意思を伝える方法も効果的です。これにより、会社側は自らの行為が問題視されると認識し、勧誘を控えるでしょう。監督官庁や消費者保護機関への相談を示唆する行動が、しつこい勧誘から自分を守り、相手の行動を抑制する効果を発揮します。
悪質な不動産投資の勧誘を見分ける方法は?

基本的に電話営業は、単なる不動産会社の営業手法の一つです。そのため、自分に必要がなければ断れば話は終わります。しかしなかには、不動産投資をフックに悪意をもって営業をしている、悪質な会社もあるかもしれません。興味があって詳しく聞いてみたいと思った方は、悪質な会社を見分ける目を持つ必要があります。では、それを見分けるにはどのような点に着目すればよいでしょうか。本章では、悪質な不動産会社を見分けるポイントを解説します。
会社の所在を確認する
悪質な不動産投資の勧誘を見分けるには、会社の所在地が確認できるかに着目しましょう。信頼できる会社は所在地を明確にしており、その住所を通じて実際のオフィスが存在しているはずです。所在地が曖昧だったり、固定のオフィスがない場合、その会社は信頼性に欠ける可能性があります。また、所在地だけでなく、その場所がどのような建物に入居しているかも確認しましょう。もし、大きなオフィスビルや商業ビルに所在していると主張しているにも関わらず、そのビルのテナントリストに名前がなかったり、オフィスの外観が説明と一致しない場合は警戒が必要です。
次に、会社の実績も確認しましょう。過去のプロジェクトや取引実績が不明瞭であったり、実際の成果を証明できない場合、その企業が信頼に足るものか再検討しなければなりません。また、取引先の金融機関なども確認し、信頼できる企業と長期的な関係を築いているかを調べる点も詐欺を避けるための大切なステップです。所在地や実績、取引先をしっかりと確認すると、悪質な不動産投資の勧誘に巻き込まれるリスクを減らせるでしょう。
名前をきちんと名乗るか確認する
悪質な不動産投資の勧誘を見分ける際、会社名や担当者名をきちんと名乗るかも確認しましょう。信頼できる会社や担当者は、自分の名前や役職、所属する会社名を明確に伝えます。これは、投資家との信頼関係を築くための基本的な態度で、業務上の透明性を確保するためにも当然のことです。一方で、名前を名乗らない、あるいは名乗っても連絡先や詳細な情報を提供しない場合、その担当者や会社の信頼性に疑問を持ちましょう。
名前をきちんと名乗ると、担当者がどのような立場で活動しているのか、どの会社に所属しているのかが確認でき、万が一問題が発生した際に責任の所在が明確になります。悪質な勧誘者は匿名性を利用し、具体的な情報を提供せず、リスクを回避しようとするでしょう。そのため、名前を名乗ることは、その人物が真剣にビジネスをおこっている証拠になります。
また、名乗った名前が実在するかの確認も重要です。インターネットなどで検索し、その人物や会社の評判や過去のトラブルを調べましょう。信頼できる会社であれば、担当者の名前も公にされており、過去の実績や評判も確認できるはずです。名前をきちんと名乗ることは、良識あるビジネスの基本であり、悪質な勧誘から自分を守るための重要なチェックポイントとなります。
営業が過度でないか確認する
過度な営業をする会社は悪質なケースが多いです。正当な活動をしている会社や担当者は、投資家の興味やニーズに応じた適切なアプローチをするため、無理に契約を迫りません。具体的には、しつこく連絡を取り続けたり、「今すぐ決めないとチャンスを逃す」など急かしたりする場合は注意しましょう。信頼できる会社は、投資家が十分に検討する時間を提供し、冷静に判断できる環境を整えます。過度な営業は、投資家の判断を鈍らせるための策略で、結果的に投資家にとって不利益になる可能性が高くなります。
また、過度な営業の一環として、高額な手数料の請求やかかる費用の総額説明を怠る場合があるので注意しましょう。契約を急ぐあまり、詳細な情報提供や説明を省略し、契約書の内容を十分に理解する時間を与えない場合もあります。過度な営業行為は、営業担当者が顧客の利益よりも自分の成約数や売上を優先しているケースも。信頼できるビジネス関係を築くためには、顧客の疑問や不安に対して丁寧に応じ、透明性のある説明をおこなわなければなりません。営業が過度でないかの観点は、悪質な勧誘を防ぎ、自分に合った投資先を選ぶための大切な判断基準になります。
嘘をつき不確定な事象を断定してくる
明らかな嘘をついてくる不動産投資の勧誘は危険です。嘘だとわかる話以外にも、メリットばかりを強調し、リスクや不確定な要素を無視したり、利益が確定していると断言している場合も警戒しましょう。信頼できる不動産投資の提案は、メリットだけでなくリスクや不確定要素も正直に説明し、顧客に対して透明性を持った情報提供をおこなうものです。
まず、メリットばかりを強調する勧誘には注意しましょう。そもそも投資は常にリスクがともなうものです。特に不動産市場は変動があるため、デメリットがない状態はありえません。悪質な勧誘者は、魅力的な点だけを大々的に宣伝し、投資家を誘惑しようとします。このようなアプローチは、実際のリスクを見逃す原因になり、のちに予期しない損失を招く要因です。
投資の提案を受ける際には、提供される情報の信憑性を自分で確認し、メリットとリスクを理解する姿勢を持ちましょう。信頼できる会社は、現実的な情報をもとに正直な説明をおこない、投資家に対して透明性を保ちます。メリットばかりを強調し、不確定な事象を断定する勧誘には警戒しましょう。
不動産投資の断り方に関するよくある質問
不動産投資の勧誘がしつこい時の断り方に関するよくある質問をまとめました。
不動産投資会社が電話で勧誘する理由は?
不動産投資の勧誘が電話でおこなわれる理由は、特に不動産会社にとって電話営業が効率的かつ低コストな営業方法だからです。電話を通じた勧誘は、セミナーや訪問、Web広告など他の営業方法に比べ、直接見込み客と対話できるため、成果が出やすくコストがそれほどかかりません。また、特別な調査や高度なマーケティング戦略がなくても、広範囲にアプローチすると、購入意欲の低い投資家からの関心を引き出せる可能性もあります。
電話営業は、リストがあればすぐに始められ、特別なスキルや知識を必要としないため、不動産会社にとって使いやすい手段です。そのため、多少迷惑に感じる人がいても、手軽で効率がよいことから不動産業界では依然として広く利用されています。
不動産投資の勧誘を適切に断る方法は?
不動産投資の勧誘を適切に断る方法は、シンプルにはっきりと断る姿勢が重要です。曖昧な返答は営業担当者に期待を持たせてしまうため、明確に「興味がない」と伝えましょう。また、感情的にならず「冷静かつ丁寧に断る」とトラブルを避けることができ、スムーズに勧誘を終わらせられます。
さらに、しつこい勧誘や違法な手法が感じられた場合は、「特定商取引法」や「宅地建物取引業法」、「個人情報保護法」に基づき法的違反を指摘することも勧誘を止めさせるのに効果的です。最後に、勧誘が続く場合には「監督官庁に相談する」と伝えると、会社は法的問題を恐れ、勧誘を控える効果がより期待できるでしょう。
悪質な不動産会社を見分けるポイントは?
悪質な不動産会社を見分けるためには、いくつかのポイントがあります。まず、会社の所在地を確認し、実際にオフィスが存在するか、信頼できる実績があるかを調べましょう。次に、担当者が自分の名前や役職、会社名を明確に名乗るか確認し、信頼性を確認します。
過度な営業も悪質な兆候で、しつこく連絡を取る、急かす、詳細な説明を省略する場合は注意が必要です。また、メリットばかりを強調し、リスクや不確定な要素を無視する勧誘にも警戒しましょう。信頼できる会社はリスクも含めて正直に説明します。これらのポイントを確認すると、悪質な不動産投資勧誘を避ける時に効果的です。
まとめ
本記事では、不動産投資の勧誘電話を適切に断るための方法を解説しました。シンプルで明確な断り方をはじめ、冷静かつ丁寧な対応、法に基づいた対処方法、さらに監督官庁への相談の意志を伝える効果的な方法などを実践してみてください。また、悪質な不動産会社を見分けるための具体的なポイントも解説しました。悪質な会社に騙されるリスクを減らす具体的な情報をよく理解し、投資に役立ててください。

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ