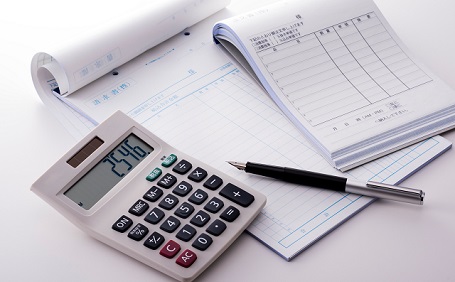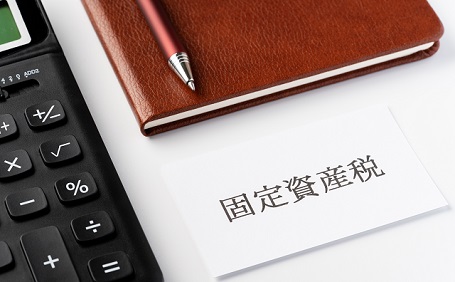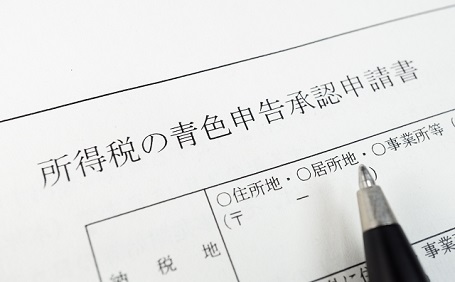家賃収入にかかる税金は?計算方法の解説やシミュレーションまで!

本記事では、家賃収入に対して、どういった税金がかかるのか、家賃収入に対してどれくらい税金がかかるのか、シミュレーションしながら解説します。
納める税金の金額は、収入や経費によって変わるため、正しく計算することが大切です。正確に計算できるよう、基本的な知識を押さえておきましょう。
記事の目次
家賃収入とは

「家賃収入と不動産所得は同じもの」と考えている方もいるのではないでしょうか。本章では2つの違いや、家賃収入に含まれるものを解説します。
家賃収入と不動産所得の違い
家賃収入とは、不動産を貸し出すことで得られる収入の総称です。例えば、部屋を貸し出して得られる家賃だけではなく、駐車場代や共益費なども家賃収入にあたります。不動産所得とはこういった家賃収入から、固定資産税や修繕費など、経費を差し引いたあとの利益を指します。式にすると次のとおり。
不動産所得 = 家賃収入 - 経費
家賃収入は不動産を貸し出すことで得られる総収入で、不動産所得は利益であることを、理解しておきましょう。
家賃収入に含まれるもの
先述したように、家賃収入は、部屋を貸し出して得られる家賃以外にもさまざまあります。
入居者に返還しない敷金・保証金
入居者が入居する際に支払う敷金・保証金の一部が家賃収入となります。原則として、敷金や保証金は、入居者が退去する際に返還するもの。しかし、賃貸借契約書で「原状回復費用に充てる」など、一部を返還しない旨が明記されている場合、その部分は収入とみなされます。
礼金
入居する際に入居者から受け取る礼金も、家賃収入に含まれます。礼金はもともと、オーナーへの感謝やお礼の意味として支払われてきたもの。相場としては家賃の1カ月〜2カ月分です。最近では、礼金が0円の場合も多くなっています。
更新料
賃貸借契約の更新時に支払われる更新料も、家賃収入に含まれます。一般的に、賃貸借の契約期間は2年間。そのため、2年ごとに契約更新の時期を迎えます。更新料の相場は家賃の1〜2カ月程度。
しかし、大阪府や兵庫県などの関西圏では更新料が設定されていない物件も多くあります。なかには、更新料の負担を避けるため、契約更新のタイミングで退去する方もいます。新しい入居者がすぐに決まるとは限らないため、更新料の設定は慎重におこなう必要があります。
共益費
共益費とは、物件の共有部を維持・管理するために入居者から徴収するものです。この共益費も、家賃収入にあたります。具体的な使途としては、エントランスや廊下などの電気代、エレベーターや消防設備などの保守点検費用、共有部の清掃費用などが挙げられます。
駐車場代
家賃とは別に、駐車場代を設定している場合も、家賃収入に含まれます。例えば、アパートやマンションなどの場合、家賃とは別に駐車場代が設定されていることが一般的です。しかし、一戸建ての場合は、家賃に含まれることが多くなります。
また、駅の近くや都心部など、駐車ニーズが高いところは、駐車場代が高くなる傾向にあるため、まとまった収入が期待できるでしょう。
家賃収入の経費として計上できるもの・できないもの
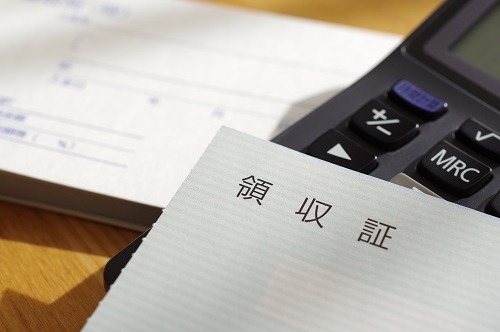
家賃収入にかかる税金を計算する際には、経費にできるものをすべて計上しなければなりません。経費をきちんと計上すると、課税所得が抑えられ、結果として納めるべき税金も減らせます。本章では、家賃収入の税金を計算する際に、経費として計上できるもの・できないものを解説します。
家賃収入の経費として計上できるもの
家賃収入の場合、家賃収入を得るにあたって直接関係するものが、経費として認められます。直接関係するものとは何なのか、詳しくみていきましょう。
| 経費にできる費用 | 内容 |
|---|---|
| 不動産取得税 | 収益物件を建築や購入した際にかかる税金 |
| 印紙税 | 売買契約書や工事契約書などの契約書に貼付する税金 |
| 登録免許税 | 収益物件の権利関係を公的に証明する登記をおこなう際に納める税金 |
| 固定資産税・都市計画税 | 収益物件を所有することに対してかかる税金 |
| 管理委託料 | 収益物件の管理業務を管理会社に委託する際に支払うもの |
| 修繕費 | 収益物件の老朽化への対処や設備の故障を修理する際に支払うもの |
| 入居者募集のための仲介手数料 | 不動産会社に入居者の仲介を依頼し、入居者が決定した際に支払うもの |
| 広告宣伝費 | 入居者を募集する際にかかる広告宣伝の費用 |
| 事務手数料 | 不動産投資ローンを借り入れる際に、金融機関に支払うもの |
| 保証料 | 不動産投資ローンを借り入れる際に、保証会社に保証を依頼する費用 |
| 不動産投資ローンの利息 | 借り入れた不動産投資ローンの利息 |
| 減価償却費 | 時間の経過とともに価値が下がっていく収益物件の購入価格を、 法定耐用年数に応じて毎年経費として計上するもの |
| 損害保険料 | 収益物件を購入する際に加入する、火災保険料や地震保険料の保険料 |
| 通信費 | 不動産会社とのやりとりで使用するインターネットやスマートフォンなどの通信費 |
| 司法書士や税理士などへの報酬 | 不動産登記や確定申告などを専門家に依頼した時の報酬料 |
| 青色専業従事者への給与 | 青色申告をしている事業主に雇われた配偶者や親族に支払われる給与 |
| 接待交際費 | 不動産会社と打ち合わせした際の飲食代など |
| 事務用品費 | 不動産経営をするにあたって購入した事務用品代 |
| 交通費 | 不動産会社への訪問や収益物件の見回りをした際にかかった交通費 |
| 立ち退き料 | 入居者に立ち退いてもらう際に負担した引越し代や新しい入居先の敷金など |
| 新聞図書費 | 不動産経営をするにあたって必要な情報収集のための新聞の購読費や本の購入代など |
なお、経費として計上するためには、支払いが証明できる領収書や請求書が必要です。確定申告をする際に必要となるため、保管しておきましょう。
家賃収入の経費として計上できないもの
次に、経費として計上できないものをみていきましょう。誤って計上すると、申告し直さなければなりません。正しく計上するためにも、しっかり理解しておきましょう。具体的には、次の4つです。
- 不動産投資ローンの元本
- 固定資産税の精算金
- 所得税・法人税
- 収益物件を購入する際の仲介手数料
不動産投資ローンの利息は計上できますが、元本は計上できません。なぜなら、不動産投資ローンは土地や収益物件を購入するために借り入れたものだからです。土地や収益物件という資産に対する対価であるため、返さなければならないものです。
精算金とは、固定資産税の年の途中における日割り計算した調整額のこと。引き渡し日以降の固定資産税は新しいオーナーが負担することになります。先ほどと同様、資産を得るための対価であると考えられるため、経費にはできません。
また、所得税や法人税も、経費として計上できません。それは、不動産経営によって得られた所得に対して課される税金だからです。他にも、収益物件を購入する際にかかった仲介手数料も経費にはあたりません。しかし、収益物件の取得に対して必要な費用であることから、取得費用に含めて計算できます。
家賃収入にかかる税金とは?
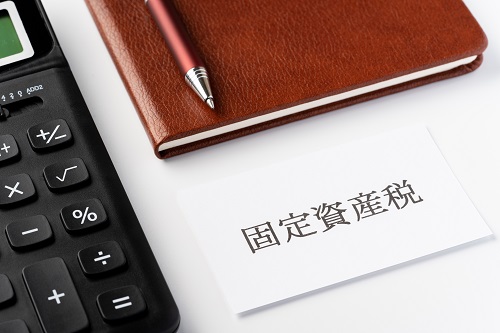
家賃収入も所得の一種とみなされることから、さまざまな税金がかかります。本章では、家賃収入にかかる税金を4つ解説します。
所得税
家賃収入から経費を差し引いた金額(不動産所得)に対して、所得税がかかります。所得税とは、1月1日〜12月31日までの1年間で得られた所得に対して課される税金です。累進課税制度が採用されており、所得が多くなるほど、税率も高くなります。
あとで詳しく解説しますが、もし家賃収入が赤字であれば、他の所得と合算して赤字を相殺することで所得を下げ、所得税を下げることも可能です。
住民税
住民税も、家賃収入から得られる所得に対して課税されるもの。住民税とは、1月1日に都道府県(市町村)に住所を有する人に課される税金で、地方自治体の運営に必要な財源となります。
住民税には、所得に応じた税金が課される「所得割」と、非課税限度額を上回る人に定額の負担が求められる「均等割」に分けられます。それぞれ道府県民税と市町村民税の2種類あり、所得割は一律10%となっています。具体的な税率は次のとおり。
消費税
消費税も家賃収入にかかる税金の一つです。しかし、アパートやマンションなどの住宅用物件の賃貸には、消費税はかかりません。一方、事業用物件の賃貸による家賃収入には消費税がかかります。事業用物件とは、オフィスビルや店舗など、事業活動に利用される物件のこと。ただし、基準期間において課税売上高が1,000万円以下の場合には、免税事業者に該当するため、消費税はかかりません。
なお、家賃収入に含まれる駐車場代も、消費税がかかる可能性があります。しかし、入居者が車を所有しているかにかかわらず、1戸につき1台以上の駐車場が用意されている場合は、非課税となります。
固定資産税
固定資産税とは、建物や土地などの固定資産を所有している人に対して、地方自治体から課される税金です。家賃収入にかかる税金というより、不動産を所有していることに対する税金となります。また、所有している不動産が市街化区域内にある場合には、都市計画税も課されます。それぞれの計算式は、次のとおり。
都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%(※)
※東京23区内の税率
固定資産税評価額とは、市町村の長が決定する土地や建物の評価額です。所有している間は毎年かかる税金のため、必ず納めるようにしましょう。
家賃収入にかかる税金の計算方法

これまでみてきたように、家賃収入にかかる税金には、所得税や住民税などさまざまです。ここでは、所得税と住民税の計算方法を解説します。
step 1. 不動産所得を計算する
まずは、不動産所得を計算しましょう。家賃収入から経費を引いたものが不動産所得です。計算式は次のとおり。
不動産所得 = 家賃収入 - 経費
経費が多ければ、不動産所得が減るため、納める税金も少なくなります。そのため、先ほど解説した経費をもれなく計上することが大切です。
step 2. 所得税を計算する
不動産所得が求められたら、所得税を計算しましょう。所得税の税率は課税される所得金額によって異なります。具体的には次のとおり。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円 から 194万9,000円まで | 5% | 0円 |
| 195万円 から 329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
| 330万円 から 694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
| 695万円 から 899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
| 900万円 から 1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
| 1800万円 から 3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
2037(令和19)年までの各年分の確定申告においては、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)をあわせて申告・納付します
例えば、家賃収入が300万円で、経費が60万円だった場合の所得税を計算してみましょう。
不動産所得
300万円 - 60万円 = 240万円
所得税
240万円 × 10% -9万7,500円 = 14万2,500円
この場合、所得税は14万2,500円となります。
step 3. 住民税を計算する
次に、住民税を計算しましょう。先述したように、住民税には所得割と均等割の2種類があります。例えば、先ほどと同じく家賃収入が300万円、経費が60万円だった場合。住民税は次のように計算できます。
所得割
240万 × 10% = 24万円(道府県民税:9万6,000円、市町村民税:14万4,000円)
均等割
5,000円(道府県民税:1,000円、市町村民税:3,000円、森林環境税:1,000円)
所得割と均等割の合計
24万 + 5,000円 = 24万5,000円
住民税は24万5,000円となりました。なお、所得税と住民税を合わせた税額は、38万7,500円となります。
家賃収入にかかる税金のシミュレーション

家賃収入に対して、実際にどれくらいの税金がかかるのか、気になるところでしょう。本章では、不動産所得が100万円、200万円、300万円の3つの場合、所得税と住民税がどうなるのかをそれぞれシミュレーションしてみました。また、それぞれ給与所得が700万円ある場合もシミュレーションしています。なお、わかりやすくするため、所得控除や税額控除を考慮しないものとします。
家賃収入が100万円の場合
まずは、不動産所得が100万円の場合、税金がいくらになるかをシミュレーションしてみましょう。
<家賃収入のみの場合>
所得税
100万円 ×5% =5万円
住民税
100万円 × 10% = 10万円
10万円 + 5,000円 = 10万5,000円
所得税と住民税の合計
5万円 + 10万5,000円 = 15万5,000円
不動産所得が100万円の場合、税金が15万5,000円となりました。
<給与所得が700万円ある場合>
課税所得
100万円 + 700万円 = 800万円
所得税
800万円 × 23% - 63万6,000円 = 120万4,000円
住民税
800万円 × 10% = 80万円
80万円 + 5,000円 = 80万5,000円
所得税と住民税の合計
120万4,000円 + 80万5,000円 = 200万9,000円
不動産所得が100万円の場合は、所得税と住民税をあわせて15万5,000円でした。しかし、700万円の給与所得がある場合には、200万9,000円となりました。
家賃収入が200万円の場合
次に、不動産所得が200万円の場合を計算してみましょう。
<家賃収入のみの場合>
所得税
200万円 × 10% -9万7,500円 = 10万2,500円
住民税
200万円 × 10% = 20万円
20万円 + 5,000円 = 20万5,000円
所得税と住民税の合計
10万2,500円 + 20万5,000円 = 30万7,500円
不動産所得が200万円の場合、税金は30万7,500円でした。不動産所得が100万円の時と比較して2倍近くになりました。
<給与所得が700万円ある場合>
課税所得
200万円 + 700万円 = 900万円
所得税
900万円 × 33% - 153万6,000円 = 143万4,000円
住民税
900万円 × 10% = 90万円
90万円 + 5,000円 = 90万5,000円
所得税と住民税の合計
143万4,000円 + 90万5,000円 = 233万9,000円
700万円の給与所得があった場合は、233万9,000円でした。不動産所得が100万円、給与所得が700万円と時と比較すると、30万円ほどしか変わりませんでした。
家賃収入が300万円の場合
最後に、不動産所得が300万円の場合を計算してみましょう。
<家賃収入のみの場合>
所得税
300万円 × 10% -9万7,500円 = 20万2,500円
住民税
300万円 × 10% = 30万円
30万円 + 5,000円 = 30万5,000円
所得税と住民税の合計
20万2,500円 + 30万5,000円 = 50万7,500円
不動産所得が300万円の場合、税金は50万7,500円でした。
<給与所得が700万円ある場合>
課税所得
300万円 + 700万円 = 1,000万円
所得税
1,000万円 × 33% ー 153万6,000円 = 176万4,000円
住民税
1,000万円 × 10% = 100万円
100万円 + 5,000円 = 100万5,000円
所得税と住民税の合計
176万4,000円 + 100万5,000円 = 276万9,000円
700万円の給与所得がある場合は、不動産所得が200万円の時と比較すると、43万円増えました。
今回のシミュレーションでは、所得控除や税額控除を考慮していないため、実際にはこれよりも下がる可能性があります。正しく計算したい場合は、税理士などの専門家に依頼しましょう。
家賃収入にかかる税金を納めるための確定申告の手順

家賃収入にかかる所得税や住民税を納めるためには、確定申告をする必要があります。正確な申告をおこなうことで、納めるべき税金も正しく計算されます。もし、確定申告をしなかった場合は、延滞税などのペナルティが課されることも。場合によっては、不動産会社や金融機関などの取引先からの信用も失ってしまうかもしれません。正確な確定申告をおこなうために、手順を押さえておきましょう。
簡単な流れは次のとおりです。
- STEP 1申告方法を決める
- STEP 2必要な書類を揃える
- STEP 3書類を作成、提出する
それぞれ詳しくみていきましょう。
step 1. 申告方法を決める
確定申告には、白色申告と青色申告の2つの方法があります。下表は2つの違いを簡単にまとめたものです。
| 申告方法の違い | 青色申告 (65万円控除) |
青色申告 (10万円控除) |
白色申告 |
|---|---|---|---|
| 開業届と青色申告承認申請書の提出 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 控除可能条件 | 事業的規模 (アパートやマンション10室以上、独立家屋5棟以上) |
マンション 1室から |
なし |
| 税制上のメリット |
・青色事業専従者控除
・3年間の赤字繰越控除
・貸倒損失を必要経費に計上できる
|
なし | |
青色申告のほうが、提出や保存をしなければならない書類が多くなります。しかし、控除額が大きいため、納める税金を抑えられる可能性があります。どちらの申告方法がいいのかは、家賃収入や受けられる所得控除などによって変わります。わからない場合は、税理士などに相談し、自分に合った申告方法を選びましょう。
step 2. 必要な書類を揃える
申告方法を決めたら、必要な書類を揃えましょう。確定申告に必要な書類は次のとおりです。
| 書類の カテゴリ |
家賃収入の確定申告で必要な書類一覧 | ||
|---|---|---|---|
| 書類名 | 内容 | 入手先 | |
| 不動産関連 の書類 |
不動産売買契約書 | 収益物件の売買契約を締結した書類 | 不動産会社 |
| 賃貸借契約書 | 入居者に部屋を貸す際に締結した 賃貸借契約の書類 |
||
| 家賃の送金明細書 | 管理会社に委託している場合、 回収された家賃などを精算した明細 |
不動産管理会社 | |
| 売渡精算書 | 収益物件を購入した際の費用明細 | 不動産会社 | |
| 経費関連 の書類 |
税金の納付通知書 | 不動産取得税や固定資産税などの納付書 | 国・地方自治体 |
| 不動産投資ローンの返済表 | 前年1年間の不動産投資ローンの返済表 | 金融機関 | |
| 管理費・修繕積立金の 証明書類 |
収益物件のメンテナンスや修繕のために積み立てているお金の領収書 | 不動産管理会社 | |
| 譲渡対価証明書 | 土地と収益物件に按分した際の割合を示したもの。減価償却を算出するための書類。 | 不動会社 | |
| 控除関連 の書類 |
損害保険料の証券・領収書 | 収益物件にかけた火災保険料や 地震保険料の保険料がわかるもの |
保険会社 |
| 源泉徴収票 | 会社員の方が確定申告をする場合、所得税の還付を受けられたり、不動産投資の赤字を損益通算できる可能性があるため | 勤務先 | |
また、申告方法によって提出しなければならない書類が異なります。漏れがあると、正確な申告ができないため、忘れないようにしましょう。
step 3. 書類を作成・提出する
必要な書類を揃えたら、確定申告書に記入して書類と一緒に提出しましょう。3つの提出方法があります。
- 税務署に持参する
- 税務署に郵送する
- 電子申告(e-Tax)をする
スマートフォンにICカードの読み取り機能が付いていれば、スマートフォンからでも電子申告(e-Tax)が可能です。もし確定申告が初めてで、疑問点や不明点がある場合は、税務署で職員に質問しながらおこなうといいでしょう。
なお、確定申告の期間は2月16日〜3月15日までとなっています。また、この期間に提出するだけでなく、納税もしなければなりません。スムーズに申告できるよう、早めに準備をしておきましょう。
まとめ
今回は、家賃収入にかかる税金の種類や計算方法を解説しました。また、不動産所得の金額別に税金がどれくらいかかるのか、シミュレーションをおこないました。家賃収入や経費、受けられる控除などは人それぞれ異なります。そのため、それぞれをもれなく計上し、正しい金額を求めなければなりません。誤った申告をすると、ペナルティが課される可能性もあります。税理士などの専門家に相談し、正確な申告をおこないましょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ