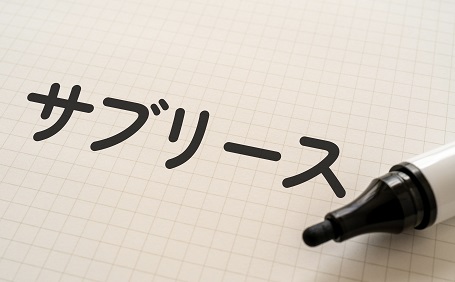オーナーチェンジ物件は危険って本当?潜むリスクや対策方法を徹底解説

しかし、オーナーチェンジ物件に投資する際は、注意すべきポイントがあります。本記事では、オーナーチェンジ物件が危険といわれている理由やリスクに対する対処方法を解説します。
記事の目次
オーナーチェンジ物件とは

オーナーチェンジ物件とは、既存の賃貸借契約を継続したまま所有者が変更される中古の収益不動産のこと。物件の種類には、アパートや一棟マンション、区分所有マンション、商業施設、オフィスビルなどがあります。
特徴は、入居者がいる状態で売買がおこなわれる点です。つまり、購入者は物件内部を直接確認できないまま売買を進めることになります。そのため、多くのリスクがともなう可能性も。具体的なリスクは以下で詳しく解説するので、参考にしてください。
オーナーチェンジ物件が危険といわれている理由と対策

ここからは、オーナーチェンジ物件が危険と言われている理由を解説します。オーナーチェンジ物件に潜むリスクには、以下の点が挙げられます。
- 入居状況が不透明である
- 入居者がいるため室内の状況を把握できない
- 家賃を滞納している入居者がいる可能性がある
- 空室が多いと利回りが下がることがある
- 住宅ローンより金利が高くなる
- 問題のある入居者を追い出すことが難しい
- 現在の賃貸借契約がそのまま引き継がれてしまう
- 基本的にリノベーションや建て替えることが難しい
- 物件を購入したあとに問題が発見される可能性がある
それぞれのリスクについて詳しく解説します。
入居状況が不透明である
オーナーチェンジ物件の大きなリスクとなるのが、入居状況の不透明性です。物件購入時に、実際の入居状況が説明と異なる場合があります。
例えば、売り出し時には満室だった物件が、契約時には空室が発生しているケースもありえます。不動産取引には数カ月を要することもあり、その間に入居者が退去する可能性も十分にあるでしょう。
このリスクを軽減するためには、以下のポイントを意識してみてください。
- 最新の入居状況を繰り返し確認する
- 入居者との契約書や家賃支払い記録を精査する
- 可能であれば、現地調査を複数回実施する
入居状況を正確に把握することで、将来の収益予測や物件の管理計画が立てやすくなります。
入居者がいるため室内の状況を把握できない
オーナーチェンジ物件では、入居者がいるため、物件内部の状態を直接確認することが困難です。
現在の状況をチェックできないとなると、内装の損傷状況や、設備の老朽化や故障の可能性を把握できません。
特に問題となる点は、将来の原状回復義務に関する不確実性です。入居時の状態が不明確なため、退去時にどの程度の原状回復が必要かを判断することが難しくなるでしょう。原状回復義務に関する情報がわからなければ、入居者とのトラブルや予期せぬ修繕費用の発生につながる可能性があります。
このリスクに対応するためにも、以下のポイントをチェックしてみてください。
- 可能な限り詳細な物件情報を手に入れる(図面、過去の修繕履歴など)
- 入居者の協力が得られる場合は内覧を実施する
- 建物の外観や共用部分から状態を推測する
- 不測の事態に備えて予備費を確保する
物件状態の不確実性は、オーナーチェンジ物件特有のリスクです。不確実性を考慮した慎重な投資判断と、将来の修繕に備えた資金計画が重要です。
家賃を滞納している入居者がいる可能性がある
オーナーチェンジ物件では、既存の入居者のなかに家賃滞納者がいる可能性があります。
一般的に、3カ月以上の家賃滞納は契約解除事由となりますが、実際に入居者を退去させる際には法的手続きが必要となるため、時間と費用がかかります。
家賃滞納のリスクへの対策として、以下のポイントを確認してみてください。
- 購入前に全入居者の家賃支払い状況を詳細に確認する
- 滞納者がいる場合、その対応状況と今後の見通しを売主から聞く
- 敷金の残高と、それが将来の原状回復費用をカバーできるかを確認する
- 深刻な滞納問題がある物件は、購入を再考する
家賃滞納の問題は、物件の収益性だけでなく、管理の手間も大きく増加させる要因となります。家賃滞納のリスクを十分に考慮し、必要に応じて購入価格の交渉や条件の設定をおこなうことが重要です。
空室が多いと利回りが下がることがある
オーナーチェンジ物件の収益性は、想定と現実の間に大きな差が生じる可能性があります。特に注意が必要なのは、「満室想定」の利回りが示されているケース。
収益性は、空室率や家賃、相場、予期せぬ修繕費用の発生などで、大きく変動します。
「満室想定」の利回りは、すべての部屋が埋まった理想的な状況を前提としています。しかし、満室の状態がずっと続くわけではありません。基本的には、どのような物件でも一定の空室率が存在すると理解しておく必要があります。
さらに、築年数が経過した物件では、予想以上に修繕費用がかさむ可能性があります。家賃相場が下落したり、空室率が増加したりなどすると、実際の収益は当初の想定を大きく下回ってしまうかもしれません。
利回りが下がるリスクを軽減するためにも、以下の対策が効果的です。
- 保守的な収益予測をおこなう(例:空室率を10〜15%と仮定する)
- 地域の賃貸市場動向を詳細に調査する
- 修繕積立金を十分に確保する
- 複数の収益シナリオ(最悪、中間、最良)を想定し、それぞれの対策を講じる
収益性の変動リスクは、投資判断に大きな影響を与えます。こまめに市場を分析したり、財務計画を慎重に検討したりなど、収益性の変動リスクに対応できるように準備しておくことが大切です。
住宅ローンより金利が高くなる
オーナーチェンジ物件の購入には、一般的に不動産投資ローンが利用されます。不動産投資ローンは一般的な住宅ローンと比較すると、いくつかの違いがあります。
不動産投資ローンの特徴
- 金利が住宅ローンより高い傾向にある
- 融資期間が比較的短い(20〜30年程度)
- 頭金の要求額が大きい場合がある
例えば、住宅ローンの金利が1%台後半であっても、不動産投資ローンは2〜3%台に設定されていることも珍しくありません。数%の違いであれば、大きな負担にならないと考える方もいますが、年間に換算すると支払い利息に大きな差が出てきます。
また、融資期間が短い場合は、月々の返済額が高くなってしまいます。月々の返済額が高くなると、キャッシュフローに大きな影響が出ることもあるでしょう。
金利対策としては、以下のポイントが挙げられます。
- 複数の金融機関から見積もりを取り、最適な条件を探す
- 自己資金を増やし、借入額を抑える
- 返済計画を慎重に立て、余裕を持たせる
- 金利の固定期間や変動金利の選択を慎重に検討する
問題のある入居者を追い出すことが難しい
オーナーチェンジ物件を購入する際、既存の賃貸借契約はそのまま引き継がれます。この時にネックとなるのが、問題のある入居者がいた場合でも追い出すことが難しい点です。
例えば、騒音や悪臭などで他の入居者に迷惑をかけていたり、違法転貸など不適切に物件を使用していたりなどが挙げられます。
日本の賃貸借契約法では、貸主からの一方的な契約解除は困難です。明らかな契約違反(長期の家賃滞納など)がない限り、入居者を退去させることは法的にはほとんどできません。
特に注意が必要なのは、軽微だが慢性的な問題を引き起こす入居者です。例えば、やや不衛生な生活をしている、騒音レベルが少しうるさい程度であるなどのケースです。
上記は契約解除事由には該当しませんが、物件の価値や他の入居者の満足度に悪影響を及ぼす可能性があります。
対策としては、以下のポイントが挙げられます。
- 購入前に入居者情報を可能な限り詳細に確認する
- 管理会社からの評価や過去のトラブル履歴を入手する
- 問題解決のための交渉スキルを磨く、または専門家に相談できる体制を整える
問題のある入居者への対応は、オーナーチェンジ物件管理の大きな課題の一つです。他の入居者を守るためにも、しっかり対策を考えておかなければなりません。
現在の賃貸借契約がそのまま引き継がれてしまう
繰り返しになりますが、オーナーチェンジ物件を購入する際、既存の賃貸借契約をそのまま引き継ぐ形になります。そのため、現在の賃料水準をそのまま継続することになったり、更新料や敷金などの契約条件も変更できなかったりなどのデメリットがあります。
相場よりも高い賃料で貸し出されている場合、短期的には有利に見えますが、入居者の早期退去リスクも高まるでしょう。一方、相場よりも低い賃料の場合、収益性は低下しますが、長期的な入居が期待できます。
特に注意が必要なのは、法人契約や定期借家契約など、特殊な条件の契約です。法人契約や定期借家契約などの場合は、一般的な賃貸借契約と異なる面があるため、よく確認をしましょう。
引き継ぎや契約条件に関するリスクに対策するためには、以下の方法が挙げられます。
- すべての賃貸借契約書を詳細に確認する
- 現在の賃料と相場を比較分析する
- 契約更新のタイミングを把握し、将来的に賃料を調整できるかを確認する
- 特殊な契約に関しては、法律の専門家にアドバイスを求める
契約内容を十分に理解し、メリットとデメリットも把握したうえで、将来の戦略を立てることが重要です。
基本的にリノベーションや建て替えることが難しい
オーナーチェンジ物件では、入居者がいる状態で購入するため、大規模な改修や建て替えをおこなうことが難しいでしょう。
特に築年数が経過した物件の場合は、改修や建て替えができないと、のちに大きな問題になる可能性があります。老朽化が進んだ設備や時代遅れの内装は、物件の競争力低下につながることも。
このリスクに対応するためには、以下の対策方法が挙げられます。
- 購入前に物件の現状を可能な限り詳細に調査し、将来必要となる改修の範囲を把握する
- 共用部分など、入居者に影響の少ない箇所から段階的に改修をおこなう
- 退去が発生した際に、速やかに個別の部屋の改修をおこなう計画を立てる
- 長期的な視点で、全面的なリノベーションや建て替えの機会を待つ
改修や建て替えが制限されるとなると、物件の価値を長期的に維持したい時に大きな影響を与えてしまうかもしれません。一度に大規模な改修や建て替えをおこなうのは難しいため、段階的な改善計画を立てておくとよいでしょう。
物件を購入したあとに問題が発見される可能性がある
中古物件であるオーナーチェンジ物件には、購入後に予期せぬ問題が発見されるリスクがあります。
例えば、構造上の問題(耐震性能の不足など)や雨漏りによる外壁の劣化、設備の老朽化(配管、電気設備など)など。
特に築年数が経った物件では、このリスクが高まります。また、上記でもお伝えしましたが、入居者がいる状態で物件を購入するため、事前に物件の詳細な調査が難しいことも、リスクを高める一つの要因です。
対策としては、以下の方法が挙げられます。
- 可能な限り詳細な建物診断を実施する(外部からの調査でも多くの情報が得られます)
- 売主から過去の修繕履歴のリストを入手する
- 瑕疵(かし)担保責任の範囲を売買契約書で明確にする
- 予想外の修繕に備えて、十分な資金的余裕を持つ
特に瑕疵担保責任の範囲を売買契約書で明確に記載しておくことが重要です。万が一問題が見つかった場合でも、契約書に記されていれば売主に責任を取ってもらうことができます。
オーナーチェンジ物件を購入する際の注意点

ここでは、オーナーチェンジ物件購入時の注意点を詳しく解説します。
契約内容を綿密に確認する
オーナーチェンジ物件の購入では、既存の賃貸借契約内容を引き継ぐため、綿密な確認が必要です。
契約内容の確認ポイントは、以下のとおりです。
- 現在の賃料設定
- 諸経費の負担区分
- 解約に関する規定
- 更新料や保証金の取り扱い
- 保証人の有無
上記の項目を事前によく確認することで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安定した収益を確保できる可能性が高まるでしょう。
実地調査と情報収集を徹底的におこなう
書面上の情報だけでなく、実地調査と情報収集を徹底的におこないましょう。調査と情報収集を徹底することで、よりよいオーナーチェンジ物件を購入できる可能性が高まります。
現地調査では以下のポイントを確認してみてください。
- 共用部の管理状態
- 入居者の生活実態
- 建物の全体的な雰囲気
また、売主に話を聞く際は、以下の項目を確認しておきましょう。
- 入居者の履歴
- 過去のトラブル事例
- 管理上の課題
市場動向を分析する
現在の賃料と周辺相場を比較分析することは、将来的な収益性を予測するうえで重要です。もし現在の賃料が周辺相場を上回っている場合、今後の賃料引き下げの可能性を考慮に入れる必要があります。
地域の賃貸市場動向を綿密に調査し、長期的な視点で投資計画を立てましょう。
経営履歴と売却動機を明確にする
物件の過去の運営状況や、売主が手放す理由を詳しく調査することも重要です。単なる高齢化による売却なのか、それとも別の要因があるのかを見極める必要があります。
赤字経営や不自然な売却理由がある場合は、物件に何か問題が生じている可能性があるため、特に注意が必要です。
過去の運営実績を調べる際は、空室率の推移や入居者募集の方法、修繕・改修の履歴などを確認しましょう。
信頼性の高い不動産会社を選ぶ
信頼できる不動産会社と取引をおこなうことで、投資の成功率を高めることができます。信頼できる不動産会社を見極めるポイントは、以下のとおりです。
- 成功事例を持つ知人から紹介してもらう
- 複数の会社を比較する
- オンラインでの評判を調査する
- 直接相談した際に担当者との相性を確認する
おすすめは、複数の不動産会社を比較検討することです。たとえ知人からの紹介であっても、自分とその不動産会社の相性が必ず合うとは限りません。
あくまでも候補の一つにし、少なくとも3社の不動産会社を比較して、自分のニーズに合う不動産会社を見極めることが大切です。
サブリース契約は慎重に検討する
サブリース契約とは、不動産オーナーが自身の物件をサブリース会社に一括して賃貸し、サブリース会社が入居者に転貸する仕組みです。
サブリース契約が付帯する物件は、一見安定した収益が見込めるように思えますが、契約解除の難しさや条件変更の制限など、買主にとって不利な面もあります。サブリース契約のデメリットを十分に理解したうえで、慎重に判断することが重要です。
まとめ
本記事では、オーナーチェンジ物件がなぜ危険だといわれているのか、その理由を詳しく解説しました。オーナーチェンジ物件には多くのデメリットがありますが、適切な対策をすれば問題なく運営できるでしょう。
オーナーチェンジ物件のメリットやデメリットを把握し、自分でも運営を維持できるか慎重に判断したうえで、オーナーチェンジ物件を購入するかどうかを決めましょう。

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ