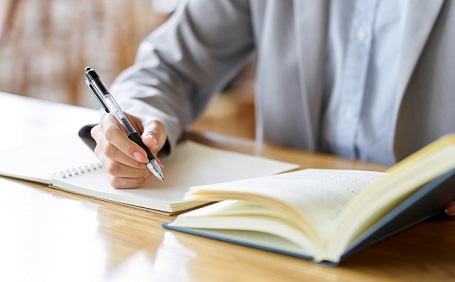不動産事業の法人化なら合同会社がいい?適切なタイミングや設立手順を徹底解説!

そこで本記事では、個人事業主が不動産事業を法人化する際に合同会社を設立するメリットや、法人化の適切なタイミング、具体的な設立手順を詳しく解説します。
記事の目次
不動産事業を法人化するなら合同会社と株式会社のどちらがよいか

個人事業主が不動産事業を法人化する際の会社の形態は、株式会社か合同会社が一般的です。では、不動産事業で法人化するなら、株式会社と合同会社のどちらが適切でしょうか。本章では、株式会社と合同会社の概要を比較し、メリットとデメリットから、判断の目安を提案します。
株式会社と合同会社の違い
株式会社と合同会社の違いは以下のとおりです。
| 株式会社 | 合同会社 | |
|---|---|---|
| 所有と経営 | 分離 | 一致 |
| 利益配分の決めかた | 株主が決める | 自由 |
| 設立費用 | 約24万円 | 約10万円 |
| 決算報告義務 | 必須 | 任意 |
| 株式公開 | できる | できない |
| 会社の信用力 | 高め | 株式会社より低め |
株式会社は、出資者(株主)が株式を購入し資金を提供する会社形態でよく知られているでしょう。取締役が経営をおこない、株主は経営に直接関与しません。株式を発行する手法で資金調達がしやすく社会的信用も高い反面、設立費用が高額で運営にあたって取締役会や株主総会の開催義務があり、管理コストがかかります。また、会社法に基づく厳格な経営体制が求められる点が特徴です。
合同会社は、少人数やスタートアップ向けの柔軟な経営に特徴があります。出資者(社員)が経営に直接関与し、意思決定が迅速で、取締役会や株主総会の開催義務もありません。設立費用や管理コストが低く、運営が簡便ですが、外部からの大規模な資金調達は難しく、社会的信用も株式会社に比べて低い場合があります。
不動産事業を法人化するなら合同会社がよい
では、不動産事業を法人化する場合、株式会社と合同会社のどちらがよいでしょうか。結論からいえば、小規模な不動産業や、柔軟な経営を求める場合には合同会社が向いています。
合同会社の主な懸念点は、資金調達と、社会的信用です。資金調達では、合同会社は株式を発行できないため、大規模な調達ができないかもしれません。しかし、少額の自己資金で始める小規模な不動産業なら、この点の検討は不要でしょう。社会的信用は株式会社に劣りますが、金融機関のローン審査を受ける際には知名度などは問われません。個人の属性や信用情報、これまでの不動産投資の実績や支払い能力などが審査されるので社会的信用の低さも不問です。
一方で、合同会社は、設立費用と運営コストや経営の自由度に優位性があります。合同会社の場合、設立費用は株式会社よりも安く、定款認証が要りません。また、株主総会や取締役会などの開催義務もなく、運営コストが低く抑えられます。さらに、出資者が経営に直接関与するため、意思決定が迅速かつ柔軟です。特に、不動産物件の購入や賃貸管理など、日常的に判断が求められる業務には、合同会社のほうが適しているでしょう。結果、不動産業で法人化するなら、合同会社が適切です。
不動産事業で合同会社を設立するタイミング
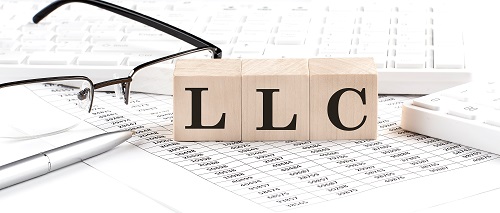
個人事業主が不動産事業を法人化するうえで合同会社を設立する適切なタイミングは、「税金の負担が増加」した時です。まずは、売上や利益に関する税金や消費税の状況を考慮しましょう。小規模に運営している段階では問題ありませんが、個人事業主の場合、利益が増えるほど適用される税率も上昇します。
課税所得が900万円になる時
個人の課税所得に対してかかる所得税は5%から始まり、最高で45%に達します。2024年4月現在、合同会社で資本金が1,000万円以下・適用除外事業者でない場合、所得が800万円以下であれば税率は15%。しかし、所得が800万円を超えると税率は23.2%に上がります。
個人の場合、課税所得が695万円から899万円の時、税率が23%ですが、900万円以上では33%に達します。したがって、課税所得が900万円になる時に法人化を検討すると、税負担を軽減する効果が期待できます。
売上高が1,000万円を超えて消費税の課税対象事業者になる時
消費税に関しても考慮が必要です。現行の税制では、課税売上高が1,000万円を超えると、その2年後から消費税の課税事業者となり、納税義務が発生します。このため、消費税の課税が決まった時点で法人化をおこなえば、さらに2年間は消費税の免税を受けられるため、経済的なメリットが増します。
このように、合同会社設立の理想的なタイミングは、次のとおりです。
-
・不動産事業の収入が上がり税負担が増加する時・法人化による税制の優遇措置を享受できる時
個人事業主としての税負担を見直し、合同会社の設立によって税率を下げたり、消費税の免税を活用する手法は、資金繰りの面でも有利です。売上や利益の状況を常に把握し、適切なタイミングでの法人化を検討するようにしましょう。
不動産事業で合同会社を設立する具体的な手順

合同会社の設立にかかる費用や手間は比較的少ないため、小規模な事業やスタートアップに適しています。合同会社を設立する際の手順は株式会社の設立に比べ比較的シンプルで、準備するべき書類も少ないです。
- STEP 1会社名(商号)と本店所在地を決定する
- STEP 2事業目的を決定する
- STEP 3定款を作成する
- STEP 4定款へ押印する
- STEP 5資本金を払い込む
- STEP 6法務局への登記申請をおこなう
なお、設立後は必要に応じて関係各所への届出をしなければなりません。では、それぞれの手順を詳しく解説していきます。
STEP 1. 会社名(商号)と本店所在地を決定する
合同会社を設立する際、最初におこなうのは「会社名(商号)」と「本店所在地」の決定です。合同会社の名称は、会社を識別するための重要な要素で、他社と区別できる必要があります。商号には、「会社」を含めなければなりません。「〇〇合同会社」や「合同会社△△」のような形式になります。
会社名は自由に選べますが、公序良俗に反する名前や、特定の業種に誤解を与える名称は避けるべきです。また、同一の所在地に既存の合同会社が存在していないか、商号の重複がないかも確認しましょう。これは、法務局での登記手続き時に拒否される可能性があるため、事前にオンラインの商号検索システムを使って確認するか、専門家への相談をおすすめします。
さらに、本店所在地の決定も重要なポイントです。本店所在地に設定する自宅やオフィスの住所は正確に記載しましょう。また、賃貸物件を使用する場合は、事前に契約書で事業利用が可能か確認し、問題がないか注意する必要があります。
STEP 2. 事業目的を決定する
事業目的は、会社がおこなう具体的な活動内容を示すもので、定款に記載する必要があります。事業目的は法的に認められたものでなければならず、違法な事業や公序良俗に反する活動はもちろん記載できません。また、取引先や金融機関に事業内容を明確に伝えるためにも、具体的でわかりやすい内容にすることが重要です。
例えば、不動産業の場合、「不動産の売買、賃貸およびその仲介」や「不動産管理業務」といった具体的な目的を記載します。また、現在の事業内容に加え、将来的におこなう可能性がある事業も含めて記載するようにしましょう。例えば、初期段階では不動産賃貸のみをおこなっていても、将来的に建築やリフォーム業など関連する分野に進出する可能性がある場合、その事業内容も記載しておくと便利です。そうすれば、定款の変更を必要とせず、柔軟に新しい事業を開始できます。
ただし、事業目的があまりにも広範囲すぎると、金融機関や取引先から「具体性がない」として不信感を抱かれるため、注意しましょう。そのため、適度な広がりを持たせつつも、明確で具体的な表現を用いることが大切です。事業目的の変更には定款変更が必要となり、コストや手間がかかるため、将来の展開を見据えた記載を心がけるようにしましょう。
STEP 3. 定款を作成する
会社の設立に必要な定款は、会社の基本ルールを定めた文書であり、設立時に重要な書類の一つ。定款には会社の根幹を定める重要事項を記載するため、内容を吟味した作成が大切です。また、款には紙の定款と電子定款があります。電子定款はPDFでデータ保存ができ、紙の定款に必要な印紙税の4万円も不要になるため、必要に応じて活用しましょう。
まず、定款には「会社名(商号)」を記載しましょう。商号には自由度があり、英数字やカタカナなどを使用できます。先述しましたが、商号を決定する際は既存の商号と重複しないか、公序良俗に反していないかを確認しましょう。
次に、事業目的を明確に記載します。これは先述したように会社がおこなう事業内容を示すもので、具体的かつ合法的でなければなりません。さらに、本店所在地も定款に記載します。会社の主な活動拠点を示すため、正確な住所記載をしなければなりません。定款には資本金額も記載しましょう。会社の経済基盤を示す重要なものです。2006年5月に施行された「新会社法」によって最低資本金制度は廃止されており、1円でも設立が可能ですが、事業規模や今後の融資を考慮して、適切な金額の設定が重要です。
出資者(社員)の氏名や出資割合、利益配分方法も定款に記載しましょう。合同会社は、出資者全員が経営に関与するため、それぞれの出資割合に応じた利益配分や損失負担のルールを明確に定めるようにします。また、定款にはこれらの内容を柔軟に変更できる条項を設け、将来の状況に対応しやすくしておきましょう。
STEP 4. 定款へ押印する
合同会社の定款は、出資者(社員)全員の同意を得て定款に押印することで、正式なものになります。株式会社の場合定款を公証役場で認証する手続きが必要ですが、合同会社ではこの認証手続きは必要ありません。定款は自社で作成し、出資者全員が同意して押印するだけで定款が成立し、法的効力を持つため、手続きが簡便でコストも抑えられる点が合同会社のメリットです。ただし、押印する印鑑は、設立後に使用する会社印を使用するようにしましょう。
STEP 5. 資本金を払い込む
続いて、設立時に定めた資本金の金額を、各出資者(社員)が決められた方法で出資します。先述したように資本金は1円からでも会社の設立が可能。この資本金は、設立後の会社の運転資金となります。払い込みは、会社設立前の個人名義の口座でも可能ですが、設立後に法人名義の口座を開設してから、あらためて資本金を移してもかまいません。通常は、資本金の払い込みを証明するために、法務局に提出する「払込証明書」を作成し、通帳の写しなどとともに提出します。資本金は、会社の信用や運営の規模を反映するため、適切な金額を設定しましょう。
STEP 6. 法務局への登記申請をおこなう
合同会社の設立の最終段階は、法務局での設立登記申請です。この手続きが完了すると、合同会社は法的に成立します。登記申請をおこなう際には、登記申請書を作成し、以下の必要書類を揃えて会社の所在地を管轄する法務局に提出しましょう。
| 主な書類 | 概要 |
|---|---|
| 定款 | 出資者(社員)全員の押印がされた会社の基本ルールを定めた書類 |
| 設立登記申請書 | 会社を設立する旨を記載した公式書類 |
| 払込証明書 | 通帳の写しなどを添付した資本金が出資者から会社へ正しく払い込まれたことを証明する書類 |
| 会社の印鑑届書 | 会社印(代表印)を法務局に届け出るための書類 |
提出した書類に不備がなく法務局に受理されると、登記簿に内容が記載され会社の存在が認められるようになります。なお、登記手続きには登録免許税がかかり、その費用は6~10万円です。登記申請は法務局への直接提出のほか、郵送やオンライン申請もあるので、利用しやすい方法を選択しましょう。申請後、一般的には1〜2週間程度で登記が完了し、完了後に登記簿謄本を取得すると、法務局で確認できるようになります。
合同会社設立後の手続き
合同会社を設立したあとにも、必要に応じていくつかの手続きがあります。まずは、設立後1カ月以内に税務署へ「法人設立届出書」を提出し、法人の登録をおこないましょう。この際、青色申告を希望する場合は、「青色申告承認申請書」も同時に提出する必要があります。青色申告が承認されると、特別控除や赤字の繰越しなどの税制優遇が受けられるため、便利です。また、源泉所得税に関する各種届出もおこないましょう。例えば、役員や従業員に支給する給与から源泉徴収をおこなうための手続きや、給与支払い事務所の届出などがあります。
地方自治体によっては、法人設立にともなう各種手当や支援制度の申請もおこなえるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
さらに、社会保険や労働保険の加入も重要な手続きの一つ。従業員を雇用する場合、社会保険(健康保険・厚生年金)および労働保険(雇用保険・労災保険)への加入手続きが必要です。社会保険は、従業員の健康や老後の生活を支える重要な制度で、加入しなければなりません。加入手続きは、最寄りの年金事務所や労働基準監督署でおこない、必要書類の提出や手数料の支払いが求められます。これらの手続きは、会社の法的な基盤を整えるもので、スムーズな事業運営のために欠かせません。将来的なトラブルを未然に防ぐためにもしっかりと準備を進めましょう。
不動産事業で合同会社を設立する際の注意点

個人事業主が不動産事業を法人化する際には合同会社が向いていると述べましたが、注意すべき点もあります。そこで本章では、不動産事業で合同会社を設立する際の注意点を2つ解説します。合同会社の設立を考えている方はこれらの点に注意しましょう。
出資者が複数いる場合の対策をしておく
不動産事業で合同会社を設立する際、出資者が複数いる場合には特に注意が必要です。出資者が知人や友人などの場合、経営に対する考え方や方針に相違が生まれるかもしれません。これが対立に発展すると、経営が停滞する危険性が高まります。したがって、出資比率や経営方針に関しては事前に明確に合意しておくことが重要です。例えば、出資比率に基づいて経営権を設定し、各出資者の役割や責任を明確化しておくと、後々のトラブルを防げるでしょう。
また、業務の執行は過半数の同意が必要ですが、社員が2人の場合は意見がわかれた際に過半数を得られず、業務執行ができない事態が発生します。このリスクを避けるため、社員の数を奇数にしておくと効果的です。例えば、3人や5人の社員を設定すれば、意見がわかれた際でも過半数が成立し、スムーズな意思決定が可能でしょう。
さらに、社員の議決権の割合を変更する手法もあります。特定の社員に対して議決権を多く持たせると、意見の対立を未然に防げるでしょう。ただし、このような変更は出資者全員の合意が必要なため、事前の話し合いが欠かせません。こうした対策を講じると、出資者間のトラブルを最小限に抑え、安定した経営を実現できるでしょう。
解散を防ぐための対策を講じておく
社員が1人だけの場合、その社員が亡くなると合同会社は自動的に解散になってしまいます。以下の2つの対策を取り入れると、解散のリスクを低減し、遺族にかかる負担を軽減できます。
複数人の社員を設定する
できれば複数人の社員を設定しましょう。社員が複数いれば、万が一の事態が発生しても、他の社員が存在する限り、合同会社は解散しません。さらに、社員間で役割や責任を分担することで、事業運営に対する柔軟性も向上します。適切な対策を講じると、会社の持続的な発展を支える基盤を築けるでしょう。
死亡時の持分引き継ぎを規定する
社員を複数人設定できない場合には、定款に、「社員が死亡した場合には、退社ではなく相続人に出資持分を引き継ぐ」と明記しておきましょう。これにより、万が一の事態が発生しても、持分が相続人に自動的に承継されるため、会社の継続性が保たれます。相続人に対する権利が明確になることで、遺族も安心して対応でき、事業運営がスムーズです。
不動産事業の合同会社化に関するよくある質問
不動産事業の合同会社化に関するよくある質問をまとめました。
不動産事業を法人化するなら合同会社と株式会社どちらがいい?
不動産事業で法人化する際、小規模や柔軟な経営を求める場合には合同会社が適しているでしょう。合同会社は設立費用や運営コストが低く、意思決定も迅速で柔軟です。一方、株式会社は資金調達や社会的信用で優れていますが、設立費用が高く運営にコストがかかります。不動産業では金融機関のローン審査で個人の信用が重視されるため、合同会社の信用力の低さは問題になりません。
不動産事業で合同会社を設立するタイミングは?
不動産事業で合同会社を設立するタイミングは、税負担が増加した時が最適です。特に課税所得が900万円に達する段階で法人化を検討すると、税率を低く抑えられます。また、売上が1,000万円を超え、消費税の課税対象となる時点で法人化すれば、さらに2年間の消費税免税措置を受けられるため、経済的なメリットがあるでしょう。常に売上や利益の状況を確認し、適切な時期に法人化することが重要です。
不動産事業で合同会社を設立する具体的な手順は?
不動産事業で合同会社を設立するにはまず、会社名と本店所在地を決定し、事業目的を明確にします。次に、定款を作成し押印後、資本金を払い込み、法務局に登記申請をおこないましょう。登記完了後は税務署への法人設立届や青色申告承認申請書を提出し、社会保険や労働保険の加入手続きをおこないます。これらの手続きは、会社運営の基盤を整えるために必要です。
不動産事業で合同会社を設立する際の注意点は?
不動産事業で合同会社を設立する際、出資者が複数人いる場合には、経営方針や出資比率を事前に話し合い、社員の数を奇数にして意見がわかれないよう対策しましょう。また、社員が1人で亡くなった場合の自動解散を防ぐため、定款に相続人への出資持分の引き継ぎを規定する点が重要です。また、複数の社員を設定すると会社の存続を確保し、安定した事業運営を実現できます。
まとめ
不動産事業を法人化する際、合同会社は設立コストが低く、経営の柔軟性も高いため魅力的な選択肢です。設立手順も比較的簡単で、適切な事前準備をおこなえばスムーズに進められます。所得が増え、税金の負担が重くなってきたタイミングや、消費税の課税対象となる場合に法人化を検討するのが賢明でしょう。合同会社のメリットを活かし、事業をより安定した基盤で運営するためにも、本記事の内容を活かしてみてください。

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ