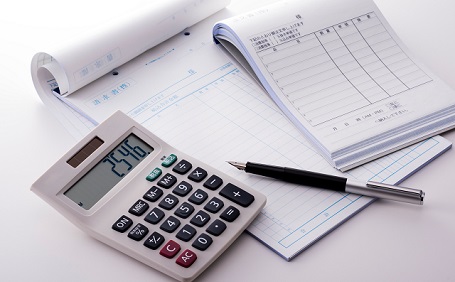賃貸物件を所有する大家さん必見!火災保険に加入しないリスクと選ぶポイントを解説

さらに、火災以外にも、台風や地震などの自然災害による被害や、設備の故障、老朽化にともなう建物の損壊による賠償事故などのリスクも見逃せません。このようなリスクは、賃貸経営の収益を圧迫する可能性があります。
さまざまなリスクに備える手段として、火災保険への加入がとても重要です。火災保険は、建物や収益を守るための基本的なリスク管理対策の一つ。この記事では、賃貸経営に関するリスクの具体例と、火災保険の必要性などを詳しく解説していきます。
記事の目次
大家さんが火災保険に加入しない場合のリスク

賃貸物件のオーナーにとって、火災保険の加入は法律で義務付けられているわけではありません。しかし、火災保険に加入していないことで予期せぬリスクを抱える可能性があります。
建物の火災リスク
建物の火災は賃貸物件を所有するオーナーにとって深刻なリスクです。火災が発生した場合、建物の一部または全体が損傷を受け、修復や再建に多額の費用が必要となる可能性があります。また、火災の発生によって入居者の生活にも支障が出るだけでなく、家賃収入の大幅な減少も考えられるでしょう。
火災の原因には、調理中の火の不始末、電気配線の故障、タバコの不始末などが挙げられます。特に古い建物では、電気やガス設備の老朽化が火災リスクを増大させます。
さらに、木造物件は燃えやすいため、火災が発生すると大規模な被害に発展しやすい傾向も。万が一、故意または重過失が原因で近隣へ延焼した場合には、持ち主から損害賠償請求される可能性もあります。火災リスクに対処するために、火災保険への加入はもちろん、日常的な予防対策が不可欠です。例えば、定期的な消防設備の点検や、入居者への防火に関する注意喚起、火災報知器やスプリンクラーの設置などが効果的です。
自然災害リスク
地震や台風、洪水、落雷などの自然災害は賃貸物件に甚大な被害を及ぼす可能性が高いものです。自然災害は予測することができないため、物件を検討する際には、ハザードマップを確認したり、性能の高い物件を選ぶなど被害を抑えられるよう対策をしましょう。
台風
台風による強風や豪雨は、建物に多大な影響を与え、屋根や窓が破損したり、内部に雨水が侵入したりすることがあります。また、大雨による洪水や土砂崩れは、建物の基礎部分に深刻な損傷をもたらし、賃貸物件が使用不能になるおそれもあるでしょう。
例えば、2019年の台風19号(令和元年東日本台風)は、過去最強クラスの台風として記録され、広範囲にわたり甚大な被害を与えました。この台風では、洪水や土砂崩れによって多数の住宅が損壊し、多くのオーナーが被害に遭っています。
台風のリスクを軽減するためには、事前の防災対策が重要です。具体的には、屋根や窓の強化、排水設備の整備、ハザードマップを活用した危険地域の把握などが効果的です。定期的な点検をおこない、自然災害への備えを万全にすることで、被害を最小限に抑えられるでしょう。
地震
地震は、日本で頻繁に発生する自然災害の一つであり、賃貸物件のオーナーにとっても大きなリスクです。地震による建物の倒壊や損傷は、入居者の生活に深刻な影響を与えるだけでなく、修復費用や収入減少などの経済的損失も招きます。例えば、2011年の東日本大震災では、多くの賃貸物件が倒壊し、オーナーは莫大な損害を受けました。
建物が大きな損傷を受けると、ガス管や水道管の破裂、電気設備の故障などが引き起こされます。修復には時間と費用がかかり、その間の家賃収入が途絶える可能性も。特に建物全体が利用不能になるケースでは、オーナーの収入源が完全に断たれることになります。
地震リスクを軽減するためには、耐震工事の実施や、地震保険への加入が重要です。また、災害時の避難経路を整備したり、設備点検を定期的におこなうことも有効でしょう。
入居者の不注意が引き起こす損害リスク
賃貸経営をおこなううえで、入居者の不注意による火災や水漏れは、オーナーにとって深刻な問題です。例えば、タバコの火の不始末が原因で発生した火災では、その損害を最終的にオーナーが負担しなければならない場合があります。
入居者が引き起こすリスクに対しても、火災保険に加入していれば、入居者の過失による損害も補償の対象となるため、オーナーは安心して経営を続けられます。また、火災だけでなく、入居者が原因で発生した水漏れ事故にも、多くの火災保険は対応してくれるため、安心でしょう。
上記のように、入居者由来のリスクを補う火災保険は、オーナーにとって欠かせない存在です。
共有部分で発生する盗難や破損のリスク
賃貸物件の共有スペースで発生する盗難や破損も、オーナーが事前に備えておくべきリスクの一つ。エントランスや廊下、駐輪場などの共有部分は、入居者や外部の訪問者が利用するため、管理が難しいエリアです。
特に、防犯カメラや照明設備などの高価な装置が盗まれたり、故意に破損させられたりした場合、修理や交換にかかる費用は無視できません。しかし、火災保険には共有部分に関する被害も補償する内容が含まれているケースが多く、予想外の出費を抑えられる可能性があります。
共有部分のリスクまでもカバーできる火災保険は、賃貸物件の管理をスムーズにおこなうための心強い味方となるでしょう。
大家さんの賠償リスク
賃貸物件を所有するオーナーには、賠償責任を負うリスクもあります。これは、建物や設備の不備による事故や、老朽化した設備の故障が原因となって発生するものです。
例えば、階段の手すりが壊れていて入居者が転倒した場合や、給湯器の不具合で火災が発生した場合などが挙げられます。さらに、給排水管の老朽化による漏水事故も大きな問題の一つ。例えば、老朽化した排水管が破裂し、下階の住居が浸水被害に遭った場合、オーナーが賠償責任を負う可能性があります。
上記のような事故は、マンションなどの集合住宅で特に発生しやすく、被害が広範囲に及ぶことも少なくありません。
こうしたリスクに備えるためには、定期的な設備点検や修繕を怠らないことが重要です。また、賠償責任保険に加入しておくことで、万が一の場合の損害をカバーできます。事前に対策を取ることで、賠償リスクを大幅に軽減できるでしょう。
大家さんが保険で優先すべき補償内容

これまで、火災保険に加入しないことによる、さまざまなリスクを解説しました。本章では、オーナーが保険でどのような補償内容を検討すべきなのかを詳しく解説します。
火災補償
火災補償は、建物が火災によって損害を受けた場合に補償してくれるものです。火災が発生すると、建物全体を焼失する可能性があり、その修復には多額の費用がかかります。また、火災が原因で入居者が退去するケースでは、家賃収入面での損失も発生するでしょう。そのため、火災保険に「家賃補償特約」を追加することで、修復費用や収入減少リスクを軽減できます。
風災補償
風災補償は、強風や台風から建物を守る保険です。例えば、強風で屋根が飛ばされたり、飛来物によって窓ガラスが割れたりするケースがあるでしょう。このような場合の修理費用を補償する保険が風災補償です。また、ひょう災や雪災による建物の損傷もカバーされます。特に沿岸部や風の強い地域に賃貸物件を所有している場合には、風災補償は欠かせません。
水災補償
水災補償は、洪水や土砂災害の被害に備える補償です。河川近くや低地に位置する物件では、浸水による損害リスクが高まるため、水災補償が不可欠に。例えば、大雨で河川が氾濫し、建物が浸水した場合の修理費用をカバーしてくれます。また、保険を選ぶ際には、物件のリスクを事前にハザードマップで確認し、水災リスクの高いエリアに対応した補償内容を選ぶことが大切です。
地震保険
地震による建物の倒壊や損傷を補償する地震保険は、地震の多い日本では賃貸物件を経営するうえで欠かせないものです。例えば、地震で基礎部分を損傷した場合、その修復費用が補償対象となります。また、地震保険では被害の程度に応じた保険金が支払われます。木造や鉄筋コンクリートでは、損害の範囲や建物の沈下・傾斜に応じた支払い基準が適用されるので、以下の表をチェックしておきましょう。
| 損害の程度 | 建物の被害程度 | 支払保険金 |
|---|---|---|
| 全損 |
・基礎や外壁などの損害額の時価額に対する割合が50%以上
・焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の70%以上
|
保険金額の100% |
| 大半損 |
・基礎や外壁などの損害額の時価額に対する割合が40%以上50%未満
・焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の50%以上70%未満
|
保険金額の60% |
| 小半損 |
・基礎や外壁などの損害額の時価額に対する割合が20%以上40%未満
・焼失・流失した部分の床面積が建物の延床面積の20%以上50%未満
|
保険金額の30% |
| 一部損 |
・基礎や外壁などの損害額の時価額に対する割合が3%以上20%未満
・全損、大半損、小半損にいたらない建物が床上浸水または地盤面から45cmを超える浸水を受けた場合
|
保険金額の5% |
被害が大きい場合ほど補償額も増加するため、リスクに見合った保険選びが重要です。
賠償責任保険
賠償責任保険はオーナーの責任リスクをカバーする保険です。賃貸経営には、入居者や第三者に対する賠償責任リスクがともないます。このリスクに対応する保険が「施設賠償責任保険(または建物管理賠償責任保険)です。
例えば、老朽化した給排水管の破損が原因で漏水事故が発生し、下階の入居者の家財に被害を与えた場合。オーナーが賠償責任を負うことになります。賠償責任保険を契約しておけば、修理費用や賠償金の負担を軽減できます。
なお、施設賠償責任保険は個人賠償責任保険とは異なり、家賃収入を得る目的の建物には適用されない場合も。そのため、しっかり補償を得るためにも賃貸物件専用の賠償責任保険を選びましょう。
また、一部の保険では示談交渉サービスを提供していないため、保険代理店や保険会社に相談し、示談交渉付きのプランを検討することをおすすめします。
火災保険の種類によっては、施設賠償責任を特約に入れることも可能です。「建物管理賠償責任特約」という名称が使われていることも。賃貸経営をするうえで火災保険が対応できるリスクはどの範囲か、また補償に不足がある場合は、どの保険を別途契約するのか、事前に内容を確認しましょう。
大家さんが火災保険で後悔しないためのポイント
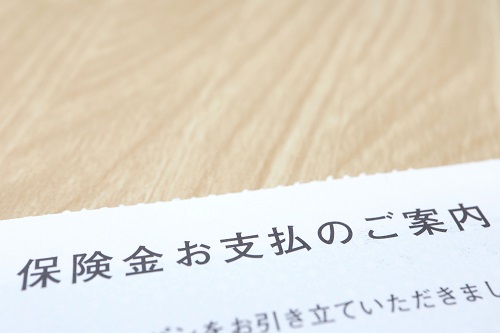
火災保険を選ぶ際には、賃貸経営特有のリスクをしっかりと補償できる内容を選ぶことが大切です。以下のポイントを参考に、自身の状況に合わせた火災保険を選びましょう。
立地や災害リスクを確認する
オーナーが賃貸物件を所有する際は、物件のリスクを正しく把握しておかなければなりません。特に、物件の所在地や老朽化の進行状況によってリスクの大きさは異なります。
主なリスク例と影響
| 対応しなければ ならないリスク |
具体例 |
|---|---|
| 火災リスク | 建物が火災で損壊し、多額の修理費が発生する可能性がある |
| 自然災害リスク | 地震や台風、洪水、落雷などで建物が損壊した場合の補償が必要 |
| 入居者の不注意 リスク |
タバコの不始末や家電の過熱などで火災が起きるリスクがある |
| 共有部分の盗難・ 破損リスク |
エントランスや廊下の破損や設備の盗難が発生した場合の修理費用が必要になる |
| 家賃収入がなくなる リスク |
建物損害により家賃収入が一時的に途絶えるリスクがある |
| 室内での死亡事故 リスク |
孤独死や自殺などの発生で清掃費用や家賃損失が発生する可能性がある |
物件特有のリスクをリスト化し、それを補償できる保険商品を選ぶことが、安心経営への第一歩です。
必要な補償を持つ火災保険を選ぶ
所有する賃貸物件が抱えるリスクに対して、それぞれ対応できる火災保険や特約を選びましょう。
リスクと対応する保険内容の例
| リスク | 対応可能な補償・特約 |
|---|---|
| 火災 | 火災保険の基本補償 |
| 自然災害 | 火災保険の基本補償 ※風・雪・ひょうは風災補償の場合あり
※ただし地震・津波に関しては、別途「地震保険」の加入が必要
|
| 共有部分の盗難・ 破損 |
共有部分損害補償 |
| 家賃収入がなくなる | 家賃収入特約 |
| 入居者の不注意 | 借家人賠償責任補償特約 |
| 室内での死亡事故 | 家主費用特約 |
上記の特約を備えた火災保険を選ぶことで、予期せぬトラブルにも安心して対応できます。保険内容をしっかりと確認し、賃貸経営をサポートしてくれる保険を選びましょう。特約については、次章で詳しく解説します。
複数社を比較する
火災保険を選ぶ際には1社のみで決めず、複数社を比較することが大切です。それぞれの保険会社が提供する補償内容や保険料は異なるため、最適な選択をするためには相見積もりが必要です。また、特約内容やサポート体制もチェックしましょう。
比較時のチェックポイント
-
補償内容
自分のニーズに最適な特約や補償が含まれているか。 -
保険料
補償内容に対して、費用が妥当であるかを比較する。 -
サポート体制
24時間対応のコールセンターや迅速な対応力があるか。
口コミや評判も参考にしながら、後悔のない保険選びをおこないましょう。
適切な保険金額かを確認する
火災保険の保険金額を設定する際には、物件の価値や修繕費を考慮し、保険料とのバランスを取ることが必要です。保険金額が高すぎると保険料が経営の負担となり、低すぎると補償が不十分なことも。適切な保険金額を設定し、万が一の際に補償を受けられるようにしましょう。
また、保険金請求の流れや支払い条件も事前に確認しておくことが大切です。請求手続きが複雑な保険会社は、いざという時に迅速な対応が難しくなることがあります。スムーズに補償を受けられる保険を選ぶことで、予期せぬトラブルにも迅速に備えられるでしょう。
契約内容を定期的に見直す
契約後も定期的に契約内容の見直しをおこない、変化するリスクに対応できる内容にアップデートすることで、安心して経営を続けられるでしょう。
大家さんにおすすめの特約

これまで、賃貸物件の管理で優先的に検討したい火災保険の基本的な補償内容などを説明しました。しかし、賃貸経営には、火災や自然災害以外にもさまざまなリスクが存在します。ここからは、オーナーにおすすめの特約をご紹介します。
家賃補償特約
火災や自然災害によって賃貸物件が使用できなくなった場合、その期間中に得られなくなる家賃収入を補償する特約が家賃補償特約です。家賃補償特約を付けておくことで、例えば火災による修理期間中、通常受け取れるはずの家賃が保険から補填されます。
多くの保険会社では、最長12カ月間までの家賃損失をカバーしており、オーナーの収益を長期間にわたって守ることが可能に。火災だけでなく、台風や水災などの自然災害による修復中の家賃減少にも対応してくれるため、賃貸物件のオーナーにとって心強い補償です。
家主費用特約
日本では高齢化が進み、65歳以上の一人暮らしが増加しています。このような状況下で問題となっているのが、入居者が賃貸住宅内で孤独死するケースです。孤独死が発生すると、その後の入居者探しが難航し、家賃収入が減少するリスクが高まります。
また、発見の遅れにより室内が損傷することもあり、復旧には高額な費用がかかることも。
さらに、孤独死だけでなく、自殺や犯罪死が賃貸物件内で発生した場合も、同様に家主に大きな負担がのしかかります。家主費用特約は、上記のリスクに備えるための特約で、家賃の損失や原状回復費用、遺品整理費用などを補償してくれるものです。
特に昨今の社会問題を考慮すると、この特約は多くのオーナーにとって欠かせない存在となっています。
火災保険の見直しをする最適なタイミング

2024年10月に実施された火災保険料の改定では、全国平均で「参考純率」が13%引き上げられ、過去最大の値上げとなりました。参考純率とは、料率算出団体が算出する純保険料率のこと。物件の構造や所在地などによるリスクの差異に応じた区分が設けられており、建物や地域によって保険料率が異なります。さらに、今回の改定による保険料の引き上げ率は保険会社によってもさまざま。そのため、現在の保険を見直すことで、場合によっては保険料を削減できる可能性があります。
特に満期が近づいている方は、この機会にあらためて保険内容を確認し、他社との比較や見積もりをおこなうこともおすすめします。
まとめ
賃貸経営には、火災や自然災害、設備の老朽化など、多様なリスクがともないます。特に火災は建物そのものの損害だけでなく、修理期間中の家賃収入減少などの大きな経済的損失をもたらします。また、地震や台風による被害、給排水設備の故障なども、賃貸物件のオーナーが考慮すべきリスクです。
上記のリスクを軽減するためには、基本的な火災保険に加えて、家賃補償特約や賠償責任保険などを適切に活用することが重要なポイント。保険内容の見直しや特約の追加をおこない、想定外の事態に備えることで、賃貸経営の安心感を高められるでしょう。自分にあった保険選びで、リスクを最小限に抑え、安定した収益を確保しましょう。

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ