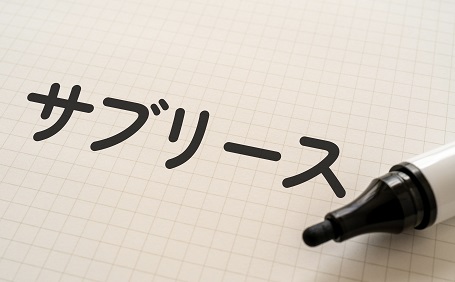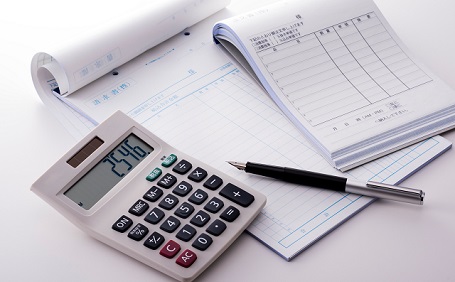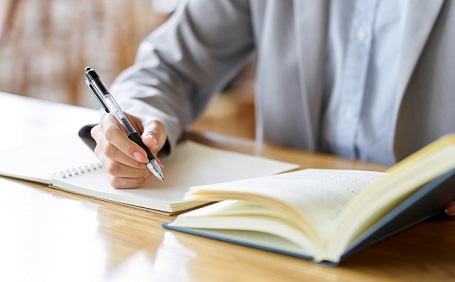不動産管理会社を設立するとどうなる?メリットやデメリットと注意点から判断基準を解説

そこで本記事では、不動産管理会社とは何かを説明し、その設立方法や注意点、メリット・デメリットを解説します。不動産管理会社設立を検討している方は、スムーズに設立を進められるよう参考にしてみてください。
記事の目次
不動産管理会社とは?

不動産管理会社とは、不動産の所有者に代わって、物件の運営や維持管理をおこなう専門の企業を指します。不動産管理会社の業務は、入居者の募集や契約手続き、家賃の徴収、物件のメンテナンス、クレーム対応、退去時の手続きなどです。不動産管理会社を設立すると、個人投資家はコスト削減や運営の効率化、税務上のメリットを教授できるでしょう。なお、不動産管理会社はその性質で大きく3種類に分類できます。
不動産保有方式
不動産保有方式は、管理会社が自ら不動産を保有する仕組みです。建物のみを所有するパターンと、建物と土地の双方を一括して所有するパターンがあります。特に建物と土地をどちらも所有する場合、所有者が同一になるため、税務上のリスクが抑えられるでしょう。
この方式では、家賃や敷金、礼金などの収益がすべて管理会社に帰属し、他の保有方式と比較しても、所得移転効果が大きい点がメリットになります。また、管理会社の株式を家族が所有して、相続時に税金の軽減が見込める点もこの方式の利点です。しかし、直接不動産を保有するがゆえに、管理料に関する紛争が生じやすくなるかもしれません。利点と欠点を慎重に判断する必要があります。
管理委託方式
管理委託方式とは、不動産の所有者から管理会社に管理業務を受託し、管理料を得る方法です。この場合、不動産所有者は委託先の管理会社に対して管理料を支払います。管理会社に役員や社員をおき、管理業務の対価として、給与を支払います。この方式では、直接不動産を所有する場合には受けられない給与所得控除を利用できる点が特徴になるでしょう。
また、不動産経営を家族でおこなう場合、給与の配分を通じて所得を分散させられるため、所得税の負担を軽減できる利点があります。しかし、不動産の規模が一定以上でないと、この方法で会社を成立させられない欠点も。管理委託方式の管理会社の収入源は管理料に依存しており、通常、管理料の相場は賃料全体の3~8%程度です。この割合を超える管理料を徴収すると、税務署から疑問視されるかもしれません。
この方式は、適切に運用すれば税務上のメリットを享受できる反面、不動産の規模や管理料の設定に対する慎重な対応が求められます。
サブリース方式
サブリース方式とは、不動産所有者が保有する物件を管理会社が一括して借り上げ、その物件を第三者の入居者に転貸借(又貸し)する仕組みです。サブリースは、所有者に代わって管理会社が物件を運営する点で管理委託方式と似ていますが、大きな違いは、管理会社が物件全体を一括で借り上げることにあります。この方式では、所有者は管理会社から一定の賃料を受け取れます。
一方注意点として、物件に空室が増えると、管理会社が赤字になるリスクが高まり、その結果、所有者に支払われる賃料が減額される場合がある点です。また、契約内容や賃料の設定次第では、管理会社が予想していた収益を得られないかもしれません。加えて、サブリース方式では、長期的な賃料の引き下げや契約解除に関するトラブルが発生するケースもあるため、契約の締結には慎重な検討が必要です。なお、サブリース方式の管理料相場は家賃収入の10~20%程度が目安になります。
不動産管理会社を設立するメリットは?

不動産管理会社の概要はわかりましたが、あえて会社を設立させるとどのような点がよいのでしょうか。そこで本章では、不動産管理会社を設立するメリットを解説します。
所得税を軽減できる
不動産管理会社を設立するメリットの一つは、所得税の軽減です。個人事業主としての収入は、累進課税制度により所得が増えるにつれて税率が高くなります。例えば、所得が高くなると、税率が30%や40%に達する場合も珍しくありません。この制度は、高所得者にとって負担が大きくなりがちです。
しかし、法人化すると、適用される法人税は一定の税率で計算されます。法人税率は23.2%なので、個人の累進課税よりも有利な税率になるかもしれません。そのため、法人設立によって、所得税の負担を大幅に減らし、結果的に税金の節約ができる可能性があります。
経費計上ができる
経費計上の幅が広がることも、不動産管理会社を設立するメリットの一つです。個人事業主の場合、経費として認められる項目は限られており、プライベートとビジネスの区別が難しい経費は計上できません。一方、法人化すると、事業に関連するさまざまな費用を経費として計上できるようになります。例えば、社員や役員の出張費、接待費、事務所の賃貸料、光熱費などが経費になるでしょう。
また、法人が所有する車両の維持費やガソリン代も経費として計上できますが、個人事業主の場合、事業とプライベートの使用割合に応じた分しか経費として認められない場合が一般的。さらに、法人化すると、福利厚生費や社員教育費も経費として計上できます。例えば、社員旅行や研修費用などは法人なら全額経費で処理できるため、業務の一環で支出が認められますが、個人事業主ではその全額を経費計上することは認められません。
このように、法人化すると認められる経費の範囲が広がり、事業運営にともなう多くの費用を税務上で適切に処理できます。結果、法人化で経費の計上を通じて税負担を軽減できるようになり、経済的なメリットとなるでしょう。
給与所得控除を適用できる
給与所得控除を適用できる点もメリットになります。給与所得控除とは、給与所得者が収入に応じて一定額を控除できる制度。この制度を利用すると、個人が給与を受け取る際に実際の収入から一定額が控除されるため、課税対象となる所得が減少し、税負担の軽減が期待できます。
また、給与所得控除を活用すると、役員報酬として支給される給与に対して個人としての税負担を軽減できる一方で、法人は経費としてその給与を計上できるため、法人全体の税負担も減少します。
相続税を減らせる相続財産の生前贈与が容易になる
不動産管理会社の設立には、相続税を減らすメリットもあります。具体的には、不動産を個人名義ではなく法人名義で保有する方法で、相続税の軽減が可能です。
個人が不動産を所有している場合、その資産は相続の対象となり、相続税の課税は避けられません。一方、法人が不動産を所有する場合、相続税の対象は法人の株式で、法人の株式評価額は個人の資産評価額とは異なります。一般的に、法人の株式の評価は低くなる傾向があり、これにより相続税の負担を抑えることができるでしょう。
また、法人設立後には法人名義で不動産を保有し、法人の役員として給与を受け取る形にすると、相続税対策だけでなく、経費計上や税負担の軽減も実現できます。法人が所有する不動産の相続時には、法人の株式の評価に基づいて税金が計算されるため、個人で直接保有するよりも税負担を軽減できる可能性が高いです。このように、不動産管理会社を設立すると、相続税対策の一環になります。
配偶者や子どもなどに所得を分散できる
不動産管理会社の設立は、配偶者や子どもなどに所得を分散できるメリットもあります。具体的には、法人を通じて家族を役員や従業員として登用し、給与や報酬を支払う方法で、所得の分散ができるでしょう。
例えば、法人設立後、配偶者や子どもを役員や従業員として雇用すれば、役員報酬や給与を支給可能です。この場合、支給された給与や報酬は個々の所得として処理されるため、家族全員の所得を分散できます。そうすると、所得税の課税対象額を分散させ、全体の税負担を軽減できるでしょう。
また、役員報酬や給与は一定の範囲内で調整可能であり、家族の個々の所得税率や控除を考慮して適切な額を設定すると、税負担を最適化できます。そうすれば、高額な所得を一人に集中させるのではなく、複数の家族に分散させ、税負担の効率的な管理が可能です。
不動産の売却損が損益通算できる
不動産の売却損を損益通算できる点もメリットです。まず、法人が保有する不動産を売却して損失が発生した場合、その損失は法人の会計上の損失として計上されます。法人税法では、事業所得や不動産所得など、法人のすべての所得を総合的に計算するため、売却損は法人全体の利益と相殺できるでしょう。
つまり、売却損が他の事業の利益や不動産から得られる収益と相殺されると、課税所得が減少し、結果として法人税の負担が軽減されます。また、法人が不動産を売却して得た損失は、翌年度以降の所得と通算も可能です。これにより、売却損を複数年度にわたって損益通算して、税負担の平準化を図れるでしょう。
なお、個人が不動産を売却して発生した損失は、一定の条件下でしか損益通算できません。そのため、法人としての運営のほうが損益通算の幅が広く、法人設立後に不動産売却をおこなうと、損失を最大限に活用し、税負担の軽減を図れます。
不動産管理会社を設立するデメリットは?

不動産管理会社を設立すると、さまざまなメリットがあることを解説しました。しかし、だからといってかならずしも法人化がよいとは限りません。法人化はどのようなデメリットがあるかを解説していきます。
会社設立にコストがかかる
不動産管理会社を設立する際のデメリットは、設立にコストがかかることです。具体的な内容は以下です。
-
登録免許税
株式会社の場合、最低15万円。合同会社の場合は6万円。 -
定款(ていかん)認証費用
定款を公証人に認証してもらうための費用として、約5万円(合同会社の場合は不要)。 -
司法書士への報酬
設立手続きを司法書士に依頼する場合、報酬として約5万~10万円。
以上のように、不動産管理会社を設立するには、さまざまなコストがかかり、初期投資が必要です。また、株式会社や合同会社など、会社形態に応じて法人設立費用が発生します。もし、オフィスを構えたり、備品を用意したり、人を雇う場合にはさらに費用がかかるでしょう。
赤字でも税金は必要になる
たとえ赤字であっても税金がかかる点も、法人設立のデメリットです。個人事業主の場合は会社の利益が出ていなければ、税金を免除される場合もありますが、法人は免除されないため、注意しましょう。
法人化すると法人住民税を支払う必要があります。これは利益の有無に関わらず、都道府県や市町村に支払わなければなりません。法人住民税は「均等割」と呼ばれる部分があり、資本金や従業員数に応じて課税されます。例えば、資本金が1,000万円以下で従業員数が50人以下の場合、最低でも年額7万円程度の法人住民税が必要です。これが資本金や従業員数の増加にともない、さらに高額になる場合もあるので把握しておきましょう。このように、不動産管理会社を設立すると、たとえ赤字でも、必ず支払わなければならない税金が発生します。
法人化すると増える費用がある
不動産管理会社を法人化すると、個人事業主として運営する場合に比べて、増える費用がいくつかあります。これらの費用は、会社運営で無視できない負担となるため、設立前に十分に理解しておきましょう。
支払いが増える費用の一つが、税理士への報酬料です。法人化すると、税務申告が複雑になるため、税理士への依頼が欠かせません。個人事業主の場合、比較的簡単な青色申告で済みますが、法人の場合は決算書の作成や法人税、消費税の申告が必要となり、そのための税理士への報酬料が発生します。通常、報酬料は年間で20万~50万円程度が相場ですが、事業規模が大きくなるとさらに増加する可能性があるので、十分な資金計画を立てておきましょう。
不動産管理会社を設立する手順は?

不動産管理会社のメリット・デメリットが理解できたところで、実際に不動産管理会社を設立したいと思ったら、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。そこで本章では、不動産管理会社の設立方法を紹介していきます。
- STEP 1重要事項を決定する
- STEP 2印鑑を作成する
- STEP 3定款を作成する
- STEP 4設立費用を準備する
- STEP 5書類を準備する
- STEP 6会社の登記をおこなう
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP 1. 重要事項を決定する
まず始めることは、会社設立に必要な重要事項の決定です。ここで決める重要事項とは、会社名、事業目的、役員構成、資本金の額、設立日などが含まれます。また、会社の住所や株主の構成も事前に決めておきましょう。これらの要素は、あとの手続きに不可欠な情報となるため、慎重に検討してください。
STEP 2. 印鑑を作成する
次に、会社の印鑑を作成します。会社の実印、銀行印、角印(社印)など、いくつか印鑑を準備しましょう。これらの印鑑は、会社設立の際に必要な書類に押印するため、早めに準備することをおすすめします。また、登記手続きでも印鑑は必要になるので、事前に印鑑証明書を取得しておきましょう。
STEP 3. 定款を作成する
定款は、会社の基本的な運営ルールを定めた書類です。ここには、会社の目的、組織、株式に関する事項、役員の任期などが記載されます。定款は紙ベースでも電子定款でも作成できますが、電子定款は印紙代が不要になり、費用の節約にもなるため、活用しましょう。定款は公証役場で認証を受ける必要があり、その際に会社の印鑑も使用します。
STEP 4. 設立費用を準備する
会社設立にはさまざまな費用がかかりますが、定款認証の際の手数料や、登記の際に必要な登録免許税が主な費用です。電子定款を使用すると印紙代が節約できますが、それ以外にも資本金の額に応じた登録免許税や、公証役場での認証手数料などが発生します。事前に費用を把握して、必要な資金を準備しておきましょう。
STEP 5. 書類を準備する
次に、必要な書類を準備します。具体的には、定款の他に発起人や役員の同意書、就任承諾書、印鑑証明書、資本金の払込証明書などです。これらの書類は、法務局での登記手続きの際に欠かせません。特に、発起人や役員の印鑑証明書は重要な書類なので、事前に取得しておくとスムーズに進められます。
STEP 6. 会社の登記をおこなう
最後に、会社の登記手続きを法務局でおこないます。登記が完了すると、会社は正式に法人として成立します。登記の際に必要な書類や印鑑を持参し、提出しなければなりません。登記手続きには数日かかりますが、これが完了すれば不動産管理会社としての活動を開始できます。
不動産管理会社を設立する時の注意点は?

不動産管理会社を設立すれば、すべてうまくいくとは限りません。会社を設立する前に、確認すべき事項があります。本章では、不動産管理会社を設立する前に理解しておくとよい注意点を解説します。
利益が少ないと法人化しても節税の効果が発揮できない
節税目的で不動産管理会社を設立する際に注意すべき点は、「利益の金額」です。法人化すれば、個人の所得税よりも法人税のほうが税率が低くなる場合がありますが、一定以上の利益が出ていないと、かえって手続きや経費が増えるため節税効果を実感できません。一般的には、課税所得が900万円以上でないと法人化しても大きな節税効果は得られにくいです。
個人の累進課税では、課税所得が330万円以上から税率が20%、695万円以上では23%に上がります。法人税は800万円以下の部分は19%、800万円を超えた部分は23.2%です。一見、課税所得が330万円を超える段階で法人化すれば、税率が低くなるため節税効果が期待できそうです。しかし、法人化には設立費用や毎年の法人維持費用がかかり、これらのコストが節税効果を打ち消す可能性があります。
例えば、法人化には登録免許税や登記費用、税理士などの専門家への依頼費が発生し、さらに法人住民税や社会保険の負担が増加します。これらの費用を考慮すると、利益が少ない場合には法人化してもかえって負担が増える可能性があり、節税効果を十分に感じられないことがあります。一般的には、課税所得が900万円を超えた段階で法人化の検討が勧められており、それ以下の収入ではメリットが薄くなるため、慎重な判断が必要です。
出資者(株主)と社長の決め方に注意する
不動産管理会社を設立する際には、出資者(株主)と社長の決め方に注意が必要です。基本的に、出資者と社長は同一でも別々の人物でも構いません。理想は出資者や社長をオーナー自身ではなく、その家族、特に次世代の子にするとよいでしょう。これは、不動産事業が安定した家賃収入を得やすく、黒字になりやすいため、法人の株価が増加する傾向にあるからです。
もし個人オーナーを法人の出資者にすると、その株式は将来的に相続財産になり、相続税の負担が増す可能性があります。これを避けるために、出資者をオーナー以外の家族にしておくとよいでしょう。さらに、複数の子がいる場合は、将来的な承継者は一人に絞っておくようにします。これは意見の対立が生じた場合、経営方針の調整が難しくなるリスクを避けるためです。まだ承継者が決まっていない場合は、設立時はオーナーが株主となり、適切なタイミングで贈与していく方法も選択肢になるでしょう。
役員報酬の金額に注意する
不動産管理会社を設立する際は、役員給与の設定にも注意が必要です。法人設立後、役員報酬は毎期の決算終了から3カ月以内に決定しなければなりません。この役員報酬は、会社の利益や税金に直接影響を与えるため、慎重に設定しましょう。なぜなら、決算間際に利益が予想以上に出て、役員報酬を急に増額させた時、その増額部分は税務上、経費として認められないためです。そうなると、想定よりも会社の利益が多くなり、その分税金の負担も増えるため、報酬額は適切に設定しておかなければなりません。
もし、役員報酬の額が高すぎると、会社のキャッシュフローに悪影響を与え、支払いが困難になるリスクも。一方で、報酬が少なすぎると、会社の利益が増えすぎ、結果的に税負担に困るかもしれません。また、役員に対するボーナスは、税務上経費として認められないため、業績が良くてもボーナスとして利益を分配できないので注意が必要です。これらの点を踏まえて、役員報酬の設定は会社の経営計画に基づいて適切におこない、税務面でのリスクを最小限に抑えるようにしましょう。
不動産管理会社の設立に関するよくある質問
不動産管理会社の設立に関するよくある質問をまとめました。
不動産管理会社とは?
不動産管理会社とは、不動産所有者に代わり、物件の運営や維持管理をおこなう専門企業です。業務内容は、入居者募集、家賃徴収、物件メンテナンス、退去手続きなど。不動産管理会社は、次の3つあります。
- 自ら物件を所有する「不動産保有方式」
- 管理業務を受託する「管理委託方式」
- 物件を一括借り上げて転貸する「サブリース方式」
不動産管理会社の設立により、オーナーは税務上のメリットや安定収入を得られる可能性がありますが、それぞれの方式にはリスクもともなうため、どの方式にするのか慎重に選択しなければなりません。
不動産管理会社を設立するメリットは?
不動産管理会社を設立すると、所得税の軽減や経費計上の幅が広がるなどのメリットが得られます。個人事業主としての収入は累進課税の対象となり、所得が増えるほど税率が高くなりますが、法人税は一定の税率で課税され、税負担が抑えられるでしょう。また、法人化により事業に関連する多様な費用を経費として計上できます。例えば家族を役員や従業員にすると所得が分散でき、税効率を高められます。相続税の軽減や損益通算も法人化のメリットです。
不動産管理会社を設立するデメリットは?
不動産管理会社を設立するデメリットは、いくつかの費用負担が増える点にあります。まず、会社設立には初期費用がかかり、登録免許税や定款認証費用などのコストが発生するでしょう。また、赤字でも法人住民税などの税金は必ず支払う必要があり、個人事業主に比べて負担が増えることがあります。さらに、法人化によって税務が複雑化するため、税理士への報酬料などの運営コストがかさむ可能性が高く、長期的な資金計画が必要です。
不動産管理会社を設立する際の手順は?
不動産管理会社を設立するには、まず会社名や資本金、役員構成などの重要事項を決定します。次に、会社の印鑑を作成し、定款を作成して公証役場で認証を受けましょう。そのあと、設立費用を準備し、必要書類(定款、同意書、印鑑証明書など)を整えます。最後に、法務局で登記手続きをおこないましょう。登記が完了すれば、正式に法人となって活動を開始できます。
不動産管理会社を設立する際の注意点は?
不動産管理会社を設立する際は、以下の点に注意しましょう。まず、利益が少ない場合、法人化による節税効果が薄く、設立や維持費用がかえって負担になる可能性があります。次に、出資者や社長の決定を慎重に。個人オーナーが出資者になると相続税の負担が増す可能性があるので、出資は家族に任せるようにしましょう。さらに、役員報酬の設定も重要です。報酬額が高すぎるとキャッシュフローに影響し、低すぎると税負担が増える可能性があります。適切な設定を心がけ、経営計画と税務リスクをよく考慮するようにしましょう。
まとめ
本記事では、不動産管理会社の基本的な説明や、設立の手順、メリット・デメリット、そして設立時の注意点まで幅広く解説をしました。特に、設立前にメリットやデメリット、注意点を十分に理解しておけば、設立後の失敗を防げるでしょう。この記事が、不動産管理会社設立に際しての計画や準備を進める際に役立ち、より効率的に法人化を実現する基盤となるよう願っています。

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ