家賃収入の消費税対策は?知っておくべき課税基準と節税方法

本記事では、家賃収入にかかる消費税の基本的な仕組みから、効果的な節税対策までをわかりやすく解説します。家賃収入を得ている方や、これから不動産投資を始めようとしている方は、ぜひ参考にしてください。
記事の目次
居住用物件に消費税はかかる?
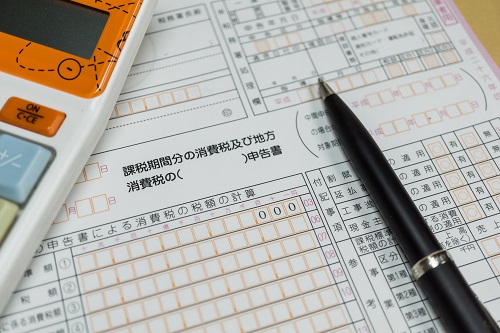
居住用物件の家賃収入や礼金、管理費・共益費などは、基本的に消費税がかかりません。ただし、非課税となるためには、特定の条件を満たす必要があります。
家賃収入の消費税がかからない3つの条件
賃貸借契約書では投資物件が住居として使用される場合、消費税はかかりません。しかし、事業用として契約された場合には、消費税が課税されるため、注意が必要です。
家賃収入を非課税とするための条件は、以下の3つです。
- 賃貸期間が1カ月以上であること
- 契約書に居住用と明記されていること
- 賃貸借契約書がない場合でも、居住の実態があること
例えば、契約書に居住用と記載されていても、賃貸期間が1カ月未満であれば、消費税が課せられます。また、ホテルやウィークリーマンションは賃貸期間が1カ月以上でも消費税の対象です。
会社が社宅として賃貸契約をおこなっている場合でも、契約に「従業員が居住する」と記載されていれば居住用物件となり、消費税は課税されません。さらに、2020年度の消費税法改正により、賃貸借契約書がない場合でも、実態として居住用であれば非課税となります。
礼金・更新料における消費税
オーナーが受け取る居住用の礼金や更新料も、家賃収入と同じように消費税はかかりません。敷金も、一般的な修繕費を差し引く形であれば、預かり金扱いとなり、消費税は課されません。
一方で、礼金は入居者に返還されないものですが、居住用物件であれば非課税です。ただし、事業用物件の場合は消費税が課されるため、注意してください。
管理費や共益費における消費税
居住用物件の管理費や共益費も、消費税はかかりません。これらは居住するために必要な費用であり、家賃収入と同じ扱いです。
家賃や共益費に水道光熱費が含まれている場合も、消費税はかかりませんが、家賃と別に請求する場合には消費税が課されるため、注意が必要です。
事業用物件の場合
事業用として賃貸している物件には、原則として消費税がかかります。では、住居と事務所が併用されている場合はどうでしょうか。
この場合、住居部分と事務所部分が明確に区分されます。独立して使用可能な場合、事務所として利用される部分のみが課税対象となります。一方、主に住居として使用され、一部が店舗や事務所としても利用されている場合は、基本的に住居扱いとなり、消費税は発生しません。
住居用として判断される基準
では、どのような基準で主に住居として使用していると判断されるのでしょうか。
まず、賃貸借契約書に「居住用」と明記されている場合は、居住用とみなされます。さらに、2020年4月からの消費税法改正により、契約書が存在しない場合や賃貸目的が不明確な場合でも、実際の居住実態が確認できれば、居住用として扱われることになりました。
上記のように、消費税の課税判断では、賃貸借契約書の記載内容が重要な役割を果たします。契約書が存在しない場合は、実際の居住状況に基づいて判断がおこなわれます。
課税売上高が1,000万円以下の場合
ただし、基準期間での課税売上高が1,000万円以下の場合、免税事業者として扱われ、事業用物件であっても消費税の納税が免除される可能性が高いでしょう。この基準期間は、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売上高を指します。
つまり、個人事業主も法人も、事業開始後の1期目と2期目は消費税が免除されることになります。しかし、以下の条件に該当する場合は、この免除が適用されないので注意が必要です。
- 前年の1月から6月までの課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与支払額も1,000万円を超える場合、2期目でも課税対象となる
- 法人の場合、資本金が1,000万円以上であれば課税対象となる
上記のように、事業用賃貸契約であっても、さまざまな要因により課税状況が変化する可能性も。そのため、消費税に関する制度を十分に理解しておくことが重要です。
また、元々非課税事業者だった場合でも、状況の変化により課税事業者になった際には、管轄の税務署に速やかに届け出る必要があります。届出が必要となる主な例としては、以下のようなケースです。
- 課税売上高が1,000万円を超えることが確定した場合
- 資本金1,000万円以上の法人を新たに設立する場合
- 免税事業者が自主的に課税事業者になることを選択する場合
消費税の課税対象となるかは、不動産経営では重要な問題です。賃貸物件の用途や契約内容、売上高などの要因を総合的に考慮し、適切に対応しなければなりません。
不明点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
駐車場における消費税
駐車場の賃料収入は基本的に消費税が課されますが、地面の整備やフェンスの設置がされていない場合、課税対象とならないことがあります。青空駐車場などの単なる土地の貸付は非課税になります。ただし、施設の利用にともなって土地が使用される場合は課税対象となるため、注意してください。
住宅に併設する駐車場は基本的には課税対象ですが、物件ごとに1台以上の駐車スペースがあり、賃料に含まれている場合は非課税です。また、駐車スペースが住宅から離れている場合、消費税がかからないケースもあります。
その他の設備に関する消費税
入居者の希望により設置された設備(家具や家電、倉庫など)は、使用料を別途請求する場合、消費税が課されます。ただし、家賃に含まれている場合は非課税です。例えば、入居者が希望してレンタルする家具や家電、倉庫の使用料は消費税の対象です。しかし、入居者の希望に関わらず、あらかじめ設置されていた場合は非課税になるため契約書の内容に注意が必要です。
家賃収入にかかる消費税の申告義務と支払うタイミング

本章では、家賃収入にかかる消費税の申告義務や支払うタイミングを解説します。
家賃収入にかかる消費税の申告義務
消費税の課税売上高が1,000万円を超える場合、申告義務が発生します。個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度の課税売上高が基準です。
免税事業者の条件
- 商取引の規模が比較的小さい
- 基準期間のなかでの課税売上高が1,000万円以下
- 特定期間のなかでの課税売上高が1,000万円以下
基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、免税事業者となり、消費税の納税が免除されます。ただし、以下の条件を満たす場合、消費税が課されることがあります。
- 前年 11月から6月までの課税売上高が1,000万円を超える場合
- 法人の資本金が1,000万円以上の場合
課税対象者になった場合の消費税を支払うタイミング
次に課税対象者になった場合の消費税を支払うタイミングを解説します。
1・2期目の場合
先述したように、課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務が発生します。個人事業者の場合、暦年の前々年、法人は事業年度の前々事業年度が課税基準期間となります。
ただし、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも、特定期間で課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間は課税事業者となるため、注意してください。
特定期間とは、個人事業者の場合前年の1月1日から6月30日まで、法人の場合は原則として前事業年度開始日から6カ月間です。
なお、特定期間の判定は課税売上高のほか、支払った給与の合計額でもおこなえます。
新規開業した法人や個人事業主は、基準期間の売上がないため、個人事業主は開業から2年間は免税事業者となります。
一方で、法人は資本金の額で判断されるため、注意が必要。資本金が1,000万円以上であれば設立1期目から課税事業者とみなされ、1,000万円未満の法人は1期目・2期目は免税事業者としてみなされます。
3期目の場合
消費税の課税対象者となった場合に気になるのは、3期目以降の消費税の支払いタイミングではないでしょうか?
基本的に、個人事業主は対象年度の翌年3月末まで、法人は課税期間末日の翌日から2カ月以内に支払わなければなりません。所轄の税務署に対して地方消費税と消費税をあわせて申告して納付します。
なお、標準税率が10%の場合、消費税率7.8%、地方消費税率2.2%となります。
家賃収入にかかる消費税の基本的な計算方法
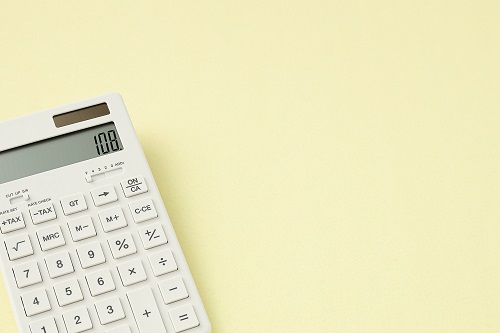
消費税の納税額は、消費者から預かった消費税額から事業者が支払った消費税額を差し引いた金額を納税します。計算方式には「原則課税」と「簡易課税」の2つがあります。それぞれ詳しくみていきましょう。
原則課税とは
原則課税とは、個別の取引で支払った消費税と受け取った消費税を差し引き、その差額を計算して納税額を決める方法です。計算式は以下のとおりです。
課税売上げにかかる消費税額 - 課税仕入れなどにかかる消費税額 = 消費税額
原則課税は、すべての取引で消費税を管理するため、正確な消費税額を計算できます。しかし、消費税がかからない取引もあるため、それらを一つずつ仕訳けて計算しなければなりません。
また、仕入税額控除を適用するためには、一定の事項を記載した帳簿および適格請求書(インボイス)などを保存しておく必要があります。
簡易課税とは
簡易課税とは、受け取った消費税に一定の割合(みなし仕入率)を乗じて算出する簡易的な計算方式です。概算で計算するため、正確な消費税額は出ませんが、作業負担が大幅に軽減されます。
ただし、消費税の還付を受けられないため、注意が必要です。
売上5,000万円以下の場合に利用できる簡易課税制度

売上が5,000万円以下なら、簡易課税制度を利用することをおすすめします。ただし、簡易課税を利用するためには、条件を満たす必要があります。本章では、条件と簡易課税制度を利用する際の注意点を解説します。
簡易課税制度を利用する条件
簡易課税制度を利用する条件は、次の2つです。
- 基準期間の課税売上高が5,000万円以下
- 「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する課税対象の取引で、売上高から非課税や不課税取引を差し引いた結果が5,000万円以下
また、所轄の税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」の事前提出が必要です。適用を受ける課税期間の前日までに提出しなければなりません。個人事業主の場合は暦年(1月1日~12月31日)なので、翌年に簡易課税を利用したい場合はその前年中に提出が必要です。
簡易課税制度を利用する際の注意点
原則課税と簡易課税の選択は、業態によってメリット・デメリットが異なります。特に不動産賃貸業では、経費が少ないことが多いため、簡易課税制度を選ぶと納税額を抑えやすいです。
ただし、高額な投資物件の購入費や設備投資がある場合は、消費税の還付を受けるために原則課税が適している場合も。また、簡易課税制度は一度選択すると2年以上継続する必要があるため、将来的な大規模修繕や改装などの計画も考慮する必要があります。
消費税に関する選択は、目先のメリットだけにとらわれず、専門家のアドバイスを受けながら慎重に決定することが重要です。
不動産投資はインボイス制度でどう変わる?

インボイス制度とは、2023年10月から導入された新しい消費税納税制度です。インボイス制度により、8%と10%の消費税率が並行して運用されることになりました。取引の合計金額だけでは税額の把握が難しいことや、公平に課税できていない現状を改善することを目的としています。
インボイス制度の影響
インボイス制度は、不動産賃貸業にも影響を与える可能性があります。インボイス制度では「適格請求書」(インボイス)を発行・保存することが仕入税額控除の条件となります。適格請求書を満たさない場合、仕入税額控除が受けられなくなるのです。
例えば、事業用物件を月10万円で貸し出している場合、年間で132万円の収益が得られることになります。しかし、インボイス制度を適用すると、インボイス発行事業者として消費税を納税する必要があります。
簡易課税制度を適用すると、年間で「12万円 × 40%」の4万8,000円を納税することになり、収入は127万2,000円に減少します。
インボイス制度の準備と対策
適格請求書は誰でも発行できるわけではなく、所轄の税務署に登録申請をしてインボイス発行事業者になる必要があります。登録事業者は、現在の制度の「区分記載請求書」の内容に加え、次の項目を記載した請求書を発行しなければなりません。
- 登録番号
- 適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額など
インボイス制度の導入にともない、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者には、一定の経過措置が設けられています。2023年10月1日~2026年9月30日は仕入税額相当額の80%、2026年10月1日~2029年9月30日は50%の控除が認められます。
事務所や店舗がある場合
基本的に家賃収入しかないオーナーはインボイスの影響を受けにくいです。しかし、事務所や店舗などの事業用物件を貸し出している場合はインボイス発行事業者の登録を検討する必要があります。
インボイス発行事業者でないと、借り主にとって消費税の納税額や計算の負担が増え、投資物件の競争力が低下する可能性があります。
また、賃貸経営が順調な場合、節税目的で資産管理会社を設立することがありますが、インボイス制度導入後は注意が必要です。オーナーが課税事業者で資産管理会社が免税事業者の場合、これまでの「益税」を得ることができなくなります。
インボイス制度の導入により、不動産賃貸業の対応方法は所有物件や借主の属性、投資規模などによって異なります。判断が難しい場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
本記事では、家賃収入の消費税対策について解説しました。家賃収入に関する消費税の問題は、不動産経営では避けて通れない重要なテーマです。課税対象となるかの判断基準、正確な申告方法、そして適切な節税対策を理解することが、安定した不動産経営の鍵となります。
わからないことや疑問点があれば、専門家の力を借りることが大切です。専門家のアドバイスを受けながら、自身の経営状況に合わせた最適な対策を取りましょう。

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ



