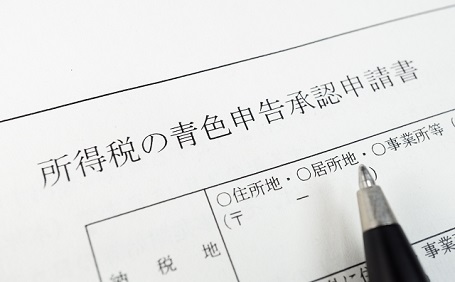不動産所得が事業的規模へ移行する効果とは?判断基準と税制メリットやデメリットを解説

そこで本記事では、不動産所得が事業的規模となる基準や、そのメリット・デメリットを解説します。賃貸経営を効率的に進めるための税制優遇を知りたい方、さらに節税効果や青色申告の特別控除の仕組みも解説するので、ぜひお役立てください。
記事の目次
不動産所得の事業的規模とは

不動産所得の「事業的規模」とは、どのような状態でしょうか。本章では、事業的規模の判断基準を解説します。
不動産所得の事業的規模とは
不動産所得の事業的規模とは、不動産賃貸業が個人の副業レベルを超え、主な事業として認められる規模です。国税庁の基準では「5棟10室基準」と呼ばれる条件が用いられ、賃貸しているアパートやマンションが5棟以上、または賃貸している部屋数が10室以上の場合が当てはまります。そのため、マンションの一室を投資用に購入して始める不動産投資では該当しません。なお、駐車場を所有する場合、台数の明確な基準はありませんが、5台分を1室として換算されるため、50台以上駐車できるものが事業的規模となります。
共同名義で所有している場合の判断基準
相続などでアパートなどの物件を共有名義で所有した場合、持ち分の規模だけでなく「共有物件全体の規模」で判断します。
例えば相続をして、兄弟で10室のアパートを半分ずつ所有し、一括で不動産会社に貸した場合はどうなるでしょうか。その場合、一括借り上げを利用しても、10室あれば事業的規模に該当します。
貸室だけでいうと10室に満たない場合でも事業的規模が認められるケースもあります。アパート4室、貸家2軒、駐車場10台分のように混在し、不動産所得の規模が大きい場合は事業的規模として認められます。
ただし、アパートで10室、貸家で5軒の基準以下であっても、賃料収入の規模が大きい場合、税務署で事業的規模と認められるケースもあります。
出典:国税庁|事業としての不動産貸付けとの区分
貸室と貸家が両方ある場合の判断基準
貸室と貸家を両方所有している場合は、貸室2室を家屋1棟分と考えて判定します。
例えば、独立家屋2棟と区分マンションの貸室6室がある場合は、貸室6室が家屋3棟分に該当し、独立家屋2棟と合わせて5棟とみなされ、事業的規模になります。
貸地の判断基準
月極駐車場などの貸地は、5台分で1室分とみなすのが一般的です。そのため、50台分以上の月極駐車場になると、原則は事業的規模になります。
貸室と合わせて所有する場合も同様に計算します。例えば、駐車場35台分ある場合は7室分とみなされるので、貸室3室を合わせると事業的規模になります。
スーパーマーケットや量販店に土地を貸し出している場合は、明確な基準がありません。そのため貸している土地は1つでも、賃貸料が1,000万円を超えるような場合は、事業的規模になる可能性があります。
貸室が空室の場合の判断基準
空室でも、いつでも貸し出しができるよう、広告・募集が恒常的におこなわれていれば、部屋は1室とみなされます。契約が解除された駐車場の場合でも、募集をかけていつでも使用開始できる状態にして、不動産賃貸業をしているとみなされれば、1台分とカウントされます。
出典:国税庁|貸家建付地等の評価における一時的な空室の範囲
不動産所得が事業的規模になるメリット
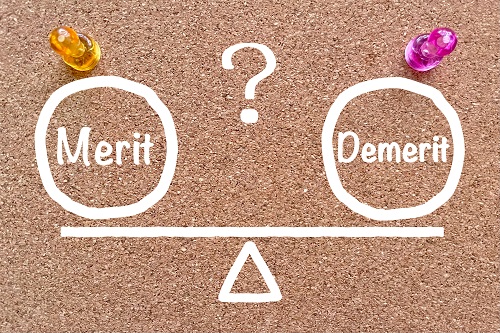
不動産所得が事業的規模と認められると、どのような優遇があるのでしょうか。そこで本章では、不動産所得が事業的規模になるメリットを解説します。
青色申告の特別控除が利用できる
不動産所得が事業的規模になると、青色申告の特別控除を利用できます。青色申告の特別控除とは、不動産賃貸業の所得から最大65万円までの控除を受けられる制度です。この特別控除を適用するためには、事業的規模、すなわち一般的には5棟10室基準と呼ばれる一定以上の規模で、賃貸経営をおこなわなければなりません。
また、正確な帳簿の記録や必要書類の提出が求められるため、準備が必要です。青色申告特別控除が適用されると、所得税や住民税の負担が軽減されるだけでなく、金融機関からの信用が増し、融資の際に有利になる可能性もあります。税負担が軽減される点とあわせてメリットになるでしょう。
家族へ支払う給与が経費になる
不動産所得が事業的規模になると、家族への給与を経費として計上できるようになります。これは、家族が不動産賃貸業に従事している場合、その労働に対して支払った給与を経費として認め、所得を圧縮し、結果的に税負担を軽減する仕組みです。ただし、この制度は賃貸経営が事業的規模でなければ適用されません。
事業的規模が認められて青色申告をおこなう場合は、事前に「青色事業専従者に関する届出書」を税務署へ提出しましょう。また、家族への給与を経費にするためには、労働内容や時間が明確で、実際にその労働に対して相応の給与が支払われている必要があります。さらに、その給与は常識的な範囲内であり、不当に高額である場合は認められません。この控除が適用されると、所得税や住民税が軽減されるとともに、家族の協力が加わり、事業の効率も向上します。
回収不能の未払いな賃料が経費になる
回収不能の未払いな賃料とは、入居者が破産したり、長期間の滞納が発生し、最終的に賃料を回収できなくなった場合の賃料です。事業的規模の場合、このような未回収賃料を損失として必要経費に計上できます。未払い賃料が経費になると、課税所得が減少し、税負担が軽減されるでしょう。一方で、事業的規模でない場合、回収不能賃料は損失として処理できず、単なる未収金として扱われます。
取り壊しなどで発生する損失が経費になる
不動産所得が事業的規模になると、建物の取り壊しなどによる損失を、全額経費として計上できます。例えば、老朽化した建物を取り壊して新しく建て替える場合、その取り壊しにかかる費用や、取り壊した建物の未償却残高が全額経費となります。不動産所得が赤字の場合は他の所得と損益通算ができ、青色申告により3年間赤字を繰り越せるので覚えておきましょう。
一方、事業的規模でない場合、このような取り壊し損失を全額経費として認められず、損失の一部しか経費に計上できません。こうしたコストの節約に貢献できる点が、事業的規模で賃貸経営をおこなうメリットになります。
延納利子税が必要経費になる
延納利子税とは、所得税や住民税の支払いが一括では難しい場合に、分割払いを選択した際にかかる利息にあたる税金です。通常、延納利子税は税金として支払う負担に過ぎません。しかし、不動産所得が事業的規模に達している場合、この利子税を必要経費として計上できます。この点は、特に多額の税金を支払う必要がある場合に、延納を活用しながら税金対策をおこなううえで有利です。税負担を減らしつつ、キャッシュフローをコントロールする方法として活用できるでしょう。
不動産所得が事業的規模になるデメリット
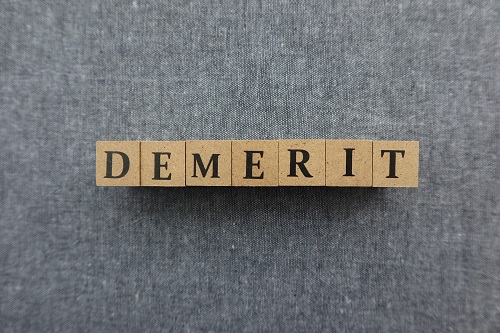
不動産所得が事業的規模になるといくつかのメリットがありましたが、よいことばかりではありません。そこで本章では、事業的規模で賃貸経営をおこなうデメリットを解説します。
事業税の対象になる
不動産所得が事業的規模になると、事業税が発生する点がデメリットです。税率は5%で、不動産所得から青色申告特別控除の金額を差し引く前の所得額から、290万円を控除した額に対して適用されます。青色申告特別控除の適用後の所得ではなく、控除前の金額が基準となるため、税額が思った以上に高くなるかもしれません。また、事業税の納付は原則年2回に分けておこなわれ、8月と11月に税金を支払います。事業税は経費として扱えるため、所得税や住民税の負担を減らす効果があります。しかし、直接的には税負担が増えるため、現金の流出も考慮に入れておかなければなりません。
記帳は複式簿記でおこなわなければならない
不動産所得が事業的規模になると、記帳を複式簿記でおこなわなければなりません。事業的規模で賃貸経営をおこなう場合、最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記での記帳と貸借対照表・損益計算書の作成が求められます。複式簿記は、収入と支出を二重に記録し、取引の全体像を正確に把握するための記帳方式です。しかし、この方法は単式簿記に比べて手間がかかり、経理知識や会計ソフトの利用が欠かせません。
複式簿記をおこなうと、青色申告特別控除が適用され、節税効果を得られる一方、記帳や決算書作成の負担が増加します。また、記帳ミスや手続きの不備があると控除を受けられないかもしれません。そのため、事業的規模に移行する際は、記帳の負担が増える点に留意が必要です。
配偶者控除や扶養控除が適用外になる
不動産所得が事業的規模に達すると、税務上の取り扱いが変わり、家族に対して「事業専従者給与」を支払えるようになります。そうなると、家族に支払う給与が経費になるのはメリットですが、反対に「扶養家族」としての資格は認められません。なぜなら、青色申告者の事業専従者である場合、扶養控除と配偶者控除を受けられないと定められているからです。
家族に給与を支払うと、事業経費として計上し税金を減らせますが、その一方で、扶養控除や配偶者控除を受けられない点はデメリットです。実施する場合、事業専従者給与の分と、扶養控除や配偶者控除を比較し、どちらがより税制上有利なのかを判断する必要があるでしょう。
不動産所得の事業的規模に関するよくある質問
不動産所得の事業的規模に関するよくある質問をまとめました。
不動産所得の事業的規模とは?
不動産所得の事業的規模とは、賃貸経営で所有する物件が副業レベルを超え、主な事業として認められる規模を指します。国税庁では「5棟10室基準」が用いられ、賃貸している物件がアパート5棟以上、または部屋数が10室以上であれば事業的規模とされます。共同名義の場合も、物件全体の規模で判断。また、貸室と貸家を混在所有する場合は、貸室2室を家屋1棟分として換算し、全体の規模で判定されます。貸地も、50台以上の駐車場は事業的規模に該当。さらに、空室でも賃貸募集がおこなわれていれば、その部屋はカウントされます。
不動産所得が事業的規模になるメリットは?
青色申告特別控除を利用できるようになり、最大65万円の控除が受けられる点がメリットです。また、家族へ支払う給与、未回収の賃料や建物の取り壊し費用なども経費にできるようになるため、損失が発生しても税負担が軽くなります。さらに、延納利子税も経費として扱うことができるため、多額の税金を分割で支払う際に、税金対策として有利になるでしょう。不動産所得が事業的規模になるとこれらのメリットがあるため、効率的な賃貸経営が実現します。
不動産所得が事業的規模になるデメリットは?
まず、事業税が発生し、青色申告特別控除の適用前の所得額に対して5%の税率が適用されるようになる点です。また、複式簿記での記帳が必要となり、経理知識が求められる点も考慮しなければなりません。さらに、帳簿の管理が煩雑化するため、会計ソフトを利用しなければ記帳が難しくなる可能性があります。青色申告特別控除を受けられるようになるものの、手間が増える点は避けられません。また、家族を事業専従者として給与を支払うと、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなる点もデメリットです。
まとめ
本記事では、不動産所得が事業的規模となる基準や、メリットとデメリットを解説しました。青色申告特別控除や家族への給与を経費にできる税制優遇が受けられる一方、事業税や記帳負担が増えるデメリットも見逃せません。この内容を理解すれば、事業的規模が自分の賃貸経営に与える影響をより深く把握でき、効率的な経営戦略を立てられるようになるでしょう。節税効果や事業の拡大を考慮したうえで、事業的規模への移行を検討してみてください。

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ