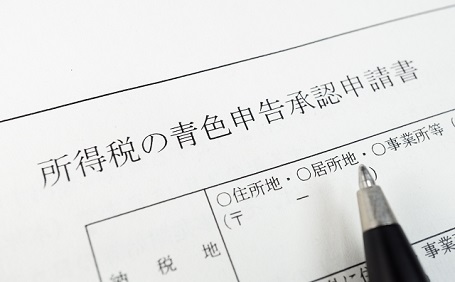アパート経営はサラリーマンでもできる?成功させるコツやリスクを徹底解説

国土交通省が2019年に実施した「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査」によれば、賃貸経営している人の約40%が会社員であることが明らかに。このデータから、会社員が本業と両立しながら不動産経営できることがわかるでしょう。
また、青色申告の適用を受けることで、税制面での優遇措置を活用しながら、事業的規模の経営を目指すことも可能です。本記事では、会社員がアパート経営を始める際のメリットや気を付けるべき点を詳しく解説します。
記事の目次
副業禁止のサラリーマンでもアパート経営はできる?

近年、副業を解禁する企業が増えていますが、依然として副業を制限する企業も少なくありません。特に、時間の制約がある仕事や競業にあたる業務は、副業禁止の対象となることが多いです。しかし、アパート経営に関しては、一定の条件を満たせば副業扱いにならないケースもあります。
例えば、小規模なアパート経営であれば、事業所得ではなく不動産所得として分類されるため、会社の副業規定に抵触しない可能性も。
また、管理業務を専門の管理会社に任せることで、実際の経営にかかる負担を大幅に減らすことが可能です。そのため、本業に支障をきたすことなくアパート経営を進められるケースもあります。
サラリーマンがアパート経営に向いている理由

会社員がアパート経営を始める際、初期費用の負担や管理業務の手間がネックになることがあります。しかし、適切な方法でおこなえば、本業と両立しながら経営を進めることが可能です。ここからは、会社員がアパート経営に向いている理由を解説します。
アパートローンを活用すれば初期費用の負担を軽減できる
アパート経営を始める際、多くの会社員が最初に直面する問題が「まとまった資金が必要になるのではないか?」という疑問でしょう。しかし、アパートローンを活用すれば、初期費用の負担を抑えながら経営をスタートさせられます。融資を利用すれば、手元資金が限られていてもアパート経営を始めることが可能です。
また、ローンを組むことでレバレッジをかけた投資ができるため、比較的少ない自己資金で規模の大きい物件を取得することもできます。金融機関の融資制度をうまく活用することで、資金の問題が解決でき、安定したアパート経営へとつなげられるでしょう。
管理会社を活用すれば本業と両立できる
会社員が本業と並行してアパート経営を成功させるためには、管理業務を管理会社に任せるのがおすすめ。実際にアパート経営をしている会社員の方で、管理会社に業務を委託しているケースもあります。
例えば、管理会社では以下のような業務を代行してくれます。
- 入居者の募集・審査
- 家賃の回収と滞納管理
- 建物の維持管理・修繕手配
- クレーム対応
上記の業務を委託することで、会社員でも時間を取られることなく安定したアパート経営が可能です。
また、「サブリース契約(一括借り上げ契約)」を活用すれば、空室が発生しても一定の家賃収入が保証されるため、リスクを抑えながら経営できるメリットも。サブリース契約とは、不動産オーナーがサブリース会社に物件を一括で貸し出し、管理会社が入居者に転貸する仕組みのことです。ただし、契約内容によっては賃料の見直しや解約条件に制限があるため、契約前に慎重な確認が必要です。
管理会社をうまく活用し、負担を軽減しながら効率的にアパート経営を進めましょう。
サラリーマンがアパート経営を始めるメリット

会社員がアパート経営を始めることで、さまざまなメリットが得られます。具体的にどのようなメリットが得られるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
収入を増やせる
アパート経営を副業としておこなうことで、会社からの給与に加えて家賃収入を得られる点が大きな強みです。部屋数や家賃設定、入居率などにより収益は変わりますが、上手に経営できれば本業の収入を超えることも可能です。
また、得た家賃収入を再投資することで、さらに資産を増やすこともできます。将来的には、老後の生活資金として活用できるため、長期的な視点で資産を形成する手段としても有効でしょう。物価上昇が続いている近年、本業以外に収入源があることは、とても大きな強みとなります。
金融機関からの融資を受けやすい
アパートを購入する際、多くの方がローンを活用しています。しかし、すべての方が融資を受けられるわけではありません。融資を受けるためには、審査に通る必要があります。
会社員は安定した収入があるため、金融機関の審査に通りやすく、比較的好条件で融資を受けやすい傾向があります。特に、年収や勤続年数、自己資金の有無が審査の重要なポイントとなるため、会社員は有利になる可能性が高いです。
もちろん、会社員であれば必ずしも融資を受けられるわけではありません。しかし、定年退職後よりも現役のうちのほうが審査のハードルは低くなるでしょう。安定した職に就いている間に、しっかりと資金計画を立てることが重要です。
団体信用生命保険に加入できる
アパートローンを利用する際、「団体信用生命保険(団信)」への加入を義務付けられることが一般的です。団信に加入すると、契約者が万が一の事態に陥った場合でも、残りのローンが保険金によって完済されるため、家族への負担を軽減できます。
また、団信は生命保険の代わりとしても機能するため、別途高額な生命保険に加入する必要がなくなることもメリットの一つです。アパート経営を検討する際には、保険の活用も考慮に入れるとよいでしょう。
節税対策ができる
アパートを所有することで、税負担を軽減できる点も大きなメリットです。例えば、不動産は現金よりも相続税評価額が低く、資産を次世代に引き継ぐ際の税負担を抑えられます。
現金の評価額が100%であるのに対し、建物や土地は約20~40%減額されるため、相続税の節税につながります。
また、アパート経営で赤字が出た場合、確定申告で本業の所得と損益通算することで、所得税や住民税を抑えられる可能性も。このような節税効果を有効活用することで、資産形成をより有利に進められるでしょう。
サラリーマンがアパート経営を成功させるためのポイント

会社員として働きながらアパート経営を成功させるためには、コツやポイントを抑える必要があります。
立地条件を重視する
アパートの立地は、経営の成否を大きく左右します。立地条件がよい物件は入居者が集まりやすく、長期的に安定した収益を見込めます。立地選びでは、周辺の生活環境やアクセスの利便性、競合物件の有無をしっかりと調査することが重要です。一度購入した土地の立地は変えられないため、慎重に選ぶ必要があります。
ターゲットを明確にする
アパート経営では、どのような入居者をターゲットにするのかを明確にすることが重要です。単身者向けなら駅近の物件やコンパクトな間取りが適しており、ファミリー層向けなら生活環境が整ったエリアが好まれます。ターゲット層に合った物件を選ぶことで、空室リスクを抑え、安定した経営につなげられます。
管理会社に業務を委託する
アパートの管理業務は、専門の管理会社に任せることが得策です。管理を外部委託すると、本業と両立しながら安定したアパート経営を続けられるでしょう。
管理会社に委託すると、費用がかかります。しかし、入居者の対応や設備の修繕、家賃の回収などを代行してもらえるため、無理なく経営を続けることが可能です。
サラリーマンがアパート経営で失敗しないための注意点

会社員がアパート経営で失敗しないためには、いくつかの点に注意が必要です。事前にリスクを把握し、慎重に準備を進めましょう。
住宅ローンがある場合は借入可能額が制限される
すでに住宅ローンを組んでいる場合、アパートローンの借入可能額を制限されることがあります。場合によっては、少額の資金からでもアパート経営を始められますが、手元に資金がなければ、いざという時に対応できない可能性があります。そのため、自己資金を多めに準備しておくことが重要です。
貯蓄や各種保険でリスクに備えておく
アパート経営には、空室リスクや修繕費の増加、金利上昇による返済負担の増加など、さまざまなリスクをともないます。特に、空室が続くと収入が減少し、アパートローンの返済が難しくなる可能性もあります。リスクを軽減するためには、貯蓄を十分に確保し、火災保険や地震保険などの備えをしておくことが大切です。
経営がうまくいかない場合の対策を考えておく
アパート経営が計画通りに進まない可能性もあるため、出口戦略を考えておくことが重要です。空室が増えたり、周辺に競合物件が増えたりなど、あらゆるシチュエーションを想定し、そのトラブルに対応できる対策を考えておきましょう。
経営が厳しくなった場合は、売却の選択肢も視野に入れ、売却のタイミングや相場を把握しておきましょう。
アパート経営が向いているサラリーマンの特徴

アパート経営を成功させるためには、安定した収入や十分な貯蓄があることに加え、長期的な視点で計画を立てることが重要です。特に、アパートローンを利用する場合、一定の勤続年数が求められるため、事前に審査基準を理解しておきましょう。
また、不動産投資にはリスクもともなうため、そのリスクをしっかりと把握し、適切に対策を取ることも重要です。では、具体的にどのような人がアパート経営に向いているのか、以下で詳しく見ていきましょう。
安定した収入と貯蓄がある人
アパート経営を軌道に乗せるためには、継続的な収入と十分な貯蓄が欠かせません。物件を購入する際、自己資金が豊富であれば頭金を多く用意できます。頭金が多く用意できればローンの借入額を抑えられるため、返済負担を軽減できます。
さらに、自己資金が多いほど金融機関からの信用も高まるため、より有利な条件で融資を受けられる可能性が高いです。突発的な修繕費や設備交換が必要になった際も、手元に資金があれば柔軟に対応できます。
十分な貯蓄と安定した収入を確保することで、経営のリスクを抑えながら、長期的に安定したアパート経営を実現できるでしょう。
一定の勤続年数がある人
アパートローンの審査では、会社員としての勤続年数も重要な判断材料になります。金融機関によって基準は異なりますが、多くの場合、最低でも3年以上の勤務実績が求められます。
現在の職場での勤務期間が短い場合、ローンの審査が厳しくなることがあるため、まずは一定の勤続年数を確保し、その間に自己資金を貯めると有効的。
また、長年同じ職場で働いていると、金融機関からの信用度が増し、融資を受けやすくなるだけでなく、金利の優遇を受けられる可能性もあります。そのため、安定した雇用環境のもとで資金計画を立て、準備を整えてからアパート経営を始めることが理想的です。
アパート経営を長期的な視点で考えられる人
アパート経営は、短期間で大きな利益を得るものではなく、時間をかけて資産を育てていく投資手法です。そのため、目先の利益だけを追い求めるのではなく、10年、20年先を見据えて計画を立てられる人に向いています。
アパート経営は始めてすぐに収益が大幅に増えるわけではありません。収益が出てもローンの返済や維持費の支払いが発生するため、長期的な収支バランスを考えながら経営していく必要があります。
将来の市場変動や物件の老朽化などの課題にも対応できるよう、長期的なビジョンを持ちましょう。資金管理を徹底することで、安定した家賃収入を得られるようになります。
アパート経営のリスクを理解して受け入れられる人
アパート経営には、さまざまなリスクがともないます。例えば、空室が発生すると家賃収入が減少したり、設備の老朽化による修繕費がかさんだりすることがあります。また、災害リスクや金利上昇による返済負担の増加などの要素も考慮しなければなりません。
しかし、事前に適切な対策を取ることで、上記のリスクを軽減できます。例えば、空室対策としては、立地や間取りにこだわることで入居率を高めたり、家賃保証制度を活用したりする方法があります。また、修繕費の積み立てをおこなうことで、突発的な支出にも備えられるでしょう。
アパート経営を成功させるためには、上記のリスクをしっかり理解し、事前に備えることが重要です。
サラリーマンがアパート経営で利益を得たら確定申告が必要

会社員がアパート経営で収益を上げた場合、確定申告をおこなう必要があります。給与所得のみであれば、通常は会社が年末調整をおこなうため、自身で確定申告をすることはほとんどありません。しかし、アパート経営で一定額以上の収益が発生した場合は、個人で確定申告の手続きを進める必要があります。
確定申告を怠ると、税務上のペナルティを科される可能性があります。延滞税や無申告加算税などの負担が発生するため、申告期限を守ることが重要です。
特に、会社員は本業が忙しく、確定申告の準備をあと回しにしがちですが、早めに手続きを進めておくことでスムーズに申告を済ませられるでしょう。
ここからは、確定申告を初めてする方のために、申告方法や申告の種類などを詳しく解説します。
青色申告と白色申告の違い
確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があり、どちらを選ぶかによって手続きの手間や控除額が変わります。
青色申告は、複式簿記で帳簿を作成し、申告書に詳細な記録を記載する方法です。手間はかかるものの、最大65万円の所得控除を受けられるため、節税効果が高い点が特徴です。
一方、白色申告は、提出する書類が比較的少なく、帳簿の作成も簡易的に済む点がメリット。しかし、青色申告のような控除を受けることはできません。
以前は白色申告のほうが手続きが楽でしたが、現在では白色申告でも帳簿の作成が義務付けられています。そのため、多少の手間をかけても青色申告を選択したほうが、控除の面で大きなメリットがあります。
最近では、クラウド型の会計ソフトを利用すれば、簿記の知識がなくても簡単に青色申告の書類の作成が可能です。税制優遇を活用するなら、青色申告を活用することをおすすめします。
確定申告の流れ
確定申告をスムーズに進めるためには、事前に必要な手順を理解し、計画的に準備を進めることが大切です。ここでは、確定申告の流れを詳しく説明します。まずは簡単に流れを押さえておきましょう。
- ステップ1青色申告の申請書を提出する
- ステップ2毎月の帳簿付けをおこなう
- ステップ3確定申告に必要な書類を準備する
- ステップ4確定申告書を作成する
- ステップ5期限までに申告書を提出する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ1.青色申告の申請書を提出する
青色申告を希望する場合は、不動産所得を得た年の2カ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出します。提出を忘れると、白色申告しか選択できなくなるため、注意が必要です。
ステップ2.毎月の帳簿付けをおこなう
収支の記録を正確に残すことが重要です。家賃収入や経費を月ごとに記帳し、領収書や契約書などの証拠書類も整理しておきましょう。
ステップ3.確定申告に必要な書類を準備する
青色申告をおこなう場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」を作成します。また、源泉徴収票や不動産関連の契約書、経費の領収書なども提出時に必要となるため、あらかじめ準備しておきましょう。
ステップ4.確定申告書を作成する
国税庁のWebサイトや確定申告ソフトを利用すると、必要な情報を入力するだけで自動的に税額を計算できます。特に、電子申告(e-Tax)を活用すれば、手続きがスムーズに進みます。
ステップ5.期限までに申告書を提出する
確定申告の提出期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。期限を過ぎるとペナルティが発生するため、余裕を持って準備を進めることが大切です。
オンライン申請なら24時間いつでも提出可能なため、忙しい会社員でも活用しやすいでしょう。
確定申告を忘れた場合
アパート経営で年間20万円以上の利益が発生した場合、確定申告をおこなう義務があります。しかし、もし申告を怠ったり、提出期限を過ぎたりした場合、税務上のペナルティを受けることになります。具体的には、「無申告加算税」と「延滞税」が発生するため、注意しましょう。無申告加算税は、納税額が50万円までなら10%、50万円を超え300万円までの部分には15%の税率が適用されます。
さらに、意図的に申告を怠り、税務署から指摘を受けた場合には、加算税率が最大40%まで引き上げられることも。申告が遅れた場合には「延滞税」も発生し、納期限の翌日から2カ月を経過する日までは、原則として年7.3%の税率が適用されるため、遅れるほど負担が増えてしまいます。たとえ短期間の遅れでも、5%程度の追徴課税が課されるため、期限を守ることが大切です。
上記のペナルティを回避するためにも、確定申告の準備は早めに進め、期限内に適切な手続きをおこないましょう。アパート経営を安定して続けるためにも、税金の管理をしっかりとおこなうことが重要です。
まとめ
今回の記事では、会社員でもアパート経営ができるのかを解説しました。安定した収入と貯蓄があり、長期的な視点で資産形成を考えられる人はアパート経営に向いているでしょう。また、融資を受ける際に一定の勤続年数が必要になるため、計画的に準備を進めることが重要です。
さらに、リスクを理解し、適切な対策を取ることで、経営の安定性を高められます。特に、所得が比較的多い人は、融資や節税面でのメリットが大きいため、より有利な条件でアパート経営を始められるでしょう。
ただし、アパート経営で収益が出た場合は、確定申告が必要です。確定申告を怠るとペナルティが発生してしまうため、余計な費用負担がかかります。確定申告を忘れないためにも、確定申告の時期や必要な書類、帳簿付けなど事前に準備しておきましょう。
上記のポイントを押さえながら、自身の状況に合わせた経営プランを立てることで、会社員の本業と両立しながら、堅実にアパート経営を進められるでしょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ