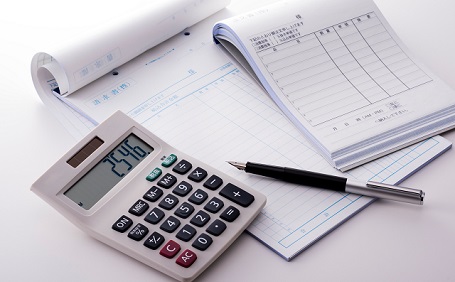不動産投資は青色申告のほうがメリット大きい?白色申告との違いや条件・注意点を解説
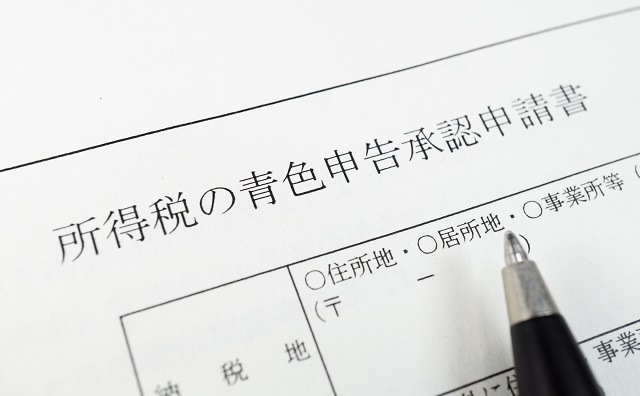
本記事では、不動産所得を得た場合、青色申告をしたほうがよいのか、条件や注意点などを詳しくまとめていきます。
記事の目次
不動産所得は確定申告が必要

会社員の給与は、源泉徴収や年末調整で税金が自動的に計算されています。しかし、不動産所得では個人が得た収入と支出を計算し、自ら確定申告をおこなわなければなりません。
不動産所得とは、賃貸物件から得られる家賃収入や駐車場収入などを指します。不動産投資で得た収入から必要経費を差し引いた金額が課税対象となります。
不動産所得を適切に申告するためには、青色申告と白色申告の違いを理解し、自身の状況に合った申告方法を選択することが重要です。以下では確定申告の種類や申告のポイントを詳しく解説していきます。
白色申告とは
白色申告とは、青色申告の承認を受けていない納税者がおこなう申告納税制度です。不動産所得の確定申告をする際、青色申告を希望しない場合や手続きをおこなっていない場合は白色申告を選ぶことになります。
白色申告の主な特徴は、青色申告に比べて必要な書類が少なく、申告手続きが比較的簡単なことです。簿記の専門知識が不要な簡易簿記でも認められるため、誰でも容易に作成可能です。
白色申告で必要な書類や保存すべき帳簿は以下のとおりです。
| 申請書類 |
・確定申告書第一表・第二表
・収支内訳書
|
|---|---|
| 保存帳簿 |
・法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿):保存期間7年
・任意帳簿(業務に関する帳簿):保存期間5年
|
白色申告では税制上の控除などのメリットはありませんが、手軽に確定申告を済ませたい方には適した方法です。
青色申告とは
青色申告は、税制上の優遇措置が受けられる申告納税制度です。青色申告をおこなうには、事前に「青色申告承認申請書」と「開業届」を所轄の税務署に提出する必要があります。
青色申告には多くの書類の準備が必要ですが、税制優遇を受けられる点が大きな魅力です。以下が青色申告に必要な書類です。
| 申請書類 |
・確定申告書第一表・第二表
・青色申告決算書
・貸借対照表と損益計算書
・第三表(譲渡所得がある場合)
・第四表(赤字がある場合)
|
|---|---|
| 保存帳簿 |
・総勘定帳
・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛金元帳
・買掛金元帳
・固定資産台帳
※保存期間はすべて7年
|
青色申告の記帳方法には、複式簿記と簡易簿記の2つの方法があります。複式簿記は専門知識が必要で初めての方には難しいですが、最大65万円の控除が受けられる大きな利点があります。
簡易簿記でも10万円の控除が適用されますが、複式簿記に比べてメリットは少ないでしょう。
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告の最大の違いは、税制上の優遇措置を受けられるかです。青色申告では、最大65万円の控除を受けられますが、白色申告には税制上の控除はありません。
どちらの申告方法を選ぶかは、個々の状況やニーズによります。青色申告と白色申告の違いを以下の表でまとめたので、参考にしてください。
| 青色申告 (65万円控除) |
青色申告 (10万円控除) |
白色申告 | |
|---|---|---|---|
| 開業届と 青色申告承認申請書 の提出 |
必要 | 必要 | 不要 |
| 控除可能条件 | 事業的規模(アパートやマンション10室以上、独立家屋5棟以上) | マンション 1室から |
なし |
| 提出書類 |
・確定申告書第一表・第二表
・青色申告決算書
・貸借対照表と損益計算書
・第三表(譲渡所得がある場合)
・第四表(赤字がある場合)
|
・確定申告書第一表・第二表
・青色申告決算書
・第三表(譲渡所得がある場合)
・第四表(赤字がある場合)
|
・確定申告書第一表・第二表
・収支内訳書
|
| 保存帳簿 |
・総勘定帳
・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
|
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・経費帳
|
・法定帳簿
・任意帳簿
|
| 記帳方法 | 複式簿記 | 簡易簿記 | 簡易簿記 |
| 税制上の メリット |
・最大65万円の所得控除
・事業専従者控除
・3年間の赤字繰越控除
・貸倒損失を必要経費に計上できる
|
・10万円の控除
・事業専従者控除
・3年間の赤字繰越控除
・貸倒損失を必要経費に計上できる
|
なし |
上記の表を見ながら自身の状況に合った申告方法を選択するとよいでしょう。
不動産投資で青色申告できる条件
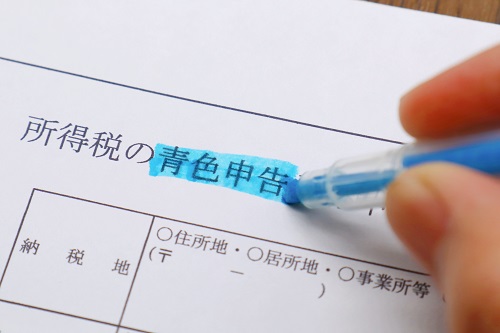
不動産投資をおこなっているすべての人が青色申告できるわけではありません。青色申告を適用するには一定の条件を満たす必要があります。ここでは、青色申告をするための条件を詳しく解説します。
条件を満たせば、確定申告時に青色申告特別控除の適用を受けられるでしょう。ただし、一部の手続きには期限が設けられており、期限を過ぎると当該年度は青色申告ができなくなるため、注意が必要です。
青色申告承認申請書の提出をする
青色申告をおこなうには、事前に「青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。申請書の提出期限は以下のとおりです。
- 青色申告開始年の3月15日まで
- 事業開始から2カ月以内(1月16日以降開始の場合)
上記の期限までに申請書を提出しないと、その年は青色申告ができなくなってしまいます。その場合、白色申告となり青色申告の特別控除のメリットは受けられません。期限に気をつけて、適切に手続きをおこなう必要があります。
青色申告で65万円の控除を受けるための条件
青色申告した場合、一定の要件を満たせば65万円分の特別控除を受けられます。
控除額には65万円、55万円、10万円の3種類があります。65万円の控除を受けるためには、まず55万円の控除を受ける必要があります。さらに一定の条件を満たすことで65万円の控除を受けることができます。
その条件を満たせない場合でも、10万円の控除は受けられるのが特徴です。
55万円の控除を受ける条件は以下のとおりです。
条件1:事業規模の不動産貸付をおこなっていること
55万円控除を受けるための条件の1つが、「事業規模の不動産貸付」をおこなっていることです。国税庁によると、おおよその基準は以下のとおりです。
- アパート・マンション: 10室以上
- 戸建て住宅: 5棟以上
自身が所有する賃貸物件の数が上記の基準を超えていれば、「事業規模」と見なされ、55万円控除の条件を満たせします。ただし、あくまでも目安なので、参考程度にしておきましょう。
10万円の控除を受ける場合は、「事業規模」の条件は不要です。
条件2: 複式簿記の適用
55万円控除を受けるための2つ目の条件が、複式簿記で帳簿を付けることです。複式簿記とは、金銭の出入りと資産の増減を合わせて記録する方式です。確定申告時には以下の書類を作成し提出する必要があります。
- 貸借対照表: 資産と負債の状況
- 損益計算書: 収益・費用・利益の状況
複式簿記は単式簿記に比べて複雑ですが、55万円控除を受けるためには複式簿記が義務付けられているので、しっかり理解しておきましょう。
さらに、65万円の控除を受けるためには、上記に加えて以下の条件のいずれかをクリアする必要があります。
条件3:e-Tax を利用する
スマホやパソコンで、e-Tax で確定申告書・青色申告決算書のデータを、確定申告の期限までに送信する必要があります。国税庁ホームページに「確定申告書等作成コーナー」があるので、そこから確定申告書・青色申告決算書のデータを作成して、e-Taxで送信してください。
条件4:優良な電子帳簿の保存を利用する
その年分の仕訳帳や総勘定元帳は、優良な電子帳簿の要件を満たし適切に保存しておかなければなりません。一定の事項を記載した届出書を確定申告の期限までに提出する必要があります。
優良な電子帳簿の要件
不動産投資で青色申告をするメリット
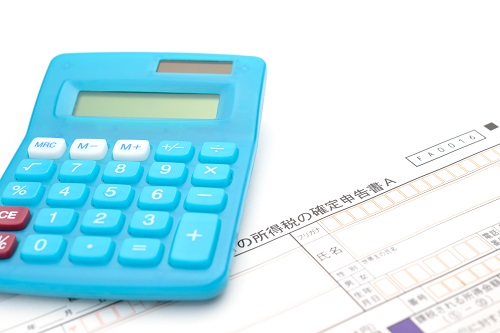
青色申告は白色申告より複雑ですが、メリットが多くあります。ここからは不動産投資で青色申告をおこなうメリットを解説します。
青色申告特別控除の額が大きい
青色申告すると特別控除が受けられます。控除額は10万円、55万円、65万円(電子申告時)の3種類があります。55万円控除を受けるには一定の条件を満たす必要がありますが、その要件を満たせなくとも10万円の控除は受けられます。
さらに、e-Taxによる電子申告か電子帳簿保存をおこなえば、55万円控除に10万円が上乗せされ、最大65万円の控除が適用されるので、税制上のメリットが大きいのが魅力です。
電子帳簿保存には税務署の承認が必要ですが、e-Taxなら比較的簡単に65万円控除を受けられるでしょう。
白色申告の場合は控除を受けられないので、青色申告には大きな節税メリットがあります。
事業専従者への給与の計上上限がなくなる
不動産収入を得るための事業を営むうえで、事業専従者に対して給与を支払うケースがあります。事業専従者とは、青色申告をしている事業主の元で働いている家族のこと。
事業専従者に給与を支払う際に青色申告をしていると、給与額の計上上限が高くなるため、より多くの金額を経費として控除できるのがメリットです。
青色申告の場合、支払った給与の全額が原則として経費と認められます。一方、白色申告の場合は上限額が決められており、配偶者には86万円、配偶者以外には50万円が上限とされています。
青色申告をすれば、事業規模に応じて高額の事業専従者の給与を経費計上できるため、節税効果が高まるのです。例えば、家族などに対して高額の給与を支払いたい場合には、青色申告を選んだほうが大きなメリットが期待できます。
赤字の繰越しが3年間可能になる
不動産賃貸事業では、投資物件の稼働状況によっては損失が出る年もありえます。不動産所得で損失が発生した際に青色申告を選択していると、その損失金額を3年間にわたり次年度以降に繰り越せる点がメリットです。
翌年以降に黒字転換しても、繰越損失から控除できるため、課税所得自体を大きく減らすことが可能です。一方、白色申告の場合は赤字の繰り越しは認められていません。そのため、青色申告には損失が発生した際でも、将来的な節税の機会を残せるというメリットがあります。
不動産投資で計上できる経費が多い
不動産投資では物件の取得から運用、売却に至るまでさまざまな費用が発生します。青色申告を選択していれば、費用のほとんどを経費として計上でき、所得から控除して確定申告時の納税額を減らせます。具体的にどのような費用が経費として計上できるのか、以下でまとめるので参考にしてください。
不動産関連税金
投資用不動産の購入時や所有期間中に課される税金は、すべて経費計上が認められています。具体的には、購入時の不動産取得税や登録免許税、所有期間中の固定資産税や都市計画税などが挙げられます。また、売買契約に貼付する収入印紙代(印紙税)も、経費計上が可能です。
保険料
投資用不動産を所有する際は、火災保険や地震保険などへの加入が必要です。リスク回避のために加入した特約の保険料も含め、支払った保険料全額を経費計上できます。
修繕費用
入居者の退去にともなう原状回復のためのリフォーム代や、日常の設備補修代など、投資物件の修繕にかかる費用はすべて経費計上が可能です。ただし、居住水準の向上を目的とした大規模な改修費用は、一括の経費計上はできないので注意してください。この場合は耐用年数に合わせて減価償却する必要があります。
不動産投資ローンの金利
投資用不動産の購入のために組んだ不動産投資ローンには、支払利息部分のみを経費計上できます。建物購入のためのローン利息は損益通算が可能ですが、土地購入ローンの利息は損益通算の対象外です。投資用不動産を購入する際は、建物と土地で分けて利息を算出しなければならないため、しっかり区別しておきましょう。
管理会社への手数料
投資物件の管理を不動産管理会社に委託する場合、支払う委託料は経費として計上可能です。管理会社がおこなう業務には、物件の清掃や家賃収納、入居者対応、新規入居者募集などがあります。上記の委託料は、投資用不動産を管理・運営するのに必要な費用なので、経費と認められています。
専門家への報酬
不動産取引では、司法書士や税理士などの専門家にサービスを依頼する機会があります。投資物件の登記手続きにかかる司法書士報酬や、確定申告のための税理士報酬など、不動産投資に関連したすべての専門家報酬は、経費計上が認められています。
減価償却費
建物の購入費用は、法定の耐用年数に応じて、毎年一定額を減価償却費として経費計上する必要があります。木造住宅なら22年、鉄筋コンクリート造なら47年の期間で償却します。中古物件を購入する際は、別途耐用年数を計算しなければなりません。
交通費・書籍代など
投資物件の視察や確認、トラブル対応のための交通費、不動産投資関連の専門書の購入代金なども、経費として計上が認められる項目です。
以上が、不動産投資で一般的に認められている主な経費です。適切に経費計上をおこなうことで、課税所得額を減らせるため、節税効果が期待できるでしょう。
一括評価の貸倒引当金の計上ができる
不動産賃貸事業では、入居者から賃料の支払いが滞ると貸倒れが発生する可能性があります。そのような事態に備えて、あらかじめ損失見込額を経費として計上しておく「貸倒引当金」の制度があります。貸倒引当金の計算方法は、以下の2種類です。
-
一括評価
年末時点での貸金の帳簿価額合計額を算出し、5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定に繰り入れる -
個別評価
破産手続き開始を申し立てた取引先や、債務超過が続き今後好転する見通しがない取引先などにかかる損失見込額を、貸倒引当金勘定に繰り入れる
個別評価の形状方法は白色申告でもできますが、一括評価の計上方法は青色申告のみとなるので、注意が必要です。
不動産投資で青色申告をおこなう際の注意点

不動産投資で青色申告をおこなう際は、注意するべきポイントがあります。条件をクリアしていなければ、青色申告ができなくなるため、以下の注意点をしっかり確認しておきましょう。
期限までに青色申告承認申請書を提出する
不動産投資で青色申告をする場合、事前に所轄の税務署に対し「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。手続きには期限が設けられているため、忘れないように注意しましょう。
上記でもお伝えしましたが、青色申告を開始する年の前年の3月15日までが期限です。
ただし、1月16日以降に新規で事業を開始した場合は、事業開始日から2カ月以内であれば、青色申告承認申請書を提出できます。
はじめから事業規模で不動産投資を考えている方は、開業届と合わせ、青色申告承認申請書の提出をおこなうとスムーズです。締め切りを守るように徹底しましょう。
経費の証拠書類をしっかりと保管する
不動産投資で発生したさまざまな経費を計上するためにも、その証拠となる領収書やレシートを保管しておく義務があります。確定申告時に添付する必要はありませんが、税務調査などで提示を求められる可能性があるためです。
書類の保管期間は7年間と定められています。
感熱紙などの書類は長期間保存すると印字が消える可能性があるので、コピーを取るなどの対策が必要です。電子データで保存しておくのもおすすめです。
不動産所得の正確な算出方法を確認する
不動産所得の金額は、以下の計算式で算出されます。
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費
総収入金額には賃料収入はもちろん、管理費や共益費、賃借人の債務不履行などで返還されないことになった敷金なども含まれます。
礼金や更新料を徴収する際も、忘れずに計上するようにしましょう。
まとめ
本記事では、不動産所得での青色申告について詳しく解説しました。申告方法には青色申告と白色申告の2種類がありますが、税制メリットを受けたい方は青色申告がおすすめです。
しかし、青色申告はすべての方ができるわけではありません。青色申告をする際は事前に書類を提出する必要がありますし、期限も設けられています。確定申告の手続きも白色申告と比べると複雑になるため、はじめはわからないことだらけで不安になるかもしれません。
わからない点や不安な点はそのままにするのではなく、税理士などの専門家に相談してみるとよいでしょう。プロに確定申告を依頼すると費用はかかりますが、適切に申告してくれるため、税務署から指摘が入ったり、税務調査が入ったりなどのリスクを軽減できます。また、専門家に依頼した費用も経費計上できるため、ぜひ検討してみてください。

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ