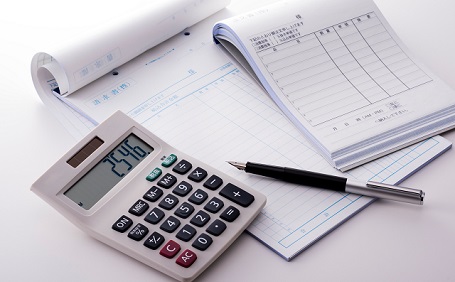アパート経営を法人化するとどうなる?判断する目安や事前に把握すべき点を徹底解説

本記事では、アパート経営を法人化する場合のメリットやデメリットを紹介します。また、アパート経営を法人化するべきかを判断する目安も紹介しているので、それぞれよく把握して効果的に法人化をすすめましょう。
記事の目次
アパート経営を法人化するメリット

アパート経営を法人化するか迷う方は、法人化するとどのようなメリットがあるのか知りたいと思っていらっしゃるのではないでしょうか。本章では、アパート経営を法人化するメリットを解説していきます。
所得税率が低くなる
アパート経営を法人化するメリットは、所得税率が低くなる点です。個人でアパート経営をおこなう場合、所得税の税率は累進課税制度で定められますが、所得が多い方では税率が45%に達する場合があります。これに対し、アパート経営を法人化すると、法人税の税率が適用され、中小企業規模なら年間の所得が800万円以下で税率が約15%。所得が800万円を超える部分に対しても、税率は約23%のため、個人の最高税率と比べると低い税率になります。
例えば、アパート経営による年間所得が1,000万円だったとしましょう。個人でこの所得を得た場合、所得税率は33%で納める税金は約176万円になります。一方、法人化した場合、800万円までの部分には15%の税率で法人税が120万円。残りの200万円には23%の税率で法人税は46万円で、合計166万円になります。このように、アパート経営を法人化すると、税率が低くなる点が大きなメリットです。
相続税対策が有利になる
アパート経営を法人化すると、相続税対策が有利になる点もメリットの一つ。個人がアパートを所有している場合、そのアパートは相続財産として評価され、相続税の課税対象となります。一方、アパート経営を法人化しておけば、オーナーが亡くなってもその資産は会社の名義になるため、個人の相続税の対象になりません。さらに、法人化してから3年が経過すると、法人の資産評価額は個人の相続税評価額を用いて設定できるようになります。資産評価額が抑えられる結果、相続税を軽減できます。
相続資産の分割がしやすくなる
相続資産の分割がしやすくなる点も法人化のメリットです。個人所有のアパートを相続する際、相続人の間でどのように分割するかが大きな問題となります。不動産は物理的な分割は難しいため、売却して現金化するか、相続人の一人が他の相続人に代償金を支払う方法を取る必要がありますが、トラブルや揉め事に発展するかもしれません。
しかし、アパート経営を法人化すると、アパートは法人の所有物となり、相続時にはその法人の株式を相続する形になります。株式は分割が容易で、各相続人に均等に分配することが可能です。例えば、法人の全株式を相続人の数に応じて等分に分割すると、各相続人が所有する割合を明確にし、相続にともなうトラブルを未然に防ぐことができます。
さらに、法人化すれば株式の持分に応じた収益の分配もスムーズです。相続人はそれぞれ自分の持ち株比率に応じて、アパート経営から得られる利益を受け取ることができるため、不動産の実物を巡る争いを避けられます。このように、アパート経営の法人化は、相続資産の分割が容易になるため、相続対策として有効な手段です。
経費の幅が広がる
計上できる経費の幅が広がる点も、法人化するメリット。個人でアパート経営をおこなう場合、経費として認められる項目は限定的です。これに対し法人化すると、社用車の購入やリース費用も経費として計上できるようになります。個人の場合、車両費用は、原則として経費と認められません。しかし、法人であれば業務に使用する車両の購入費用、燃料費、保険料などを経費に含めることができます。
また、法人では事務所の賃貸料や通信費、消耗品費など、日常の運営にかかる費用も幅広く経費として認められます。その他、経費には以下のものがあります。
- 税金
- 減価償却費
- 管理費(委託する場合)管理委託費用
- 修繕費
- 広告宣伝費
- 損害保険料
- 通信費
- 接待交際費
- 事務用品費
- 消耗品費
- 交通費
これにより、実際の課税対象になる利益を効果的に抑えて、法人税の軽減が可能です。
役員報酬で税負担を軽減できる
役員報酬を設定できる点もメリットの一つです。個人事業としてアパート経営をおこなう場合、経営者自身の報酬は事業所得として扱われ、経費として計上できません。しかし、法人化すると、経営者やその家族を役員に任命し、役員報酬として支払うことができ、これを経費として計上できるようになります。役員報酬を経費として計上すると、法人の課税所得が減るため、支払うべき法人税の額を減らすことが可能です。
また、役員報酬を設定し社会保険料を支払えば、それが将来の年金額の算定基礎となるため、適切な報酬設定は老後の生活資金の確保にも貢献。このように、アパート経営を法人化して役員報酬を設定できるメリットは大きいです。役員報酬を経費として計上すると法人税の節税ができ、個人の所得税負担も分散させられます。
欠損金の繰越期間を長く持てる
欠損金の繰越期間を長く持てる点も、法人化のメリットです。個人事業主としてアパート経営をおこなう場合、欠損金(赤字)の繰越期間は3年間に限定されます。しかし、法人化すると、この繰越期間は10年間に延長され、長期的な経営戦略が立てやすいです。なお、欠損金の繰越とは、ある年度に発生した赤字を翌年度以降の黒字と相殺し、課税所得を減少させ、結果的に法人税の支払いを減らす仕組みです。
例えば、アパート経営初年度に修繕費や設備投資がかさみ、初年度に500万円の赤字が発生したと想定します。その場合、個人事業主であれば、欠損金を無駄にしないためには3年以内に500万円の黒字を出さなければなりません。しかし、法人化している場合、10年間で500万円の黒字を出せばよくなります。その赤字を翌年度以降の利益と相殺できるため、課税対象となる所得が減り、税負担の軽減が可能です。
さらに、繰越欠損金を活用すると、利益が出る年度に備えた節税対策もできます。計画的な資金管理がしやすくなり、経営の安定性を高めることができる点も大きなメリットです。
認知症対策で活用できる
アパート経営の法人化は、認知症対策にも有効になります。なぜなら個人が認知症を患うと、財産の管理や重要な意思決定が難しくなり、不動産の管理や経営が困難になってしまうためです。個人名義でアパートを所有している場合、所有者が認知症を患うと、財産管理を第三者に委ねるために成年後見制度の利用が必要。この制度を利用するには、家庭裁判所の手続きに委ねられるため、時間や手間がかかります。また、成年後見人の選任後も、不動産の売却や重要な契約には家庭裁判所の許可が必要となり、柔軟に経営できません。
一方、アパート経営を法人化しておくと、財産は法人名義となり、経営の意思決定は法人の役員会や取締役会でおこなわれるようになります。仮に経営者が認知症を患っても、他の役員が経営を継続できるため、事業運営に大きな影響を及ぼすことがありません。法人の経営は複数の役員によっておこなわれるため、一人が意思決定できなくなった場合でも、残りの役員が引き継ぐことで、事業の継続性が確保されます。
さらに、事前に役員の選任や交代のルールを定めておける点もメリットといえます。もし経営者が認知症になった場合でも、スムーズに経営権を移譲できるでしょう。役員の選任や交代は定款や株主総会で決議されるため、予期せぬ事態にも柔軟な対応が可能です。このように、アパート経営の法人化は、認知症リスクへの備えも強化できます。
アパート経営を法人化するデメリット
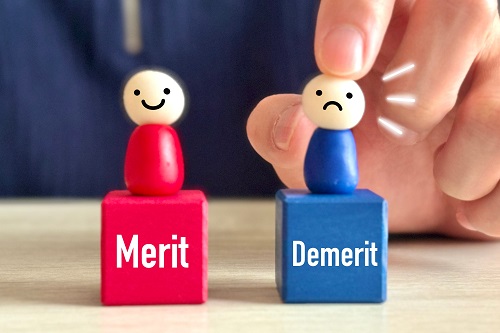
アパート経営を法人化するメリットはわかりましたが、実際にはよいことばかりではありません。そこで本章では、アパート経営を法人化する主なデメリットも紹介します。
売却時の税率が高くなる
アパート経営を法人化すると、売却時の税率が高くなる点がデメリットです。個人がアパートを売却する場合、売却益に対してかかる税金は所得税と住民税で、長期譲渡所得として扱われると税率は比較的低く抑えられます。譲渡所得とは、一定期間所有した物件を売却した時の所得を指し、所有期間が5年を超える長期譲渡所得では所得税が15%、住民税が5%の合計20%です。
一方、法人がアパートを売却する場合、その売却益は法人の事業所得として計上されます。法人税の実効税率は約30%のため、個人所有の場合に比べて売却時の税負担が大きいです。例えば、アパートの売却益が1,000万円の場合、個人所有では税金が200万円に対し、法人所有では税金が約300万円かかります。このように、アパート経営を法人化すると、売却時の税率が高くなるデメリットは避けられません。
法人になって3年以内は通常の取引価額で評価される
法人化して3年以内に相続が発生してしまった場合、相続税評価額が個人同様に下がる仕組みが適用されず、通常の取引価額で評価される点がデメリットです。仮に、アパート経営を法人化して1年目に相続が発生した場合、設立時の出資金やアパートの資産価値がそのまま評価に反映されて計算されるため、相続税は高くなります。
法人経営の規模が小さいとコストが高くつく
法人経営の規模が小さいとコストのほうが高くなってしまう点も法人化するデメリットです。法人化には設立費用や運営費用、税務や会計のコストなど、多くの費用がかかります。しかし、法人の規模が小さい場合、これらの費用が割合として高くなり、法人化したことがむしろデメリットになりかねません。
法人を設立する際には、法人を設立する費用が必要で、特に書類の作成や手続きは煩雑なので、税理士などの専門家のアドバイスや支援が必要です。これらの費用は法人の規模に関わらず一定で、規模が小さい場合は負担が多くなるでしょう。
また、法人の経営状況や規模に応じて定期的な会計監査や税務調査もおこなわれるため、これらの費用も負担になるでしょう。このように、法人経営の規模が小さい場合、設立費用や運営費用、税務や会計のコストなどが割合として高くなり、経営の効率性が損なわれる可能性があります。法人化する際には、メリットだけでなくさまざまなデメリットを考慮して総合的に判断すべきです。
アパート経営を法人化する目安は?

アパート経営には、メリットもデメリットもある点は理解できましたが、何を目安に決めるべきでしょうか。結論からいうと、課税所得が900万円以上を目安に法人化すべきと考えられています。理由としては、課税所得が900万円以上になると、個人経営より法人経営のほうが、所得税が低くなるためです。現在の累進課税制度で決められている所得税の割合は以下になっています。
| 課税所得金額 | 所得税率(個人) | 住民税率(個人) |
|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 10% |
| 195万円以上330万円未満 | 10% | |
| 330万円以上695万円未満 | 20% | |
| 695万円以上900万円未満 | 23% | |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% | |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | |
| 4,000万円以上 | 45% |
※1,000円未満の端数は切り捨て
一方、法人税率は、資本金1億円以下の会社で800万円以下の部分には15%、800万円以上の部分には23.2%の税率(参考:国税庁 No.5759 法人税の税率)が設定されています。また、住民税は、規模にもよりますが、2018年(令和元年)10月1日以後に事業を始めた場合、約10%の税率(参考:東京都主税局ホームページ 法人事業税・法人都民税)の設定です。そのため、個人の税率が33%を超えるラインから法人化のメリットが強調されてきます。すると、個人の課税所得が「900万円以上1,800万円未満」の時、所得税と住民税をあわせた税率が43%になり、法人のほうが個人より税金が低いです。
ただし、課税所得が900万円とは、家賃収入が900万円ある状態ではありません。家賃収入から必要経費を引いた金額が不動産収入になるため、不動産収入以外の所得をあわせて総合的に判断する必要があります。他の収入もあわせて、課税所得が900万円のラインが、法人化の目安です。
アパート経営を法人化する際の注意点

課税所得が900万円を超えたら法人化すべきラインですが、焦りは禁物です。そこで本章では、法人化を検討している場合に事前に把握しておくべき注意点をまとめます。
法人化には費用がかかる
アパート経営を法人化する際は、法人化にともなう費用がかかる点に注意が必要です。法人化にはまず、法人を設立する際の登記費用や手数料、顧問税理士や弁護士の相談料などの費用がかかります。法人の設立には書類の作成や手続きが煩雑であり、専門家のアドバイスや支援が必要です。さらに、法人経営では会計や税務関連の業務も煩雑で、これらの業務を専門家に委託します。
税理士や会計士の報酬は、法人の売上や利益に応じて決まることが多いため、規模によっては高額に。また、法人の経営状況や規模に応じて定期的な会計監査や税務調査もおこなわれるため、これらの費用もかさみます。さらに、法人経営では事務や管理のための人件費やオフィスの費用も必要です。
これらの費用は法人の規模や運営方針に応じて変動しますが、経営者はこれらのコストも考慮して経営計画を立てる必要があります。総じて、法人化には多くの費用がかかるため、事前にしっかりと費用を見積もり、予算を立てることが重要。また、費用を抑えるためには、効率的な運営や経営戦略の見直しが必要となります。経営者は慎重に法人化のメリットとデメリットを比較し、費用対効果を考慮して経営方針を検討しなければなりません。
法人化の手続きには時間と手間がかかる
法人化の手続きには時間と手間がかかる点も理解しておきましょう。まず、法人を設立するためには、登記手続きや書類の作成が必要です。これには、定款や役員の選任、役員の住所や氏名の登記など、さまざまな書類が必要となります。これらの書類は法的に正確でなければならないため、専門家の助言やアドバイスを仰ぎ丁寧に作成しなければなりません。
また、法人化には税務や会計の手続きも必要です。法人としての税務登録や税務申告書の作成、会計処理の準備など、これらの手続きも時間と手間がかかります。特に、税務関連の手続きは厳密な規定があり、誤りがあると税務署からの指摘や追加の手続きが必要となるため、気をつけましょう。
さらに、法人化すると、会社の組織や運営に関するルールや規定を定める必要が生じますが、これらの手続きや準備にも時間がかかるため、十分な計画と準備が求められます。このように、アパート経営を法人化する際には、法人化の手続きに時間と手間がかかることを認識しておかなければなりません。
アパート経営の法人化に関するよくある質問
本章では、アパート経営の法人化に関するよくある質問をまとめました。
アパート経営を法人化するメリットは?
アパート経営を法人化すると、所得税率が低くなり、相続税対策や相続資産の分割が容易になります。また、幅広い経費が計上可能で、役員報酬や欠損金の繰越期間の長期化もメリット。さらに、認知症対策や経営継続性の確保も法人化の利点になります。
アパート経営を法人化するデメリットは?
アパート経営を法人化するデメリットは、売却時の税率の上昇と、法人化して3年以内の相続時の株価高騰、法人経営の規模が小さい場合のコスト増加です。法人所有のアパートを売却すると、法人税率の影響で税金負担が増えます。また、相続時には法人化による評価の下落が適用されず、高い相続税がかかる可能性があるため注意です。さらに、規模が小さいと法人化にかかる費用が割合として高くなり、経営の効率性が損なわれる恐れがあります。
アパート経営を法人化する目安は?
アパート経営を法人化するのは、課税所得が900万円を超える時が目安になります。なぜなら、課税所得が900万円から1,800万円までの方の個人所得税率が、法人税率よりも高くなるためです。なお、総所得は不動産収入以外の収入が含まれる点に考慮が必要で、総合的な判断が必要になります。
アパート経営を法人化する際の注意点は?
アパート経営を法人化する際の注意点は、設立時に費用が必要な点と時間や手間がかかる点です。法人化には設立費用や税務、会計関連の費用が必要になるため、費用の捻出と予算立てが欠かせません。また、法人を設立するためには登記手続きや書類の作成が必要であり、税務や会計の手続きも時間と手間がかかります。これらの手続きは正確さが求められるため、専門家のアドバイスやサポートが必要です。さらに、会社の組織や運営に関するルールや規定を定める準備も必要になるため、法人化には慎重な計画と準備が求められる点に注意しましょう。
まとめ
本記事では、アパート経営を法人化する場合のメリットやデメリットを紹介しました。アパート経営を法人化するべきかを決める目安も紹介しているので、検討してみてください。

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ