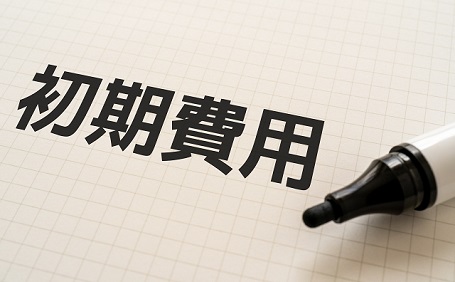アパート経営を始めて30年後に起こりうるトラブルとは?将来のことを見越した戦略が大切

記事の目次
アパート経営を始めて30年後に起こりうるトラブルと対策方法

アパート経営を始める際は、空室問題や金利の上昇リスクなど、月日が経っていなくてもトラブルが起きる可能性があります。しかし、安定した経営をしていても、30年も経てば新たに出てくるトラブルもあります。
ここでは、アパート経営を始めて30年後に起こりうるトラブルを見ていきましょう。
アパート老朽化のリスク
築年数が経つごとに、アパートは老朽化していきます。アパートが老朽化すると、修繕リスクが高まったり、維持費のコストが増えたりなどさまざまな影響がでてきます。具体的なリスクを以下で詳しく見ていきましょう。
コストが増えるリスク
アパート経営を長期間続けていくと、アパートの老朽化や設備の劣化にともない、維持・修繕のためのコストが次々と発生するようになります。築30年を経過したアパートでは、特にこの問題が顕著になってきます。
古い部分の修繕だけでなく、時代に合った新しい設備を追加していく必要もあり、コストがどんどん増大していく可能性も。入居者確保のための広告費などもかさんでくるため、収支バランスが崩れるリスクも高まります。
コスト増大問題への対策は、建て替えやリフォームです。建物の法定耐用年数を過ぎたアパートは、修繕費が収入を上回るため、赤字経営に陥る可能性があります。そのため、取り壊して新築アパートに建て替える、もしくは大規模リフォームをおこない、建物の状態を一新する方法が考えられます。
建て替えやフルリフォームには多額の資金が必要となりますが、再スタートによって、経年劣化にともなうリスクを一気に解消できるでしょう。一方、税金面での影響は大きくなるため、事前に税理士に相談しながら慎重に検討する必要があります。
大規模修繕が発生するリスク
アパート経営を長期的におこなううえで、定期的な大規模修繕への備えは欠かせません。一般的に、アパートは建築後10〜15年を経過すると、建物の劣化が進み、外壁の塗装や屋根の修繕が必要になってきます。
外壁の塗装は単なる美観の問題だけではなく、建物の構造を守るためにも重要な工事です。塗装が剥がれると、外壁そのものの劣化が進み、最悪の場合は通行人に危害を及ぼすリスクもあります。同様に、屋根の修繕も雨漏りを防ぐうえで欠かせません。雨漏りが放置されると、基礎部分の老朽化にもつながるでしょう。
その他にも、ベランダの防水工事や給排水管の点検・修繕など、さまざまな大規模工事が必要になってきます。これらの工事は、見た目の美観はもちろんのこと、建物の機能性や安全性を維持するうえで重要です。
大規模修繕には多額の費用がかかるため、オーナーにとっては大きな負担となるでしょう。さらに、工事の時期によっては人件費や建材価格の高騰など、想定している以上の費用がかかる可能性もあります。場合によっては予算を大きく上回り、経営が苦しくなるケースも少なくありません。
そのため、修繕費用の積み立てを計画的におこない、いざという時に備えておくことが重要です。共益費や修繕積立金の設定など、中長期的な視点から経営計画を立てる必要があります。また、工事の時期や内容を見極め、適切なタイミングで修繕をおこなうことで、コストカットにもつながるでしょう。
アパートの老朽化リスク
アパート経営が長期化すると、建物や設備の老朽化が避けられない問題となります。築年数が経過すると、トイレやお風呂、キッチンなどの水回り設備の汚れや損傷が目立ってきます。
もちろん、入居者が退去する際には原状回復工事がおこなわれますが、長年の使用でどんどん劣化していくため、アパートや室内の古さが目立つようになるのは避けられないでしょう。
アパートの老朽化は、入居者の獲得にも大きな影響を及ぼします。新築や築浅物件に比べ、アパートの老朽化が目立つと、入居希望者から敬遠される傾向にあります。特に、アパートの第一印象を重視する入居者が多いため、外観や室内の印象がよくないと、空室増加につながりかねません。
そのため、修繕や改修をおこなってアパートの魅力を維持することが重要です。なかには、家賃を下げて空室率を下げようと考える方もいるでしょう。しかしこの場合、他の部屋の家賃も下げざるを得なくなり、収益の悪化という悪循環に陥る可能性があります。
適切な修繕や改修をおこない、アパートの状態を良好に保つことで、入居者の獲得と家賃収入の確保が可能になるでしょう。
入居率低下のリスク
築年数が古い物件は退去率が高く、新しい入居者も見つかりづらい傾向にあります。それは、新築時と比較してアパートの競争力が低下しているためです。近隣に新しい賃貸物件ができていれば、築年数を見て新しいほうを選ぶ入居者が多いでしょう。耐震性の面でも、新築のアパートが有利となります。また、賃貸需要が変化している可能性も。築年数が経っても、競争力のあるアパートにするためには、設備を新しくするなどの対策が必要でしょう。
入居者の高齢化
アパート経営で30年も経つと、入居者の高齢化も考慮しなければなりません。なかでも、定年退職後の年金生活者の方などが長期にわたって入居し続けることが考えられるでしょう。
しかし、高齢入居者の方には一定のリスクがともないます。例えば、年金しか収入源がなくて家賃の支払いが滞ったり、体調が悪化して事故が起きたりなどの問題も考えられます。
一方で、高齢入居者は転居が少なく、空室リスクが低いメリットもあります。
高齢入居者にはメリット・デメリットの両面があるため、適切な対策を立てることが重要です。
それ以外にも、一定の年齢に達した入居者には、保証人の確保を義務付けるなどの対策を取ることで、家賃滞納リスクを軽減できます。また、見守りセンサーの設置や、バリアフリー化など、高齢者に配慮した設備投資もおこなうことで入居者トラブルを防ぎ、安定したアパート経営がしやすくなるでしょう。
家賃収入の低下
アパートは、築年数が経つほど資産価値が下落していきます。特に築年数が30年以上にもなると、大幅に価値が下落することも多くあります。
アパートの資産価値が下がると、家賃も安く設定しなければならなくなるため、これまで得られていた収入と比べると大幅に収入が減ってしまうでしょう。
また、経年劣化が進むと、大規模な修繕が必要になるタイミングもあります。その場合は家賃収入のなかから捻出する必要があるため、結果的に家賃収入の低下につながってしまいます。
なお、アパートを売却する際も、築年数が古い物件は売れにくい傾向があるため、場合によっては格安で売却せざるをえないケースも少なくありません。
周辺環境の変化
アパート経営を長期的におこなううえで、周辺環境の変化にも注意が必要です。30年の長期間では、駅の移転や大規模開発、企業・大学の撤退などで、立地条件が大きく変わる可能性があります。
人の流れが変われば、アパートの賃貸需要が低下し、空室率の上昇や家賃下落につながる恐れがあります。立地条件の悪化は、アパート経営にとって致命的なリスクといえるでしょう。
そのため、事前に周辺の開発計画や環境変化を把握しておくことが重要です。自治体のホームページを確認したり、地域情報の収集を定期的におこなったりなど、変化をいち早くキャッチできるように対策しておく必要があります。
大規模な開発計画がわかった場合は、計画に合わせた対応策を早めに検討することが大切です。例えば立地条件が悪化するようであれば、建て替えや用途変更、あるいはアパートの売却などを検討するべきでしょう。
一方で、開発によって立地が良くなる可能性もあります。その場合は、新しい設備投資や改装などをおこなう、変化に応じた対応をとることで、経営の好転が期待できます。
状況をきめ細かくモニタリングし、適切なタイミングで対策をとれるように準備しておきましょう。
サブリース契約のリスク
サブリース契約は、オーナーの経営リスクを大きく軽減できる一方で、長期的な視点では問題が生じる可能性があります。
サブリース契約は一般的に解約することが難しいです。解約が認められたとしても違約金が発生したり、立ち退き料も請求されたりなど、さまざまなリスクがあります。
また、サブリース期間中は定期的に契約内容の見直しがおこなわれるため、家賃保証額の大幅な引き下げを迫られる可能性もあります。新築から10年目くらいを目安に契約内容の見直しがおこなわれることが多いため、30年目となると3回程度の見直しがおこなわれると考えておいたほうがよいでしょう。
サブリース契約のリスクに備えるためには、契約内容を十分に理解し、弁護士などの専門家にも相談しながら検討することが重要です。契約解除時の違約金条項やその他不利な条項がないかを確認し、交渉できる部分がないかを検討する必要があります。
30年後も安定してアパート経営を続けるためのポイント

ここからは、30年後もアパート経営を安定して続けるためのポイントを詳しく解説します。リスクを把握し、事前に対策を立てることで、トラブルが起きても柔軟に対応できるでしょう。
アパート経営を開始する前に立地条件を確認しておく
長期的にアパート経営を安定して続けるうえで、立地条件のよし悪しは重要な要素です。入居者のニーズにマッチした立地を選ばなければ、時間が経つにつれて入居率が低下し、経営が成り立たなくなってしまう恐れがあるからです。
具体的な条件とは、駅からアパートまでの距離が近い立地、保育園・小学校・スーパーマーケットが近いというような生活利便性が高い立地などが挙げられます。ターゲットとする入居者層のニーズを十分に満たせる場所を選ぶことで、たとえ築年数が経過しても賃貸需要は根強く残り、安定した高い入居率が見込めるでしょう。
アパート経営を始める前の準備段階で、専門家のアドバイスを仰ぎながら、ターゲット入居者層とニーズに合う立地はどのようなものなのかを分析することが大切です。
将来を見据えたうえで、最適な立地を見極めることで長期的な経営の安定につながるでしょう。
アパートローンの返済計画を慎重に立てる
アパートローンの融資を受けるには、金融機関に事業計画書を提出しなければなりません。アパートローンでは高額な融資を受ける可能性が高いため、住宅ローンよりも審査基準が厳しくなっています。また、何よりも自分がしっかりアパートローンを返済できるように、準備しておくために返済計画は必要なものでもあります。
なかには、家賃収入を得られるからとフルローンを検討している方もいるでしょう。しかし、アパート経営では大規模修繕費が高額になってしまったり、空室が増えて収入が得られなくなったりなど、アパートローンの返済が厳しくなることも十分に考えられます。また、退去時に入居者トラブルが発生して、計画どおりに返済が進まない可能性もあります。
計画どおりにアパートローンの返済ができなくなったなどの状態にも対応できるように、頭金を多めに用意するなど、将来を見越したうえで資金計画を立てることが大切です。
アパート経営30年後の出口戦略

30年後も安定してアパート経営を続けるためには、将来を見越した出口戦略が重要です。出口戦略をしっかり考えておけば、30年後でも安定してアパートを経営していけるでしょう。
ここでは、30年後も安定してアパート経営を続けるための出口戦略を詳しく解説します。
アパートを売却する
アパートの老朽化が進み、入居者を募るのが難しくなった場合は、売却を検討することをおすすめします。少しでも手元に残す資金を増やして売却したいなら、築30年よりも前に行動したほうがよいです。築25〜29年の間に売却することで、アパート修繕費の負担が減るため、余計な出費を抑えられるでしょう。
ただし、古くなった建物はなかなか売れにくい現実もあります。その場合は、内装やインフラのリフォームで建物の価値を高めるのも一つの手です。とはいえ、資金に余裕がある場合に効果的な方法なので、資金に余裕がない場合は、不動産管理会社などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
アパートを建て替える
立地条件に恵まれた土地であれば、古いアパートを建て替えることで収益アップを狙えます。新築アパートならば需要が根強く、古いアパートを継続するよりも家賃水準を上げられるため、キャッシュフローの改善が期待できるからです。
また、相続対策として不動産を活用する場合、建て替えた新築物件は評価額が抑えられるため、売却して現金化するよりも節税メリットが大きくなる可能性があります。
ただし、立退き交渉をしたり、もう一度アパートローンを組んだりなど、建て替えには課題もあります。専門家に適切にアドバイスを受けながら、総合的に判断しましょう。
アパート解体後に土地を売却する
賃貸需要が見込めないと判断した時は、アパートを解体して更地の状態で土地を売却するのも選択肢の一つです。建物に価値が見込めない場合、更地のほうが土地の資産価値を高く評価してもらえる可能性が高くなります。
ただし、入居者がいる場合は退去交渉をしなければなりません。退去交渉にはトラブルがつきものです。退去交渉に時間がかかると、希望の時期に売却できない可能性があります。不動産会社や管理会社とあらかじめ相談し、計画的に進めることが大切です。
また、更地のままでいると住宅地特例の適用がなくなり、固定資産税・都市計画税の税負担が大幅にかさむデメリットもあります。固定資産税は最大6倍、都市計画税は3倍まで上がる可能性も。
節税を考えるなら、取り壊し時期には注意しなければなりません。
リフォーム・リノベーションで資産価値を向上させる
賃貸アパートは新しい物件ほど人気が高く、築年数の経過とともに相対的な資産価値が下がっていく傾向にあります。古くなったアパートの価値を維持・向上させるには、リフォームやリノベーションによる改修が有効的です。
具体的には、トイレ・浴室・キッチンなどの古くなった水回り設備の一新や、現代的な居住スタイルに合わせた間取り変更などのリノベーションが挙げられます。さらに外壁の塗り替えや防犯カメラの設置などで、外観や防犯性能の向上を図るのも有効でしょう。
リフォームには一定の費用がかかりますが、設備の一新や資産価値の向上を考えれば、必要な投資といえます。家賃を設定する際は、大規模修繕費を考慮して資金計画を立てましょう。
また、費用が20万円以上、かつ資産価値や耐久性が明らかに向上する修繕に関しては、「資本的支出」となります。資本的支出は減価償却の対象となるため、確定申告に役立つでしょう。
30年後も保有する
家族に代々と土地を継承していきたい場合は、将来的に家族が使いやすい形での土地活用を心がける必要があります。
例えば短期から中期の活用プランとして、賃貸併用住宅や二世帯住宅を建設し、のちに一戸建て住宅にリノベーションするなどの選択肢があります。もしくは全住戸を賃貸に切り替える運用も可能です。
より長期的なスパンで経営を見据えるなら、鉄筋コンクリート造マンションを建設するのも一つの手です。初期投資は大きくなりますが、50年以上にわたり家族に住まいと収入をもたらせるでしょう。
また、周辺環境の変化に合わせて、店舗併設住宅やビル経営に転用することも。将来的に家族がほぼ持ち家に住むようであれば、地域貢献の観点から福祉施設(グループホーム・老人ホームなど)の運営も選択肢に挙げられます。
今後30年の間には、現時点で想定できない新たな活用法が生まれている可能性もあります。いずれの方法でも、土地には可能な限り住居を残しておき、無用な固定資産税の負担がかからないように対策しておくことをおすすめします。
現在から30年後のアパート経営の予想図

今から30年後のアパート経営はどうなるのでしょうか。本章では考えられることを2つご紹介します。
外国人の増加
今後、日本では外国人労働者や留学生の増加にともない、アパートの入居者にも外国人が増えていくことが予想されます。
外国人入居者の場合、日本人とは生活習慣や文化が異なるため、問題が発生するリスクが高いです。例えば、靴のままでの生活や頻繁な家庭内パーティー、ゴミの分別ルールを理解しない、無断での同居者の増加などが考えられます。
このような問題が発生すると、日本人入居者とのトラブルにつながり、結果的に空室リスクや家賃下落リスクの増加にもつながるでしょう。
重要なのは、不動産管理会社の選定です。外国人入居者への対応実績があり、多言語対応が可能な会社を選ぶとよいでしょう。
さらに、外国人向けの生活ルールを明記した入居マニュアルの作成や、ペナルティ条項の設定など、契約面での対策も必要です。入居時の事前説明や、違反時の厳格な対応も欠かせません。
外国人労働者の増加は避けられない傾向なので、柔軟に対応していくことが求められます。
賃貸市場の縮小
厚生労働省によると、2070年代になると、日本の人口は9,000万人を割るといわれています。また、人口の4割にあたる約3,600万人が65歳以上の高齢者になるとされていました。
このまま日本の人口減少が進めば、30年後にはアパートを借りる人の市場規模が大きく減退し、アパートの需要が少なくなることも考えられます。アパートの需要は人口の多さとも関係しているため、日本の少子高齢化および人口減少の動向も把握しておかなければなりません。
アパート経営は長期的な視点でおこなわなければなりません。出口戦略も考えたうえで、よく検討しましょう。
まとめ
30年後も安定したアパート経営を続けるためには、将来のことも見据えたうえで計画を立てる必要があります。30年後には社会情勢や周辺環境がどのように変化しているのか、予想を立てることで、立地選びにも役立てられるでしょう。
また、長期間のアパート経営では建物の老朽化も考慮しなければなりません。大規模な修繕が必要になった際に、どれだけの費用がかかるのかをあらかじめ計算しておくことで、維持管理費も貯めやすくなるでしょう。
本記事では、30年後もアパート経営を安定して続けるためのポイントや出口戦略もご紹介したので、ぜひ参考にしてみてください。

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ