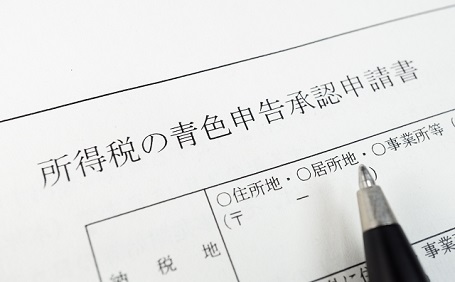不動産投資における金利上昇リスクとは?万が一の時のために準備しておこう

しかし、不動産投資には金利市場の動向に左右されるリスクがあります。金利が上昇した際のリスクを把握しておかなければ、不動産投資ローンの返済や投資物件の経営に影響が出てしまうかもしれません。
本記事では、不動産投資の金利上昇リスクを詳しく解説します。金利が上昇するとどうなるのか、金利上昇リスクに備えた対策方法などもまとめるので、ぜひご参考ください。
記事の目次
不動産投資における金利上昇リスクとは

金利の上昇は、不動産投資では深刻なリスク要因となります。金利が上昇すると、オーナーの収支に直接的な影響を与えるだけでなく、不動産市況全体の減速にもつながるため、慎重な対応が求められるのです。それでは、具体的にどのようなリスクとなるのか、以下で見ていきましょう。
キャッシュフローが悪化する
不動産投資では、借り入れたお金で投資物件の購入資金を賄うのが一般的です。金利が上昇した場合、月々の返済負担が増え、家賃収入から得られる純利益が減ります。
例えば、2,000万円の不動産投資ローン(期間35年)で、金利が2.5%から3.0%に上昇すると、月々の返済額は約5,500円も増加します。
このように金利変動は、キャッシュフローに直接影響を与えます。
投資を始める時から十分な余裕をもって資金を確保しておかなければ、金利が上昇した際に不動産投資ローンの返済が困難になる可能性があります。自己資金を抑えたフルローン購入では、このリスクがより高くなるため、慎重に検討しなければなりません。
資産価値が下落する
金利上昇は不動産需要の低迷を招き、結果として資産価値の下落リスクにもつながります。金利が上がれば、新規購入層の購買力が低下するため、不動産の売買自体が減少傾向に。
需要の減少は供給過剰につながり、価格競争が生じて不動産価格が下落する要因にもなるのです。
投資物件の所有者にとって、期待した価格で資産を売却できないリスクがあり、キャピタルゲイン獲得の障害にもなります。キャピタルゲインとは、所有している不動産を売却することによって得る利益のことです。
日本の金利動向

日本銀行が2024年3月19日の金融政策決定会合で、「2%の物価安定の目標が持続的・安定的に実現していくことが見通せる状況に至った」と判断したうえで、マイナス金利政策を解除しました。
階層型の日銀当座預金制度を廃止し、2016年にマイナス金利政策を導入する以前の当座預金(所要準備と超過準備)に戻し、そのうえで超過準備への付利金利を+0.1%としました。
長らく続いてきた超低金利環境が変化しつつあります。国債金利の上昇にともない、固定金利はすでに値上がりしている状況です。
マイナス金利政策が解除されたため、変動金利の上昇も避けられない状況となっています。
アメリカの影響力
日本の金融政策には、常にアメリカの影響が色濃く反映されてきました。新型コロナウイルス禍からの経済回復を背景に、アメリカでは大幅な金利引き上げを実施。
アメリカと日本が経済的に密接な関係にあることから、アメリカの金利上昇は日本にも相当な影響を及ぼすと考えられています。
国際情勢の影響
世界の政治的な混乱も、日本の金融動向に大きな影響を及ぼす要因の一つです。ロシアによるウクライナ侵攻や長年の懸案であるイスラエル・パレスチナ問題など、地政学的なリスクの高まりは、原油をはじめとするエネルギー価格の高騰を招きました。
エネルギー価格の上昇は、国内の物価を押し上げるインフレ要因にも。日本銀行には、インフレ抑制のための金利引き上げ措置が求められる可能性が出てくるでしょう。その際には、不動産投資でも不動産投資ローン金利の上昇は避けられません。
不動産投資を始める際のポイント・注意点

これから不動産投資を始めようとする方は、特に慎重な計画が欠かせません。金利上昇の影響を見据え、不動産投資ローンの返済計画を綿密に立てる必要があります。さまざまなシミュレーションをおこない、いざという時の状況変化に備えることも大切です。
ここからは、不動産投資を始めるうえでのポイントや注意点をご紹介します。
頭金を多めに確保する
不動産投資ローンを組む際は、できる限り頭金を多めに用意しておきましょう。頭金の額が多いほど、利息負担が低減され、月々の返済額を抑えられます。
例えば、次の場合をシミュレーションしてみましょう。
<条件>
借入金額:2,000万円
返済期間:35年
返済方式:元利均等返済
金利:1.0%
この条件で、頭金を100万円と500万円の場合で比較してみます。
| 頭金 | 月々の返済額 | 返済総額 |
|---|---|---|
| 100万円の場合 | 5万3,634円 | 2,252万6,399円 |
| 500万円の場合 | 4万2,343円 | 1,778万3,999円 |
比較してみると、500万円のほうが、月々の返済額は約1万1,000円も少なくなることがわかります。
とはいえ、月々の返済負担を減らしたいからと無理に頭金を捻出すると、生活費に影響が出てしまうため注意が必要です。頭金を多く入れた分だけ月々の返済額が減りますが、生活資金を十分に確保したうえで、どの程度の頭金を算出できるかを検討しましょう。
低金利の不動産投資ローンを選ぶ
月々の返済負担を軽減するには、低金利の不動産投資ローンを組むことが重要です。金利が少し違っただけで、返済総額が100万円以上開く可能性があります。審査の通過しやすさも加味しつつ、複数の金融機関を比較検討することがおすすめです。
一般的に、メガバンクや大手都市銀行は変動金利で1〜2%程度と低金利ですが、審査は厳しい傾向があります。
一方、地方銀行などの中小規模の金融機関では2〜3%程度と高めの金利となりますが、審査に通りやすい傾向があります。
それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の資産や状況に合わせて、不動産投資ローンの種類を選びましょう。
金利上昇に備えた金融機関のルールを確認する
不動産投資ローン返済中に金利が上昇した際、借り手の急激なキャッシュフロー悪化を防ぐため、金融機関ではいくつかの対応ルールが設けられています。代表的なものが「5年ルール」と「1.25倍ルール」です。金融機関のルールを適用することで、返済額の値上がりによる生活への影響を一時的に緩和できるでしょう。
5年ルールとは、金利上昇で不動産投資ローンの返済額が増額した場合でも、最初の5年間は従来どおりの返済額に据え置くというルールです。増額分は、6年目以降の返済額に上乗せされます。金利変動の影響をいったん凌ぐことで、借り手の生活への急激な圧迫を回避できるメリットがあります。
一方で、6年目以降の返済額が大幅に増額されるため、それに備えた事前の対策が必要です。5年間の猶予期間を有効活用し、増額分の返済を滞りなく済ませるための準備を怠らずにおこなうことが重要です。5年の間にコツコツ貯金したり、資産を運用したり、副業したりなどして、資金を用意しておきましょう。
1.25倍ルール、または125%ルールと呼ばれるこの対応策は、上限額を設けることで返済額の急増を抑制するものです。1.25倍ルールが適用されると、金利上昇後の返済額は従来額の1.25倍を超えない範囲に収められることになります。
例えば、これまで月10万円の返済をおこなっていた場合、金利変動後も最大で12.5万円までの増額に留まります。いきなり返済負担が大きくなるのを抑えられるため、精神的・経済的ともに安心感が得られるルールです。
ただし、5年ルール・1.25倍ルールにはともに重要な注意点があります。5年ルール・1.25倍ルールはすべての金融機関で設けられているわけではなく、適用されない場合もあります。
また、ルールが適用されても増額分の支払いが先送りされるだけで、総返済額への影響は避けられません。未払い金利の割合が大きくなれば、長期的には多額の返済が求められる可能性があります。
金融機関ごとのルールの有無と内容を、あらかじめ確認しておくことが大切です。
不動産投資ローンの返済期間を長期間に設定する
不動産投資ローンでは、返済期間を長期に設定するのも有効です。不動産投資ローンの返済期間を長めに設定することで月々の返済額が減少し、資金繰りが楽になるメリットがあります。
一度設定した返済期間は短縮できても延長はできないため、最初は余裕を持たせておくといいでしょう。最初から期間を短くすると、状況によっては返済が難しくなることもあるかもしれません。将来的に自己資金に余裕ができれば、繰り上げ返済などで期間を短縮できるため、最初の返済スケジュールは余裕を持たせるのがおすすめです。
ただし、返済期間が長いほど、支払う利息総額は増加します。繰り上げ返済ができれば利息の負担を減らせますが、そのまま長期のスケジュールで返済する場合は利息の負担が増えることを頭に入れておきましょう。
すでに融資を受けている方の金利上昇リスクを抑えるポイント

すでに不動産投資ローンを利用中の方も、今後の金利上昇リスクに備える必要があります。ここでは、すでに融資を受けている方の金利上昇リスクを抑えるポイントをご紹介します。
変動金利から固定金利へ切り替える
変動金利での借り入れをおこなっており、今後の金利上昇を危惧している場合は、固定金利への変更を検討してみましょう。ただし、金利引き上げ時期は事前に明らかにされることはありません。
金利の引き上げが公表されると、固定金利に変更したとしても引き上げ後の利率が適用されます。このリスクを回避するには、金融機関に早めに相談し、タイミングをしっかり見極めたうえで切り替えることが大切です。
不動産投資ローンを借り換える
不動産投資ローンの借り換えも有効です。賃貸経営が順調に推移しており、運用実績を提示できる場合は、投資物件購入時よりも、比較的簡単に低金利での融資承認を得られる可能性があります。
特に残りの返済期間が長ければ、借り換えにより総返済額を大幅に削減できるかもしれません。
ただし借り換えには、金融機関への手数料などの諸経費が別途かかります。また金融機関は、顧客の借り換えを好まない傾向があるため、借り換えを検討していると伝えると、現状の利率よりも下げてもらえるケースも。しかしあくまでも一例なので、借り換えを検討していることを伝えても、利率を下げてもらえないことを前提に行動しましょう。
自己資金を活用して繰り上げ返済をする
手元に残しておいた自己資金を有効活用し、繰り上げ返済をおこなえば、金利上昇によるダメージを最小限に抑えられます。ただし不動産投資には、空室や修繕、災害などのリスクが常に付きまとうものです。
そのため、繰り上げ返済をおこなう際は、不測の事態に対処できる十分な資金を確保したうえで、余剰分のみを繰り上げ返済に回すことがポイントです。
また、将来的に投資物件を増やす考えがある場合は、追加物件の購入資金に必要な自己資金の用意も並行しておこなう必要があります。これらのバランスを慎重に考慮し、繰り上げ返済を検討してみましょう。
売却によって不動産投資ローンを完済する
金利上昇は不動産投資に大きな打撃を与えるリスク要因です。そのため、投資物件を売却して不動産投資ローンの返済を完済するのも、リスク回避の選択肢の一つです。
金利上昇と不動産価格の下落には、必ずしも直接的な因果関係はありませんが、長年の低金利政策により不動産の価格は上昇傾向をたどってきました。
しかし、この流れに逆らうように、金利の引き上げが実施されれば、やがて物件価格は下落していくでしょう。
金利上昇の動きが見られた場合は、物件価格が底値まで下落する前に売却し、不動産投資ローンを完済することをおすすめします。特に、昨今は新型コロナウイルスやロシアによるウクライナ侵攻の影響で、光熱費や生活必需品が大幅に値上がりしたり、住宅ローンの審査がより厳しくなるなど、生活にも大きな影響を及ぼしています。
生活にかかる費用が増えたため、買主探しに時間がかかることが考えられます。スムーズに売却できたとしても、3カ月から半年程度かかるため、早めに行動することが大切です。
遅れれば遅れるほど、有利な条件での売却が難しくなる恐れもあるため、売却タイミングを逃さないようにしましょう。
まとめ
本記事では、不動産投資の金利上昇リスクを詳しく解説しました。2024年3月19日にマイナス金利政策の解除が発表され、今後の金利上昇リスクが高まっています。いざ金利が上昇した際の影響を最小限に抑えるためにも、しっかり金利上昇のリスクを理解しておくことが大切です。
そのうえで、不動産投資ローンの借り替えをおこなったり、繰り上げ返済をおこなったりなど、自分の状況に合わせて対策しなければなりません。ぜひ今回の記事を参考に、金利上昇リスクに備えた対策を今からでも準備しておきましょう。

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ