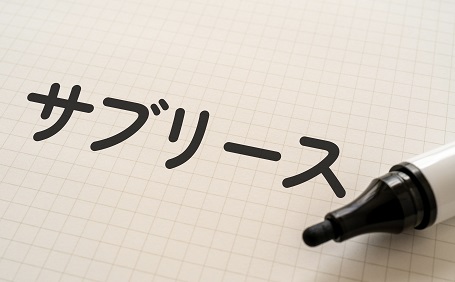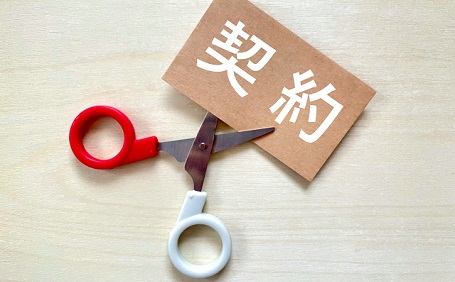サブリース新法で何がどう変わった?導入された背景や義務化されたものなどをわかりやすく解説

記事の目次
サブリースとは

サブリース新法について知る前に、サブリースとは何なのか、基本的な知識を押さえておきましょう。
サブリースの仕組み
サブリース契約とは、まずオーナーが所有する投資物件を、サブリース会社が一括で借り上げます。そして、サブリース会社がその物件の入居者の募集をおこない、家賃を回収。オーナーには、回収した家賃からサブリース会社への手数料を引かれた分が支払われます。手数料の相場は、家賃の1〜2割程度。例えば、投資物件の家賃が10万円であれば、オーナーの手元に入る収入は8〜9万円です。
サブリースのメリット

サブリースのメリットも確認しておきましょう。
安定した家賃収入が見込める
サブリースのメリットは、安定した家賃収入が見込めることです。サブリースでは、オーナーがサブリース会社に投資物件を貸している状態のため、空室状況に関わらず、一定の家賃収入を得られます。一般的な管理契約では、空室があれば、その分家賃収入が減ってしまいます。もし家賃を滞納されれば、家賃収入が得られません。しかし、サブリースでは空室リスクを抑えつつ、一定の家賃収入が確保できます。
管理業務を委託できる
管理業務を委託できることも、サブリースのメリットです。通常の賃貸経営では、入居者の募集や契約手続き、クレーム対応など、さまざまな管理業務が発生します。しかし、サブリースでは、これらの管理業務をサブリース会社に委託できるため、オーナーの手間がかかりません。専門的な知識があり、経験が豊富なサブリース会社であれば、オーナー自身で管理するよりも安心して任せられるでしょう。
相続税対策になる
サブリースは、相続税対策になることも一つのメリットです。もともと、投資物件は人に貸し出していることから、通常よりも相続税評価額が低く評価されます。さらにサブリースの場合、サブリース会社に一棟を丸ごと貸し出しているため、満室であると仮定して相続税を計算。自宅を所有している場合と比較して、相続税評価額は8割ほど低くなります。
サブリースのデメリット

サブリースは、オーナーの手間がかからず、一定の家賃収入が見込めるため、メリットが多いように見えます。しかし、一部ではトラブルが発生しているように、デメリットも多々あります。本章では、サブリースのデメリットを見ていきましょう。
賃料が減額される可能性がある
サブリースのデメリットは、賃料が減額される可能性があることです。周辺の賃料相場が下落したり、投資物件の入居率が下がったりした場合は、賃料が減額されるかもしれません。賃料が減額されれば、賃貸経営が厳しくなるおそれもあるでしょう。投資物件の立地や賃貸需要、サブリース会社の経営状態など、さまざまな視点からサブリースを検討することが大切です。
入居者を選べない
メリットでお伝えしたように、サブリースでは、管理業務をサブリース会社に委託します。入居者の募集・契約もサブリース会社に委託するため、オーナー自身が入居者を選べません。なぜ、選べないことが問題になるのでしょうか。それは、家賃滞納のリスクがある人が入居したり、知らない間に別の会社に貸し出されたりする可能性があるからです。
もし、サブリースを解約した際、オーナーが管理業務を引き継ぎます。その際、問題のある入居者がいれば、オーナーが対応をしなければなりません。特に家賃滞納は経営面だけでなく、精神面でもダメージが大きくなります。入居者を選べないことは、賃貸経営のリスクが高くなることを理解しておきましょう。
オーナーからの解約が難しい
サブリースは、正当な事由がなければ、オーナーからの解約が難しくなっています。サブリースは借地借家法が適用され、借主であるサブリース会社が保護されているためです。オーナーから解約する場合は、一定期間前に通知をしなければなりません。また、契約内容によっては、違約金を支払わなければならないことも。サブリースはオーナーの意思で自由に解約できないため、利用するか、慎重に判断しましょう。
サブリース新法とは

サブリース新法とは、2020年6月に国会で成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の通称です。サブリース契約の適正化のために、必要な規則が設けられました。なぜサブリース新法が施行されたのか、背景を詳しく解説します。
サブリース新法が施行された背景
国土交通省の「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律について」によると、管理業務を委託しているオーナーは2018年度で約8割。また、全国消費生活情報ネットワークに寄せられた、サブリースを巡る相談件数も増加していました。サブリースでは、オーナーが家賃保証を中心に契約条件を誤認したことによるトラブルが多発していたのです。
国土交通省の「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査(家主)」によると、実際にあったトラブルとして、次のようなものが挙げられています。
- 契約の途中で大幅な賃料減額などの予期せぬ条件変更を求められた
- 物件の収入や費用、契約内容の変更条件などに関する十分な説明がないまま契約を求められた
また、同アンケート調査では、サブリースを契約しているオーナーのうち、サブリースを前提として投資物件を購入した方が7割以上であることもわかりました。
これらのことから、トラブルを未然に防ぐためサブリース新法によって、サブリース会社の勧誘時や契約締結時に一定の規制が導入されることになったのです。同時に、不動産業界の健全な発展・育成を図るため、賃貸住宅管理業の登録制度が創設されました。
サブリース新法の内容

オーナーの知識不足を利用して、サブリース会社にとって有利な条件で契約されていたり、契約条件における認識の相違からトラブルが多発。そういった状況を変えるため、サブリース新法によって勧誘時や契約締結時に一定の規制が導入されることになりました。それでは、具体的に何が規制されているのでしょうか。本章では、サブリース新法で規制されている内容について、わかりやすく解説します。
誇大広告等の禁止
誇大広告等の禁止とは、事実と異なる表示や、実際のものより優良、あるいは有利であるような表示をおこなうことを禁止するものです。オーナーになる方は、賃貸経営の経験や専門知識が豊富であるとは限りません。サブリース会社がそれを利用し、賃貸経営のリスクを小さく見せた場合、オーナーは広告の真偽を判断できないでしょう。
例えば、サブリース会社が支払うべき家賃や賃貸物件の管理方法、契約の解除に関する事項などについて、誇大広告がされている可能性があります。具体的な内容としては、次のようなものが挙げられます。
- 「○年家賃保証!」「契約期間内は確実に保証!収入が下がりません!」などと表示をし、該当する期間の家賃収入が保証されているかのように表示している
- 休日や深夜は受付業務のみ、または対応しないにも関わらず、「入居者のトラブル対応を24時間体制でおこなっている」と表示をしている
- 毎月オーナーから一定の費用を徴収し、原状回復費用に当てているにも関わらず、「原状回復費の負担はなし」といった表示をしている
誇大広告が禁止されたことにより、オーナーはより正確な情報に基づいて、投資判断ができるようになりました。しかし、サブリース契約はデメリットもあるため、契約条件を慎重に確認し判断しましょう。
不当な勧誘等の禁止
国土交通省がおこなった調査では、サブリースを前提として勧誘されていることが明らかになりました。そこで、サブリース新法によって、サブリース会社が誤った情報や不正確な情報による勧誘、オーナーの意思決定を歪めるような勧誘が禁止されました。例えば、故意に事実を告げない、または事実ではないことを告げる行為です。具体的な行為としては、次のようなことが該当します。
- 将来の家賃減額のリスクがあることや契約期間中であっても、サブリース会社からの契約解除の可能性があることを伝えず、メリットばかりを伝えるような勧誘をする
- 原状回復費用をオーナーが負担する場合があるにも関わらず、「原状回復費用はサブリース会社がすべて負担する」と伝える
これまで、オーナーが契約内容を十分に理解できないまま、契約を結んでしまうことがありました。しかし、サブリース新法で不当な勧誘を禁止することで、オーナーが契約内容を冷静に判断できるようになり、契約の透明性が高まりました。
重要事項説明の義務化
サブリース新法では、誇大広告や不当勧誘の禁止だけではなく、重要事項説明をおこなうことが義務付けられました。賃貸住宅に住んだ経験のある方であれば、契約前に重要事項の説明を受けたことがあるでしょう。
重要事項説明とは、サブリース契約の締結にあたり、家賃の改定条件や契約の解除条件などの契約内容を書面で交付し、説明することです。オーナーが契約内容を正しく理解したうえで、適切な投資判断ができるよう、義務付けられました。重要事項説明を義務付けることで、サブリース会社とオーナー間の認識の相違によるトラブルの発生防止を図っています。
違反者への罰則
サブリース新法では、違反者に対して罰則も設けられました。罰則が設けられたことで、サブリース会社は法令を遵守するようになり、禁止行為が抑制されることを期待できます。例えば、不当な勧誘等の禁止に違反した時、6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれを併科となります。
賃貸経営でサブリースを利用する際のポイント

サブリース新法で、誇大広告や不当な勧誘などが禁止されました。しかし、国土交通省がおこなった「賃貸住宅管理業者等への全国立入検査結果(令和5年度)」によると、立入検査をした179社のうち、106社に是正指導がおこなわれています。指導率は59.2%と高く、サブリース会社もサブリース新法を十分に理解しているとはいえない状況です。オーナー自身も知識を身に付け、適切な投資判断をおこなう必要があります。そこで本章では、賃貸経営でサブリースを利用する際のポイントを見ていきましょう。
サブリースが必要かをよく検討する
まず、賃貸経営をするにあたって、サブリースが本当に必要なのかを検討しましょう。これまで見てきたように、サブリースには安定した家賃収入を得られる、管理業務を委託できるといったメリットがあります。しかし、手数料があるため家賃収入が低くなる、オーナーからの契約解除が難しいといったデメリットがあることも事実です。また、管理委託方式で経営することもできます。賃貸経営をするうえで、サブリースが適切なのか、事前によく考えましょう。
サブリース会社の実績を調べる
サブリース会社を選ぶ際には、経営状況や賃貸管理の実績をよく調べましょう。安定した賃貸経営をおこなえるかは、サブリース会社の実力によります。インターネットや他の投資家などから、口コミや評判を調べておきましょう。
また、サブリース新法が施行されたのと同時に、「賃貸住宅管理業者の登録」が義務付けられました。ただし、管理戸数が200戸未満の場合は、任意登録とされています。サブリース会社が登録されているかは、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で検索できます。登録をしている会社であれば、信頼性は高いでしょう。
複数のサブリース会社を比較検討する
サブリース契約を考えているのであれば、複数社を比較検討しましょう。サブリース会社によって、管理内容や手数料などは異なります。トラブルが発生した場合の対応も、サブリース会社を選択するうえで、重要な要素となるでしょう。複数社を比較することで、よりよい条件で契約を結ぶことができます。
サブリース契約の条件をよく確認する
サブリース契約は一度締結すると、簡単に解除できません。そのため、契約を締結する前に、契約条件をしっかりと確認しましょう。特に確認すべき項目は、契約期間、手数料、解約時の違約金・条件などです。先述したように、サブリース会社もまだ十分にサブリース新法を理解しているとは言いがたい状況です。重要事項説明書を隅々まで確認しましょう。もし、勧誘時や契約締結時に違反行為を見つけた場合は、国土交通省の「賃貸住宅管理業法ポータルサイト」から申し出をおこない、適切な措置を求めることができます。
サブリース新法に関するよくある質問
サブリース新法に関するよくある質問をまとめました。
サブリース新法の重要事項説明はいつから?
サブリース新法は、2020年12月15日に施行されました。施行とは、計画を実行に移すこと。そのため、重要事項説明も2020年12月15日から義務付けられています。
サブリース新法の対象となる会社は?
サブリース新法の対象となるのは、サブリース会社だけではありません。サブリース会社から委託を受けて勧誘をおこなう人も対象となります。具体的には、建設会社や不動産会社、金融機関、ファイナンシャルプランナー、コンサルタントなどです。サブリースの勧誘をおこなっていれば、サブリース会社からの依頼の形式や、資本関係は問われません。サブリース会社だけでなく、勧誘をおこなう人も対象となることを理解しておきましょう。
サブリース新法で義務化されるものは?
サブリース新法では、重要事項の説明が義務化されました。サブリース契約を締結する前に、重要事項が説明されることで、オーナーは契約内容を正しく理解できるようになり、認識の相違によるトラブル発生の防止にもつながります。
まとめ
サブリースでは、法整備がされていなかったことから、契約条件の認識相違によるトラブルなどが多発していました。そこで、オーナーが正確な情報をもとに契約を進められるよう、定められた法律がサブリース新法です。サブリース新法によって、不当な勧誘や誇大広告が禁止されました。しかし、サブリース会社や勧誘者への浸透率は決して高いとはいえません。オーナー自身も、サブリースやサブリース新法に関する知識を学び、適正に判断する姿勢が求められます。サブリース会社や勧誘者の言葉を鵜呑みにするのではなく、正しい知識をもとに、慎重に判断しましょう。

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ