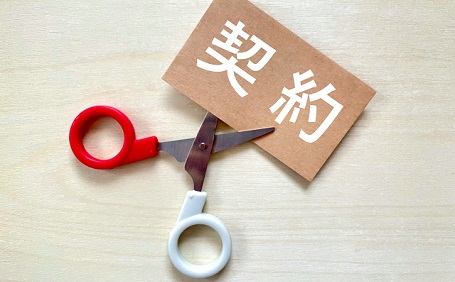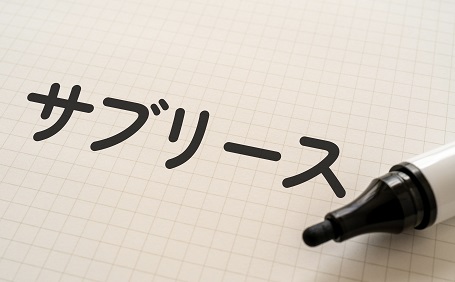サブリース契約は後悔する?「やめとけ」と言われる理由とは

不動産投資を成功させるためには、契約内容を十分に理解し、リスクやメリットを把握することが重要です。本記事では、サブリース契約は本当に後悔するものなのか、その仕組みや「危険」と言われる理由、後悔しないためのポイントを詳しく解説します。
記事の目次
サブリース契約とは

サブリース契約とは、オーナーが所有する賃貸物件をサブリース会社が一括で借り上げ、第三者に貸し出す転貸借契約のことです。サブリース会社がオーナーから物件を借り、入居者と賃貸契約を結ぶ仕組みを指します。そのため、オーナー自身が直接入居者とやり取りすることはありません。
サブリース契約の仕組み
サブリース契約では、サブリース会社がオーナーの所有する物件を借り上げ、オーナーに一定のリース料を支払います。オーナーに代わって入居者の募集、賃貸契約の締結、クレーム対応、退去時の手続きなど、管理業務の大部分をサブリース会社が担うことが特徴です。
そのため、オーナーは手間をかけずに賃貸経営をおこなえます。
契約期間はサブリース会社によって異なり、2年ごとに更新される短期契約から、10年以上の長期契約までさまざま。なかには30年契約のプランもありますが、一定期間経過後に年単位で更新されるケースもあります。
ただし、サブリース契約には「免責期間」と呼ばれる、家賃保証が適用されない期間が設けられている場合もあります。免責期間中は、入居者が決まってもオーナーに家賃が支払われないため、契約内容を事前にしっかり確認することが大切です。
サブリース契約の種類
サブリース契約には、「家賃保証型」と「パススルー型」の2種類があります。一般的にサブリース契約は家賃保証型を指すことが多いですが、パススルー型を採用しているサブリース会社も存在します。
家賃保証型は、サブリース会社がオーナーに対して一定の賃料を支払う仕組みのこと。たとえ空室が発生しても、毎月の収入が安定するため、賃貸経営のリスクを軽減できるメリットがあります。
一方で、サブリース会社が設定する保証賃料は、実際の家賃相場よりも低めに設定されることが多いため、収益性には注意が必要です。
パススルー型は、入居状況によってオーナーの収入が変動するタイプのサブリース契約です。満室時には家賃保証型よりも多くの収益を得られる可能性があります。しかし、空室が増えるとその分収入も減るため、リスク管理が求められるでしょう。
管理委託との違い
サブリース契約の仕組みを理解するには、同じく賃貸経営のサポートを受けられる「管理委託」との違いも把握しておく必要があります。サブリース契約と管理委託では、契約の主体や管理業務の範囲が異なるため、それぞれの特徴を比較しながら、自分に適した方法を選ぶことが重要です。
管理委託とは、賃貸物件の管理業務を専門の管理会社に依頼する方法です。サブリース契約とは異なり、オーナー自身が入居者と賃貸契約を結ぶため、収益のコントロールをしやすい点が特徴。
サブリース契約では、オーナーとサブリース会社の間で賃貸借契約が交わされ、実際に入居者と契約を結ぶのはサブリース会社です。一方、管理委託の場合は、オーナーと入居者が直接契約を交わし、管理業務のみを管理会社に委託する形態です。
さらに、サブリース契約には家賃保証があるのに対し、管理委託では家賃保証がありません。空室時には家賃収入がゼロになる可能性があるため、賃貸経営のリスクをしっかりと理解したうえで、自分に合った経営方法を選択しましょう。

- 不動産経営における委託管理とは?サブリースとの違いや費用相場を解説
- 不動産経営をするにあたり、どのように管理をおこなうのか、悩んでいる方もいるでしょう。そもそも、「どういった業務があるのか
続きを読む

サブリース契約が「やめとけ」と言われる理由

サブリース契約には一定のメリットがあるものの、オーナーにとってはリスクをともなう契約であることも事実です。特に、サブリース会社は「借地借家法」によって守られているため、契約を交わしたあとに想定外のトラブルが発生するケースが少なくありません。
契約内容をよく理解せずに締結すると、収益を思うように得られないばかりか、経済的な負担を抱える恐れもあります。
ここでは、サブリース契約は「やめとけ」と言われる理由を詳しく解説します。
一度契約すると解約が難しい
サブリース契約は一度契約すると、解約が難しい点がデメリットとして挙げられます。これは、サブリース会社が借地借家法に基づき、「借主」としての権利を持つためです。
一般的な賃貸契約では、貸主側からの解約には正当な理由が必要です。サブリース契約でもこの原則が適用されるため、オーナーが契約解除を希望しても、サブリース会社が契約の継続を望めば、それに従わざるをえない場合も。
また、契約内容によっては違約金が発生するケースもあり、解約するために高額な費用を負担しなければならないこともあります。契約前には、解約条件や違約金の有無をしっかり確認することが大切です。
賃料が下がるリスクがある
サブリース契約では「家賃保証」があるため、一定の収入が確保されると考えがちですが、実際には保証額が下がる可能性もあります。サブリース会社が物件の築年数や周辺環境の変化を理由に、家賃の減額交渉をできるためです。
特に、賃貸市場の相場が下がった場合、サブリース会社は契約更新時に家賃を引き下げる交渉を持ちかけてくることも。その結果、オーナーが想定していた収入よりも実際に得られる金額が少なくなってしまうこともめずらしくありません。
契約時に「一定期間は家賃の減額なし」の条件が盛り込まれている場合もありますが、永続するわけではありません。長期的に見ると、収益が減少する可能性があることを理解しておきましょう。
修繕費用やリフォーム費用の負担が発生する
賃貸経営では、物件の維持管理が欠かせません。サブリース契約でも、修繕やリフォームの費用はオーナーが負担することが一般的です。
問題は、サブリース会社が修繕業者を選定するため、相場よりも高い費用が請求されたり、不必要な工事がおこなわれたりする可能性があることです。オーナー側で修繕業者を選べない契約になっている場合、費用の透明性に不安が残るでしょう。
物件の老朽化は避けられないものの、修繕費用がかさむと収益を圧迫するようになります。契約時に修繕費用の負担範囲を明確にし、費用の妥当性を確認できる仕組みを作っておくことが大切です。
免責期間によって収入が減少するリスクがある
サブリース契約には「免責期間」が設定されている場合があります。免責期間とは、入居者が退去した際に一定期間、オーナーへの家賃保証がストップする仕組みのことです。
例えば、免責期間が3カ月と定められている場合、入居者が1月に退去すると、その後の2月〜4月の間は家賃収入がゼロになります。仮に新しい入居者が2月に決まっても、免責期間が適用されるため、オーナーには家賃が支払われません。
免責期間の仕組みがあるため、サブリース契約が必ずしも「安定収入を得られる手段」ではないことを理解しておきましょう。免責期間の有無や長さを、契約前にしっかり確認することが重要です。
入居者を選べずトラブルが発生する可能性がある
サブリース契約では、入居者の募集や選定をサブリース会社が担当します。オーナーにとっては管理の手間を省ける点ではメリットですが、オーナーが希望する入居者を選べないというデメリットもあります。
例えば、「禁煙者限定」の条件をオーナーが希望していても、サブリース会社はこれを考慮せずに喫煙者を入居させる可能性も。また、騒音の問題やゴミ出しルールの違反など、住民間のトラブルが発生するケースも考えられます。
入居者トラブルが頻発すると、物件の評判が悪化し、長期的には資産価値の低下を招く恐れもあります。サブリース契約を結ぶ前に、入居者の選定基準を確認し、可能であればオーナーの意向が反映されるように交渉することが重要です。
サブリース会社が倒産するリスクがある
どの企業にも倒産するリスクがあるように、サブリース会社が経営破綻する可能性もゼロではありません。もしサブリース会社が倒産すれば、オーナーは契約を継続できなくなり、家賃収入が途絶えてしまいます。
また、入居者がサブリース会社に支払っていた家賃や敷金が未払いのままになることもあり、オーナーと入居者の双方に混乱が生じることになります。オーナー側が直接入居者と新たに契約を結ぶことで収益を確保できますが、その手続きには大きな手間がかかることも。
サブリース会社を選ぶ際は、財務状況や経営の安定性をしっかり調べ、倒産リスクの少ない企業を選ぶことが重要です。
賃貸住宅管理業法の制定とサブリース契約への影響
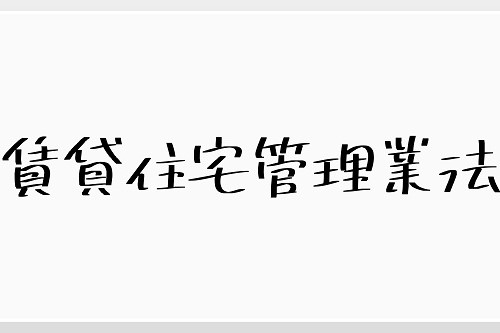
賃貸経営のトラブルを防ぐため、2020年(令和2年)に国土交通省によって「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が制定されました。この法律では、賃貸住宅管理会社やサブリース会社の業務に対して明確なルールが設けられ、オーナーに対して適切な情報提供をおこなうことが義務付けられています。
さらに、法律の具体的な運用指針として「サブリース事業にかかる適正な業務のためのガイドライン」も策定されました。このガイドラインでは、オーナーとサブリース会社の間で起こりやすいトラブルを未然に防ぐために、契約時の説明義務やサブリース会社が遵守すべきルールが細かく定められています。
サブリース契約は長期間におよぶケースが多いため、オーナーが契約内容を正しく理解し、リスクを把握したうえで契約を結ぶことが重要です。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の施行と目的
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律は、サブリース契約に関するトラブルを防ぐことを目的としており、「サブリース新法」とも呼ばれています。施行により、賃貸住宅管理業者に対する登録制度が義務化され、サブリース会社の営業活動にも一定の規制がかかるようになりました。
特に注目すべき点として、サブリース契約を勧誘する事業者の定義が明確になったことが挙げられます。これまで、サブリース契約の勧誘はサブリース会社だけがおこなうものと考えられていました。しかし、サブリース新法の施行によって、不動産の売買や建築をおこなう企業がサブリース契約の勧誘をした場合も、規制の対象になることが明確になりました。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の導入によって、オーナーが十分な情報を得たうえで適切な判断を下せるようになり、不当な契約や強引な勧誘を防ぐ効果が期待されています。
登録制度の義務化による影響
以前は、賃貸住宅管理業をおこなう事業者の登録は任意でした。しかし、サブリース新法の施行により、200戸以上の物件を管理する事業者は、国土交通省への登録を義務化されました。登録された事業者は、契約書や重要事項説明書の交付義務のほか、預かり金の分別管理など、さまざまなルールを守る必要があります。
さらに、国土交通大臣による監督権限が強化され、登録業者に対する立入検査や業務改善命令が可能になりました。賃貸住宅管理業者の透明性が向上し、不適切な管理業務を防ぐための仕組みが整えられています。
オーナーは登録された事業者との契約を選ぶことで、一定の安全性を確保できるようになった点がメリットです。サブリース契約を検討する際には、サブリース会社が適切に登録されているかどうかを確認しましょう。登録されているかどうかは、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で検索できます。
サブリース会社に対する行為規制とは
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」およびガイドラインの施行により、サブリース会社の営業活動に関する規制が厳格化されました。主な内容は以下のとおりです。
契約時の書面交付義務
サブリース契約を締結する際、サブリース会社は契約書だけでなく、契約前にオーナーに対してリスクを記載した重要事項説明書を交付しなければなりません。具体的には、以下のリスクに関する説明を明確にすることが求められます。
- 家賃保証額の減額リスク
- 契約期間中の解約リスク
- 賃貸物件の維持管理に関する費用負担
誇大広告や不当な勧誘の禁止
サブリース契約の勧誘時に、実際よりも有利な条件に見せかけるような誇大広告や、不都合な事実を伏せた説明が禁止されました。例えば、「空室保証100%」などの誇張表現や、「家賃が下がることはない」と誤解を招くような説明が規制の対象になります。
国による監督体制の強化
違反行為をおこなったサブリース会社に対して、国土交通大臣が業務改善命令や営業停止命令を出せるようになりました。また、一般のオーナーや関係者がサブリース会社の違反行為を通報できる「申出制度」も導入されており、行政による監視が強化されています。
サブリース契約で後悔しないためのポイント

サブリース契約には魅力的な面がある一方で、リスクやデメリットも少なくありません。契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、事前にしっかりと準備をしておくことが大切です。
以下のポイントを押さえて、サブリース契約のトラブルを避け、安定した賃貸経営を目指しましょう。
契約内容を細かく確認する
サブリース契約では、契約内容を十分に理解しないまま締結してしまうと、のちにトラブルに発展する場合があります。そのため、契約書の細部までしっかりと確認し、不明点があれば弁護士や不動産の専門家に相談することをおすすめします。契約書のなかで特に注意すべきポイントは、以下のとおりです。
家賃保証があっても減額の可能性がある
契約書に「家賃保証」と記載されていても、必ずしもその金額が長期間維持されるわけではありません。借地借家法の第32条に基づき、サブリース会社は「現在の賃料が市場相場より高い」と判断すれば、家賃の引き下げを求めることができます。
また、契約更新時に条件を見直し、家賃が引き下げられる可能性もあるため、「保証」の言葉に安心せず、実際にどのような条件が設定されているのかを確認することが重要です。
解約時の条件を確認する
契約解除に関する違約金の有無や、解約の際に必要な予告期間も重要な確認事項です。サブリース契約には「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」の2種類があります。
普通賃貸借契約の場合、契約期間が終了しても基本的には自動更新され、オーナー側からの解約が難しい点が特徴。
一方で、定期賃貸借契約の場合は、契約満了時に再契約の交渉が可能であり、オーナーが契約を終了しやすくなります。自分の経営方針に合った契約形態を選ぶことが大切です。
入居者情報の開示について確認する
サブリース契約では、入居者の情報がオーナーに開示されないことが一般的です。入居者の属性や契約内容を事前に把握しておきたい場合は、契約書に「入居者情報の開示」を求める条項を追加できます。
これらにより、サブリース契約終了後の対応や、入居者トラブルのリスクを軽減できます。
家賃の減額交渉への対応
借地借家法の第32条に基づき、サブリース会社は賃料の引き下げを求める権利を持っています。しかし、これは必ず応じなければならないものではなく、オーナーが拒否することも可能です。ただし、オーナーが減額要求を受け入れない場合、契約解除を申し出てくる可能性があります。
契約解除となった場合、オーナーは物件の管理を自らおこなわなければなりません。新たな管理会社を探す、入居者との直接契約に切り替えるなどの対応が必要です。手続きには時間と手間がかかるため、事前に代替策を検討しておきましょう。
また、家賃減額の交渉を受けた際には、専門家のアドバイスを求めることもおすすめです。不動産コンサルタントや弁護士に相談することで、適切な対応策を見つけられるため、交渉を有利に進められるでしょう。
周辺エリアの家賃相場を事前に調べる
契約時に提示される家賃保証額が適正かどうかを判断するには、周辺エリアの家賃相場を正しく把握しておくことが必要です。相場を知らないまま契約してしまうと、相場よりも低い家賃で契約してしまい、後悔することになりかねません。
周辺の類似物件の家賃を調査すれば、適正な賃料がわかります。不動産会社の話を鵜呑みにせず、自分で情報を集め、相場と照らし合わせながら交渉することが大切です。
また、将来的な家賃相場の変動も視野に入れ、長期的な収支計画を立てることも忘れないようにしましょう。
修繕費用の見積もりを把握しておく
賃貸経営を続けるうえで避けて通れない費用が修繕費用です。サブリース契約を結んでいても、物件の修繕費用はオーナーが負担するケースがほとんどです。そのため、どのような修繕が発生し、どれくらいの費用がかかるのかを事前に把握しておきましょう。
例えば、築年数が経過するにつれて、外壁塗装や屋根の補修、給排水設備の交換など、さまざまなメンテナンスが必要になります。また、退去後の原状回復費用や空室対策のリフォーム費用なども考慮しておくべきポイントです。
修繕費用を想定せずに契約すると、思いがけない出費で経営が圧迫され、最悪の場合、ローンの返済が厳しくなることもあります。契約前に必要な修繕費用をリストアップし、長期的な資金計画を立てておきましょう。
管理委託契約と比較してから決める
サブリース契約を検討する際、最初から「これしかない」と決めつけるのではなく、管理委託契約と比較することが重要です。先述したように、サブリース契約では空室リスクを回避できる一方で、家賃保証の減額や契約解除のリスクがともないます。
一方、管理委託契約では、不動産会社が入居者募集や家賃回収、建物の維持管理をおこなってくれるため、オーナーの負担を軽減できます。特に、安定した賃貸需要が見込めるエリアであれば、サブリース契約よりも管理委託のほうが収益性が高くなる可能性も。
それぞれの契約形態のメリット・デメリットを十分に比較し、自分の経営スタイルに合った選択をしましょう。目先の「家賃保証」にとらわれず、長期的な視点での判断が大切です。
信頼できるサブリース会社を選ぶ
サブリース契約を結ぶ際には、複数のサブリース会社を比較し、それぞれの財務状況や経営の安定性、過去の実績をしっかりと調査することが重要です。サブリース会社によって経営方針や契約内容に違いがあり、条件をよく比較せずに契約すると、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
特に、上場企業や大手の不動産関連会社が運営するサブリース会社は、資金力があり、経営基盤が安定しているケースが多いです。上記のような企業と契約することで、未払いリスクや突然の倒産リスクなどを軽減できるでしょう。
また、過去にそのサブリース会社と契約を結んだオーナーの評判や口コミの確認も有効です。インターネット上のレビューや実際に契約しているオーナーの体験談を参考にすると、サブリース会社の対応や信頼性を見極められます。
長期間にわたる契約となるため、慎重に比較検討することが成功への第一歩です。
強引な営業に流されない
サブリース契約を勧める不動産会社のなかには、メリットばかりを強調し、リスクを十分に説明しないケースもあります。「家賃保証があるから安心」「空室リスクなし」などの甘い言葉だけを信じてしまうと、後悔することになります。
実際に、誇大広告や強引な勧誘は法律で規制されていますが、悪質な業者が完全になくなるわけではありません。そのため、契約を急がされても焦らず、冷静な判断が大切です。
契約前に、複数の不動産会社の話を聞き、比較検討することも有効な手段です。自分の意思をしっかり持ち、納得できるまで情報を集めることで、リスクを最小限に抑えられるでしょう。
信頼できるサブリース会社を選ぶポイント

サブリース契約は長期にわたるものが多いため、契約後にトラブルが発生しないよう、慎重にサブリース会社を選ぶ必要があります。以下のポイントを押さえて、信頼できるサブリース会社を見極めましょう。
経営状況の健全性を確認する
いくら契約条件がよくても、サブリース会社の経営が不安定だと、途中で倒産するリスクがあります。特に未上場企業の場合、財務状況の透明性が低いため、経営が安定しているかどうかを慎重に見極める必要があります。
上場企業であれば、財務諸表が開示されているため、ホームページなどで確認する方法も有効な手段です。
市場分析力やリサーチ力を持っているかを確認する
サブリース会社が地域の市場動向を正しく分析できるかどうかは、賃貸経営の成功に大きく影響します。適切な家賃設定や、競争力のある賃貸経営プランを提案できる会社を選ぶことが重要です。
実績とノウハウが豊富であるかを確認する
サブリース契約には、通常の賃貸経営よりも多くの知識が求められます。契約の仕組みやリスク管理に精通し、豊富な実績を持つサブリース会社を選ぶことで、トラブルを避けやすくなるでしょう。
親身に対応してくれるかを確認する
契約時だけでなく、契約後も誠実に対応してくれるサブリース会社を選ぶことが大切です。契約内容をわかりやすく説明し、オーナーの質問に対して的確に答えてくれる会社を選びましょう。
まとめ
サブリース契約は、一見すると「家賃保証」があるため、安定した収入を得られるように思えますが、実際には多くのリスクをともないます。契約解除の難しさや家賃の減額リスク、修繕費用の負担、サブリース会社の倒産などがあるため、慎重に検討しなければなりません。
契約を結ぶ前に、契約内容を細かく確認し、リスクを十分に理解したうえで判断することが大切です。安易にサブリース契約を選ぶのではなく、自身の経営方針に合った方法を見極めることが成功のカギとなります。

執筆者
長谷川賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ