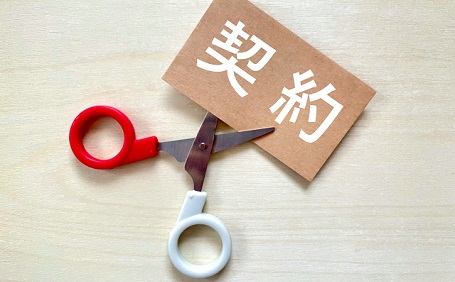サブリース契約のデメリットとは?メリットや注意点も把握して検討しよう
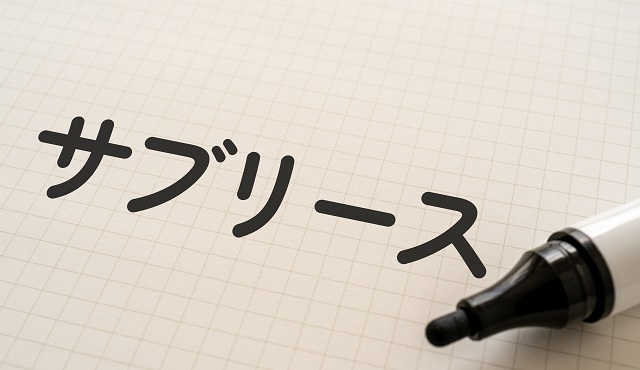
しかし、過去にサブリース契約に関するトラブルがメディアで取り上げられたことから、否定的な印象を持つ方もいるかもしれません。とはいえ、基本的な仕組みや注意点を正確に理解すれば、安定収入の確保や管理業務の簡素化など、多くのメリットを得られるでしょう。
本記事では、サブリース契約の仕組みやメリット、デメリットを解説します。サブリース契約を活用した不動産投資に興味がある方は、ぜひ参考にしてください。
記事の目次
サブリース契約とは

サブリース契約は、賃貸物件の管理を専門会社に依頼する契約方式の一つです。似たようなものに「管理委託方式」がありますが、どちらもオーナーの負担軽減に有効です。
ここでは、サブリース契約と管理委託方式の仕組みの違いを詳しく説明します。
管理委託方式の仕組み
管理委託方式とは、不動産管理会社がオーナー所有の物件に関する入退去手続きや日常的な管理業務を担当する契約形態のこと。管理委託方式の特徴は、管理業務のみを委託する点です。入居者との賃貸借契約は、不動産会社を介してオーナー自身が締結します。
賃料の支払いは通常、入居者からオーナーに直接おこなわれますが、契約内容によっては集金代行までを委託することも可能。管理を受託している不動産管理会社の報酬である管理費は、一般的に家賃収入の5~10%程度に設定されています。
管理委託方式では、家賃設定や入居者の審査など、賃貸借に関する重要事項をオーナーが決定できるメリットがあります。しかし、空室リスクはオーナーが負うことになるため、注意が必要です。
サブリース契約の仕組み
サブリース契約は、オーナーが不動産管理会社に物件を賃貸し、その会社が入居者に転貸(又貸し)する方式を指します。このような契約を結ぶ不動産管理会社は、「サブリース会社」と呼ばれます。
管理委託方式では「オーナーと入居者」が直接、賃貸借契約を結びますが、サブリース契約では「オーナーとサブリース会社」の間で契約が締結される点が特徴です。
賃料の徴収や入居者の募集はサブリース会社がおこない、契約で定められた金額がオーナーに支払われます。
サブリース契約の大きなメリットは、物件の空室率に関わらず、満室時の収入からサブリース会社の取り分(通常10~20%程度)を差し引いた金額がオーナーに保証される点です。そのため、空室リスクを大幅に軽減できます。
ただし、サブリース契約ではほとんどの業務をサブリース会社に委ねるため、どの会社に依頼するかは慎重に決めなければなりません。
サブリース契約のデメリット

サブリース契約にはいくつかのデメリットが存在します。過去には賃料の改定をめぐってトラブルが発生するケースが見られました。サブリース契約の主なデメリットは以下のとおりです。
- 収益性が低下する
- 定期的な賃料の見直しがある
- 免責期間が設定されている
- オーナー側からの解約が難しい
- 入居者を選べない
- 売却時になかなか買い手がつかないこともある
それぞれのデメリットを詳しく見ていきましょう。
収益性が低下する
サブリース契約では、サブリース会社がオーナーと入居者の中間に位置します。そのため、入居者が支払う家賃の全額がオーナーの収入になるわけではありません。一般的に、家賃保証率は家賃全額の80〜90%程度です。
そのため、物件の投資利回りもサブリースを利用しない場合と比べて低くなります。「必ず満室になる」という確信がある場合は、サブリースを選択しないほうが有利かもしれません。とはいえ、満室に確信を持てるケースは稀でしょう。
空室リスクを負って高い収益性を目指すか、収益性を抑えてリスクを回避するかの選択になります。オーナー自身が状況を判断し、どちらを選ぶかを決める必要があります。
定期的な賃料の見直しがある
サブリース契約では安定した家賃収入を得られますが、同額の家賃が永続的に保証されるわけではありません。多くの場合、2年ごとに家賃保証の見直しがおこなわれ、その際に賃料が引き下げられることが一般的です。
過去には賃料改定をめぐってトラブルが発生し、問題視されているケースがあります。例えば、ある会社が「10年間家賃を下げない」と約束しながら、経営悪化を理由に賃料減額を要求し、訴訟に発展した事例もあります。
賃料改定を巡るトラブルを発生させないためにも、事前にサブリース会社とはしっかり話し合っておくことが大切です。具体的な対策は、あとでも詳しく解説していくので、ぜひ参考にしてください。
免責期間が設定されている
サブリース契約では、物件の新築後や入居者の退去後に免責期間を設けられることがあります。この期間中は、入居者募集のための時間として扱われるため、サブリース会社による家賃保証がありません。
通常、免責期間は1~6カ月程度で設定されます。この間はサブリース契約を締結していても家賃収入が得られないため、注意が必要です。
オーナー側からの解約が難しい
基本的にサブリース契約では、オーナー側からの契約は難しいといわれています。なぜなら、オーナーとサブリース会社の契約では、サブリース会社が借主として借地借家法の保護を受けているからです。
オーナー側から解約したいと申し出ても、正当な理由がなければ拒否されてしまいます。契約更新の拒否に関しても、正当な理由がなければ受け付けてもらえないため、難航する可能性が高いです。
一方で、借地借家法で保護されているサブリース会社からの解約や更新の拒否は簡単におこなえるのが難点です。いきなりサブリース会社から解約や更新の拒否がおこなわれる可能性もあるため、オーナーにとっては大きなデメリットとなるでしょう。
入居者を選べない
サブリース契約では、入居者の選定もサブリース会社がおこないます。そのため、オーナーが入居者を選べないデメリットがあります。
管理委託方式の場合、管理会社が見つけた入居希望者に関しては、オーナーの承諾を得る必要があります。しかし、サブリース契約の場合はオーナーの承諾を得る必要がないため、確認なしに入居が決まることも。
そのため、一人暮らしの高齢者の入居による孤独死のリスクや、外国人入居者によるマナー低下の可能性などの問題が生じる場合があります。もちろん、上記の入居者が必ずしもトラブルを起こすわけではありません。
家賃保証に影響はありませんが、望ましくない入居者を避けられないことは、オーナーにとって精神的な負担となる可能性があります。
また、サブリース契約終了後は、契約期間中に入居した人々とオーナーが直接やり取りをしなければならなくなります。入居者が選べない点はあまりデメリットに感じないかもしれませんが、のちのちトラブルが発生する可能性もあるため、注意が必要です。
売却時になかなか買い手がつかないこともある
サブリース契約では、売却時になかなか買い手がつかないこともデメリットです。売却時にサブリース契約を解約できなかった場合は、新しいオーナーにサブリース契約が引き継がれます。
しかし、不動産管理会社を自分で選びたい、サブリース契約を利用したくないと思っている買い手もいるため、契約の引き継ぎが必要な物件の購入は避ける傾向にあります。買い手が少ない物件では、満足できる価格で売却できる可能性は低いでしょう。
サブリース契約のメリット

サブリース契約のデメリットを解説しましたが、もちろんメリットもあります。物件所有者がサブリース契約の締結で得られる主なメリットは以下のとおりです。
- 空室・未払いリスクの軽減と安定収入の確保ができる
- 運営管理業務を全面委託できる
- 宣伝費・修繕費の負担を軽減できる
- 相続税対策ができる
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
空室・未払いリスクの軽減と安定収入の確保ができる
通常の管理契約では、空室が発生するとオーナーの収入が減少します。一方、サブリース契約では、サブリース会社が物件全体を借り上げ、オーナーに賃料を支払う仕組み。そのため、オーナーは空室の有無に関わらず、一定の家賃収入を得られます。
また、入居者の家賃滞納リスクも軽減されます。通常の管理契約では滞納分だけ家賃収入が減少しますが、サブリース契約では一定の家賃収入が保証される点がメリットです。
空室や滞納の影響を受けず、安定した家賃収入を得られることが、サブリース契約の特徴でしょう。
運営管理業務を全面委託できる
不動産経営には多岐にわたる管理業務がともないます。入居者の募集から賃料徴収、契約更新、退去手続き、建物の保守点検など、さまざまな業務が発生します。上記をすべて個人で対応する場合、専門的に不動産経営をおこなっているオーナーでなければ困難でしょう。
一方、サブリース契約では、サブリース会社が煩雑な業務を一括して引き受けてくれます。そのため、オーナーは煩雑な事務作業から解放されるのです。毎月、サブリース会社から送付される入金明細を確認するだけでよいのが大きなメリットです。
宣伝費・修繕費の負担を軽減できる
不動産経営では、入居者の入退去にともない、多くの経費が発生します。具体的には、新規入居者獲得のための広告費や、退去後の原状回復費用などが挙げられます。
上記の費用は、入退去の度にオーナーの大きな負担となるでしょう。サブリース契約では、上記の費用の多くをサブリース会社が負担するのが一般的です。
そのため、入退去時の経費を抑えられ、オーナーの経済的負担が軽減されます。
相続税対策になる
サブリース契約には、相続税を軽減する効果も期待できます。オーナーが亡くなり相続が発生した場合、物件に対して相続税が課されます。
相続税が課される際、物件の入居率が高いほど、相続税額は低くなることが一般的です。これは、税法上、賃貸中の物件は資産価値が低く見積もられるためです。
サブリース契約の場合、入居率100%として相続税が算出されるため、相続税の軽減が期待できます。税金対策でもサブリース契約は役立つでしょう。
サブリース契約時の注意点

サブリース契約を検討する際は、いくつかの点に注意する必要があります。ここからは、サブリース契約時の注意点を詳しく解説します。
賃料保証の見直し・賃料改定を確認する
サブリース会社による賃料保証は、契約期間中でも変更される可能性があります。また、賃料改定の条件や頻度も契約ごとに異なるため、事前に確認が必要です。
実際に、賃料保証や賃料改定の際にトラブルが起きた事例がいくつもあります。トラブルを避けるためにも、契約する前に賃料保証や賃料改定に関する事柄は念入りに確認しておきましょう。
免責期間の有無を確認する
空室が発生した時に、一定期間は賃料保証が免除されている場合があります。免責期間の設定がある場合、サブリース会社は免責期間中、オーナーへの賃料支払いが不要となります。契約時には免責期間の有無や長さを確認しておきましょう。
違約金を確認する
オーナーが契約を途中解約する場合、違約金が発生することがあります。違約金の額や条件は契約によって異なりますが、一般的には月額賃料の数カ月~1年分程度です。
違約金の金額だけでなく、適用される具体的な状況や、免除される条件なども確認することが重要です。また、契約期間によって違約金の額が変動する場合もあるため、長期的な視点で検討する必要があります。
契約期間と更新条件を確認する
サブリース契約の期間は契約によってさまざまです。また、期間満了後の更新条件も契約ごとに異なるため、しっかりと確認しておくことが大切です。
解約条件を確認する
サブリース契約では、オーナーやサブリース会社が契約を解約できる条件が定められています。解約条件は契約ごとに異なるため、注意深く確認する必要があります。
オーナー側の解約条件としては、物件の売却や自己使用の場合などが一般的ですが、具体的な手続きや予告期間なども確認しましょう。
一方、サブリース会社側の解約条件も重要です。例えば、長期の空室や大規模修繕の必要性が生じた場合などが考えられますが、これらの条件が不明確だと、将来的なトラブルの原因となる可能性があります。
また先述したように、基本的にオーナー側から解約することは難しいです。正当な理由がなければ、オーナー側から解約できるケースはほとんどないため、サブリース契約を検討する際は慎重に決めなければなりません。
修繕費用の負担を確認する
物件の修繕費用の負担者は契約で定められており、多くの場合はオーナー負担となっています。サブリース会社が担当するリフォームの種類や、追加工事が必要になった場合の手順と費用分担は、事前に明確にしておくことが重要です。
メンテナンスや大規模な設備設置、緊急時の修繕対応なども確認しておきましょう。
失敗しないサブリース会社の選び方

サブリース契約を検討している場合は、信頼できるサブリース会社を選ぶことが大切です。信頼できる会社と提携することで、安定した収益と適切な物件管理が可能になるでしょう。しかし、会社選びを誤ると、トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。ここからは、サブリース会社選びのポイントを解説します。
複数社の見積もりを比較する
一社のみではなく、複数のサブリース会社を比較して検討することが大切です。各社のWebサイトから見積もりを依頼するか、一括査定サイトを利用するのもよいでしょう。
気になる会社を見つけたら、それぞれのWebサイトを確認してみましょう。契約の内容が明確になっているか、トラブルが起きた際の対処法などが詳しく載っている会社がおすすめです。複数の会社を比較検討し、自身のニーズに合った会社を選びましょう。
また、管理戸数や満室率などの実績もしっかりと確認しましょう。営業手法や客付けのためのネットワークも確認し、安心して業務を任せられる会社かを判断することが重要です。
賃料査定の根拠の具体性を確認する
提案される賃料の根拠をしっかりと確認することが重要です。実際の募集物件や成約事例に基づいた査定を求めましょう。
根拠のない賃料を提示する会社は信頼性に欠け、今後の管理業務委託にも不安が残るため、避けるべきです。
収支計画のシミュレーションをチェックする
気になるサブリース会社が見つかった場合は、収支計画の提出を求めましょう。現実的でないシミュレーションを提示する会社には注意が必要です。
必要経費の計上漏れや老朽化による家賃低下の考慮不足など、不適切な項目がないか確認することが大切です。
担当者との相性を確認する
サブリース契約では長期的なやり取りが必要となるため、担当者との相性も重要なポイントです。コミュニケーションが円滑に取れなかったり、価値観が一致しなかったりする担当者では、お互いが満足する契約にならないでしょう。
また、レスポンスの遅さや質問への不適切な回答が続く場合、無駄な時間や労力を費やすことになり、トラブルにつながる可能性もあります。契約の話になった際には、担当者との相性や質も確認しておきましょう。
サブリースに関するトラブルに巻き込まれた時の対処法

サブリース契約に関する問題に対応するため、行政も対応を進めています。実際にサブリース契約でトラブルが生じた場合の相談窓口として、消費者庁など各省庁が窓口を設置しています。
最後に、省庁(金融庁・消費者庁・国土交通省)がまとめた相談窓口の一覧を載せておくので、必要に合わせてご利用ください。
賃貸住宅に関するトラブル相談
・公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会
電話:03-6265-1555
賃貸住宅のオーナーに対し、賃貸住宅のトラブルや悩みに関するアドバイスをおこなっています。
賃貸住宅管理業者に関する相談
国土交通省などの窓口
(最寄りの窓口にご連絡ください)
- 北海道開発局: 011-709-2311
- 東北地方整備局: 022-225-2171
- 関東地方整備局: 048-601-3151
- 北陸地方整備局: 025-280-8880
- 中部地方整備局: 052-953-8119
- 近畿地方整備局: 06-6942-1141
- 中国地方整備局: 082-221-9231
- 四国地方整備局: 087-851-8061
- 九州地方整備局: 092-471-6331
- 沖縄総合事務局: 098-866-0031
賃貸住宅管理業者には、国土交通省の登録を受けた業者と受けていない業者があります。
国土交通省は賃貸住宅管理業の適正化を図るため、賃貸住宅管理業者登録制度を実施しています。登録した業者は一定のルールを守らなければなりません。また、登録を受けていない業者にも登録を推進しています。
融資などに関する相談
金融庁 金融サービス利用者相談室
電話:0570-016811(IP電話:03-5251-6811)
金融庁では、金融行政・金融サービスに関する一般的な質問や相談・意見を受け付けています。利用者と金融機関との個別トラブルに関して、他機関の紹介や論点の整理などのアドバイスをおこないますが、あっせん・仲介・調停はおこなわれないため、注意してください。
消費者トラブルに関する総合案内窓口
消費者ホットライン 局番なしの188(いやや!)
消費者ホットラインは、最寄りの消費生活センターなどの相談窓口につながる電話番号です。消費生活センターなどに相談できる時間帯は、窓口によって異なります。
お問い合わせ内容に合わせた、解決に役立つ法制度や相談機関・団体に関する情報提供をおこなっています。
法的トラブルに関する総合相談窓口
法テラス・サポートダイヤル
電話:0570-078374(おなやみなし)
法テラス(日本司法支援センター)とは、法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスを提供してくれる国の施設です。相談窓口や、犯罪被害者支援、国選弁護人指名など幅広い相談を受け付けています。
まとめ
今回はサブリース契約のデメリットやメリットを詳しく解説しました。煩雑な業務をおこなってくれるメリットがある一方で、免責期間が設定されていたり、賃料改定がおこなわれて収入が減ったりなどのデメリットもあります。
サブリース契約を選んでトラブルに発展した方も少なくないため、慎重に検討しなければなりません。サブリース契約を選ぶ際は、信頼できるサブリース会社を慎重に選びましょう。契約する前に確認すべき事柄をしっかり確認し、納得したうえで契約することが大切です。

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ