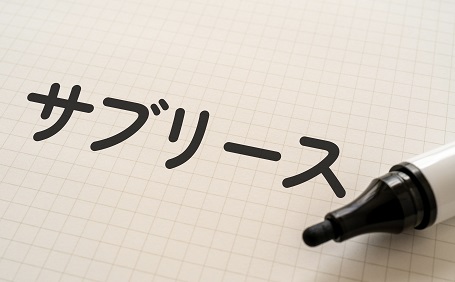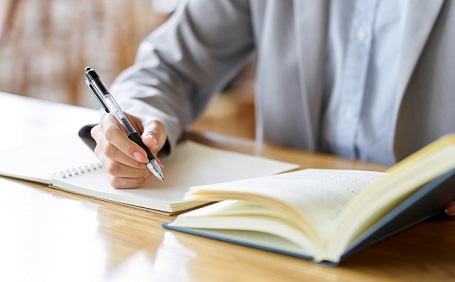賃料査定とは?査定の方法や依頼する不動産会社の選び方を知ろう

そこで本記事では、賃料査定の種類や方法、賃料査定を依頼する不動産会社の選び方を解説します。賃料設定に悩まれているオーナーの方は、ぜひご参考ください。
記事の目次
賃料査定とは

賃料査定とは、所有している投資用物件を「どれくらいの家賃で貸し出せそうなのか」適切な賃料を算出することです。先述したように、賃料が高すぎても低すぎても、賃貸経営に支障が出る可能性があります。例えば、賃料が高すぎる場合、入居者が集まりにくく、空室期間が長期化するおそれも。空室期間が長期化すると、その間の家賃収入が減少してしまいます。
一方、賃料が低すぎる場合、投資用ローンの返済額や修繕費用などの経営コストがキャッシュフローを圧迫し、最悪の場合には破綻する可能性もあります。安定した賃貸経営のために、適切な賃料の設定は欠かせません。
また、適切な賃料の設定は、入居者とのトラブルや退去を未然に防ぐことができます。国土交通省の「令和5年度住宅市場動向調査報告書」によると、民間賃貸住宅入居世帯における住宅の選択理由は「家賃が適切だったから」が51.1%でもっとも多くなっています。賃料は継続的に支払わなければならないため、入居者は賃料が適切かを確認していることがわかります。もし相場と比較して賃料を高く設定した場合、入居者が見つからなかったり、一時的に見つかってもより賃料が安い物件へ引越してしまうかもしれません。長期的な入居のためにも、適切な賃料設定は重要です。
賃料査定の種類

賃料査定には、「机上査定」と「訪問査定」の2種類あります。それぞれどういったものなのか、詳しくみていきましょう。
机上査定
机上査定とは、物件の基本情報や周辺の相場をもとに、賃料を算出する方法です。「机上」の名のとおり、データさえあれば机の上で算出できるため、手間がかからず、コストも抑えられる点がメリット。ただし、物件の細かな特徴や実際の状態を反映しきれないため、精度は低い傾向にあります。複数の物件をまとめて査定したり、初期段階でおおむねの相場を把握するために利用されることが多いです。
訪問査定
訪問査定とは、実際に物件を調査し、細かな特徴や周辺環境なども踏まえたうえで、賃料を算出する方法です。具体的には次のような内容を確認し、賃料が算出されます。
- 住戸の位置・階数・向き
- 室内の日当たり、眺望、傷み具合
- 周辺施設の充実度
- 賃貸前のリフォームや修繕の必要性
これらの数値化しにくい要素も考慮されるため、より実態に即した賃料が算出されます。主に、入居者を募集する際の賃料設定時に利用されます。なお、訪問査定を依頼するにあたって必要なものは次のとおりです。
- 地図
- 間取り図
- 登記簿
- 管理費や修繕積立金の明細
- 購入時の重要事項説明書
- 建築関係書類
物件の正確な面積を把握するために、登記簿が必要となります。依頼する不動産会社によっても異なるため、事前に確認しておきましょう。現地での調査は1〜2時間程度で終わり、査定結果は調査のあと1週間程度で通知されます。
賃料査定の方法

賃料査定には机上査定や訪問査定といった種類がありますが、査定額はどのようにして決まるのでしょうか?本章では、賃料がどのようにして決まるのか、具体的な方法を解説します。
類似物件と比較して決める
類似物件との比較は、基本的な賃料査定の方法の一つです。周辺の似たような物件の賃料を参考にすることで、市場に即した適切な賃料設定が可能となります。例えば、次のような条件で類似物件を探します。
- 賃料査定をおこなう物件と同じエリアにある
- 駅からの距離が同じ範囲である
- 部屋の広さや間取りが似ている
- 築年数が近い
- 建物の構造が似ている
また、マンションの場合には、同じ物件内で現在入居者を募集している部屋や、以前に成約した部屋と比較します。なお、不動産情報サイトで類似物件を探し、平均金額などをオーナー自身で調査することも可能です。しかし、掲載されている情報は、現在募集中のものです。掲載されている物件のオーナーが希望する賃料が反映されたものであるため、実態に即していないことも。不動産会社に依頼したほうが、より正確なデータをもとに比較できるでしょう。
レントロールから決める
レントロールとは、部屋別に家賃や敷金、契約期間などの契約条件がまとめられたもので、家賃明細表とも呼ばれます。過去にどれくらいの賃料で借りられていたのか、データをもとに、適切な賃料を設定します。築年数が経っている物件では、入居者が入れ替わるたびに賃料が下がることも。その場合は、直近に入居が決まった部屋の賃料を参考にするのが一般的です。
エリアの需要を分析する
適切な賃料を設定するために、エリアの需要の分析もおこなわれます。例えば、地域の人口動態や経済状況などを把握すれば、より適切な賃料設定が可能となります。
具体的には、大学が近いエリアであれば、学生向けの物件のニーズが高まるでしょう。初めて一人暮らしをする方も多いため、家具や家電が付いた物件が好まれるかもしれません。また、学生であることを踏まえ、賃料を低めに設定すると、入居者を集めやすくなるでしょう。所有している物件がどのような層をターゲットにすべきか、ターゲット層のニーズは何なのかを分析しましょう。そして、エリア内にある類似物件と比較し、賃料を算出します。
賃料に影響を与える契約形態
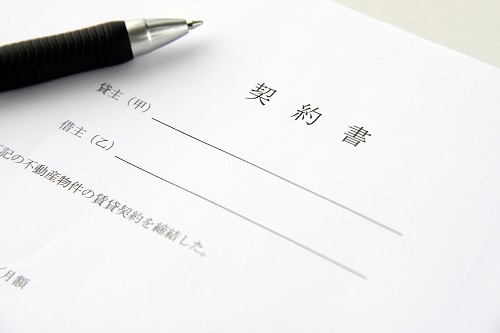
契約形態も賃料に影響を与える要素の一つです。本章では、それぞれの契約形態の特徴や具体的にどのように賃料が変わるのかを解説します。
普通賃貸借契約
普通賃貸借契約とは、賃貸借契約のなかでもっとも一般的な契約形態です。借地借家法に基づき、入居者が更新しない旨を通知した場合を除いて、以前と同じ条件で契約が更新されます。一方、オーナーから契約を更新しない旨を通知する場合は、正当の事由が必要。入居者にとって安定した住まいを確保でき、好きなタイミングで退去できるため、メリットがあります。そのため、賃貸需要が高いことから、賃料を高く設定できるでしょう。また、契約更新を前提としているため、オーナー側にも安定的な家賃収入を得られるメリットがあります。
定期賃貸借契約
定期賃貸借契約は、あらかじめ契約期間が定められており契約期間満了後は自動的に契約が終了する契約形態。入居者とオーナーが合意すれば、再契約が可能です。しかし、契約期間終了後は退去が前提となっているため、需要が低いことから、賃料も低めに設定される傾向にあります。一般的に、普通賃貸借契約よりも10%ほど低い賃料で設定されることが多いようです。
サブリース契約
サブリース契約とは、サブリース会社がオーナーから物件を一括で借り上げ、入居者に転貸借する契約形態です。空室が発生しても賃料が保証されるため、空室リスクを抑えつつ、安定した家賃収入が得ることができます。また、管理業務をサブリース会社に委託できることから、手間もかかりません。一方、賃料が市場価格の80〜90%に設定されるため、直接貸し出す場合と比較して、収益性が低下するおそれがあるでしょう。さらに、サブリース会社へ手数料を支払わなければならないため、オーナーの手元に残る収益はさらに減少します。
サブリース契約は、3つの契約形態のなかでも、賃料設定が一番低くなります。もともと収益性が低い物件の場合、サブリース契約を締結するとキャッシュフローが悪化する可能性も。賃料を設定する際には、契約形態も事前によく検討しておきましょう。
賃料査定を依頼する不動産会社の選び方

適切な賃料設定は、安定した賃貸経営をおこなううえで重要なポイントです。本章では、賃料査定を依頼する不動産会社の選び方を解説します。それぞれ詳しくみていきましょう。
実績や規模を調べる
賃料査定を依頼する不動産会社を選ぶ際は、実績と規模を確認しましょう。実績が豊富な不動産会社は、これまでに多くの物件を取り扱っており、不動産市場の動向も熟知しているため、より精度の高い査定を期待できます。また、規模の大きい会社であれば、幅広いネットワークや資金力を活かし、さまざまな提案をしてくれる可能性があります。反対に、地域密着型の会社であれば、地元の不動産市場に精通していることから、より実態に即した賃料設定が可能となるでしょう。幅広く情報収集をおこない、信頼できる不動産会社を見つけましょう。
査定額の根拠を示してくれる会社を選ぶ
賃料査定を依頼する際には、査定額だけでなく、根拠を明確に示してくれる不動産会社を選びましょう。査定額の根拠が明確であれば、信頼性が高まり、査定額に対する妥当性が判断できます。
賃料査定は、賃料を設定するためのものですが、これから賃貸経営をするうえで、信頼できるパートナーを見つける作業でもあります。提案内容に納得でき、質問にも丁寧に答えてくれる会社であれば、経営をするにあたっても信頼できるでしょう。
複数の不動産会社に査定を依頼する
賃料査定を依頼する際は、複数の不動産会社に依頼しましょう。複数の会社に依頼することで、賃料相場を把握でき、最適な賃料設定が可能となります。不動産会社によって査定方法や不動産市場のとらえ方、物件の評価基準などが違うため、査定額も異なります。複数の会社から査定を受けることで客観的に所有物件の価値を把握でき、適切な賃料を設定できるでしょう。また、先述したように、信頼できるパートナーを見つける機会でもあるため、複数社を比較検討して、より自分に合った不動産会社を選択しましょう。
まとめ
賃料査定は、安定した賃貸経営をするうえで欠かせません。適切な賃料を設定できれば、長期的に安定した家賃収入を期待できるでしょう。賃料査定を依頼する不動産会社は、今後賃貸経営をするにあたり、大切なパートナーとなる可能性があります。これまでの実績や規模などを確認し、信頼できる不動産会社を選びましょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ