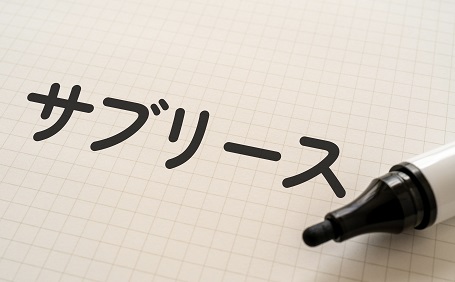賃貸管理の仕事内容は?管理会社を選ぶ際のポイントも解説

記事の目次
賃貸管理とは

賃貸管理は、大きく「入居者への対応業務」と「建物の管理業務」の2つに分けられます。どちらも、入居者の満足度を高めるためのものです。入居者の満足度が高ければ、長期にわたって安定した家賃収入を見込めます。それぞれどのような業務があるのかを解説します。
入居者への対応業務
入居者への対応業務は、入居者と直接関わるものです。具体的には、次のようなものが挙げられます。
- 入居者の募集・契約
- 家賃の回収
- トラブルやクレーム対応
入居者と良好な関係を築き、円滑なコミュニケーションを取ることで、入居者の満足度を高められます。また、入居者から寄せられる設備の不具合などの情報は、物件の適切な維持管理にも役立つでしょう。それぞれどのような内容なのか、さらに詳しく解説します。
入居者の募集・契約
入居者の募集・契約は、物件の収益性に大きな影響を与える業務です。入居者を効率よく集め、スムーズな契約手続きができれば、空室期間を短縮し、安定した家賃収入を得られます。しかし、入居希望者であれば、誰でもいいわけではありません。入居者のモラルにより、物件の価値や評判が大きく左右されます。例えば、入居者のモラルが高ければ、近隣住民とのトラブルも少なく済むでしょう。入居者の募集・契約にあたり、具体的には次のような業務があります。
- 物件情報の作成:物件の写真撮影、間取り図の作成
- 広告掲載:チラシの作成・配布、不動産ポータルサイトへの掲載
- 内見対応:入居希望者の内見対応
- 契約手続き:賃貸借契約書や重要事項説明書の作成、入居希望者への説明、保証人確認など
重要事項の説明は、宅建士(宅地建物取引士)がおこなう必要があります。入居者とのトラブルを防ぐためにも、慎重に契約手続きを進めましょう。
家賃の回収
家賃の回収も、入居者への対応業務の一つです。もし家賃を滞納されてしまうと、その分の家賃収入が減少するため、収益も減ります。家賃保証会社を利用すれば、入居者が家賃を滞納しても、家賃保証会社が代わりに支払ってくれます。しかし、家賃の滞納が長期化すると回収が難しくなり、場合によっては法的手段を取らなければならないおそれも。裁判となれば、時間と費用がかかるため、オーナーにとっては大きな負担となるでしょう。管理会社に委託すると、これらの業務を担ってくれます。
トラブルやクレーム対応
入居者への対応業務として一番イメージしやすいものが、トラブルやクレーム対応でしょう。これらを迅速かつ適切に対応することで、入居者の満足度を維持でき、安定した賃貸経営につながります。例えば、エアコンや給湯器などの設備が故障した場合。冬場であれば、すぐに修理してほしいと入居者から依頼があるでしょう。もし、これを放置したままにすると、入居者の満足度が低下し、最悪の場合、退去につながりかねません。他にも、入居者同士のトラブルも考えられます。初期の対応によっては、事態がさらに悪化してしまうことも。トラブルやクレームには、迅速かつ適切な対応が重要です。
建物の管理業務
建物の管理業務は、物件の価値を維持するためにおこなう業務です。具体的には、次のようなものがあります。
- 建物の維持・管理
- 設備の維持・管理
- 定期的な清掃
- 修繕計画の策定
これらにより快適な住環境を提供することで、入居者の満足度を高め、長期的な入居を期待できます。また、定期的なメンテナンスをおこなうことで、建物の劣化を遅らせ、物件の価値を維持できます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
建物の維持・管理
賃貸物件を良好な状態で保つために、建物の維持・管理は欠かせません。具体的には、次のような箇所をチェックしましょう。
- エントランス
- 外壁
- 屋上
- 廊下
- 駐車場
早期に劣化箇所を発見して修繕できれば、トラブルの発生も防げるでしょう。物件の価値を高く維持すると、将来的に高値で売却できる可能性も。建物の維持・管理を適切におこなうためには、建築基準法や消防法などの知識も必要です。専門知識の豊富な管理会社に依頼すると安心でしょう。
設備の維持・管理
設備の維持・管理も、建物の管理業務の一つ。例えば、給湯器やエレベーターなどの設備が故障してしまうと、入居者の生活に不便が生じます。また、賃貸物件の価値低下にもつながります。設備の維持・管理には「法定点検」と「任意点検」の2種類があります。法定点検とは、法律によって点検が義務付けられているもの。具体的には、次のようなものがあります。
- 建築設備定期検査(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水・排水設備)
- 消防用設備点検(消火器、自動火災報知器、スプリンクラーなど)
- 浄化槽法定検査(外観検査、水質検査、書類検査)
- 水道(簡易専用水道、専用水道)の法定検査(水道の点検、清掃など)
- 昇降機の保守点検・定期検査
建物の構造や規模によって、必要な点検は異なりますが、意外と多いと感じた方もいるでしょう。しかし、これらの法定検査は義務化されているもので、入居者が安心して過ごせる住環境を提供するためにも欠かせません。必ずおこなうようにしましょう。管理会社に依頼する際は、過去の実施状況を見せてもらい、きちんとおこなわれているか確認しましょう。
また、国土交通省のホームページには、必要な修繕や点検を確認できる簡易診断やチェックシートが用意されています。ぜひ活用してみてください。
定期的な清掃
賃貸物件の共有部を定期的に清掃することも、建物の管理業務の一つです。清潔な環境が保たれていると、入居者の満足度も向上します。また、建物の外観が美しく保たれ、入居希望者からの印象もよくなるでしょう。他にも、定期的に清掃がおこなわれることで、早く汚れや設備の破損などに気付き、迅速に対処できます。管理会社に委託する際は、専門会社への委託の有無や、清掃の頻度、内容などを確認しておきましょう。
修繕計画の策定
建物の管理業務の一つに、修繕計画の策定も挙げられます。修繕計画とは、建物の老朽化を予測し、必要な工事と時期、費用などを事前に計画すること。修繕計画を立て、適切な時期に工事をすると、賃貸物件の資産価値を維持しやすくなります。国土交通省からは、「長期修繕計画作成ガイドライン」が公表されています。また、マンションに限ったデータですが、国土交通省の「令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査」によると、大規模修繕工事の平均修繕周期は12〜15年。修繕計画を立て工事を実施することで、入居者の満足度を高められます。また、資産価値を維持できるため、将来的に売却する際も買い手が付きやすくなるでしょう。
賃貸管理の種類

賃貸管理には、次の3種類があります。
- 自主管理
- 委託管理
- サブリース
それぞれの特徴やメリット・デメリットを押さえ、どのような形で賃貸経営をおこなうのが適切かを考えてみましょう。
自主管理
自主管理とは、オーナー自身がすべての管理業務をおこなう管理方法です。管理会社に委託しないため、手数料がかからない点がメリットです。また、管理のために賃貸物件に出向くことで、入居者との関係を築きやすくなるでしょう。しかし、すべての業務を一人でおこなうとなると、時間や労力がかかります。本業があるオーナーの場合、時間や労力の捻出が課題となるでしょう。また、専門知識も必要となるため、対応を間違えてしまうと、入居者の不満を募らせてしまう可能性も。知識やノウハウが必要になるので、賃貸経営の経験が豊富な方におすすめの方法です。
委託管理
委託管理とは、オーナーが管理業務を管理会社に委託する管理方法です。管理業務のすべてを委託する「全部委託管理」と、一部を委託する「一部委託管理」の2種類があります。管理会社に委託すれば、オーナーは他の業務に専念できます。また、管理会社は専門知識や経験が豊富のため、オーナーでは対応が難しい問題にも対処できるでしょう。ただし、委託する場合には手数料がかかります。相場は、家賃収入の5%程度。管理会社によっては、同じサービス内容でも手数料が異なることもあります。委託する場合には、複数社を比較検討し、安心して任せられる管理会社を選ぶことが大切です。
サブリース
サブリースとは、オーナーが所有する物件をサブリース会社が借り上げ、入居者に転貸(又貸し)することです。サブリースでは家賃が保証されるため、契約形態によっては物件の空室率に関わらず安定した家賃収入を期待できます。また、管理業務の負担がかからない点もメリットです。一方、家賃の保証は定期的に見直しされるため、保証額が減額することも。他にも「借地借家法」により、借主であるサブリース会社が保護されるため、オーナーからの解約が難しいというデメリットがあります。サブリース契約を結ぶ際には、契約内容をよく確認しましょう。
賃貸管理会社を選ぶ際のポイント

賃貸物件の管理業務は幅広いため、管理会社に委託することが一般的です。しかし、数ある管理会社のなかから最適な会社を選ぶとなると、何を基準に選べばよいのか、悩むオーナーも多いでしょう。本章では、管理会社を選ぶ際のポイントを解説します。
集客力があるかを確認する
管理会社を選ぶ際には、集客力があるかを確認しましょう。集客力が高ければ、賃貸物件の空室期間を短縮でき、安定した家賃収入を期待できます。また、集客力があると、さまざまな入居希望者のなかから、賃貸物件に合った入居者を選定でき、入居者同士のトラブルを防ぎやすくなるでしょう。集客力の高さを見極めるためには、次のような方法があります。
- 不動産ポータルサイトを活用しているかを確認する
- 他の賃貸物件の入居率を確認する
賃貸物件に入居した経験があるオーナーであれば、物件を探す際に不動産ポータルサイトを利用した方も多いでしょう。物件を探す際、写真の多さやコメントの中身を確認する入居希望者が増えています。オーナー自身でも不動産ポータルサイトを検索し、管理会社がどのような掲載をしているのかをチェックしてみましょう。また、他の賃貸物件の入居率も重要なポイントです。特に築年数や立地が近い物件の入居率がどうなっているのかを調べてみましょう。
業務範囲が十分かを確認する
管理業務の範囲が十分かを確認することも、管理会社を選ぶ際のポイントです。管理会社によって、業務の範囲や得意分野は異なります。例えば、全部委託管理を検討しているのであれば、仲介、管理の両方をおこなっている管理会社を選ばなければなりません。委託したい管理業務をすべて挙げ、それらがカバーされている管理会社を選びましょう。
会社の規模や業歴を確認する
管理会社を選ぶ際は、会社の規模や業歴も確認しましょう。実績がある会社は、これまでに多くの賃貸物件を管理していることから、ノウハウもあり、安心して任せられるでしょう。具体的には、次のポイントを確認します。
- 設立年数
- 管理物件の数
- 取引している金融機関や不動産会社
設立年数が長ければ、実績や経験が豊富であることから信頼できるでしょう。また、管理物件の数も、確認しておきたいポイントの一つ。数が多ければ、ノウハウが蓄積されており、適切な対応が期待できます。また、すぐに対応できるスタッフも多いと考えられるため、入居者からのトラブルやクレームにも、迅速に対応できるでしょう。取引している金融機関や不動産会社が多ければ、ネットワークを活用し、より安定した経営が可能となります。
なお、200戸以上の賃貸住宅を管理している管理会社は、「賃貸住宅管理業者」として登録が義務付けられています。登録されていれば、一定の基準を満たしているため、安心して任せられるかの一つの判断基準となるでしょう。登録されている管理会社は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で検索できます。
対応力があるかを確認する
対応力の有無も、管理会社を選ぶ際のポイントです。入居者からの問い合わせやクレームに、迅速かつ適切に対応できれば、入居者の満足度を高められます。また、オーナーも安心して管理業務を委託できるでしょう。具体的には、次のポイントを確認しましょう。
- 管理会社の拠点から賃貸物件の距離が近いか
- 管理業務に携わる人員が多いか
- 夜間や休日にも対応できる窓口があるか
- 委託契約締結前の対応は適切か
管理会社の拠点から、賃貸物件までの距離が近ければ、トラブルが発生した際にも、迅速な対応を期待できるでしょう。しかし、距離が近くても人員が少なければ、すぐに対応をしてもらえない可能性も。そのため、管理業務に携わる人員の数も重要です。
また、夜間や休日にも対応できる窓口があるかもチェックしておきましょう。トラブルはいつ発生するかわかりません。夜間や休日でも対応できる体制が整っていれば、万が一の時にもすぐに対応してもらえるため、入居者の安心感にもつながるでしょう。さらに、委託する管理会社を選んでいる段階での対応が適切かの確認も大切。その段階で適切に対応してくれる会社であれば、締結後の対応力にも期待ができ、安心して委託できるでしょう。
手数料が適正かを確認する
管理会社を選ぶ際は、手数料が適正なのかも確認しましょう。先述したように、管理会社によってサービス内容や手数料は異なります。そのため、まったく同じ業務内容でも、手数料が異なる可能性も。経費を抑えるために、手数料が安い管理会社を選ぶと、サービス内容に不満を抱くかもしれません。そのため、複数の管理会社を比較検討し、最適な会社を選ぶようにしましょう。
まとめ
本記事では、賃貸管理の仕事内容を詳しく解説しました。賃貸管理は、入居者への対応業務と建物の管理業務の大きく2つに分けられます。しかし、それぞれの業務範囲は幅広く、適切な対応をしなければ、入居者の満足度を下げてしまう可能性も。安定した賃貸経営をおこなうためには、適切な管理によって、入居希望者や入居者の満足度を高めなければなりません。専門知識や経験のないオーナーにとっては負担が大きいため、安心して任せられる管理会社に委託することが重要です。集客力の有無や業務範囲などを確認し、最適な管理会社を選びましょう。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ