オーナーチェンジ物件の追い出しとは?メリットやデメリットを詳しく解説

本記事では、オーナーチェンジ物件の追い出し(立ち退き)の過程を中心に、賃貸借契約の種類や、退去してもらうことのメリット・デメリットを解説します。さらに悪質入居者を退去させる方法や立ち退き料の相場も詳しく解説するので、参考にしてください。
記事の目次
オーナーチェンジ物件とは

まずは、オーナーチェンジ物件とは何かを見ていきましょう。オーナーチェンジ物件は、入居者がすでにいる状態で売買される収益物件のことです。オーナーチェンジ物件の売買では、賃貸人としての権利と義務がそのまま新たなオーナーに引き継がれます。
すなわち、新しいオーナーは、旧オーナーが持っていた家賃収入の権利をそのまま継続して受け取れますが、同時に敷金返還義務や修繕義務などの義務も引き継がれることが特徴です。オーナーチェンジ物件は、すでに収益を生んでいるため、不動産投資では魅力的な選択肢の一つでもあります。
一方で、現行の賃貸借契約に基づく制約もあり、特に入居者を退去させたい場合には注意が必要です。
賃貸借契約の種類
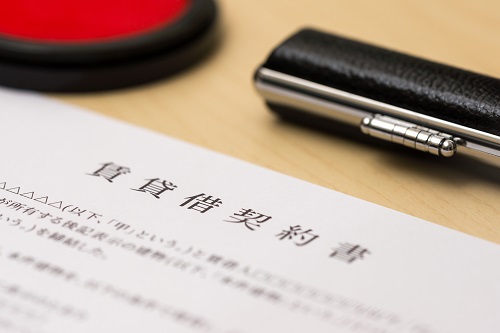
賃貸借契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。それぞれの違いを見ていきましょう。
普通借家契約
普通借家契約は、更新が可能な賃貸契約です。普通借家契約では、入居者が契約期間満了後も更新を希望すれば、契約期間の更新が認められます。多くの賃貸物件で、この普通借家契約が採用されています。
普通借家契約で入居者を立ち退かせるには、貸主には「正当事由」が必要であり、そのうえで「立ち退き料」を支払うことが一般的。
「正当事由」とは、契約の更新を拒絶するための合理的な理由を指します。単に「建て替えをしたい」、「家賃を引き上げたい」などの理由では正当事由として認められない場合があります。
そのため、正当事由が弱い場合には、立ち退き料を支払うことで入居者に退去を促すことになるのです。
定期借家契約
一方、定期借家契約は、契約期間が満了すると自動的に契約が終了する賃貸借契約です。更新の概念がなく、契約終了時には確実に物件が返還されることが保証されています。
そのため、定期借家契約であれば、契約期間満了後に正当事由や立ち退き料の支払いなしで入居者を退去させることが可能です。
立ち退き要求が認められるケース

上記でもお伝えしましたが、多くの物件で用いられている普通借家契約では、正当事由がなければ ち退きを促すことは困難です。では、どのような場合に立ち退き要求ができるのか、認められるケースをみていきましょう。
オーナーが物件を自宅として利用する場合
オーナーが収益物件を自分の住居として使用する際、立ち退き要求が認められることがあります。オーナーが他に住む場所がない場合に認められることが多いです。
ただし、このケースで立ち退きを求める場合でも、入居者が突然住む場所を失うことがないように、立ち退き料を支払う必要があることも。
また、入居者が立ち退きに応じない場合は、法的なトラブルに発展する可能性もあり、その際には裁判所の判断が求められることもあります。
老朽化した物件を建て替える場合
老朽化が進行している収益物件の場合、立ち退き要求が認められることがあります。ただし、建物が多少古くなっただけでは立ち退きの要求が認められることはほとんどありません。要求が認められるのは、建物が著しく老朽化し崩壊する危険性があるような場合です。
老朽化にともなって立ち退きを求める際は、入居者に対して相応の立ち退き料を支払い、建て替えや修繕をおこなうことが一般的です。
行政による再開発計画がある場合
行政が都市再開発をおこなう場合、該当する収益物件は立ち退き対象となり、所有者には補償金が支払われます。このような場合、立ち退きは強制的におこなわれることが多く、オーナーはその決定に従わなければなりません。
この場合の立ち退き要求は、公共事業の一環でおこなわれるため、オーナーが入居者に対して特別な補償をする必要はありませんが、このようなケースが起きるのは稀でしょう。
オーナーチェンジ物件での追い出しのメリット

オーナーチェンジ物件での入居者に退去してもらうことには、多くのメリットがあります。それぞれのメリットを以下で見ていきましょう。
物件の活用方法が広がる
問題のある入居者がいなくなれば、オーナーは物件を思い通りに活用できるようになります。
入居者が退去したあとの物件の用途は、オーナーの判断次第です。例えば、賃料を見直して市場相場に合わせる、あるいは売却してキャピタルゲインを狙うなどの投資方針を自由に選べます。
また、自分や家族の住居として利用することも一つの選択肢です。上記のように、自分の判断や状況に合わせて柔軟に物件の利用ができる点は、長期的保有を考えるオーナーにとって大きなメリットになるでしょう。
賃貸経営のリスクを低減できる
賃貸経営のリスクを減らせるのも、入居者を退去させるメリットです。
悪質な入居者がいると、家賃が支払われない、物件が荒らされる、近隣住民とトラブルが発生するなどのリスクがともないます。これらの問題が解消されることで、オーナーは物件管理に専念でき、結果的に長期的な収益を得やすくなるでしょう。
また、悪質な入居者がいなくなることで、物件の状態も改善されやすくなるため、管理コストの削減にもつながります。
物件の市場価値が向上する
物件の評価は、入居者の質に大きく影響されます。悪質な入居者がいると、物件の価値が下がるだけでなく、潜在的な購入者や他の入居者にも悪い印象を与える可能性があります。
反対に、悪質な入居者が退去し、物件を適切にリノベーションや清掃することで、物件の魅力が向上するでしょう。物件の市場価値が向上すれば、賃料の引き上げや売却価格の増加に直結するため、オーナーにとって大きなメリットになります。
新規入居者を適正賃料で募集できる
悪質な入居者を退去させることで、適正賃料で新規の入居者を募集できることもメリットです。
すべての入居者が期限までに家賃を支払うとは限りません。なかには、期限までの支払いが遅れたり、支払いすらしなかったりするケースもあります。
そのような悪質な入居者を退去させることができれば、家賃をきちんと支払う入居者を新たに募集できるため、収益の向上につながるでしょう。
オーナーチェンジ物件の追い出しのデメリット

オーナーチェンジ物件で入居者を退去させることはメリットだけではありません。いくつかのデメリットもあるため、メリットと比較したうえで判断することが大切です。どのようなデメリットがあるのか、以下で詳しく見ていきましょう。
法的手続きが必要になると精神的なストレスが大きくなることも
入居者が退去に応じない場合、法的手続きを取る必要があります。契約解除の通知を出し、裁判所へ訴えなくてはならないケースも少なくありません。
裁判に発展すると長期間にわたり対応が必要になり、その間の費用(弁護士費用、裁判費用、物件の管理費など)はオーナーが負担します。このことから裁判費用はオーナーにとって大きな経済的負担となるでしょう。
また、入居者との立ち退き交渉も一筋縄ではいかないことが多く、場合によっては高額な立ち退き料を支払わなければならないケースもあります。実際に退去させるとなると時間やコストがかかるだけではなく、精神的負担もかかることを頭に入れておきましょう。
立ち退きに時間がかかる
上記でもお伝えしましたが、実際に立ち退きを進めるとなると、長い時間がかかります。立ち退きはあくまでも交渉ごとであり、入居者が納得しない限りは強制的に立ち退かせることができません。
場合によっては、裁判にまで発展し、裁判が長期化することも少なくないでしょう。裁判が始まると、解決までに2年程度かかることもあり、オーナーにとっては不確実な状況が続くことになります。
立ち退き料が必要となる
立ち退きには立ち退き料が必要となることもデメリットです。立ち退き料は交渉次第で金額が変動するため、最終的にどれだけの費用がかかるか、予測がつかないことがあります。
特に、入居者が交渉に応じない場合、立ち退き料が膨らむ可能性もあるため、オーナーにとっては負担が大きいです。
入居者とのトラブルが発生する可能性がある
退去を説得する際、入居者とのトラブルが起こるリスクがあります。入居者が追い出しに反発し、収益物件の破壊や周囲とのトラブルを引き起こすと、周辺住民との関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。
このような問題が公になれば、物件の評判は大きく損なわれ、物件価値も大きく下がってしまうでしょう。
また、新たな入居者を見つけるのが難しくなることも考えられます。さらに退去の手続きを進める過程で、精神的なストレスや、オーナーと入居者との関係がさらに悪化するリスクも考慮する必要があります。
悪質な入居者を追い出す方法

悪質な入居者の場合は、すぐに立ち退きに応じるケースは少ないです。何かにつけて理由をつけたり、オーナーを責めたりなどして、居座るケースも多くあります。時には多額の立ち退き料を請求してくることも。できればスムーズに退去の手続きを進めたいものです。次に、悪質入居者に退去してもらう方法やポイントをご紹介するので、参考にしてみてください。
契約解除事由に該当するかを確認する
まず、入居者の行動が契約解除事由に該当するかを確認することが重要です。賃貸借契約書には、入居者が守るべき禁止事項が記載されています。
例えば、家賃の未払いが続く、他の入居者や近隣住民に迷惑をかけるなどの行為がある場合、契約を解除する正当な理由として認められることも。正当な理由に該当する場合、オーナーは入居者に対して契約解除を通知し、退去を求めることができます。
定期借家契約に切り替える
普通借家契約を定期借家契約に切り替える方法もあります。定期借家契約に切り替えることで、契約満了時に確実に入居者を退去させることができます。
ただし、切り替えには入居者の同意が必要であり、賃料の値下げなどの条件を提示しての交渉が一般的です。
立ち退き料を支払う
最終手段として、立ち退き料を支払うことで入居者に退去を促す方法もあります。しかしこの場合、立ち退き料の支払いが必ずしも退去を保証するものではないため、まずは入居者との交渉をおこない、合意を目指すことがポイント。穏便な交渉を心がけ、無理に退去を迫らないようにしましょう。
立ち退き料の目安
立ち退き料の額は、収益物件がある地域、入居者の状況によって異なりますが、一般的な目安は「移転に要する実費の補償」が基準です。「移転に要する実費の補償」には、引越し代や新居の仲介手数料、移転先の賃料と現在の賃料の差額が含まれることが多いです。
多くの場合、立ち退き料は40〜80万円の間で決着するのが一般的。もちろん、ケースによってはこの額を大幅に超えることもありますし、逆に低く抑えることも可能です。
重要なのは、入居者との信頼関係を維持しながら、合意に至る金額を提示することです。
立ち退き交渉を成功させるためのコツ

立ち退き交渉は、慎重に進めなければトラブルに発展する可能性が高くなります。以下で、交渉を成功させるためのポイントをいくつか紹介します。
事前通告をおこなう
立ち退きを求める場合、少なくとも6カ月前に入居者へ通告する必要があります。事前通告は法的に義務付けられており、怠ると交渉が不利になる可能性があります。できれば、1年程度前から入居者に告知し、余裕を持った対応を促すのが理想的です。
事前通告をおこなう際には、内容証明郵便を用いて公式な文書として通知する のがポイント。この際、立ち退きを求める理由を明確に説明し、入居者が理解しやすい形で伝えることが大切です。
そうすることで、入居者との信頼関係を保ちながら交渉を進められるでしょう。
代替物件を紹介する
代替物件の紹介は、入居者の負担を軽減する手段となります。入居者が次に住む場所を確保できるように支援することで、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。特に、代替物件の条件が入居者にとって魅力的であれば、立ち退きに対する抵抗感を減らす効果が期待できるでしょう。
弁護士を活用する
立ち退き交渉が難航した場合や、入居者が立ち退きを拒否する場合には、弁護士への依頼も検討しましょう。弁護士を通して交渉を進めることで、法律に基づいた正当な手続きを踏むことができ、トラブルの回避につながります。
特に、裁判に発展する可能性がある場合には、早期に専門家に相談することが重要です。
まとめ
本記事では、オーナーチェンジ物件での追い出しの過程や退去してもらうことのメリット・デメリットを解説しました。借地借家法によって入居者の権利が強く保護されていることから、追い出しの問題は容易には進まないことが多くなっています。しかし、適切な手続きを踏み、慎重に交渉を進めることで、オーナーの利益を守りながら問題を解決できるでしょう。
なにより、賃貸借契約の種類や、立ち退き料の相場、悪質な入居者に対する対応策など知識を深めることが大切です。何か不明点がある場合や、交渉が難航する場合には、弁護士や専門家に相談し、適切なサポートを受けることをおすすめします。

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ





