賃貸物件入居者のプチリフォームについて

原状回復義務とプチリフォームについて
借主による「プチリフォーム」で問題となるポイントは、「原状回復義務」との兼ね合いになります。入居者(貸借人)には「原状回復義務」があるため、物件の退去時には物件を借りてから入居者自身の故意・過失により生じた損傷箇所については、元の状態に戻さなければなりません。民法では、原状回復義務を下記のように定義しています。
(賃借人の原状回復義務)
第621条
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
この条文に照らすと、賃貸物件への借主が「プチリフォーム」を行った賃貸物件の退去時の原状回復義務は、基本的には借主側にあると言えます。
ここでまず考えるべきは、冒頭の「『原状回復義務』との兼ね合い」です。借主の立場になれば、「プチリフォームはしてもいいですけど、退去時には自費で完全に元に戻してくださいね」と貸主に言われたら、なかなか借りにくいものです。とはいえ、オーナーにしてみれば大事な所有財産を好き勝手に改修されたくはないですし、必要以上の原状回復工事費を負担したくないというのが正直なところでしょう。
そうなると、このプチリフォームについては、オーナーがどこまで許容するかということが根幹の部分になります。
なぜ「プチリフォーム可」にするのか
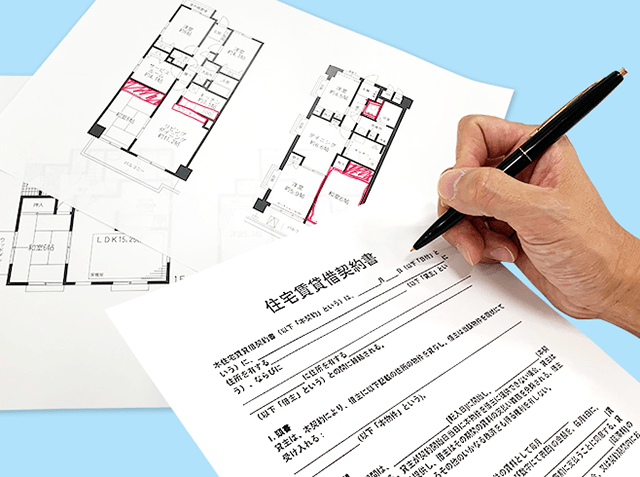
オーナーが、所有する賃貸物件を「プチリフォーム可」にする理由は、「空室対策」にほかなりません。物件の競争力を高め、入居者ニーズを取り込むために行うわけです。
特に築年が古い物件、立地が不便など不利な物件、同一エリアに競合が増えてしまった物件など、空室リスクが高くなる原因はいろいろありますが、「プチリフォーム可物件」として募集すれば、ある程度自分好みの住まいが作れるため、入居者にとっては魅力的な物件になります。入居した後も、愛着がわくことで長期の契約更新も期待できます。このようにプチリフォーム可にすることで、空室リスクが減り安定した家賃収入も見込めるわけです。
プチリフォームの許容範囲と注意点
では、どの程度プチリフォームを許容すればいいのでしょうか。入居者のニーズに応えることと所有物件の資産価値を守るということ、また退去時の原状回復を念頭に考えていきましょう。
【プチリフォームの範囲について】
どの範囲までプチリフォームを許容するかはオーナー次第ですが、一般的に多く見られるのは、壁紙の張り替え、備え付け棚の設置などです。
壁紙・クロスはそもそも経年による変色や剥がれなどが起こるものですし、退去時の原状回復義務は元々貸主側にありますから、借主が好みのものに変えたとしても特に問題はないでしょう。
備え付けの棚については、クギやネジで壁などに穴をあける場合は、どの程度までOKなのかを細かく決めておく必要があります。壁は、画びょう程度の穴ならば借主に原状回復義務は生じませんが、長いくぎなどはNGというのが一般的です。これは住戸の構造的に、深く穴をあけると壁の奥の階層まで達してしまい、その穴を埋めるのに費用がかかるからです。画びょうの小さく浅い穴ならば特に問題ないわけです。これを許容するには、例えば特定の壁面だけを釘打ちOKにするとか、壁の上にさらに板を取り付けて壁面を守りながら加工可にする、などの工夫が必要かもしれません。
この他、トイレにウォシュレットを導入したいとか、エアコンを自分で選んだものにしたいとか、既存設備の交換を希望する人もいます。この場合は、それを許容するのかというほかに、退去時にその設備をどうするかを決めておくことが必要です。元に戻すのか残していくのか、残す場合オーナーが一部費用を負担するのかなど、契約時に明確にしておきましょう。
この他、入居する人によって要望はそれぞれありますから、あとは個別の相談になるかと思います。それをOKにするかどうかは、やはりオーナーが都度判断することになります。
【プチリフォーム可にするときの注意点】
前項でも触れましたが、どのようなことがOKで、どのようなことがNGかを明確にしておくことが大事です。「OK」とはつまり借主は原状回復義務を負わないということで、反対に「NG」はやってしまったらお金をかけて元に戻してもらいますよ、ということです。
これは退去時のトラブルにつながるので、賃貸借契約時にすべて「特約」として明文化しておく必要があります。入居中に要望として出てきたものについても、必ず双方合意の上、契約書の内容を改訂しておきましょう。
また、もしもプチリフォームを許容するつもりはあるが、自分が知らないところで入居者に変えられるのは抵抗があるという場合や、事細かくできることを確認されるのが煩わしいという場合は、入居希望者が内見に来たときなどに、ある程度はプチカスタマイズの要望に応えられますということを伝えて、その時点で可能な範囲で改修を受け入れてしまうというのも一つの方法です。
入居希望者を満足させて入居を確定させる決め手になりますし、最初からその施工費を予算に入れて収支計算しておけば、経営戦略上問題はないでしょう。いずれにしても、顧客のニーズをつかみ入居してもらうこと、原状回復を考えて退去時のトラブルを予防しておくこと、もちろん賃貸経営にプラスになることを考えてプチリフォームの形を決めていきましょう。
物件を探す



