一人暮らしの生活保護いくら支給される?金額シミュレーションと注意点を解説
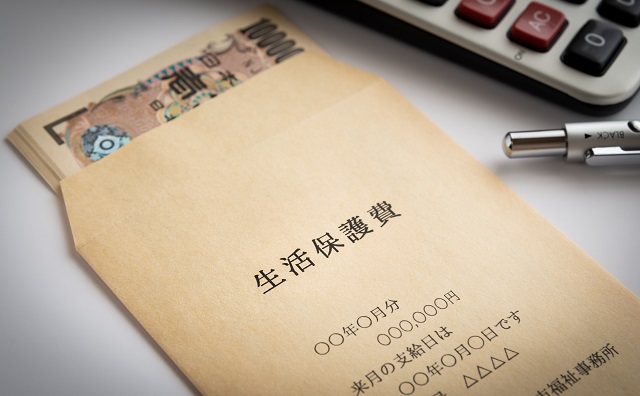
では、実際に生活保護を申請した場合、どのような支援を受けられるのでしょうか。本記事では生活保護の仕組みや、支給されるお金について丁寧に解説します。
記事の目次
生活保護で支給される金額は?

生活保護で支給されるお金を「保護費」といいます。保護費がいくらもらえるかは、受給者の生活状況によります。生活状況をどのように分類し、どのように計算するのかを見ていきましょう。
まず、生活保護を受けようとする方の居住地域、世帯人員、年齢に合わせて厚生労働大臣が定める基準で最低生活費を算出します。収入がある方の場合、最低生活費から収入を引き、その差額が保護費となるでしょう。収入がまったくない方の場合、最低生活費が保護費となります。
- 保護費(受け取れる金額)= 最低生活費 ― 収入
なお、受給者が障害者の場合は障害の程度に応じて障害者加算があります。また、母子世帯、養育する児童がいる場合にも加算手当があります。
参考までに、厚生労働省が公開しているファミリー世帯と単身世帯の最低生活費の例を見てみましょう。
【最低生活費の目安】
| 東京都区部等 | 地方郡部等 | |
|---|---|---|
| 3人世帯 (33歳、29歳、4歳) |
164,860円 | 145,870円 |
| 高齢者単身世帯 (68歳) |
77,980円 | 68,450円 |
厚生労働省によると、2023年10月1日時点での最低生活費は、東京都区部等に住む3人世帯で約16万4,860円、地方郡部等に住む3人世帯で約14万5,870円。東京都区部等に住む高齢者単身世帯で約7万7,980円、地方郡部等に住む高齢者単身世帯で約6万8,450円となっています。
最低生活費とは?
最低生活費とは、最低限度の生活をするうえで必要とされるお金のことです。先ほどもお伝えしましたが、生活保護を受けようとする方の居住地域、世帯人員、年齢、家庭内事情に応じ、金額が違います。
収入が最低生活費を上回る場合は、生活保護を受けることができません。最低生活費の具体的な計算方法については後ほど解説します。
8種類の扶助
生活保護は8種類の扶助の組み合わせで構成されています。扶助の内容は、以下の表をご覧ください。
生活扶助、住宅扶助、教育扶助は毎月支給されますが、医療扶助や介護扶助は、直接医療機関や施設に実費が支払われる仕組みとなっています。出産扶助、生業扶助、葬祭扶助は別途申請が必要です。教育扶助は、該当する子どもがいる場合に支給されます。しかし、義務教育を受けている子どもがいない世帯である、一人暮らしの方は、教育扶助を受けることはできません。また、持ち家に住み続けることを認められた場合には住宅扶助の支給対象外となります。
【扶助の種類と内容】
| 生活扶助 | 食費や被服費、水道光熱費など、日々の暮らしに必要な費用。所定の計算に基づいて支給。 |
|---|---|
| 住宅扶助 | 家賃、火災保険料、更新料、保証料など住まいに関する費用。定められた範囲内で実費支給。 |
| 医療扶助 | 病院の診察、治療を受けるための費用。直接医療機関へ支払。 |
| 介護扶助 | 介護サービスを受けるために必要な費用。直接介護事業者へ支払。 |
| 出産扶助 | 分娩費、出産にともなう入院費、衛生材料費など出産にかかる費用。定められた範囲内で実費支給。 |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品代、給食費などの費用。定められた基準額を支給。 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能を習得するための費用。定められた範囲内で実費支給。 |
| 葬祭扶助 | 葬式を執りおこなうための費用。定められた範囲内で実費支給。 |
医療扶助は、医療機関へ行くための交通費や眼鏡を買うための購入費も含まれます。
また、生業扶助には生業費、技能習得費、高等学校等就学費、就職支度費があり、上限金額がそれぞれ異なります。他に、身体上、または精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者が入所して、生活扶助を受ける救護施設などがあります。
最低生活費の計算方法
生活保護の受給額を計算するうえで、一番複雑なのが生活扶助の支給額の計算です。生活扶助と住宅扶助の金額がわかれば、最低生活費を把握することができます。生活扶助の計算方法、住宅扶助についてより詳しく見ていきましょう。
最低生活費を計算する時の流れ
最低生活費は、以下の流れに従って計算します。
住んでいる地域の等級(級地区分)を調べる
まず、自分が住んでいる地域の等級(級地区分)を調べましょう。住んでいる地域によって生活様式の違いや物価差による生活水準の違いがあるため、生活保護基準には地域差が設けられています。このことを「級地制度」と呼び、現在1級地から3級地までがあります。さらに各級地は2つに区分されており、地域差は合計6区分に分かれています。
主な自治体の級地区分は以下の通りです。級地区分は厚生労働省のホームページや、福祉事務所で確認することができます。
| 級地区分 | 市区町村名 |
|---|---|
| 1級地 -1 | 東京都23区、八王子市、横浜市、さいたま市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、豊中市、神戸市など |
| 1級地 -2 | 札幌市、仙台市、青梅市、所沢市、千葉市、横須賀市、大津市、宇治市、岸和田市、明石市、岡山市、広島市、北九州市 など |
| 2級地 -1 | 函館市、青森市、盛岡市、秋田市、山形市、福島市、水戸市、宇都宮市、前橋市、川越市、柏市、海老名市、新潟市、富山市、金沢市、泉佐野市、奈良市 など |
| 2級地 -2 | 夕張市、名取市、日立市、足利市、長岡市、上田市、多治見市、三島市、瀬戸市、松坂市、加古川市、三原市、尾道市、大牟田市、佐世保市 など |
| 3級地 -1 | 北見市、弘前市、宮古市、石巻市、能代市、米沢市、郡山市、石岡市、栃木市、伊勢崎市、行田市、銚子市、飯田市、洲本市、海南市 など |
| 3級地 -2 | 1級地 -1~3級地 -1以外の市町村 |
※ 参考:厚生労働省「級地区分」(PDF)
年齢から生活扶助基準額を算出する
自分の住んでいる級地区分の確認ができたら、次に生活扶助の金額を計算します。生活扶助で支給されるお金は、生活扶助基準に基づいて計算されます。
生活扶助基準には、年齢ごとに決まっている第1類と、世帯人数によって決まっている第2類があります。第1類、第2類の表から該当する金額を探してください。
【生活扶助基準第1類】
生活保護基準第1類とは、生活扶助基準の内、食費や被服費等の個人的経費に該当する費用の基準額のことで、年代別に定められています。
| 基準額の内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年齢 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
| 18~64歳 | 46,930円 | 45,520円 | 43,640円 | 41,760円 | 41,290円 | 38,950円 |
| 65~74歳 | 46,460円 | 45,060円 | 43,200円 | 41,350円 | 40,880円 | 38,560円 |
| 75歳 以上 |
39,890円 | 38,690円 | 37,100円 | 35,500円 | 35,100円 | 33,110円 |
※参考:厚生労働省:「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和5年10月)」(PDF)
【生活扶助基準第2類】
生活保護基準第2類とは、生活扶助基準の内、水道光熱費や家具什器など、世帯共通の経費に該当する費用の基準額のことです。級地区分に関係なく世帯人数ごとに定められています。
| 基準額の内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人員 | 1級地-1 | 1級地-2 | 2級地-1 | 2級地-2 | 3級地-1 | 3級地-2 |
| 1人 | 27,790円 | |||||
| 2人 | 38,060円 | |||||
| 3人 | 44,730円 | |||||
| 4人 | 48,900円 | |||||
| 5人 | 49,180円 | |||||
生活扶助基準額の計算式
第1類と第2類の表で該当する金額を見つけたら、生活扶助基準額の計算をしてみましょう。生活扶助基準は、世帯人員それぞれの第1類基準額を合計し、世帯人員に応じた逓減(ていげん)率を乗じ、世帯人数に応じた第2類基準額を加えて算出します。さらに特例加算として、1人あたり月額1,000円が加算されます(2025年3月日までの対応)。
- [計算式]
- 生活扶助基準((第1類×逓減率)+第2類 )+ 特例加算 + 生活扶助本体における経過的加算
なお、逓減率は以下のとおりです。
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0000 | 0.8700 | 0.7500 | 0.6600 | 0.5900 | 0.5800 |
生活扶助における経過的加算とは、2023年度の基準額改定にともなう加算です。級地や世帯人数、母子世帯であるか、児童がいるかによって金額が決まっています。
家賃を補助する住宅扶助を調べる
住宅扶助とは、家賃を支払うための費用で、一定の額の範囲内で支給されます。支給される家賃補助の金額は、自治体、世帯の人数によって異なります。保護費は、生活扶助に住宅扶助を加算して計算します。
以下は、首都圏を例にした単身世帯の住宅扶助の上限額です。
| 都道府県 | 1級地 | 2級地 | 3級地 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 53,700円 | 45,000円 | 40,900円 |
| 神奈川県 | 41,000円 | 41,000円 | 41,000円 |
| 千葉県 | 46,000円 | 41,000円 | 37,200円 |
| 埼玉県 | 47,700円 | 43,000円 | 37,000円 |
住宅扶助の対象となるのは、月々の家賃です。敷金・礼金、更新料は対象外なのかというと、そうではありません。一時的な費用については、一時扶助金として受け取ることができます。引越し費用や、火災保険料も扶助の対象となりますが、一時扶助金の範囲内でなければなりません。
居住するうえで必要になる費用、例えば水道光熱費や維持修繕費は住宅扶助に含まれません。生活扶助として支給される額から支払う必要があります。
なお、生活保護受給者が新たに家を借りる時は、ケースワーカーの了承を得る必要があります。賃貸物件を探す場合、家賃が上限額を超えると、ケースワーカーより物件の見直しを求められる可能性があることに注意が必要です。
加算項目に該当するか確認する
生活保護を受けることでもらえる保護費は、生活扶助、住宅扶助のほか、以下の加算項目に該当する場合に金額が加算されます。
【主な加算項目】
| 加算条件 | 加算額 (最大) | |
|---|---|---|
| 妊婦加算 | 妊娠6カ月未満 | 9,140円 |
| 妊娠6カ月以上 | 13,810円 | |
| 産婦加算 | 産後6カ月以内 | 8,490円 |
| 母子加算 | ひとり親世帯 | 23,260円 |
| 障害者加算 | 身体障害者障害程度等級表 1、2級 |
26,580円 |
| 介護施設入所者加算 | 介護施設入所者 | 9,890円以内 |
| 児童養育加算 | 中学校修了前の 児童 |
13,000円以内 |
※参考:厚生労働省「生活保護基準の体系等について」(PDF)
【一人暮らし】支給額のシミュレーション
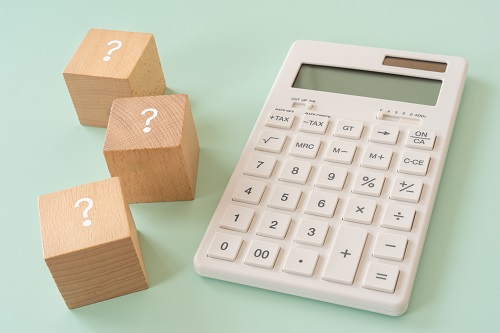
では、今までの内容を踏まえて、一人暮らしで生活扶助と住宅扶助を受ける場合の支給額の計算例を見てみましょう。ここでは、居住地と年齢が異なる方の支給額を2例ご紹介します。
※厚生労働省「令和5年度10月からの最低生活費の算出方法(PDF)」に基づき計算
【東京都23区内に住む30代・女性の場合】
級地区分:1級地 ー1
生活扶助基準(第1類)46,930円(逓減率 1.0000)
生活扶助基準(第2類)27,790円
特例加算 1,000円
生活扶助本体における経過的加算 700円
① 生活扶助計 76,420円
② 住宅扶助 53,700円
支給額概算(①+②)=130,120円
【千葉県柏市に住む70代前半・男性の場合】
級地区分:2級地 ー1
生活扶助基準(第1類)43,200円(逓減率 1.0000)
生活扶助基準(第2類)27,790円
特例加算 1,000円
生活扶助本体における経過的加算 0円
① 生活扶助計 71,990円
② 住宅扶助 41,000円
支給額概算(①+②)=112,990円
生活保護を受けるための条件
ここまで、生活保護の支給額について説明してきました。収入がなく生活に困窮している方は、すぐにでも生活保護の受給を検討すべきでしょう。しかし、実際に生活保護を受けるためには、条件があります。生活保護の受給条件を5つにまとめました。
最低生活費より収入が少ない
生活保護は、国が定めた最低生活費よりも収入が少ない場合に、最低生活費と収入の差額を保護費として受給できる制度です。よって、最低生活費よりも収入が多い場合には、生活保護を受けることができません。
ケガや病気によって働くことができない
働ける人は働いて収入を得るということが、生活保護制度の基本的な考え方です。憲法27条では、勤労の義務を定めています。ケガや病気で働くことができない場合はやむを得ませんが、働くことができるのに働かない場合には、働いて自分の力で収入を得ることが求められます。
家族・親族からの支援を受けられない
親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を受けられる時には、生活保護より優先して援助を受ける必要があります。生活保護は扶養義務者からの扶養や支援の有無に関わらず受けることができますが、生活保護決定のためには扶養義務者についても調査がされます。
売却できる資産がない

利用していない不動産や、貴金属、車など資産がある場合はすべて処分して生活費に充てなければなりません。そのような売却できる資産がない場合に、生活保護を受給することができます。なお、住まいとして使っている不動産があるけれども売却価格が引越しに必要な費用を下回るケースなど、現金化する必要がないと認められれば、持ち家をそのまま自宅として使い続けることができる可能性があります。
年金・手当などの制度を利用しても生活維持が難しい
障害があって働けなくなったのに、障害年金を受給していないという場合には、まず障害年金の受給手続きをする必要があります。年金・手当も、最低生活費から差し引かれる収入のひとつです。
生活保護を受ける時の注意点
生活保護は、生活に困窮する方の最低限度の生活を保障し、自立を支援するためのものです。当然ですが、法の趣旨に沿って受給を受けなければなりません。生活保護を受ける時は、特に以下の点について理解する必要があります。
不正受給をすると逮捕される
本当は収入があるのにも関わらず、虚偽の収入の申告をして不正に生活保護を受給する行為は違法です。それまでに受けた保護費の返還はもちろん、懲役や罰金などの刑事罰が科されることがあります。
ケースワーカーの家庭訪問がある
ケースワーカーは受給者の自立のため、受給者の支援をおこないます。生活保護の受給が決まったら、ケースワーカーの定期的な訪問があります。生活の様子を確認するため、訪問は事前連絡なくおこなわれる場合もあるでしょう。また、生活保護受給額や追加支援の相談は、ケースワーカーを通しておこないます。
支出を抑える必要がある
保護費と収入を合わせた生活費は、計画的に管理する必要があります。生活費で支出できるのは生活必需品のみであり、趣味やぜいたく品にお金を使うことはできません。また、保護費の前借りはできません。
クレジットカードを作ることはできますが、ケースワーカーや福祉事務所に事前に相談し、許可を得ることが必須です。無許可でクレジットカードを作ると最悪の場合、生活保護が取消しになります。
また、資産を持つことはできませんので住宅ローンを組んで自宅を購入することもできません。すでに持ち家があって月々住宅ローンの返済をしている方の場合、資産の形成になるため生活保護の受給はできない可能性が高いでしょう。
借金の返済はできない
生活保護の趣旨は、最低限度の生活を維持することです。支出の節約は義務であり、借金をすること、借金を返済することは、その趣旨から外れるため認められません。生活保護を受ける前から借金の返済がある場合は、ケースワーカーに相談して対処法を検討します。
生活保護で物件を探す時のポイント

生活保護を受給することになった場合、住宅扶助の上限内の家賃で生活するため、新たに部屋を借りるケースがあります。しかし、生活保護を受給している方が家を借りる時は、物件探しから契約まで通常とは流れが異なります。以下で、生活保護受給者が住まいを借りる際のポイントをまとめました。
ケースワーカーに相談する
まず、家を借りる時は勝手に物件を決めて契約をすることはできません。借りたい物件が見つかったら、ケースワーカーに相談する必要があります。不動産会社から家賃や初期費用の見積もりをもらい、ケースワーカーに提出して了承をもらってから契約の準備を進めます。
審査が厳しくなる可能性がある
物件探しは、限度額の範囲内で生活保護受給者でも入居できる物件を条件としておこないます。ただし、条件に合う物件が見つかったとしても、生活保護受給者が入居するということは家賃滞納のリスクが高まるため、一般的に入居審査は厳しくなる可能性があるでしょう。
代理納付を利用する
入居審査に通りやすくするための方法として、「代理納付」があります。代理納付とは、生活保護受給者の代わりに、福祉事務所が貸主や管理会社に家賃を納付する仕組みのことです。代理納付を利用することにより、貸主や管理会社は家賃滞納のリスクが軽減されるため、生活保護受給者が物件を借りやすくなります。
補助の上限を超えたら引越ししなければならない
家賃は、補助の上限以内に収めるようにしなければなりません。そのため、たとえ上限金額を超える物件で、超えた部分は生活扶助の受給額から支払うことにしても、ケースワーカーから指導を受ける可能性があります。また、家族構成が変わるなど事情があって補助費が下がり、結果的に家賃が補助の上限を超えることになった場合には、ケースワーカーから転居を促される可能性があるでしょう。
保証会社の審査に通る必要がある
最近では家を借りる際、連帯保証人の代わりに保証会社を利用するケースが増えています。保証会社を利用すると、保証会社の審査がありますが、クレジットカード系の信販会社が運営する保証会社の場合、クレジットカードの滞納歴がある方は審査に通りにくくなる可能性があるので注意しましょう。
一人暮らしの生活保護に関してよくある質問

一人暮らしの方が生活保護を受けるにあたり、よくある質問と回答をまとめました。
一人暮らしで生活保護を受けることはできる?
一人暮らしでも、条件を満たしていれば生活保護を受けることができます。
生活保護を受けながら働くことはできる?
生活保護は受給者が自立して生活できるようになるための制度ですので、生活保護を受給しながらも働くことはできます。ただし、収入が最低生活費を超えた場合には、生活保護は受けられなくなります。
医療費は免除になる?
生活保護を受給する方は、国民健康保険、介護保険の支払いができないため、健康保険を脱退します。その代わり医療扶助、介護扶助という形で、医療費を払うことなく治療や介護を受けられるようになっています。
家賃が補助の上限を超えたらどうなる?
家賃の上限を超えても同じ住まいに住み続けるためには、上限を超えた分を生活費から払わなければなりません。ただし、ケースワーカーから上限内の物件に転居するよう指導が入る可能性があります。
まとめ
生活保護の内容と注意点、支給される金額について解説しました。収入が最低生活費を下回っている場合、一人暮らしの方でも生活保護の申請をすることができます。ただし、生活保護を受けるためには、それまで住んでいた家から引越ししたり、車などの資産を売却したりしなければならない可能性があることを覚悟しなければなりません。
また、一人暮らしの方が生活保護を受給しながら賃貸物件を契約する場合には、原則として住宅扶助の額を超えないようにする必要があります。引越し代や火災保険代などの一時的な費用も出してもらえますが、こちらも上限がありますので注意してください。
最後に、生活保護の申請は簡単にはできない場合があります。生活保護を申請する際には通帳や年金証書などの資産・収入がわかるものや、診断書など働けない理由がわかるものを事前に用意することをおすすめします。
もし、ひとりで福祉事務所に行くのが怖い、行ったけど受け付けてもらえなかったという場合には、生活保護相談の同行サービスをおこなっている司法書士に相談してください。専門家の力を借りることで、精神的にも安心して手続きができるでしょう。




