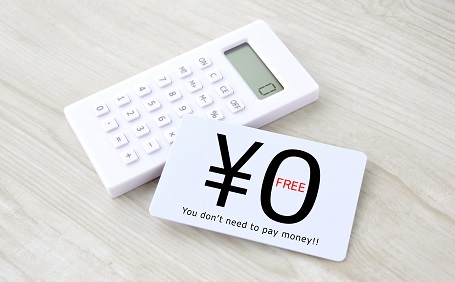家賃補助制度とは?種類や仕組み、注意点をわかりやすく解説

それでは、どのような家賃補助制度があり、どのような要件で、どれくらいの金額を補助してもらえるのでしょうか。本記事では、各種家賃補助制度について詳しく解説していきます。
記事の目次
家賃補助制度とは?
家賃補助制度とは、民間賃貸住宅に住む人を対象にし、家賃の一部を補助する制度です。民間賃貸住宅とは、アパートやマンションなどの賃貸物件のことをいいます。
家賃補助制度は大きく分けて、以下の4つの制度に分けられます。
- 会社の家賃補助制度
- 国・各自治体の家賃補助制度
- 特定の優良住宅に入居した時の補助制度
- 生活が苦しくなり家賃を払うのが困難になった時の補助制度
会社の家賃補助制度は、福利厚生のひとつであり、補助内容は会社により異なります。国・各自治体の家賃補助制度は、各自治体が子育て世帯や高齢者・障がい者などを対象に、安心して住み続けてもらう施策として実施している補助制度です。
また、特定の優良住宅に入居した時の補助制度には、特定優良賃貸住宅などがあります。そして、生活が苦しくなり家賃を払うのが困難になった時の補助制度は、住居確保給付金が代表的な補助制度です。
会社の家賃補助制度

会社の家賃補助制度とは、会社が実施する福利厚生の一環で、社員の住宅費用の一部を補助する制度です。それでは会社の家賃補助制度について詳しく解説します。
福利厚生の一部である
会社の家賃補助制度は、会社の福利厚生のひとつです。この家賃補助制度は、住宅手当や家賃補助、家賃手当などと呼ばれます。会社が保有する借り上げたアパートやマンションに無料で住めたり、近隣相場より安い家賃で住めたりする制度も、会社の家賃補助制度の一種。
家賃補助を受けるための条件は会社ごとに異なる
この家賃補助を受けるための条件は、会社によって異なります。
福利厚生は法定福利厚生と法定外福利厚生に分かれます。法定福利厚生は、健康保険や厚生保険など実施が義務付けられている福利厚生のため、法律で決まった内容を遵守しなければなりません。一方、法定外福利厚生は、家賃補助や通勤手当など会社が独自に設定してよい福利厚生です。
法定外福利厚生である家賃補助は、補助制度を導入するかどうか、あるいは補助額をどうするのかを会社が決定します。そのため、会社の家賃補助制度は各会社により内容が異なるのです。
会社の家賃補助は所得税の対象である
会社からの家賃補助が金額支給の場合、家賃補助には所得税が課税されます。なお、会社から支給される手当はすべて所得税課税対象のため、家賃補助以外の通勤手当や家族手当なども所得税の課税対象です。
国・各自治体の家賃補助制度

民間家賃補助制度のなかには、国や各自治体がおこなっている補助制度もあります。国や各自治体は、居住者の経済的負担を軽くして、居住者がその自治体に定住することを目的に補助制度を実施しているのです。
各自治体の補助制度は自治体ごとに補助内容を決定しているため、自治体ごとで内容が異なります。ここでは、国や各自治体の家賃補助制度について詳しく見ていきましょう。
条件や補助内容は自治体によって異なる
国や各自治体の家賃補助制度は自治体ごとで内容を決定するため、補助額や補助条件などが異なります。
補助導入は新婚の人に定住してもらうためだったり、子育て世帯を応援したり、移住者を呼んだりと、目的はさまざま。そのため、各自治体の家賃補助制度の内容は異なります。補助制度を利用する場合には、利用する地域の自治体に内容を事前に確認しておきましょう。
申請をおこなう必要がある
国や各自治体の家賃補助制度の受ける条件を満たしたとしても、自動的に国や各自治体から補助金が支払われるわけでなく、申請をおこなわなければなりません。家賃補助制度によっては、申請できる期間を設けている場合があります。そのため、補助制度の内容を調べる時には、申請期限があるかも確認しましょう。
現金で支給された補助金は所得税の対象である
現金で支給された補助金は、所得税の課税対象になります。そのため、一定条件を満たす場合は確定申告をしなければなりません。
確定申告が必要かどうかは、受け取った補助金が事業所得か一時所得、雑所得のどれに該当する補助金かにより異なります。それぞれの区分により確定申告が必要な所得金額も違うため、現金で補助金を受け取る時には、税理士などの専門家に所得税について相談しておきましょう。
自治体ごとのさまざまな家賃補助制度
自治体では、それぞれ独自の家賃補助制度を実施しています。ここでは具体的に、東京都千代田区、東京都豊島区、新潟県糸魚川(いといがわ)市の家賃補助制度について簡単な概要をご紹介します。
次世代育成住宅助成(東京都千代田区)

東京都千代田区では、家賃補助制度として「次世代育成住宅助成」を実施しています。次世代育成住宅助成の適用要件や補助金額は、次のとおりです。
【適用要件】
- 千代田区内の民間賃貸住宅かマイホームへの住み替えをする世帯のうち、次の①②いずれかに該当する世帯
①親元近居助成
千代田区内に5年以上居住する親がいる新婚世帯か子育て世帯
千代田区外から区内への住み替えまたは区内での住み替えをすること
②区内転居助成
千代田区内に1年以上住んでいる子育て世帯
千代田区内での住み替えをすること - 世帯の年間所得合計が次の所得範囲内であること
2人世帯の場合:189万6,000円~1,038万8,000円
3人世帯の場合:189万6,000円~1,076万8,000円
4人世帯の場合:189万6,000円~1,114万8,000円 - 原則住み替え先の住宅の専有面積は住み替え前の住宅より広くなること
【補助額】
- 最長8年間補助が受けられる
- 月額:6,000円~8万円
参考:次世代育成住宅助成 (千代田区公式ホームページ)
子育てファミリー世帯家賃助成制度(東京都豊島区)

東京都豊島区では、家賃補助制度として「子育てファミリー世帯家賃助成制度」を実施しています。子育てファミリー世帯家賃助成制度の適用要件や補助金額は、次のとおりです。
【適用要件】
- 子育てファミリー世帯とは、申請時点で15歳以下の児童1名以上と、その児童を扶養している人が同居していることが条件
また、その居住者の条件に加えて住所の移動時に、次の①~⑩のすべてに該当する必要があります - 転居、転入する住宅の面積が①~③の最低居住面積を超えていること
①世帯人数2人未満の場合:30平方メートル
②世帯人数2~4人の場合:10平方メートル × 人数 + 10平方メートル
③世帯人数4人を超える場合:(10平方メートル × 人数 + 10平方メートル)×0.95
①住所移転後1年以内であること
②世帯の前年所得合計が月額26万8,000円以下であること
③豊島区内の民間賃貸住宅へ転居、転入して月額家賃が15万円以下であること
④家賃を滞納していないこと
⑤住民税を滞納していないこと
⑥公的住宅扶助を受けていないこと
⑦補助制度の申込者が賃貸契約上の借主になっていること
⑧住み替え後の民間賃貸住宅の住戸専用面積が居住水準を満たし台所・便所・浴室がある住宅
⑨日本国籍か日本に永住する資格を有している人であること
⑩従業員寮や間借りなど2親等内の親族の所有住宅ではないこと
【補助額】
- 最大月額:2万5,000円(申請月から3年間・4年目からの補助額は2分の1)
参考:子育てファミリー世帯家賃助成制度 (豊島区公式ホームページ)
UIターン促進家賃支援事業補助金(新潟県糸魚川市)

新潟県糸魚川市では、家賃補助制度として「UIターン促進家賃支援事業補助金」を実施しています。UIターン促進家賃支援事業補助金の適用要件や補助金額などは、次のとおりです。
【適用要件】
- 次の①~⑦すべてに該当するUIターン者※1
①申請日において賃貸住宅※2の賃貸借契約を締結した賃借人であり、現に当該住宅に居住している方
②初回の申請年度の4月1日において、年齢が18歳以上40歳未満の方(子育て世帯※3の場合は子の父母のいずれか一方の年齢が40歳未満の方)
③常用労働者として就業している方、個人事業を営んでいる方、又はテレワークで引き続き移住元の業務を行う方
④他の公的制度による家賃助成を受けていない方
⑤勤務する事業所の人事異動等により、市外へ転出する見込みがない方
⑥市税を滞納していない方
⑦国家公務員及び地方公務員でない方※1…UIターン者
定住する意思をもって市外から糸魚川市に転入して住民登録をした者※2…賃貸住宅
一戸建て住宅又は集合住宅で、当該賃貸住宅の所有者との賃貸借契約により当該賃貸住宅の賃借人が自己の居住の用に供する住宅。
ただし、公営住宅又は社宅、官舎、寮等の給与住宅を除く※3…子育て世帯
出生した日から満18歳に達した日以後の最初の3月末日までの間にある子どもがいる世帯
【補助額】
- 最長2年間受けられる(交付決定後、最初に家賃を支払った月から)
- 家賃の2分の1 上限20,000円/月(居住誘導区域※4内の場合、上限25,000円/月)
- 子育て世帯の場合
家賃の3分の2 上限30,000円/月(居住誘導区域※4内の場合、上限35,000円/月)※4…居住誘導区域
人口密度の維持による生活サービスやコミュニティの維持のために、糸魚川市立地適正化計画で定められた区域
参考:UIターン促進家賃支援事業補助金 (新潟県糸魚川市ホームページ)
特定優良賃貸住宅

特定優良賃貸住宅(特優賃)とは、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」に基づいて建設された賃貸住宅のことです。特定優良賃貸住宅として認められるには、専有面積や構造などに条件があり、一般の賃貸物件より住宅性能が高い建物となります。中堅所得階層のファミリー向けに供給される賃貸物件のため、間取りは2LDK~3LDKが多く、単身者や大家族に向けた間取りは少ない傾向にあります。
特定優良賃貸住宅によっては家賃補助を受けられなかったり、家庭の合計所得に条件が付されたりします。そのため、特定優良賃貸住宅家賃補助制度が利用できるかを、賃貸借契約前に不動産会社に確認しましょう。
入居条件がある
特定優良賃貸住宅に入居する時の条件として、各自治体や賃貸物件により入居者の世帯年収に上限や下限を設けているケースがあります。例えば、名古屋市住宅供給公社の特定優良賃貸住宅の場合は、所得月額は20万円以上60万1,000円以下であることが入居条件です。
特定優良賃貸住宅は数が比較的少ない
特定優良賃貸住宅は建設数が少ないため、入居することが難しい賃貸物件です。また、特定優良賃貸住宅の家賃補助制度自体を実施している自治体が減少してきており、新規入居は困難な状態に。
仮に、特定優良賃貸住宅の入居募集があったとしても人気が集中し、この場合には抽選で入居を決めることがあります。そのため、抽選に従った日に引越しをする必要があり、入居のタイミングを計れる方ではないと入居できない可能性があるでしょう。
初期費用が抑えられる
特定優良賃貸住宅に入居できると国や自治体から家賃補助が受けられるほか、礼金や仲介手数料、更新料が不要のため初期費用も抑えられます。
自治体から補助金が適用される
特定優良賃貸住宅の家賃補助適用要件を満たした場合、自治体などから補助を受けられます。ただし、適用要件を満たさなくなった場合は、家賃補助が減額になったり補助が打ち切られたりすることも。特に、入居者の人数が変更になることや、所得が増減して適用要件から外れてしまうことが多くあるため注意しましょう。
家賃補助の適用要件を満たさなくなった場合の対処は、物件や自治体ごとに異なります。条件などは、あらかじめ確認が必要です。
ヨコハマ・りぶいん(神奈川県横浜市)

神奈川県横浜市では、家賃補助制度として「ヨコハマ・りぶいん」を実施しています。ヨコハマ・りぶいんの適用要件や補助金額などは、次のとおりです。
【適用要件】
- 申込本人と同居者が横浜市の住民基本台帳に記載されている人が申請すること
- 親族がいる場合一定条件を満たす親族と同居すること
- 収入基準条件を満たす人であること
- 連帯保証人を立てられる人であること
- 家賃の3カ月分に相当する敷金を預け入れできること
- 住民税を滞納していないこと
- 申込者と同居の親族が自己名義の家屋を所有していないこと
- 現在ヨコハマ・りぶいん制度による助成を受けていないこと
【補助額】
- 月額家賃の1.75%~50%を自治体が負担
参考:ヨコハマ・りぶいん(横浜市公式ホームページ)
新婚・子育て世帯向け家賃減額補助事業(大阪府)

大阪府では、家賃補助制度として「新婚・子育て世帯向け家賃減額補助事業」を実施しています。新婚・子育て世帯向け家賃減額補助事業の適用要件や補助金額などは、次のとおりです。
【適用要件】
- 対象住宅への入居する際は、次の①②の2つの要件を満たすことが条件
①月額の所得が15万3,000円~60万1,000円の間であること
②同居親族がいること - 家賃の減額の対象となるためには、次の①②の2つの要件を満たすこと世帯であることが条件
①新婚世帯:申込日時点で婚姻1年以内、かつ夫婦の年齢がともに50歳未満の世帯であること
②子育て世帯:申込日時点で小学校卒業前の子どもを扶養している世帯であること
【補助額】
- 入居者世帯の月額所得:26万8,000円以下の場合の月額補助額は2万円
- 入居者世帯の月額所得:26万8,000円を超え32万2,000円以下の場合の月額補助額は1万円
- 入居者世帯の月額所得:32万2,000円を超える場合の月額補助額は0円
参考:新婚・子育て世帯向け家賃減額補助事業(大阪府公式ホームページ)
住居確保給付金
住居確保給付金とは生活困窮者自立支援法に基づき、離職などにより経済的に苦しくなり、居住している賃貸物件から退去しなければならないおそれのある人に対して、家賃相当額を支給する制度です。ここでは、住宅確保給付金について解説していきましょう。
給付を受けるための対象要件がある
住居確保給付金を受けるためには、一定条件を満たす必要があります。住居確保給付金の給付要件は、次のとおりです。
- 家計を主として支えている人が、次の①②の条件のどちらかを満たすこと
①離職や廃業後2年以内であること
②個人の責任や都合ではないのにも関わらず給与などを得る機会が、離職や廃業と同程度まで減少している状態であること
- 直近の月の世帯収入合計額が、次の①②の金額を合計した金額を超えていないこと
①住民税の均等割が非課税となる額の1/12
②家賃 - 現在の世帯の預貯金合計額が各自治体で定める額を超えていないこと
- ハローワークに登録したりして求職活動を積極的におこなうこと
上記の条件を満たした場合、住居確保給付金が支給されます。
ただし、支給額は居住している自治体や世帯の人数により異なります。補助額など詳しい情報は、厚生労働省や各自治体のホームページなどでご確認ください。
参考:厚生労働省 生活支援特設ホームページ 住居確保給付金
参考:厚生労働省 住居確保給付金について (PDF)
まとめ
家賃は月々の支出のなかでも、比較的高額な支払い項目です。そのため、家賃補助制度の受けられる条件を満たしているのであれば、家賃補助制度を活用することも選択のひとつです。
家賃補助制度には、会社の福利厚生や国・各自治体の家賃補助制度、特定優良賃貸住宅の補助制度、住宅確保給付金などがあります。各補助制度は利用できる条件が異なるため、それぞれの適用要件を把握しておかなければなりません。適用要件を把握しておけば、家賃補助制度を受けられる可能性が高まります。家賃補助制度の条件を満たしているのであれば、制度を活用し支出を減らし、ゆとりある生活を送っていきましょう。