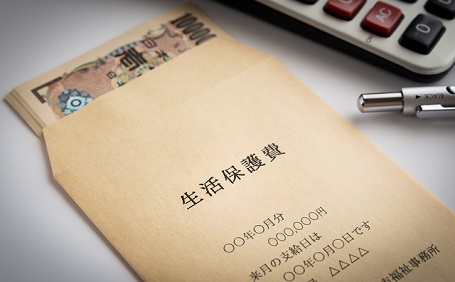家賃滞納するとどうなる?督促や強制退去までの流れと対処法を解説

そこで、今回は家賃を滞納してしまった時の一般的な流れやリスク、トラブルに発展しないようにするための対処法などについて解説します。現在の給料に対して家賃の負担が大きい方や、すでに家賃の滞納をしてしまい悩んでいる方はぜひ参考にしてください。
記事の目次
家賃を滞納するとどうなる?滞納してしまった場合の流れ

家賃を滞納した場合、支払いの遅延に対して延滞損害金が発生します。損害金の請求頻度や方法は保証会社や管理会社などによって異なりますが、すぐに裁判沙汰や強制退去となるわけではありません。以下では、強制退去となるまでにどのような手順を踏んでいくのかを見ていきましょう。
【翌日~1カ月】電話や督促状による連絡
家賃支払い日の翌日以降、保証会社や管理会社、大家さんから賃借人本人へ電話連絡や督促状の送付がおこなわれます。賃貸では保証会社を利用するケースが多く、数日経過しても賃借人から連絡や入金がなかった場合には、保証会社が大家さんに対して家賃を立て替え払いします。
支払いに遅延が生じておよそ1カ月以内に、賃借人へ支払いの意思を確認しようとするのが一般的です。
【1~2カ月】連帯保証人への連絡・督促
賃借人本人からの家賃回収が難しいと判断された場合、管理会社や大家さんから連帯保証人に対して連絡や督促をおこないます。連帯保証人は賃借人本人と同じ債務を負っていることから、家賃の支払い義務が生じます。
また、連帯保証人に家賃滞納を知らせることで、賃借人へ催促してもらい早期解決を図る目的もあるでしょう。
保証会社を利用している場合はどうなる?
大家さんが不動産経営をおこなうにあたり、家賃滞納リスクや入居者トラブルリスクなど、さまざまなリスクが考えられます。未然のトラブル回避や大家さんの安定した家賃収入を確保するために、賃貸では保証会社への加入が求められるケースが多い傾向にあります。
連帯保証人を立てるのではなく保証会社を利用している場合は、管理会社や大家さんから保証会社に代位弁済を請求し、保証会社が家賃を立て替え払いしなければなりません。以後の督促などは、保証会社から賃借人に対しておこなわれます。
【3カ月~】賃貸借契約の解除通知の送付
家賃滞納から3カ月程度が経過すると、内容証明郵便にて賃貸借契約の解除通知が送付されるのが一般的です。賃借人に解除通知が送られたことを証明する郵便方法なので、「通知が届いていない(確認していない)」とごまかすことはできません。しかし、3カ月以内に家賃や延滞損害金を支払えば、「継続契約書」を取り交わして住み続けることが可能です。継続契約書には、次に家賃滞納をした際の明け渡しに関する条件も記載されるケースが多いため、滞納を繰り返さないように十分注意しましょう。
【3~6カ月】裁判などによる法的手続き
上の手順で解決しない場合には、裁判などによる法的手続きがおこなわれます。滞納している賃借人に支払い能力がある場合には「支払督促」や「少額訴訟」をおこなうのが一般的です。一方、支払い能力がない場合は「明け渡し訴訟」をおこないます。明け渡し訴訟を請求するには多くの費用と時間を要し、もっとも労力がかかる方法なので、大家さんや管理会社が手の施しようがない時の最終手段といえるでしょう。
【6カ月~】強制退去
滞納が3カ月以上続き支払いの意思もなく、賃貸人と賃借人の間の信頼関係が喪失していると判断された場合、大家さんから契約解除や強制退去、家賃回収に向けた法的な申し立てが可能です。法的手続きの結果、強制退去や給与などの差し押さえが執行されることになるでしょう。
ただし、先述のとおり訴訟を起こすと、費用負担は大家さんであるうえに時間もかかります。強制執行となる前に、話し合いによって退去に合意してもらう「任意による退去」という方法を取るケースが多い傾向にあります。
賃貸の家賃を滞納するとどんなリスクがある?

家賃を滞納することで、退去すること以外にどのようなリスクが生じるのでしょうか。以下では「現在の家に住めなくなる」だけでなく、起こりうるリスクについて解説していきます。
延滞損害金を支払うことになる
先述のとおり、家賃を滞納すると滞納分の家賃だけでなく延滞損害金が発生します。延滞損害金の利率の上限は法律で14.6%と定められており、14.6%以内の利率を大家さんが自由に設定することが可能です。ただし、賃貸借契約書に延滞損害金の利率に関して記載がない場合には、一律3%となります。
例えば家賃8万円で延滞日数が90日の場合、延滞損害金利率が14.6%であれば2,880円、3%であれば約590円です。14.6%という利率はクレジットカードの利息と同等であるほか、延滞日数が長ければ長いほど支払う金額は高くなっていきます。延滞損害金が膨れ上がらないよう、十分注意しましょう。
信用情報に延滞したことが記録される
家賃を滞納した場合、信用情報に延滞した記録がつく可能性があります。特に、保証会社を利用している場合は注意が必要です。家賃を滞納して2カ月が経過すると、信用情報に登録されるケースが多いです。また延滞の記録がつくことで、クレジットカードやローンの審査に落ちたり、発行済みのクレジットカードが利用停止になったりするケースがあります。
家賃滞納によって、生活全般に悪影響を及ぼす可能性があることを理解しておきましょう。
今後、賃貸物件を借りづらくなる可能性がある
信用情報に延滞記録があると、クレジットカードやローンの審査に通りづらくなるだけでなく、賃貸物件の入居審査にも影響が出ます。同じ不動産グループや関連会社の物件が借りづらくなったり、保証会社の審査に通らないため借りられる物件が限られたりする可能性があります。その場しのぎで家賃滞納をおこなうと、今後の生活が危ぶまれるでしょう。
家賃滞納後も住み続けるにはどうしたらいい?

何らかの事情により家賃を滞納してしまった場合、同じ物件に住み続けることはできるのか不安に感じることもあるでしょう。ここからは、家賃を一定期間滞納している場合を想定し、その対処法について解説します。
督促の段階で支払いの意思を示す
大家さんや管理会社などから家賃の支払い督促が届いたら、しっかり支払う意思を示しましょう。賃貸借契約は、大家さんと賃借人との間の信頼関係のもとに成り立つ契約です。やむを得ない事情があったとしても、家賃滞納は賃貸借契約に違反していることになります。
大家さんの心証が悪くならないよう、いち早く連絡して滞納した理由やいつまでに支払えるのかを伝え、大家さんに安心してもらいましょう。すぐに支払うことが難しい場合には、分割払いの相談をしてみるとよいかもしれません。
契約解除が成立する前に家賃と延滞金を払う
契約解除となる前に、滞納分の家賃と延滞金を支払うことが大切です。一般的に滞納して3カ月以内に支払うことで、解除通知が届いたとしても契約を継続できる可能性が高くなります。大家さんなどが法的手続きに移って契約解除が成立する前に、支払いを完了させるようにしましょう。
事情を説明して支払い計画を立てる
支払う意思はあるものの、すぐに滞納分を全額支払うことが難しいケースもあります。その際は一時的に支払いができない事情を説明し、分割払いや支払いの期間を決めるなど、支払い計画を立てるようにしましょう。大家さんが事情を理解してくれれば、提案を受け入れてくれるかもしれません。
できるだけ具体的に金額や日付の数字を示した支払い計画を立てるのが、受け入れてもらうためのポイントです。
家賃を滞納する前にできる対処法
上記では家賃を滞納してしまった場合の対処法について紹介しましたが、本来は滞納を未然に防ぐ対処をするべきです。家賃滞納は大家さんと賃借人の信頼関係に亀裂が入りやすく、解決に時間がかかるケースも少なくありません。家賃滞納を未然に防ぎ、トラブルなく過ごせるように注意しましょう。以下では、家賃を滞納する可能性がある場合を想定して対処法を解説します。
支払いを忘れないようリマインドを設定する

お金が足りないわけではなく、「支払い忘れ」のケースも家賃滞納を引き起こす原因の一つです。一般的に家賃の支払いは指定口座からの引落し、もしくは振り込みのいずれかですが、「口座に家賃分のお金が入っていなかった」「振込日を忘れていた」というケースもあります。
支払いを忘れないよう、携帯のカレンダーや指定口座のアプリなどでリマインドを設定しておくと安心です。
滞納しそうな時は大家さん・管理会社に相談する
どうしても滞納しそうな状況に陥った場合は、できるだけ早めに大家さんや管理会社に相談するようにしましょう。正直に事情を説明すれば、理解を得られるかもしれません。一時的に支払いが難しい状況なのであれば、分割支払いや支払期限に猶予を与えてくれる可能性があります。
何も言わず滞納してしまうと督促や契約解除の手続きが進められるため、事前に状況を説明して解決したい意向を伝えるようにしましょう。
公的支援制度について調べる
場合によっては、公的支援制度を利用できる可能性があります。条件は限定されますが、離職や廃業などの事情により家賃の支払いが難しい場合に、家賃額が支給される制度が利用可能です。「住居確保給付金」や「生活福祉資金貸付制度」など、国や自治体が実施する支援制度で条件に当てはまるものがないか確認してみましょう。
借入は返済まで見越して利用する
家賃滞納後のリスクを避けるために、家族や友人、金融機関などから一時的に借り入れすることも方法の一つです。キャッシングは金利が高く返済の負担が大きくなりがちですが、家族などであれば無利息でお金を貸してくれる可能性があります。ただし、どこから借り入れする場合でも、しっかりと返済計画を立てたうえで借りなければ、後々のトラブルにつながりかねません。どのような場合でも返済までを見越し、お金を借りることが重要です。
家賃は無理のない金額にする
家賃が収入に見合わず支払いが難しい場合には、無理のない家賃の家に引越すことも視野に入れましょう。そもそも家賃滞納が発生するのは、生活資金のなかで家賃の割合が大きく、支払いが苦しくなるケースがほとんどです。
一般的に、無理のない家賃の目安は月収の20~30%以下といわれています。支払いが厳しい月がある、使っていない部屋があるような場合には、思い切って引越すほうが負担を減らせるかもしれません。
現在の収入に合った家賃の家への引越しを検討している場合は、以下から物件を検索してみてください。
家賃を滞納することについてよくある質問

ここからは、家賃を滞納することについて考えられる、よくある質問を解説していきます。
家賃を滞納はどのくらいまで大丈夫?
家賃は滞納しないことが基本です。しかし、さまざまな理由で滞納してしまうこともあるかもしれません。一般的には、強制退去となるまで6カ月程度の猶予があります。
支払い期限の翌日から1カ月ほどで電話や督促状による連絡が入り、賃借人本人と連絡が取れない場合は連帯保証人に対して連絡や督促がいきます。3カ月滞納が続いた場合は賃貸借契約の解除通知が送付され、法的手続きをおこない6カ月ほどで強制執行・退去となるケースが主な流れです。
家賃を滞納するリスクは?
家賃を滞納すると、延滞損害金が発生するため滞納分の家賃に加えて支払いが必要になります。また、信用情報に延滞の記録がつく可能性があり、賃貸物件が借りづらくなるかもしれません。一度の滞納で、生活全体に大きな影響を受けてしまうかもしれないので、十分注意が必要です。
家賃の支払いが遅れたらどうする?
家賃の支払い期日を過ぎてしまったら、まず大家さんに支払いの意思がある旨を伝えましょう。事情を理解してもらったうえで支払い計画を立て、契約解除となる前に支払いを完了させることが大切です。
また、支払いが遅れそうな場合は事前に大家さんや管理会社に相談したり、忘れやすい方はリマインドを設定したりするなど、トラブルにならないための対処を心がけてください。滞納を防ぐには、無理のない家賃設定や公的支援制度の活用も検討するといいでしょう。
まとめ
今回は賃貸物件の家賃を滞納するとどうなるのか、督促から退去となるまでの一般的な流れや対処法について解説しました。大家さんとの信頼関係が重要な賃貸借契約は、コミュニケーションをしっかり取ることで継続できるケースも少なくありません。
家が借りられなくなるなどの事態に発展することがないよう、収入に見合った家賃の物件を借りるようにして、大家さんと良好な関係を保てるように滞納リスクをなくしましょう。