アパートの最強ゴキブリ対策!侵入経路や、駆除・予防方法を解説

記事の目次
ゴキブリはどこから侵入する?

新築アパートやマンションのほか、借りる前に害虫駆除をおこなってから入居した部屋にも、ゴキブリが出現する可能性はあります。では、いったいどこから侵入してくるのでしょうか?
玄関
ゴキブリの侵入経路の1つ目は、玄関です。「玄関の扉に隙間なんてない」と思う方は、一度見てみてください。うっすらとでも光が漏れていれば、隙間が開いている証拠。幼虫であれば、0.5mmの隙間があれば侵入可能です。ほかに、人が扉を開け閉めした際に一緒に入ったり、扉に付いている郵便受けの隙間から入ったりする場合もあります。
窓・網戸
外からの侵入経路の2つ目は窓。なんと、外から直接飛んで入ってきます。網戸にしているから大丈夫と思っている方も要注意。窓は雨を保つために密閉度が高くきっちり閉まるようにできていますが、網戸にそこまでの気密性はなく、年季が入ると隙間もできることからゴキブリの侵入を完璧に防ぐことは難しいのです。
排水溝
排水溝も外と室内をつなぐ経路のひとつ。排水溝には動物や虫が入り込まないように、S字トラップやU字トラップといった仕掛けがついています。これはSやUの曲線部分に溜まった水で、虫などの侵入を防ぐ仕組みです。しかし、水が溜まっていなかったり、そもそも排水トラップがついていなかったりする場合は、排水溝を通ってゴキブリが侵入してくることがあります。中にはゴキブリを排水溝に流して、処理したつもりになっている方がいるかもしれません。しかし、実際にはその程度で駆除できるものではなく、適切な対処が必要です。
換気扇や通風口
換気扇や通風口は、部屋の空気を入れ替えるために必要なものです。しかし、ここもゴキブリの侵入口となり得ます。換気扇についたギトギトの油とほこりは、ゴキブリの大好物。ニオイで寄ってきて、そのまま室内に侵入してしまいます。
エアコンの室外機
エアコンからゴキブリが出てきたという経験をしたことのある方は、室外機から侵入したと考えるかもしれません。しかし実際は、他の場所から侵入したゴキブリが、エアコンの中に隠れていたということが多いでしょう。エアコンの本体と室外機をつなぐ配管から、ゴキブリが入ってくるということはあまり考えられません。隙間があれば冷媒ガス漏れになりますし、本当に室外機からゴキブリが入ったということがあったとすれば、エアコンの故障が考えられます。エアコン関連でゴキブリが入ってくるとすれば、考えられるのは設置穴。エアコンの穴は設置時にパテで防ぎますが、パテが劣化すると隙間ができ、そこからゴキブリが入ってくることがあるかもしれません。
ベランダ・バルコニー
ベランダにゆとりのあるスペースがあれば、鉢植えを置いて花を育てたり、家庭菜園のプランターでハーブや野菜を育てたりするのも楽しみのひとつです。ただ、毎日水やりをして湿った植木鉢は、ゴキブリにとって水分補給の場所。土の中や植木鉢の裏に隠れられる格好の住処になります。潜んでいたゴキブリが、窓を開けた隙に部屋の中に侵入してきたということも考えられるでしょう。
宅配便で届いた段ボール
段ボールは、ゴキブリが好むような、暖かくジメジメとした生息環境ができやすい絶好の住処です。場合によっては、宅配便で届いた荷物にゴキブリの卵が付着していて、段ボールを放置している間に成虫となって室内で発生してしまうケースも。そのまま気が付かずにいると、何匹も増殖してしまう可能性もあり、外から持ち込まれた段ボールには注意が必要です。
ゴキブリが出やすい時期は?
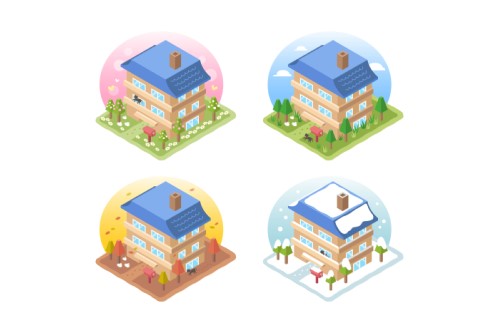
ゴキブリは、高温多湿の時期になると動きが活発になる習性があり、特に発生しやすい季節は夏です。ちなみに産卵時期となるのは秋で、冬には静かに身を潜めつつ、春になると成虫になりはじめます。よく目にしやすいのは夏頃ですが、そもそもゴキブリの発生源をしっかりと根絶させるには、特に秋や春に駆除しておくのがベスト。なかには冬でも活動している種類もあるので、基本的には年中対策をしておくのが無難です。ゴキブリに遭遇しやすい夏はもちろん、秋や春の予防策にも注目しつつ、日頃から侵入・繁殖させないための対策を心がけるようにしましょう。
ゴキブリが出やすい部屋の特徴は?

ゴキブリが好む生息環境にあると、当然ながら遭遇する危険性はぐっと高くなります。なおゴキブリが出やすい部屋の特徴としては、おもに次のような例が挙げられます。
部屋が汚れている
食べ残しや生ゴミはもちろん、ホコリや髪の毛なども、ゴキブリにとっては生き延びるための立派なエサになります。またキッチン周りやシンクなどが汚れていると、ニオイに寄ってきてしまうことも考えられるので要注意。さらに水分が溜まっている場所を好む傾向も見られるため、お風呂やキッチンなどの水場がずっと濡れた状態になっていると、ゴキブリが集まりやすくなってしまいます。あまり掃除されていない部屋だと、ゴキブリが寄ってきやすい条件が揃いやすいともいえるでしょう。
宅配便がよく届く
前述にもあるように、宅配便の段ボールにはゴキブリの卵が付いていることもあり、知らず知らずのうちに室内へ持ち込んでしまうケースがあります。ずっと放置していると卵が孵化してしまう可能性があるうえに、段ボールはゴキブリが好む生息環境でもあるので、いつの間にか侵入して潜んでいる場合も。宅配便をよく利用していて、さらに段ボールが溜まっている部屋では、ゴキブリに遭遇する確率は高くなりやすいため注意が必要です。
家電製品が多い
家電製品は、電力を使うことで熱を発しやすく、特にその周辺はゴキブリが好むような暖かい空間ができやすくなります。また大型家電の場合は、壁に寄せて配置していることも多く、ゴキブリが住みやすい狭く暗い場所が自然とできているケースも。こうした家電製品がある分、ゴキブリの住処も増えやすくなる傾向にあります。
植物を育てている
植物が生えている土は、水やりで湿っていることが多く、湿気を好むゴキブリの住処にもなりやすい場所です。鉢のなかのすき間など、暗くて身を潜めやすい空間もあり、なおかつジメジメとしていてゴキブリにとっては絶好の生息環境といえます。観葉植物の周辺も、ゴキブリが出やすい要注意スポットです。
窓や扉を開けっぱなしにしている
窓や扉が開いたままになっていると、ゴキブリが簡単に部屋まで侵入できてしまいます。ちょっとしたすき間でもゴキブリにとっては侵入経路になるので、窓や扉が開いていれば、当然ながら室内に入れてしまいます。また窓の網戸も、比較的すき間が多く侵入経路になりやすいので、特に夏場には注意が必要です。
ゴキブリが隠れやすい場所は?

具体的にゴキブリが好むのは、どのような場所なのでしょうか。まずひとつめは、湿気の多い水回りの暗がりといえば、洗面所の下、キッチンのシンク下など。暗くて狭い場所といえば押し入れの奥、大型家具の裏や隙間などが挙げられます。気付かないだけで、足元の暗がりや壁の隙間にゴキブリが潜んでいるかもしれません。
ゴキブリを発見!自分で駆除するには?

「ゴキブリは1匹見つけたら100匹いる」と聞いたことのある方は多いでしょう。家の中でよく発見されるゴキブリは「クロゴキブリ」という種類で、鞘状の卵を産みますが、1つの鞘の中には22〜28個ほどの卵が入っています。メスのクロゴキブリは、半年の生涯のうちに平均10回ほど卵鞘を産むといわれています。つまり、1匹のメスゴキブリから、シーズン中に200匹以上のゴキブリが誕生する可能性があるということです。
こうして考えると、「1匹見つけたら100匹いる」というのも、あながち間違いとはいえないかもしれません。とにかく、見つけたらしっかり駆除しましょう。
燻煙剤で駆除する
短時間で徹底的に駆除するのならば、燻煙剤がおすすめです。ミクロの霧が部屋の隅々まで行き渡り、隠れたゴキブリにもしっかりと有効成分を届けてくれます。ただし、それだけ威力の強い殺虫剤ですから、人体やペットへの影響も心配です。必ず、使用上の注意をよく読んで使いましょう。特に病人や妊婦、子どもは薬剤(煙)に触れないようにして、セットした部屋から退室してください。少なくとも2~3時間以上は放置し、充分に換気をしてから中に入るようにしましょう。燻煙剤を撒いたあとの部屋は、すみずみまでしっかりと掃除することも大切です。
設置型の薬剤で駆除する
燻煙剤を撒くために部屋を片付けたり、そのあとに掃除したりするのが面倒という方は、置き型の薬剤が簡単です。ゴキブリの好むニオイの誘引剤が、ゴキブリを薬剤に誘き寄せます。殺虫効果の強いホウ酸を含む薬剤を食べたゴキブリは、巣の中でホウ酸を多く含んだフンをし、そのフンを食べた仲間のゴキブリも次々と駆除できます。
駆除剤やアロマスプレーで駆除する
前述の2つは、潜んでいるゴキブリを駆除する方法です。もしゴキブリを見つけたら、スプレーですぐに駆除しましょう。動きの早いゴキブリを一発で仕留める即効性の高いもの、泡のスプレーで閉じ込めるもの、殺虫成分の入らない冷却剤スプレー、天然由来成分で虫除けと殺虫するアロマタイプなど種類はさまざま。ペットの苦手とする香りや成分を含むものもあるので、ペットを飼っている方は注意書きをよく確認しましょう。
発生を防ごう!最強ゴキブリ対策は?

ゴキブリの駆除ができたら、続いて、ゴキブリが発生する原因となるものを排除するようにしましょう。ここからはゴキブリの発生を防止する方法について解説していきます。
侵入経路をしっかり塞ぐ
クロゴキブリは外と室内をウロウロと行き来しながら生活しており、さまざまな経路から侵入してきます。ゴキブリを見かけたら、隙間をしっかり塞いで入らないように対策し、玄関や窓はちゃんと閉めましょう。隙間がある場合には隙間予防のテープやシートなどを使えば、自分で簡単に補修できます。網戸や窓枠など経年劣化で隙間があるなら、隙間テープを貼ったり張り替えたりという対策が有効です。
食べものや汚れた食器を放置しない
食べものや汚れものなど、ゴキブリのエサになるものを置かないことも一つの対策です。食べ残しや生ゴミ、汚れたままの食器についたニオイを嗅ぎつけてゴキブリがやってきます。特にゴキブリが活発に活動する夜に、汚れた食器をそのまま放置しておくのは危険です。使ったスポンジに食品のカスが残っていると、それもエサになります。スポンジなども、清潔に保っておけばさらに安心でしょう。また、ゴキブリが発生しやすい季節は生ごみのニオイが漏れないように、毎日密閉して処分してください。
キッチンの排水溝は定期的に掃除する

排水溝ネットが登場して、排水溝の掃除は格段に楽になりました。しかし、ネットを取り外して新しいものに交換するだけではなく、定期的にカゴや排水トラップも掃除しましょう。
ゴミ捨ては短いスパンでおこなう
地域によって、ゴミ収集日が週2日など決まっているでしょう。それでも、小さいサイズのゴミ袋を使って毎日密閉しておくとゴキブリ予防になります。収集日には、毎回忘れないようにゴミ出しをしてください。集合住宅で24時間ゴミ出しができる場合は、毎日夜にゴミ出しすると安心できそうです。
室内の物陰を掃除する
毎日の掃除では大変ですが、大きな家具や家電の下など影になる場所はこまめに清掃しましょう。特に食べもののカスが落ちやすいシンク下、冷蔵庫の下、コンロの下などにカスが落ちたときは、すぐ掃除しておくといいでしょう。
新聞紙や段ボールを放置しない
段ボールはその構造上、保温と保湿効果があります。段ボールがつくる高温多湿の環境は、ゴキブリにとっての好環境。湿気を含みやすい新聞紙も同様です。重ねて捨てる新聞紙や段ボールの隙間の暗がりは、ゴキブリが身を隠すにも、卵を産み付けるにも最適な空間になります。特にベランダや物置などの湿気を含みやすい場所に、こういった紙類を放置しないようにしましょう。
結露や湿気を放置しない
結露のような水分や湿気が溜まった、ジメジメとした場所を好むのもゴキブリの習性です。湿度の高い場所に集まりやすいので、そのまま放置せずに、こまめに換気したり結露を拭き取ったりなどの対策も重要。特に結露対策として、発生防止用のスプレーやシートなども市販されているので、窓付近の水気が気になる時には活用してみるとよいでしょう。
ゴキブリが発生しにくい部屋選び

ゴキブリが絶対に出ない部屋を探すのは難しいですが、一般的にゴキブリが侵入しにくい・出にくい部屋には条件があるといわれています。ゴキブリが侵入しにくい部屋の条件は以下のとおり。引越しの予定がある方、住み替えの予定がある方は、事前にチェックしておきましょう。
新築・築浅
建物自体が新築であれば、最新の設備が使われているので隙間は少なく、前の入居者がいないことからゴキブリが住み着いている可能性は低いでしょう。築浅の物件の場合も経年劣化による隙間などは少なく、同様のことが考えられます。前の入居者の生活状況によりますが、滞在期間は短いことから汚れも少なく、ゴキブリが住み着いている可能性は低いでしょう。
日当たりがいい
日がよく当たる部屋は明るいので、暗い場所が好きなゴキブリにとっては居心地の悪い空間になります。
風通しがよく湿気がこもりにくい
南北や東西に窓があるなど空気の通り道がある部屋は、風通しがよく湿気がこもりにくくなります。ジメジメとした場所が好きなゴキブリは住み着きにくいでしょう。
上層階
ゴキブリは体の重さや大きさの割に羽が小さく、動きが活発になる夏でも上へは最高5m程度しか飛べないといわれています。建築基準法で居室の天井高は2.1m以上と決められていますが、マンションの天井高は2.4mが平均的。そのため、3階以上であれば、地面から飛んで入ってくることは考えにくいでしょう。もちろん、通気口や植え込みの木などを伝ってあがってくることもあるので、可能性がゼロとはいえません。しかし、上層階であるほど窓からの侵入を防げる可能性が高いでしょう。
ポストとドアが離れている
玄関ドアに直接穴があいているタイプのポストは、その隙間からゴキブリが侵入してくる可能性があります。不便ではありますが、ポストとドアが別々または集合ポストのある物件を選ぶと、ゴキブリは入って来にくくなるでしょう。
管理が行き届いている
マンションなどの集合住宅では自室だけをいくらキレイに掃除しても、周りにゴキブリの好む環境があると、そこが発生源になります。特に気をつけたいのがゴミ収集場所。常にゴミ出しできるタイプのマンションだと、ゴミ収集庫が定期的に掃除されているか、どのくらいの頻度でゴミ収集されているかをチェックしましょう。自治体のゴミ回収に出す場合は、回収日以外の日にゴミが捨てられていないか、ゴミが散乱していないかなどを確認してみてください。住み替えを考えている方は、内見の際にゴミ捨て場の状況を見ておくといいですね。さらに建物の外から、住民がバルコニーにゴミを放置していないか確認しておくとより安心です。
窓の外に電柱や木がない
窓の近くに電柱や高い木があれば、そこから侵入する可能性もあるでしょう。そのため、窓のそばに電柱や木がない部屋を選ぶのも一つの方法です。
近隣に飲食店やコンビニがない
飲食店やコンビニは食材を扱うため、きちんと清掃をしていてもゴキブリの発生するリスクは高くなりやすいでしょう。
近隣に公園がない
ゴキブリは公園のような茂みが多く湿気がある場所に隠れていることがあるので、近くにそのような施設がないほうが安心です。窓を開けっぱなしにしないなどの対策が必要です。
近隣の道路や建物が清潔
自身が住む部屋や建物自体が清潔であること以外に、周りの環境も大切です。ゴミが放置されているような建物が多いと、ゴキブリが集まりやすく危険。周辺環境もよく確認しておきましょう。
ゴキブリが出にくいと思われる環境にあり、侵入されにくい部屋を選んだとしても、発生する確率はゼロではありません。また、すべての条件を満たす部屋を探すのも、限られた予算の中では至難の業です。そこで、引越しの前後には、事前に引越し先のゴキブリ対策をしておきましょう。
引越しの前後にもゴキブリ対策をしておこう
いざ引越しが決まったら、荷物を運び入れる前と後にやっておきたいゴキブリ対策を、それぞれご紹介していきます。
荷物を運び込む前の対策
引越し前の部屋は空っぽの状態。だからこそ、できる対策があります。
燻煙剤を焚く
入居前には管理会社が部屋を清掃してくれていて、基本的にキレイな状態で引き渡されます。しかし、目の届かない暗所にゴキブリが隠れていたり、卵が残っていたりする可能性は拭えません。まだ荷物がない状態で、部屋のすみずみまで殺虫しておくと安心でしょう。
可能であれば、鍵の受け取りと電気の開通を引越し作業の前日にしておき、燻煙剤を焚いて3〜4時間密閉しておきます。しっかりと害虫駆除ができたら、すみずみまで掃除機をかけて事前準備は完了。翌日に、すっきりした気分で引越し作業を始めましょう。
燻煙剤には煙タイプと無煙タイプがありますが、アパートやマンションなどの集合住宅では周りに迷惑がかからないよう無煙タイプを選んでください。ゴキブリだけではなく、ダニやノミも退治してくれるタイプのものを選ぶと、他の害虫もまとめて事前に対策できます。
侵入経路を塞ぐ
玄関や窓の隙間などゴキブリが侵入しやすい隙間を再度チェックし、侵入経路があれば防いでおきましょう。
毒餌剤を設置する
家具を運び込む前に室内のレイアウトを決めて、設置型の毒餌剤(ベイト剤)を仕掛けましょう。重いものを置いたあとだと陰になる部分に置きにくくなるので、先に設置するのがおすすめです。
毒餌剤を食べたゴキブリはその場で死なず、巣に帰って死ぬことが多いため、毒餌を食べたゴキブリの糞で仲間のゴキブリを巣ごと退治できます。小さいお子さんがいたりペットを飼っていたりする家庭では、誤食の恐れのあるホウ酸団子は避けましょう。忌避剤やハッカ油のようなアロマも有効ですが、それぞれ注意書きをよく読んで使用してください。
引越しが完了した後の対策
引越し後は、荷解きや収納など面倒な作業がたくさん。それでも最後まで手を抜かず、ゴキブリの出没しない部屋を目指しましょう。
段ボールは早めに処分する
引越しに用いられる段ボールは、ゴキブリの巣になる可能性があります。「何かに使えるかも」と保管しておきたい気持ちもわかりますが、早めに処分・回収してもらったほうがすっきりします。ゴキブリ対策と思えば、引越し後のお片付けもスピードアップするかもしれませんね。
部屋の掃除をこまめにおこなう
せっかくの新生活。事前に害虫対策もしているなら、クリーンな状態を保てるよう日々の掃除はこまめにおこないましょう。
毒餌剤を交換する
毒餌剤の有効期間は、およそ半年〜1年です。期限を確認しておき、時期が訪れたら新しいものに交換しましょう。半年か1年に一度、部屋の模様替えをすれば隅に溜まったホコリの掃除もできますし、毒餌剤も交換できて一石二鳥です。
ゴキブリが発生しにくい快適な暮らしを
ゴキブリが発生しにくい部屋は、明るくて風通しがよく、掃除が行き届いた快適な部屋です。この記事を参考に対策し、ゴキブリの出にくい住環境を作りましょう。これから引越しを考えているなら、できるだけゴキブリの出にくい物件選びや、引越し前後の対策などもぜひ参考にしてください。





