コウモリ対策の5ステップ!初心者にもできる駆除方法とおすすめグッズ

ただし、コウモリが家に住み着くようになると、フンの被害やニオイの問題などが起き、家が傷む原因や健康被害に発展することも心配されます。では「捕獲して駆除すればいいのでは?」と思われがちですが、コウモリの捕獲は法律によって禁止されているため、そう簡単には駆除できません。
そこで本記事では、コウモリが住み着いているか確認する方法や、一般家庭でもできるコウモリ対策をわかりやすくご紹介します。
記事の目次
コウモリが住み着いているサインとは?

コウモリが住み着いているサインは主に2つ。家の周りのフンと、夕方・夜間の活動音です。屋根裏や軒下、ベランダ、窓枠の近くなどにフンが落ちている場合は、コウモリが住み着いている可能性も。コウモリのフンは小さくて黒っぽく、ネズミのフンに似ていますが、乾燥すると崩れやすい特徴があります。
また夜になると「キーキー」「チチチ」と鳴き声がしたり、壁の中や屋根裏から小さな羽ばたき音がしたりする場合もあります。夕方頃に屋根の隙間や換気口からコウモリが飛び立つ姿を見かけることもあるでしょう。
では、どのようなコウモリが家に侵入して住み着いてしまうのでしょうか。家に住み着くコウモリの解説をします。
家に侵入するコウモリの種類は?
家に侵入するコウモリは、日本を含む東アジアに広く分布するアブラコウモリ(別名:イエコウモリ)です。市街地や森林、河川沿いなどさまざまな環境に適応し、人間の生活圏で比較的よく見られる種類です。
茶色っぽい体毛を持ち、体長は4〜6cm、翼を広げると20cmほど、体重も5~10gと小型です。夜行性で、日没後に活動を開始し、おもに蛾(ガ)や蚊、カゲロウ、小型甲虫や、街灯の周りに集まる虫を捕食します。
コウモリが好む場所は?
アブラコウモリは適度な湿度と温度があり、静かで暗い場所を好み、壁の隙間やひび割れ部分に住み着きます。また、外敵から身を守れて、安全な寝床になる屋根裏、物置や倉庫の天井部分などの高所も好まれやすく、コロニー(集団のねぐら)を形成することもあります。
コウモリの侵入経路は?
アブラコウモリは1~2cm程度の隙間でも通り抜けられます。そのため、通気口や換気口はもちろん、外壁のひび割れや屋根の隙間など、隙間があればどこからでも侵入してきます。
また、エアコンの室内機の周辺は温かいため、冬場に特に好まれるので、配管を通すための穴が十分に塞がれていない場合は、エアコンの配管周りからも侵入してくることもあるでしょう。
コウモリによる被害とは?
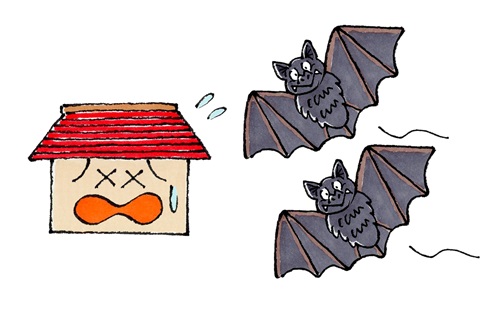
コウモリが住み着いてしまうと、次のような被害が問題になることがあります。詳しくみていきましょう。
糞尿による腐食・シミ
アブラコウモリが住み着くと、大量の糞尿が溜まり、強い悪臭と、ダニ、ノミ、ハエなどの害虫が発生することがあります。天井裏や壁、ベランダなどに付着した糞尿を長期間放置するとシミになり、腐食して建物の強度が低下することもあります。
騒音
アブラコウモリは夜行性のため、夜間に活動し、屋根裏や壁の隙間で「カサカサ」「チューチュー」と音を立てることがあります。コロニーを形成すると、鳴き声や羽音が騒音の原因になります。
噛みつかれることによるけが
アブラコウモリは基本的におとなしく、積極的に人を噛むことはありません。しかし、驚かせたり、素手で捕まえたりすると防御のために噛むことがあります。
コウモリの歯は小さいですが鋭く、皮膚を貫通してしまうことがあります。また、コウモリの口内には細菌が多く、傷口から細菌感染する可能性もあります。
日本ではほとんど報告されていませんが、コウモリは狂犬病やヒストプラズマ症(糞に含まれるカビが原因の肺感染症)などの病原体を媒介する可能性もあり、感染症のリスクも否定できません。
「鳥獣保護法」によりコウモリの捕獲は禁止されている

10種類以上のコウモリが環境省のレッドリストに記載されており、絶滅の危機に瀕している種も少なくありません。そのためアブラコウモリをはじめとするコウモリは、「鳥獣保護法」により無断で捕獲・殺処分することが禁止されています。コウモリの被害に悩まされた際には駆除以外の対策を取りましょう。次の章からは、コウモリ対策に有効な5つの手順をご紹介します。
コウモリ対策の手順│簡単5ステップ

コウモリは法律で捕獲や駆除ができないため、コウモリが家に侵入したら、追い出して再び戻ってこないように侵入を防ぐことで対処しましょう。
コウモリの巣を特定する
換気口や通気口、エアコンの配管周り、外壁のひび割れや壁の隙間などをチェックして、コウモリのフンが落ちていないか確認してください。一か所に大量に落ちていることが多くあります。屋根の隙間や軒下、天井裏などの高所を確認する場合は、落下しないように細心の注意を払いながら確認作業をおこないましょう。
コウモリを追い出す
巣が特定できたら、次は即効性のある忌避スプレー(忌避剤)を使って巣からコウモリを追い出します。巣にコウモリが取り残されていないか注意深く確認しましょう。
清掃・消毒をする
コウモリのフンには病原菌が含まれていることが多いため、健康被害にあわないように適切な掃除・消毒が重要。乾燥するとフンが粉々になって空気中に舞いやすくなるので、マスク・手袋を着用し、吸い込まないように気を付けましょう。フンを掃き取り、ビニール袋に密封して処分します。消毒用アルコールや次亜塩素酸水で拭き掃除をすれば、病原菌やダニの発生も防ぐことができます。
侵入場所を封鎖する
コウモリがいないことを確認できたら、侵入場所を塞ぎましょう。確実に隙間を塞がないと再び侵入される可能性があるので、パテやシーリング材で隙間を埋めたり、通気口は目の細かい防鳥ネットや金網で覆うのが効果的です。家の中や周辺の隙間もチェックして、コウモリに侵入されそうな隙間をなくしましょう。
再来していないかチェックする
コウモリの性質に、元の住処に戻ろうとする帰巣本能があるため、再来していないか確認することが重要です。コウモリのフンが落ちていないか、日没頃にコウモリが家から飛び立っていないかなどを確認しましょう。こまめにチェックをおこなえば、再来されても早めに対処できます。
コウモリ対策のおすすめグッズ
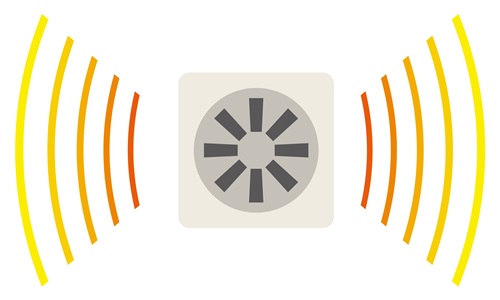
コウモリの被害を防ぐには、「追い出し」と「侵入防止」を上手に組み合わせることが重要です。ここからはそれぞれの具体的な対策方法をみていきましょう。
コウモリを追い出すためのグッズ
コウモリは、ハッカ、唐辛子エキス、ハーブ系成分、化学的な刺激臭などを嫌います。
コウモリが嫌う成分を配合した忌避剤も種類がいろいろあるため、状況に応じて使い分けましょう。
スプレータイプのコウモリ忌避剤
コウモリが嫌う成分を含んだスプレーを、コウモリが侵入している狭い場所に吹きかけて使います。スプレー式なので簡単に噴射でき、コウモリの追い出しに威力を発揮します。持続時間は短めなので、定期的な噴霧が必要です。
ジェルタイプのコウモリ忌避剤
コウモリの侵入や定着を防ぐジェル状の忌避剤です。揮発しにくく長時間効果が持続しやすく、雨や風にも比較的強いので、屋外でも使いやすいのが特徴です。
軒下、ベランダ、屋根の隙間などコウモリがよくとまる場所に適量を塗布すれば、コウモリが嫌がってとまりにくくなります。
燻製タイプのコウモリ忌避剤
屋根裏や倉庫などの閉鎖空間に煙で忌避成分を充満させ、コウモリにとって不快な環境を作って追い出します。短時間で広範囲に効果を発揮できます。
煙が拡散している間はコウモリを追い出せますが、根本的な侵入対策をしないとまた戻ってくる可能性があります。また、使用前に成分表示を読み、人やペットへの影響がないかや注意事項の確認も重要です。屋内の火災警報器にも注意しましょう。
錠剤タイプのコウモリ忌避剤
コウモリが嫌がる成分を含んだ固形の忌避剤で、コウモリが出入りする場所や、屋根裏、軒下、換気口周辺など巣を作りやすい場所に置きます。ニオイがかなり強めですが風通しのよい場所では成分が拡散しやすいため、効果を持続させるために1〜2カ月程度の頻度で定期的に交換が必要な場合もあります。スプレータイプに比べて持続性が高いですが、即効性が低いため、複数の方法と併用して使うとより効果的です。
超音波発生装置
コウモリは、エコーロケーション(反響定位)といわれる超音波を発してその反響を聴くことで周囲の環境や獲物の位置を把握する能力を持っています。超音波発生装置を設置しこれを妨害することで、コウモリが寄り付きにくくなるでしょう。
コウモリの侵入を防ぐためのグッズ
コウモリを追い出したあとは再侵入を防ぐため、住処を塞ぎましょう。侵入口や隙間を塞ぐのに、場所や状況に応じて適切な材料や方法を選びましょう。
パテ
パテは、配管の隙間やエアコンホースの周囲の隙間や穴を埋めるペースト状の充填剤(じゅうてんざい)です。隙間や穴の形状にあわせて埋められます。硬化後に適度な硬さを保ち、コウモリも簡単には壊せないので、隙間への侵入を防げます。
シーリング材
シーリング材は、外壁のひび割れや建築物の隙間、目地を埋めるために使用するペースト状の充填剤です。1~2cm幅程度の線状の隙間を埋めるのに適しています。パテよりも柔軟性があり、乾燥後も比較的伸縮するためひび割れしにくい性質があります。
ステンレス金網
コウモリ対策としてステンレス金網は非常に効果的です。ステンレス金網は耐久性が高く、錆びにくいため屋外や湿気の多い場所でも長期間使用可能。ステンレス金網はコウモリの小さな歯や爪では破れにくい強度があります。メッシュの大きさは5mm以下がおすすめです。
コウモリ対策に適した時期

春(4月~5月)または秋(9月~10月)は活動が活発で、巣の出入りが多いため、追い出しや侵入口の封鎖をしやすく、コウモリ対策に適しています。逆に冬眠中(11月~3月)は動きが鈍く、隙間に深く入り込んでいるため難しくなります。
また、夏(6月~8月)は繁殖期にあたるため、子どもがいる可能性が高くなるでしょう。せっかく対策をおこなっても子どもが巣の中に取り残されると、悪臭や害虫の原因になるため、避けたほうが無難です。
コウモリ対策の注意点

コウモリ対策をする際に注意したい点がいくつかあります。
1つ目は、適応能力が高いコウモリが、超音波発生装置の音にもすぐに慣れてしまう恐れがある点です。この場合、超音波発生装置の効果は一時的なものになる可能性があります。
また、市販の超音波装置の周波数がコウモリの生態と合っていないと、効果が出づらくなります。超音波の性質上、装置の設置場所によっては障害物の影響でコウモリに十分に届かないケースもあるでしょう。
2つ目は、磁石によるコウモリ対策。巣の近くに強力な磁石を置いて方向感覚を狂わせ、巣に戻れないようにする方法があるとされています。しかしこの対策の効果はまだまだ根拠が乏しい状態です。磁石による対策の前に、本記事でご紹介した効果的な対策を試すことをおすすめします。
自力でコウモリ対策が難しい場合はプロに相談する

コウモリは鳥獣保護法で保護されているので、自分でコウモリ対策をおこない捕獲や殺傷をしてしまった場合は法令違反となります。同法により、自治体でも基本的にコウモリ駆除ができません。
どこから侵入しているのか自分では探せない場合や高所での対策が必要な場合、自分では対策が難しそうだと不安を感じたら、専門の害獣駆除会社への相談がおすすめです。コウモリ駆除の見積りを無料でしてくれる会社もあるので、プロへの依頼も検討しましょう。
コウモリ対策のまとめ
先述したコウモリ対策の内容を、簡単にまとめてみました。
コウモリ対策の手順
落ちているフンから巣を特定し、忌避剤を使ってコウモリを追い出します。コウモリがいなくなったことを確認できたら、ステンレス製の金網などを使って再侵入経路を防ぎます。そのあとは、再びコウモリが戻ってきていないか、こまめにチェックしましょう。
コウモリ対策に適した時期
コウモリの活動が活発になる春(4月~5月)または秋(9月~10月)が適しています。巣の出入りが多いため、追い出しや侵入口の封鎖をするなどの対策がしやすくなります。
コウモリ対策の注意点
鳥獣保護法により、コウモリの捕獲や殺処分が禁止されています。自分でコウモリ対策をおこなう際には、コウモリを傷付けたりしないように注意しましょう。
アブラコウモリの生態はまだ解明されていない部分も多いですが、人を襲うことは少なく、おとなしい性格をしています。適切な距離を保てば、人間に害を与えることはほとんどありません。ただ、家に住処を作られそのまま放置してしまった場合は、騒音やフンによる被害が大きくなってしまうでしょう。放置せずにできるだけ早めの対策がおすすめです。




