準防火地域とは?防火地域との違いや調べ方もわかりやすく解説

記事の目次
防火地域・準防火地域とは
土地や住宅を探している際に、物件情報内の法令等制限の項目で「防火地域」「準防火地域」という記載を見かけることがあるのではないでしょうか。これらは、なかなか日常では聞きなれない言葉かもしれません。
防火地域・準防火地域とは、都市計画法において、火災が発生した場合の被害を最小限に食い止めるために指定される地域のことをいいます。そのため、防火地域や準防火地域に指定されている地域で家を建てる場合には制限があり、耐火性や延焼防止性の高い建物にする必要があるのです。
そこで本記事では、それぞれの地域に関する解説や調べ方、さまざまな条件下での家を建てる方法などを詳しくご紹介していきます。
防火地域と準防火地域の違い
先ほどご紹介したように、街づくりのルールを定める都市計画法には、住民の安全面に配慮した防火、防災による地域区分があります。火災の被害が起きやすく最も規制が厳しいエリアが防火地域として指定され、それを囲むように準防火地域が指定される傾向にあります。

まず、防火地域と準防火地域から、具体的にどのような違いがあるのか見ていきましょう。
防火地域とは?
防火地域は、火災の被害が起きやすく、火災を予防するために特に厳しい建築制限がかかる地域です。都市計画で指定されます。防火地域は建物の密集度が高く、また、火災の際に消防車・救急車などの緊急車両が通る主要な幹線道路沿いのエリアなどが指定され、都市の中心部であることが多い傾向にあります。
地域によってそれぞれの建築制限が設けられますが、防火地域はもっとも厳しい制限があり、基本的には地域内で木造建築物を建てることができません。詳しい建築上の制限については、後の章でご紹介します。
準防火地域とは?
準防火地域は、火災を予防するために厳しい建築制限がかかる地域です。防火地域と同様に都市計画で指定されます。住宅などの建物が集まり、防火地域を囲んだエリアが準防火地域に指定されます。
通常、準防火地域は防火地域の周辺(外側)の地域にあたるため、防火地域よりも建築制限は緩和されています。建物は規模に応じて防火措置を施し、延焼の抑制を図ります。
また、準防火地域では建築上の制限のほかに、屋根を不燃材料で造る、または不燃材料で葺く「屋根の不燃化」や、玄関や窓に防火戸などの防火設備を設ける「延焼の恐れのある開口部の防火措置」などの規制もあります。いずれも、建物が耐火構造や準耐火構造でない場合に適用されます。
その他の規制区域
以下では、防火地域・準防火地域のほかの規制区域についてご紹介します。
法22条区域とは?
法22条区域は正式には「建築基準法第22条指定区域」といい、防火地域・準防火地域以外の木造住宅が集まる地域が指定されます。名称のとおり建築基準法で指定される地域です。
制限がもっとも厳しい防火地域を囲む準防火地域、さらにその周りが法22条区域になることが多い傾向にあります。
建築上の制限も準防火地域より緩和され、屋根を不燃材料で造る、または不燃材料で葺くことが義務付けられた区域で、「屋根不燃区域」や「屋根不燃化区域」と呼ばれることもあります。また、この区域に指定された場合、外壁や軒裏についても特別な防火規制をクリアしなければなりません。
新たな防火規制区域とは?
木造住宅が密集する東京都には、「新たな防火規制区域(新防火地域・新防火区域)」の指定があります。
新たな防火規制区域は、東京都知事が指定する災害時の危険性が高い地域で、特に震災時に発生する火災などの危険性が高い区域が指定されます。
防火規制の度合いは、防火地域と準防火地域の中間程度です。原則、地域内のすべての建築物を準耐火建築物以上にしなければなりません。
以下から新たな防火規制区域が調べられるので、ぜひ参考にしてください。
参照:東京都 新たな防火規制の指定区域図
防火地域・準防火地域の調べ方
自分が住もうとしている地域が上記のような規制区域に該当するかどうか、事前に調べておきたいという方も少なくないでしょう。この章では、ご自身で防火地域・準防火地域、またはその他の規制区域を調べる方法についてご紹介します。
インターネットで検索して出てくる場合もありますが、都市計画は常に見直しがおこなわれており、検索結果が最新の情報かどうか定かではありません。そのため、以下のような方法で直接確認するとよいでしょう。
自治体の都市計画課に聞く
まずは、対象地を管轄する役所の都市計画課に聞いて確認する方法があります。この方法が一般的で、もっとも正確に調べることが可能です。
不動産会社は物件情報を取得する際に各自治体の都市計画課で確認しているため、基盤となっている調べ方ともいえます。場所を特定できるよう住宅地図を持っていくのがベストですが、難しい場合は住居表示や周辺の情報を把握して役所の方に伝えるとスムーズです。
なお、担当する課の名前は都市計画課以外にも「建築指導課」や「都市政策課」「まちづくり推進課」など、自治体によって異なる可能性があります。課の名前が分からない場合は、役所内のインフォメーションの方に聞くか、役所の代表電話番号にかけて用件を伝えて担当課へつないでもらうようにしましょう。
不動産会社に聞く
不動産会社やハウスメーカーの担当の方に聞いて確認するのも一つの方法です。すでに物件探しを始めていれば、担当の方に依頼して調べてもらうとよいでしょう。ご自身で役所へ出向いたり電話したりする手間も省け、スムーズな方法といえます。
防火地域や準防火地域に家を建てるには
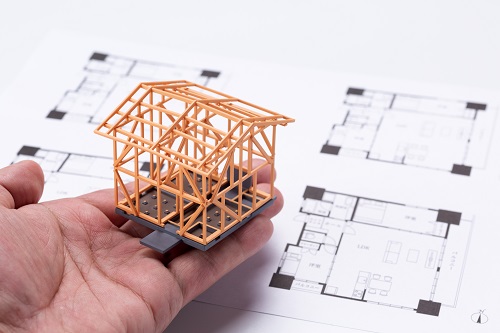
住むことを検討しているエリアが防火地域や準防火地域に該当する場合、その地域の規制に従って建築しなければなりません。
そこで、対象地域で家を建てる場合に知っておきたいポイントを以下で詳しく解説します。
防火地域や準防火地域の建物制限
防火地域・準防火地域、その他の規制区域に該当すると、建物の建築に関する制限があります。それぞれの地域の建物制限について、内容を確認しておきましょう。
防火地域の建築制限
防火地域に建物を建てる場合は、以下のような建築基準法で設けられた構造の制限があります。
| 階数 | 防火地域 | |
|---|---|---|
| 100㎡以下 | 100㎡超 | |
| 3階建て以上 | 耐火建築物等 | |
| 2階建て以下 | 準耐火建築物等 | 耐火建築物等 |
防火地域では、3階建て以上または延床面積100平方メートル超えの建物は耐火建築物に、それ以外の建物は準耐火建築物等にすることです。
耐火建築物とは、壁・柱・梁・床・屋根・階段など建築物の部分の構造のうち、耐火性能(火災が終了するまでの間、火災による建築物の倒壊および延焼防止のために建築物の部分に必要な性能)に関して一定の技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造やれんが造等の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる、あるいは国土交通大臣の認定を受けたもののことを指します。
また、準耐火建築物は、耐火建築物の「耐火性能」の部分が「準耐火性能(火災による延焼を抑制するために建築物の部分に必要な性能)」になったものをいいます。
準防火地域の建築制限
準防火地域に建物を建てる場合の構造の制限は、以下のとおりです。
| 階数 | 準防火地域 | ||
|---|---|---|---|
| 50㎡以下 | 500㎡超~1,500㎡以下 | 1,500㎡超 | |
| 4階建て以上 | 耐火建築物等 | 耐火建築物等 | |
| 3階建て | 準耐火建築物等 | ||
| 2階建て以下 | 防火構造の建築物等 | 準耐火建築物等 | |
準防火地域は、防火地域よりも制限が比較的緩めです。階数が高かったり延床面積が広かったりと、規模の大きい建物については耐火建築物にする必要があります。しかし、3階建てや木造の2階建てでも、一定の基準を満たせば建築可能です。
例えば2階建て以下かつ500平方メートル以下の建物の場合、防火構造であれば木造でも建築できます。
「防火構造の建築物等」とは、外壁または軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲で発生する火災による延焼を抑制するために外壁または軒裏に必要とされる性能)に関して一定の技術的基準に適合する鉄網モルタル塗りや漆喰塗りなどの構造をいいます。
国土交通大臣が定めた構造方法を用いて建築すること、または国土交通大臣の認定を受けた木造であること、そして同等以上の延焼防止性能が確保された建築物も含まれます。
法22条区域の建築制限
先ほどご紹介したように、法第22条区域とは屋根を不燃材料で造る、または不燃材料で葺くことが義務付けられた区域のことをいいます。屋根は火事の広がりを防ぐ重要な部分になっており、「屋根不燃区域」などとも呼ばれています。
また、建物が木造の場合は屋根以外にも、延焼の恐れがある外壁の部分を準防火性能がある構造にしなければなりません。
不燃材料とは、不燃性能(火災時における火熱により燃焼しない性能)に関して一定の技術的基準に適合する建築材料で、国土交通大臣が定めたものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいいます。
防火地域・準防火地域の建ぺい率緩和特例
都市計画区域内・準都市計画区域内では、用途地域によって建ぺい率や容積率の限度が決まっています。これらは、敷地に対してどのくらいの規模の建物が建てられるかが変わる、非常に重要な数値です。
建ぺい率は防火地域・準防火地域であることなど一定の要件を満たすことによって、指定建ぺい率に10%が加算される緩和措置がとられています。緩和特例が適用されるのは、延焼しにくい条件が整っているためです。
建ぺい率の緩和特例が適用される要件は、以下のとおりです。
- 防火地域内にある耐火建築物等
- 準防火地域内にある耐火建築物等または準耐火建築物等
その他、敷地が角地である場合にも適用され、また角地かつ上記2つの要件のうちいずれかが重なっている場合は、指定建ぺい率に20%が加算されるようになっています。
防火地域と準防火地域にまたがる場合
では、敷地が防火地域と準防火地域にまたがっている場合はどうなるのでしょうか。
2つの異なる規制区域にまたがっている場合、そのすべてにおいて規制の厳しいほうの規定が適用されます。そのため、防火地域と準防火地域にまたがっているのであれば、防火地域とみなして防火地域の規制内容に従わなければなりません。
そして、準防火地域とそれ以外の規制区域にまたがっている場合は、準防火地域とみなされます。ただし、異なる規制区域にまたがっているのは「建築物」のことであり、「敷地」がまたがっている場合ではない点に注意しましょう。
先述の建ぺい率緩和特例に関しては、建築物の敷地が防火地域とそれ以外にまたがっている場合、かつその敷地内の建築物すべてが耐火建築物等の場合は防火地域内にあるものとされ、建ぺい率の緩和が適用されます。
防火地域や準防火地域で木造住宅を建てるには
防火地域・準防火地域は、火災の危険を防除するために建築制限をしている地域です。そのため、この地域内で木造住宅を建てるのは難しいのではないかと考える方は少なくないでしょう。しかし、一定の基準を満たせば木造住宅の建築も可能です。
防火地域内で木造住宅を建てる場合は、2階建て以下で延床面積100平方メートル以下という制限が従来のものでした。しかし、現在は3階建て以上で100平方メートルを超えるものでも、耐火建築物の基準を満たせば建築できるようになっています。
準防火地域内の場合は3階建て以下で500平方メートル以下のもの、かつ外壁・軒裏など延焼の恐れのある部分が防火構造であれば、木造住宅の建築が可能です。
ただし、木造を耐火建築物とするには施工が難しく、通常の木造住宅よりも費用がかかりやすくなっています。そのため、施工前によく考えて決めるようにしましょう。
まとめ
防火地域や準防火地域、それ以外の規制区域など、それぞれの区域によって特徴や規制が異なります。このような規制があることによって、物件を探す際には、ただ住みたいエリアに建てたい家を建てられるというように簡単には進められません。しかし、建ぺい率が緩和されることなどその規制や特徴を活かして、こだわりの家を建てることも可能です。
住みたいエリアが決まっている場合には、防火地域や準防火地域であるからと希望の建物を諦めるのではなく、不動産会社やハウスメーカーなどに相談し最新の情報を得ながら、エリア内で希望の家を建てられるかどうか検討してみましょう。
物件を探す




