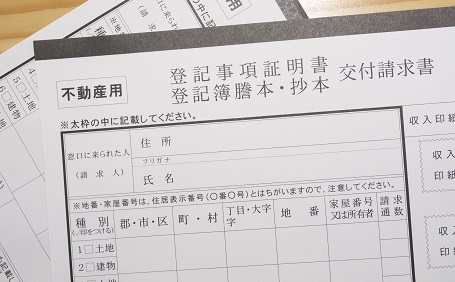地番とは?住所との違いや調べ方をわかりやすく解説

ちなみに地番も住所と同様に、土地の所在地を示すものに変わりはありません。ですが実際は地番と住所で同じ場所を表していても、情報の内容は異なっていることがあります。そこで今回は、地番と住所では具体的にどのような差があるのか、それぞれの違いについて詳しくご紹介。また地番を確認したい時に、知っておきたい調べ方なども解説していきます。
記事の目次
地番とは?

地番とは、登記情報として土地一筆ごとに設定されている区分番号を指します。例えばマイホームを買った場合、家を建てた敷地そのものに付与されるのが地番です。どこからどこまでが誰の所有地なのか、各敷地の区切りを明確にして管理する目的で設けられています。
なお地番が大きく関係しているのは、主に所有権と税金です。地番によって各土地の所有状況を明らかにすることで、敷地の授受や納税が適正におこなえる利点があります。このように地番は、各土地の権利に対してともなうもので、日本国内すべての土地に付けられているわけではありません。例えば国が所有している庁舎や皇居の敷地は、税金が発生しないため地番はない土地になっています。他にも登記がされていない土地なら、管理する必要がないため、地番は設定されていません。
ちなみに分譲マンションの場合、入居している所有者ごとに土地を持っているわけではないので、住民全員で地番は共有することになります。そのためマンションのような集合住宅では、住戸ごとに家屋番号を設定。登記上でも、この家屋番号によって所有状況が管理されています。
ここまでに出てきた地番や家屋番号は、相続などで「登記事項証明書を取得したい」場合に、申請に向けて必要な情報です。
地番と住所の違いは?

地番が敷地に割り当てられた番号である一方で、住所は建物自体に設定されている点が大きな違いです。
住所は、正しくは住居表示と呼ばれており、一定の基準によって市区町村が定めた登録情報を指します。ちなみに地番は登記上のデータなので、法務局が設定しています。
もともとは地番のほうが先に存在していて、古くの日本に住所という概念はありませんでした。当時は、例えば隣接する土地同士なら連番になっていて、場所の特定もしやすかった背景があります。そこでかつては地番=各建物の所在地情報となっており、地番をそのまま住所として扱っていました。しかし市街地の発達や土地の区分けの繰り返しにより、地番が複雑になってしまい、建物の所在地とも一致しづらい状況ができてしまいます。
そして郵便や訪問の際に、場所がわかりにくいなどの問題が生じたことから、1962年より住居表示法が施行。地番とは別に、新しく住所制度が導入されました。
そこから現在では、住所(住居表示)を各個人の所在地情報として使うのが一般的になっています。例えば宅配や郵送などの配達をはじめ、身分証明書の表示や、雇用・各種サービスといった契約など幅広く利用されるようになりました。
なお地番と住所(住居表示)では、次のように表示方法も異なります。
- 地番:町名(+字名)+番地(+枝番)(※1)
- 住所:町名(+字名)+街区符号(道路名称)+住居番号
【例】
- 地番:○○町二丁目1500番地(※1)
- 住所:○○町二丁目2番3号
(※1) 土地の分割がおこなわれた敷地では、番地のあとに枝番が付くケースがあります。
また住所(住居表示)は、政令指定都市をはじめとした、都市部を中心に利用されています。地域によっては、以前と同じように、地番を住所としているケースも。特に京都市では、歴史のある地名を残す意味もあり、住所は取り入れられていません。
| 種類 | 管轄 | 内容 |
|---|---|---|
| 地番 | 法務局 |
・土地ごとにつけられた番号
・土地の登記関係で利用する
|
| 住居表示 (住所) |
市区町村 |
・各住宅・施設など建物につけられた番号
・郵便配達などで利用する
|
本籍は地番と住所のどちらで登録する?
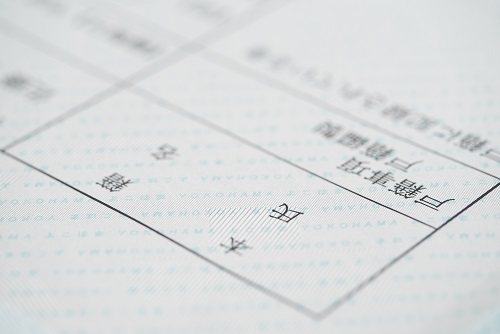
例えば入籍などで本籍地を登録する場合には、住居表示を実施している自治体であれば、地番と住所のどちらを使っても問題はありません。住居表示を実施していない自治体なら、そもそも住所がないため、地番で本籍を登録します。
ちなみに本籍地は、あくまで本籍がある土地を示す情報のため、住所を使うのであれば一般的には街区符号までしか登録できません。もし住所が「○○町二丁目2番3号」なら、語尾の「3号」は住居番号なので、本籍情報は「○○町二丁目2番」となります。マンションなどの集合住宅でも同様に、住居番号以降は本籍情報には表示されないため、通常の住所のように部屋番号まで記載する必要はありません。
なお地番で登録する際には、土地のみの所在地を示しているため、最後の「番地」まで記載します。
また住居表示については、自治体によって導入の時期には違いがあるため、本籍地を登録してから新たに住所が設定されるケースもあります。そうした場合には、本籍情報は引き続き地番が使われます。新しい住居表示の内容に変更することも可能ですが、いずれにしても本籍情報では、地番も住所もどちらでも使えるため、特別な手続きは必要ありません。
地番の調べ方は?

もし地番の情報が必要になった場合、調べ方にはいくつかの方法があります。
ここからは、地番を確認したい時の具体的な手順を見ていきましょう。
法務局に問い合わせる
不動産登記を管理している法務局へ、直接問い合わせをして調べるのが確実な方法です。地域ごとに、各エリアを管轄する法務局があるので、お住まいの市区町村が該当する分局まで電話をして確認します。なお各法務局の公式ホームページでは、登記関連全般の問い合わせ先だけでなく、地番照会専用の直通番号が設置されているケースもあります。まずは、お住まいの地域を管轄する法務局の公式ホームページをチェックし、連絡先を探してみてください。
地番参考図から確認する
地方自治体によっては、地番参考図と呼ばれる、固定資産税の税額の判断基準などに使われる情報を公開している場合があります。地番参考図では、住所をもとに、調べたい場所の地番を探せるようになっています。なお地番参考図は、基本的に各自治体の公式ホームページから利用できるシステムです。インターネットの検索エンジンにて、「お住まいの市区町村+地番参考図」のキーワードで調べてみると、すぐにアクセスできるようになっています。
ただし検索しても出てこない場合には、その自治体では地番参考図が公開されていないため、別の方法に切り替えましょう。
固定資産税納税通知書で調べる
固定資産税の納税通知書には、土地・建物の種類や課税区分など、詳細な不動産情報が記載されています。地番についても、通常は納税通知書の明細欄に載っているので、手元に保管している場合には確認してみましょう。なお固定資産税の納税通知書は、地域ごとに異なりますが、毎年4月~5月頃には自宅に届くのが一般的です。口座振替などで自動的に納税している場合でも、何かあった時に備えて、捨てずに保管しておくといいかもしれません。
登記識別情報や登記済証(権利証)で調べる
いずれも登記が完了した際に届く証明書となるもので、地番をはじめとした詳細な不動産情報が記録されています。なお法改正にともない、不動産登記をおこなった時期に応じて、登記識別情報か登記済証(権利証)のどちらが通知されているかは異なります。2005年3月7日以降に登記した場合には登記識別情報、それよりも前だった場合には登記済証(権利証)が交付されているので、確認してみてください。
登記情報提供サービスで調べる
登記識別情報サービスでは、オンライン上にて、法務局が保有する不動産のデータを閲覧できます。基本的に登記識別情報サービスは、登記簿内容を取得するためのシステムで、利用するには必ず会員登録が必要です。会員登録の方法は、一時利用・個人・法人・公的機関という4つの種類に分かれています。一時利用であれば無料ですが、それ以外は登録費用(個人なら300円)がかかります。さらに登記簿内容を請求するなど、各種サービスは原則有料です。
また登記識別情報サービスで地番を確認する際には、ログイン画面の「不動産請求」のメニュー内にある「地番検索サービス」を使います。一時利用の場合、会員登録をした当日中でないと「不動産請求」のメニューには入れなくなるので要注意。なお会員登録後の「地番検索サービス」に限っては無料です。
ブルーマップで調べる
ブルーマップとは、一般的な住宅地図上に、地番をはじめとした不動産データが記載された資料です。土地の所有者などは確認できませんが、地番や用途地域などのデータが青字で書かれていることから、ブルーマップと呼ばれています。よくある地図のなかに各種データが載っているため、大体の所在地や住所がわかれば、地番はすぐに調べられます。
ブルーマップは地図会社・ZENRINから出版されており、書店で購入もできますが、国立図書館や各地の中央図書館にて無料で閲覧もできます。また各地の法務局・登記出張所などでもブルーマップを置いているので、現地で確認も可能です。
この記事のおさらい

建物本体の位置情報を示す住所とは異なり、地番は特定の敷地の所在を表すものです。そのため実際の住所と地番では、詳細な内容が違っているケースがあります。なお不動産登記関連の手続きが必要な場合には、地番がわからないと申請ができないため要注意。住所だけでは、手続きができないので、地番を調べて準備しましょう。ちなみに地域によっては、住居表示制度を導入しておらず、地番がそのまま住所になっていることもあります。
また地番の調べ方には、いくつかの手段がありますが、やはり確実なのは法務局に電話で確認してみる方法です。その場ですぐに地番がわかりますし、お金も手間もかからないのでおすすめ。地番が必要になった際には、ぜひ参考にしてみてください。
Q:地番とはどのような情報?
A:地番とは、法務局によって定められた、各不動産が存在する土地の場所を示した情報です。不動産の権利状況や固定資産税の管理に向けて、法務局によって定められています。ちなみに特定の土地を複数の所有者で共有している、分譲マンションなどの集合住宅では、地番とは別に家屋番号が割り振られています。こうした地番と家屋番号により、不動産の所有権や税金の管理がおこなわれています。
Q:地番と住所に違いはある?
A:住所とは、各建物そのものの所在地を示した情報で、地番よりもあとに誕生した制度です。街の構造が複雑化したことから、土地の場所だけを表す地番に代わって、より位置情報をわかりやすくした住所が設定されました。地番は登記などの法律関係、住所は郵便や契約などの日常的な手続きに使用するイメージです。また地番は法務局、住所は市区町村で設定される違いもあります。なお住所は、住居表示制度を導入している地域でしか使われていません。なかには地番=住所になっている自治体もあります。
Q:地番を調べるにはどのような方法がある?
A:地番の調べ方としては、法務局に問い合わせをするのが一般的な方法です。もしくは自宅に固定資産税納税通知書や、登記に関する証明書があれば、地番が記載されているので確認できます。また地番参考図・登記情報提供サービスといったオンラインサービスや、ブルーマップを活用しても地番を調べられます。なおブルーマップは市販品を購入するか、または法務局などに備え付けられたものを閲覧して調べるのも可能です。
物件を探す