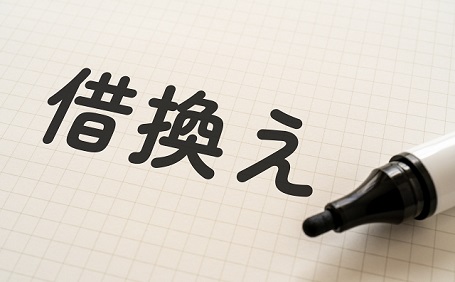リ・バース60のデメリットは?仕組みやメリット、活用例も合わせて解説

本記事では、リ・バース60の概要やメリット・デメリット、活用例を解説します。メリット・デメリットをよく理解し、選択肢の一つとして検討するのもいいでしょう。
記事の目次
リ・バース60とは?

リ・バース60とは、60歳以上の方が不動産を担保に資金を借りる住宅ローンです。ここでは、仕組みやよく似ている「リバースモーゲージ」との違いを解説します。
リ・バース60の概要
リ・バース60とは、住宅金融支援機構と金融機関が提携して提供している、満60歳以上の方を対象とした住宅ローンです。毎月の支払いは利息のみとなっています。元金は契約者が死亡した際に、担保物件を売却する、もしくは相続人の一括返済により完済します。一括返済した場合、契約者が亡くなったあとも、配偶者はそのまま住み続けることができるため、老後の住まいの心配が減ります。
リバースモーゲージとの違い
リ・バース60と似たような仕組みで、リバースモーゲージという商品があります。違いは何なのかを見ていきましょう。
| 項目 | リ・バース60 | リバースモーゲージ |
|---|---|---|
| 形態 | 住宅ローン | 不動産担保ローン |
| 資金使途 | 住宅に関するもの (建設・リフォーム・借り換えなど) |
原則自由 |
| 利息の支払い | 月払い | 月払い |
| ノンリコース型の有無 | あり | 取り扱っている金融機関が少ない場合がある |
| 地域 | 全国 | 特定のエリアに限定されている |
リ・バース60は住宅ローンのため、使い道は住宅の建設や購入、リフォームなど、住宅に関することに限られます。一方、リバースモーゲージは不動産を担保にしたローンのため、使い道は原則自由です。生活資金や趣味やレジャーなどにも使える場合が多いため、用途が幅広い点が魅力でしょう。ただし、金融機関によっても資金使途は異なるため、事前の確認が必要です。
他にも違う点はノンリコース型の有無が挙げられます。詳しくは後述しますが、ノンリコース型とは、契約者が亡くなった際、相続人が返済しなければならない債務をなくすものです。相続人に負担をかけたくないと考える方も多いでしょう。リバースモーゲージでは取り扱っている金融機関が限られていますが、リ・バース60では、取り扱っているすべての金融機関でノンリコース型を選択できます。
また、リバースモーゲージは地域が限定されているのに対し、リ・バース60は、全国で取り扱われています。お住まいの地域でどこの金融機関が取り扱っているか、住宅金融支援機構のホームページで確認できるため、チェックしてみましょう。
リ・バース60のメリット

本章で、リ・バース60のメリットを具体的に見ていきましょう。
高齢者でも借り入れができる
リ・バース60のメリットは、高齢者でも借り入れができる点です。住宅ローンは高額な借り入れになるため、安定して返済できることが条件となり、審査では年齢や収入などが確認されます。高齢のため返済期間が短くなったり、定年を迎え収入が減ってしまうことから、一般の住宅ローンでは不利になりやすいです。
しかし、リ・バース60は、満60歳以上を対象とした商品であり、年齢に上限はありません。また、住宅ローンを組む際には、通常、「団体信用生命保険」(以降、団信)の加入が求められます。団信とは、契約者が死亡、または高度障害になった場合、住宅ローンの残債を保障してくれるものです。加入する際には、健康状態を告知しなければなりませんが、リ・バース60では団信への加入は必須ではありません。そのため、加齢によって健康状態に不安がある方でも、借り入れできる可能性があります。
月々の返済負担が軽い
月々の返済負担が軽い点も、リ・バース60のメリットです。先述したように、元金は契約者が亡くなった際に返済する仕組みのため、月々の支払いは利息のみとなります。一般的な住宅ローンと比べ、支払い額は少ないことから、家計に占める割合も低く、経済的な負担は軽くなるでしょう。例えば、下記の事例の場合、毎月の支払い額は3.5万円となっています。
<自宅の老朽化にともなう住み替え>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 所要資金 | 2,800万円 |
| 借入額 | 2,100万円 |
| 自己資金 | 700万円 |
| 毎月支払額 | 3.5万円(金利が2.0%の場合) |
参照:住宅金融支援機構【リ・バース60】お申込み事例集(2023年度版)
担保評価額によっては、自己資金が必要になる場合があることも理解しておきましょう。実際の負担がどれくらいになるのか知りたい方は、取り扱いがある金融機関に問い合わせてみましょう。
ノンリコース型は相続人の負担が少ない
リ・バース60にはノンリコース型とリコース型の2つがあります。2つの大きな違いは、契約者が亡くなった時、相続人が残った債務(残債)を返済する必要性の有無です。契約者が亡くなった時、元金は相続人が一括返済する、もしくは担保物件を売却して返済します。もし担保物件の売却代金でも完済できなかった場合、ノンリコース型は相続人の方は残債を返済する必要がありません。一方、リコース型は相続人の方が残債を返済する必要があります。残債の返済についての不安や相続人の負担を解消できる点はメリットでしょう。
ただし、ノンリコース型の場合、残債分には一時所得が発生し、所得税が課税される可能性があります。詳しくは、税務署や税理士に相談しましょう。
不動産価値の下落するリスクが低い
不動産価値の下落リスクを抑えられる点もメリットです。リ・バース60では、申し込みの際に担保評価が一度だけおこなわれます。一方で、リバースモーゲージでは不動産を担保にしているため、不動産価値が下がると、その分返済を求められることもあります。その点、リ・バース60では一度だけのため、追加で返済を求められることはありません。返済額が増えることがないため、安心して利用できるでしょう。
リ・バース60のデメリット

リ・バース60はメリットばかりではありません。デメリットも理解したうえで、検討しましょう。それぞれ詳しくみていきます。
借り入れ限度額が低い
リ・バース60のデメリットは、借り入れ限度額が低い点です。限度額は担保評価額の50%または60%とされています。なお、担保となる住宅が長期優良住宅で、契約者が満60歳以上の時は「担保評価額の55%または65%」です。
一般的な住宅ローンの場合、頭金なしで、満額融資を受けることも可能です。しかし、リ・バース60では担保評価額の50%または60%となっているため、自己資金が必要となります。また、金融機関によって金額は異なりますが、手数料もかかるため、全体でかかる費用を事前にシミュレーションしておきましょう。
リコース型は相続人の負担が大きい
先述したように、リコース型は契約者が亡くなった際、相続人が元金の返済義務を負います。担保物件の売却代金で完済できれば問題ありませんが、完済できない可能性もあります。そのため、相続人の経済状況によっては、大きな負担となる可能性があるでしょう。なお、ノンリコース型では相続人の債務の義務がありませんが、適用金利が上がるため、利息が増え、月々の負担が増える点を理解しておきましょう。
金利上昇リスクがある
金利上昇リスクがある点も、リ・バース60のデメリットです。取り扱っている金融機関の多くが、変動金利のみとなっています。金利が低い時には返済額も少なく済みますが、高くなった時には返済額も増えるため、返済計画をしっかり立てましょう。現在、みずほ銀行が固定金利も取り扱っていますが、金利が高くなるため、よく検討しましょう。
長生きするほど支払い額が増える
繰り返しになりますが、リ・バース60は契約者が亡くなった際に、元金を一括返済するものです。契約者が生きている間の支払いは利息のみのため、長生きすれば、その分利息の支払いが増えてしまいます。また、前項で説明したように、ほとんどの金融機関は変動金利のみのため、金利が上昇すれば返済額がさらに増えることになります。リ・バース60のデメリットを理解したうえで、利用を検討しましょう。
リ・バース60の活用例

リ・バース60は住宅の建築やリフォームなどに利用できる住宅ローンです。本章では、具体的な活用例を見ていきましょう。
老朽化した自宅をリフォームする
リ・バース60は、老朽化した自宅のリフォーム費用を調達する方法として活用できます。住宅金融支援機構の「お申込み事例集(2023年度版)」によると、一戸建てのリフォームに活用した事例の特徴は下記のとおりです。
| 項目 | 割合・金額 | |
|---|---|---|
| 利用エリア | 首都圏 | 34% |
| 中国地方 | 16% | |
| 近畿地方 | 11% | |
| その他 | 39% | |
| 融資額の平均 | 549万円 | |
| 自己資金の平均 | 49万円 | |
| 毎月の支払い額の平均 | 1.2万円 | |
| 申込人の平均年収 | 291万円 | |
| 申込人の平均年齢 | 73歳 | |
| 申込人の業種 | 年金受給者 | 76% |
| 会社役員・会社員 | 14% | |
| その他 | 10% | |
報告書によると、契約者は70歳以上の方が半数以上で、年金受給者の割合も多くなっています。また、毎月の支払額も1.2万円と他の資金使途に比べて少ないのも特徴です。住み慣れた自宅を快適な空間にリフォームすることで、老後も安心・安全に生活できるでしょう。
新居へ住み替える
リ・バース60を利用して、バリアフリー設備の整った家やコンパクトな家など、希望にあった新居へ住み変えることができます。先ほども紹介した「お申込み事例集(2023年度版)」によると、新築・中古マンション、新築・中古一戸建てなどに住み替えるために、リ・バース60が活用されています。
| 項目 | 割合・金額 | |
|---|---|---|
| 利用エリア | 首都圏 | 23% |
| 北関東・甲信地方 | 17% | |
| 近畿地方 | 16% | |
| 東海地方 | 15% | |
| 融資額の平均 | 2,345万円 | |
| 自己資金の平均 | 1,718万円 | |
| 毎月の支払い額の平均 | 4.8万円 | |
| 申込人の平均年収 | 410万円 | |
| 申込人の平均年齢 | 68歳 | |
| 申込人の業種 | 年金受給者 | 41% |
| 会社役員・会社員 | 36% | |
| その他 | 23% | |
2022年度、戸建住宅の建設の申請件数は512件と、申請件数全体に占める割合は28.8%と約3分の1を占めており、もっとも多くなっています。
融資額の平均は2,000万円を超えていますが、毎月の支払額を見ると5万円を下回っており、一般的な住宅ローンと比較して支払額が低いことがよくわかります。60代で申し込む方が多く、定年を迎える頃に購入される方が多いようです。老後の快適な生活を実現するための選択肢の一つとして検討できるでしょう。
住宅ローンを借り換える
リ・バース60を利用して、既存の住宅ローンを借り換えることで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。住宅金融支援機構の「お申込み事例集(2023年度版)」によると、特に都市部での利用が多くなっています。
| 項目 | 割合・金額 | |
|---|---|---|
| 利用エリア | 首都圏 | 61% |
| 近畿地方 | 19% | |
| その他 | 20% | |
| 融資額の平均 | 956万円 | |
| 自己資金の平均 | 50万円 | |
| 毎月の支払い額の平均 | 2.7万円 | |
| 申込人の平均年収 | 393万円 | |
| 申込人の平均年齢 | 68歳 | |
| 申込人の業種 | 年金受給者 | 46% |
| 会社役員・会社員 | 40% | |
| その他 | 14% | |
定年を迎えると、収入源が限られてしまうと同時に、医療費や介護費など支出が増えていきます。そういったなかで、住宅ローンの負担を減らしたいと考える方が多いようです。ただし、借り換えには金利上昇のリスクがあり、手数料などの諸費用もかかります。これらのデメリットを理解したうえで利用するようにしましょう。
リ・バース60のよくある質問
リ・バース60に関してよくある質問をまとめました。
リ・バース60は相続人がいない場合どうなる?
相続人がいない場合、契約者が亡くなったあと、住宅金融支援機構が金融機関から債権を取得します。住宅金融支援機構は裁判所に対して、相続財産清算人の選任と担保物件の競売の申し立てをおこないます。そして、配当金をローンの残債に充てることになります。相続人がいなくても、申し込みできるかは金融機関によって異なるため、詳細は問い合わせてみましょう。
リ・バース60は新築でも利用できる?
リ・バース60は新築でも利用できます。住宅金融支援機構の「【リ・バース60】の利用実績等について(2023年10〜12月)」によると、資金使途の32%が注文住宅、18.1%が新築マンションとなっています。リ・バース60を利用する半分近くが新築物件の購入に利用されていることがわかります。
リ・バース60はやばい?
契約者が亡くなったあと、債務が相続人に引き継がれることから、「やばい」「怖い」といった口コミがあるようです。デメリットでも説明したように、リコース型を選択した場合、ローンの残債の返済を相続人がしなければなりません。しかし、ノンリコース型を選択すれば、相続人に返済義務はなくなります。ただし、金利が上乗せされるなど、契約者の負担が増えることになるため、事前に相続人とも相談しましょう。
まとめ
今回は、リ・バース60のデメリットをはじめ、メリットや活用例を解説しました。リ・バース60は、満60歳以上の方を対象にした、不動産を担保にして資金を借り入れる住宅ローンです。契約者が生きている間は利息を支払い、亡くなったあとは相続人が一括返済するか、不動産を売却して、元金を返済します。金利を上乗せしなければなりませんが、ノンリコース型を選択することで、相続人の返済債務をなくすことができます。
一方で、利用期間が長いと利息の支払いが増えるなどのデメリットもあります。よろこばしいはずの長生きが、デメリットにつながってしまうため、リ・バース60を利用するか、よく検討しましょう。
物件を探す

執筆者
民辻伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ