住宅ローン控除が終わったらどうなる?次に必要な対応を紹介

住宅ローン控除が終わったあとも返済を続ける場合は、控除期間が終わったらどうなるのか、不安に思う方もいることでしょう。また、住宅ローンの現行制度は2025年までのものであるため、制度の廃止・変更があった場合は、どのような影響があるのか心配になりますよね。
この記事では、住宅ローン控除が終わったらどうなるのかを解説し、次に必要な対応も紹介します。本記事を読むことで、住宅ローン控除を受けてから控除終了時までの疑問が解消され、安心して住宅ローン控除を利用できるようになります。
記事の目次
住宅ローン控除が終わったらどうなる?

住宅ローン控除が終わると、翌年から住宅ローン控除による税金の還付がなくなります。控除額は住宅ローンの年末残高の0.7%と決まっています。住宅ローンの返済状況によって控除額は変化するため、人によって影響は大きく異なるでしょう。
住宅ローン控除が終わったらどうなるのか、具体的な例を挙げながら解説します。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
税負担が増加する
住宅ローン控除の終了で増える税負担は、具体的にどれくらいの影響をおよぼすのでしょうか。住宅ローンの年末残高ごとに失われる控除額を0.7%の控除率で計算してまとめました。
| 住宅ローンの年末残高 | 控除額 |
|---|---|
| 1,000万円 | 7万円 |
| 2,000万円 | 14万円 |
| 3,000万円 | 21万円 |
| 4,000万円 | 28万円 |
| 5,000万円 | 35万円 |
控除が終わった最初の年度末の住宅ローン残高が大きいほど、控除額の影響が大きく、税負担が増加する計算になります。仮に35年の返済期間で住宅ローンを組んだ場合は、住宅ローンの控除期間が10年~13年であることから、控除を受けずに返済する期間は22年~25年です。
住宅ローン控除の終了時点で住宅ローン残高と返済期間が残っているほど、控除額の減少により実質的な税負担が増加するでしょう。
可処分所得の減少で家計が圧迫される
税金の控除額が減少すれば、所得にかかる税金が増えることから、自由に使える可処分所得が減少します。可処分所得が減少すれば、家計が圧迫されて生活に影響をおよぼすかもしれません。
住宅ローン控除終了のタイミングの残高が3,000万円であり、控除を限度額まで受けられる場合の控除額は21万円。住宅ローン控除は税額控除であるため、60万円の税金を納める必要があると仮定すれば、納める税金から控除額を差し引けます。具体的には、以下の納税額で済みます。
60万円(納税額)-21万円(住宅ローン控除)=39万円(最終的な納税額)
しかし、住宅ローン控除が終了すると税額控除を受けられなくなることから、控除を受けていた前年度と比較すると、税金の負担が重くなることが予測されます。住宅ローン控除は節税効果が大きい反面、控除期間終了前後では家計の状況が大きく変化する可能性があるでしょう。
住宅ローン控除はいつまでに終わる?
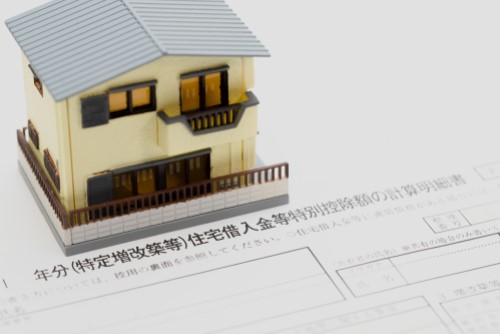
住宅ローン控除は人によって入居開始時期が異なることから、終わるタイミングも変化します。
住宅ローン控除はいつまでに終わるか、住宅の購入・入居時期から計算される年度を控除期間別に早見表にしました。
| 住宅の購入・ 入居時期 |
控除期間: 10年 |
控除期間: 13年 |
|---|---|---|
| 2015年 | 2024年 | ― |
| 2016年 | 2025年 | ― |
| 2017年 | 2026年 | ― |
| 2018年 | 2027年 | ― |
| 2019年1月~9月 | 2028年 | ― |
| 2019年10月~12月 | ― | 2031年 |
| 2020年 | ― | 2032年 |
| 2021年 | ― | 2033年 |
| 2022年 | 2031年 | 2034年 |
| 2023年 | 2032年 | 2035年 |
| 2024年 | 2033年 | 2036年 |
| 2025年 | 2034年 | 2037年 |
上記の早見表を確認すれば、ご自身の入居開始時期から控除期間が終わるタイミングがわかります。控除期間に違いがある理由がわからない方や、そもそも自身の控除期間がわからない方は、以下の補足も確認してください。
控除期間が10年になる場合
住宅ローンの控除期間は、2019年の税制改正以前では10年間となっていました。実際に控除期間が10年となる例は以下のとおりです。
- 2019年9月以前に入居した
- 2022年以降に中古住宅を購入・入居した
2019年9月まで住宅ローンの控除期間は10年であったこと、2022年以降に中古住宅を購入・入居した場合は控除期間が10年であることから、上記の条件を満たします。
控除期間が13年になる場合
住宅ローンの控除期間を10年から13年に延長するルールが登場した時期は、2019年10月以降であるため、それ以前の住宅の購入・入居では13年となる例は存在しません。控除期間が13年となる例は以下のとおりです。
- 2019年10月以降から2021年12月までに住宅へ入居している
- 2022年以降に新築住宅・買取再販住宅を購入・入居している
2019年は消費税率を8%から10%に引き上げた対応で、控除期間を2020年12月まで13年に延長。さらに、新型コロナウイルス感染症の特例で2021年12月まで、入居・購入期間が1年延長されました。
2022年の住宅ローン控除の改正によって、以降は新築住宅・買取再販住宅を購入・入居している場合に限り、控除期間が13年になりました。
ここまでの内容からご自身の住宅ローンの控除期間がわかるはずです。控除を受けた年がわからない場合は、住宅ローンを契約した金融機関に問い合わせましょう。
住宅ローン控除が終わったらどうすればいい?

住宅ローン控除が終わったらどうすればいいのか、具体的な対応方法を以下でそれぞれ詳しく解説します。
繰り上げ返済をする
繰り上げ返済は、通常の返済とは別にまとまったお金を返済することです。住宅ローン控除期間中の繰り上げ返済は、年末残高を減少させるため、基本的には推奨されません。しかし、住宅ローンの控除期間終了後の繰り上げ返済は、控除額を減らすデメリットがなくなり、利息負担を減らせるメリットがあります。
住宅ローン控除の終了後に返済負担を少しでも緩和するなら、余裕資金で繰り上げ返済を検討したいところです。また、繰り上げ返済には2つの種類が存在するため、それぞれの特徴を理解しておきましょう。
| 繰り上げ返済の種類 | 内容 |
|---|---|
| 期間短縮型 | 毎月の返済額はそのままに 返済期間を短縮する |
| 返済額軽減型 | 返済期間はそのままに 毎月の返済額を減少させる |
利息負担の減少効果が高く、最終的な返済額が減少するタイプは期間短縮型です。しかし、家計の負担を減らしたい場合は、毎月の返済額を減少させる返済額軽減型が有効な場合もあります。住宅ローン控除が終わると繰り上げ返済を実施しやすくなるため、無理のない範囲で検討しましょう。
借り換える
住宅ローンの控除期間は10年以上であることから、現在の時点で契約しているローンよりも、低い金利のローンが登場している可能性があります。借り換えで現在の住宅ローンよりも金利を安くできれば、毎月の返済負担も減ります。
ただし、借り換えには手数料、諸費用などのコストがかかるため、総合的に判断して借り換えをおこないましょう。手数料や諸費用で100万円かかると仮定して、メリットがある借り換えのパターンを以下にシミュレーションしました。
現在返済している金融機関の住宅ローン
- 住宅ローン残高:3,000万円
- 返済期間:25年
- 金利:2.0%
- 返済方法:元利均等返済
借り換え先の金融機関の住宅ローン
- 住宅ローン残高:3,000万円
- 返済期間:25年
- 金利:1.0%
- 返済方法:元利均等返済
| 借り換え前 | 借り換え後 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 毎月の返済額 | 12万7,156円 | 11万3,061円 | 1万4,095円 |
| 総返済額 | 3,814万6,800円 | 3,391万8,300円 | 422万 8,500円 |
| 利息分 | 814万6,800円 | 391万8,300円 |
手数料・諸費用の差し引きで期待される利息の軽減額
422万8,500円(借り換えで軽減される利息)
-100万円(手数料・諸費用)
=322万8,500円(最終的に節約される金額)
適切な借り換えをおこなうと毎月の返済額の負担が緩和され、住宅ローンの負担も大きく減少します。住宅ローン控除が終わるタイミングを機会に借り換えを検討してみましょう。
各種節税対策を検討する
住宅ローン控除の終了によって税負担が増加したのであれば、他の節税対策の実施によって税負担を軽減できる可能性があります。代表的な節税対策を以下にまとめました。
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- ふるさと納税
- 医療費控除
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、公的年金とは別に、自ら掛金を積み立てて作る私的年金です。掛金の全額が所得控除の対象であるため、節税しながら将来のための資産形成ができます。
ふるさと納税は、寄付金の一部が所得税・住民税から控除される制度。税金として支払う額を寄付金として支払うことから支出は変わりませんが、返礼品として地域の特産品を受け取れるため、受け取る品によっては家計の助けとなるでしょう。
医療費控除は、年間の医療費が一定の額を超えた場合に所得税・住民税が控除される制度です。家族全体の医療費を合算して申請できるため、医療費の領収書をすべて保管して確定申告します。
住宅ローン控除の終了によって失われた控除額は、他の節税制度を活用して少しでも補いましょう。
抵当権の抹消手続きをする
住宅ローン控除の終了と同時にローンを完済する計画を立てるなら、終わったあとの負担を気にする必要はありません。ただし、住宅ローンを完済した場合は、抵当権を抹消する必要があります。
抵当権は住宅ローンを提供する金融機関が融資の担保に設定する権利です。抵当権は自動的に抹消されません。ご自身で法務局に申請をおこなうか、司法書士などの専門家に依頼するようにしましょう。
住宅のメンテナンス費用を確保する
住宅ローンの控除期間終了時には、住宅の購入・入居から最低でも10年以上が経っています。10年が経過すれば、外壁・屋根の塗装、室内設備のメンテナンスが必要になりやすい時期に。目先の返済ばかりに目を向けていると、大規模な修繕が必要になる可能性があります。
定期的な点検・早めの対策により、大きな修繕費用がかかるリスクを減らせるため、住宅ローン控除の終了を機会に、住宅のメンテナンス費用も確保しておきましょう。
住宅ローン控除の制度自体が廃止されるとどうなる?

住宅ローンの控除期間の終わりではなく、制度自体の終了を心配している方もいるかもしれません。住宅ローン控除の終了には以下の疑問があると考えられます。
- いつまで制度の存続が確定しているのか?
- 既存の利用者に影響を与える可能性はあるか?
以上の疑問を踏まえて、住宅ローン控除の制度自体が廃止された場合にどうなるかを解説します。
2026年以降も制度が存続するかは確定していない
結論からいうと2026年以降も確実に制度が存続するかどうかは確定していません。2026年以降の住宅ローン控除は、例年どおりであれば2025年末に発表される税制改正大綱によって決定します。
住宅ローン控除の制度は2021年に終了する予定でしたが、税制改正により2025年に延長された歴史があります。現行の住宅ローン控除も、2025年12月31日までの入居を条件としていることから、2026年1月1日以降の住宅ローン控除の内容は誰にもわかりません。
万が一制度が廃止されれば、住宅を購入しても新たに住宅ローン控除を申請できなくなります。
廃止されない場合も条件が変化する可能性はある
住宅ローン控除が2026年以降も存続すると仮定しましょう。しかし、住宅ローン控除は数年ごとに見直されていることから、条件が変化する可能性があります。2022年度の税制改正では住宅ローンの控除率が1%から0.7%に減少しました。
利用者にとって有利な改正になる可能性はありますが、反対に不利な改正になる場合も。住宅ローン控除の制度内容は恒久的に保証されているわけではなく、時代に合わせて変化していることを理解しておきましょう。
既存の利用者の権利は確保されやすい
万が一、住宅ローン控除が廃止、もしくは制度内容が変更された場合、既存の利用者の権利は確保される傾向にあります。そのため、すでに住宅ローン控除を受けている方は、当初の適用条件通りに制度を利用できる可能性が高いです。
よって、すでに住宅ローン控除を利用している方が制度の終了によって権利を害されることは考えにくいため、控除期間の終了まで安心して控除を受けられるでしょう。
まとめ
住宅ローン控除が終わると、翌年度以降は控除による税金軽減がなくなるため、税負担が一気に増える可能性があります。控除期間中は住宅ローンの年末残高に応じて税額控除が適用されますが、控除が終了するとその恩恵は消えるため、可処分所得の減少や家計への影響が心配されるところです。
無理のない範囲の繰り上げ返済、金利の低いローンへの借り換え、iDeCo、ふるさと納税などの節税対策も活用して負担を減らしていきましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
長谷川 賢努
AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士
大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ









