離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法は?確認事項と注意点を解説

本記事では、離婚後も住宅ローンが残る家に住む方法と注意点を解説します。確認事項をもとに、離婚後の生活をスムーズにスタートさせましょう。
記事の目次
離婚後も住宅ローンが残る家に妻は住むことができる?

結論からいうと、離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住むことは可能です。しかし、住宅ローンの名義や返済義務を負う人などを決める必要があります。もし、妻がローンを引き継ぐ場合は、金融機関の審査が必要になり、収入などの条件を満たさなければなりません。妻が住み続ける場合は、トラブルを防ぐために事前にしっかりと話し合い、法的手続きをおこないましょう。
離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法

離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住み続けるためには、夫か妻のいずれかが住宅ローンの返済を続ける必要があります。住宅ローンの返済が滞る状態が続くと、強制退去となり持ち家が引き上げられてしまうため、夫婦間でよく話し合っておくことが重要です。では、離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住む方法を解説します。
夫が住宅ローンの返済を続ける
住宅ローンの契約者は夫のままで、妻が家に住み続けるケースです。ただし、口約束だけでは返済の継続が保証されないため、「公正証書」を作成し夫がローンの返済を続けることを正式に取り決めなくてはなりません。公正証書とは、公証人が当事者の依頼に基づいて作成する公文書のことです。証拠能力を保証するため、今後のトラブルを防ぐ役割があります。住宅ローン以外にも、固定資産税や維持費の分担なども事前に話し合いましょう。
住宅ローンの名義を妻に変更する
家の名義変更をおこない、妻が単独で返済を続けるケースです。名義変更には、住宅ローンを借り入れた金融機関の承諾が必要です。妻の返済能力が不安な場合は、承諾されないため注意しましょう。また、家が夫婦の共有名義の場合、夫婦の合計年収から融資額を決めているため、単独名義への変更が難しくなります。確実に進めるためには、金融機関と事前に相談し、準備を整えることが重要です。
住宅ローンの借り換えをする
借り換えとは、現在の住宅ローンをいったん完済し、新たに妻名義でローンを組み直す手続きのことです。借り換え先を妻名義にすれば、単独でローンの返済を続けられます。ただし、借り換えには金融機関の審査が必要で、妻の収入や信用情報が基準を満たさなければならないため、事前に確認が必要です。また、借り換えには手数料や税金が発生するため注意しましょう。
妻が夫に家賃を払う
夫が住宅ローンの返済を続ける代わりに、妻が毎月一定額の家賃を支払うケースです。家の名義や住宅ローンの契約者は夫のままとなり、妻は賃貸契約のような形で住み続けます。妻が借り換え審査に通らない可能性がある場合、有効な手段です。ただし、支払い条件や契約期間を明確にし、公正証書など書面で取り決めを残すことが重要です。
離婚前に持ち家について確認するべきこと

持ち家がある場合、離婚後の住まいや経済状況に大きく影響をおよぼすため、慎重に判断しなければなりません。
特に、離婚後に妻が住み続ける場合、ローンの返済方法や契約変更の可否など事前に確認すべきポイントが多いです。
では、離婚前に押さえておくべき確認事項を解説します。後悔しない選択をするために参考にしてください。
登記名義人の変更の必要性
登記名義人とは、法的にその不動産の所有者として登録されている人のことです。離婚後に家をどちらが所有するかによって、登記名義人の変更が必要なケースがあります。例えば、妻が家に住み続ける場合、夫の名義になっているとトラブルの原因になるため、妻に名義を変更することが望ましいです。
住宅ローンが残っている場合、金融機関の承認が必要であり、ローンの借り換えや返済方法の見直しが求められることもあるため、注意しましょう。
住宅ローンの残債
住宅ローンの残債とは、完済までに残っている金額のことです。妻が家に住み続けるか、売却するかを判断する際に重要な要素となります。残債が少ない場合は、一括返済する方法も有効です。金融機関の承諾や借り換えの手間が省けるため、スムーズに新しい生活を送れるでしょう。
もし売却を検討する場合は、売却価格が残債を上回るかを確認し、売却価格よりローン残債が多い状態にならないよう注意が必要です。
連帯保証人の確認
住宅ローンを組む際、夫婦のどちらかが連帯保証人になっているケースは注意が必要です。例えば、夫が住宅ローンの契約者で妻が連帯保証人になっている場合、妻に名義変更をする際は新たに保証人を立てなくてはなりません。連帯保証の解除や変更が必要な場合は金融機関に確認し、手続きをおこないましょう。
将来的な売却の可能性や相続時の手続き
離婚後に家を売却する可能性がある場合、住宅ローンの残債や市場価値を把握しましょう。売却益が出るのか、残債が売却価格を上回る状態になるのかを、事前に確認することが重要です。
売却しない場合、将来的に持ち家を相続する際の手続きも話し合いましょう。特に、子どもがいる場合はどのように相続を進めるか、明確にすることが望ましいです。
離婚後も住宅ローンが残る家に住む際の注意点

離婚後も住宅ローンが残る家に住み続ける場合、リスクや注意点があります。特に、ローンの返済負担が生活に影響をおよぼすと、強制退去や売却につながるため慎重に検討しましょう。では、離婚後に家に住む際の注意点を解説します。
公正証書を作成しておく
夫婦間の合意内容を公証役場で文書化しましょう。口約束では法的な拘束力がないため、公正証書を作成することでトラブルが起こった際に役立ちます。例えば、夫が住宅ローンの返済を続ける場合や、妻が一定額の家賃を支払う場合、条件を明確に記載することで、のちの支払いトラブルを回避できます。また、住宅ローンの返済が滞った際は、公正証書に基づき強制執行をおこなうことも可能です。
住宅ローンを滞納すると強制退去となる
住宅ローンは契約者が返済を続ける義務があります。返済が滞ると、金融機関が担保としている家が差し押さえとなり、競売にかけられてしまいます。
夫が契約者のまま住宅ローンを返済するケースでは、夫が返済を滞らせると妻も住み続けられないため注意しましょう。住宅ローンの返済状況を定期的に確認し、万が一に備えて毎月の返済額を積み立てましょう。
夫が家を売却する可能性がある
家の名義が夫のままになっていると、夫が勝手に家を売却することが可能です。よって、妻は住み続けられなくなるリスクがあります。夫が住宅ローンの返済を続けている場合、経済的な事情や再婚などの理由で家を手放す決断をする可能性も考えられるでしょう。妻が確実に住み続けるためには、家の名義を妻に変更したり、夫との間で「一定期間売却しない」旨を公正証書で取り決めるなど対策が必要です。
離婚後も夫と連絡を取り合う必要がある
夫が住宅ローンの返済を続けるケースでは、返済状況の確認や固定資産税の負担など、継続的なやり取りが発生します。よって、離婚の原因によっては精神的負担が生じる可能性があります。また、家のメンテナンスや将来的な売却の判断が必要になった際も、夫と協議する必要があるため、完全に関係を断つことは難しいでしょう。
離婚後も家に住み続けるメリット
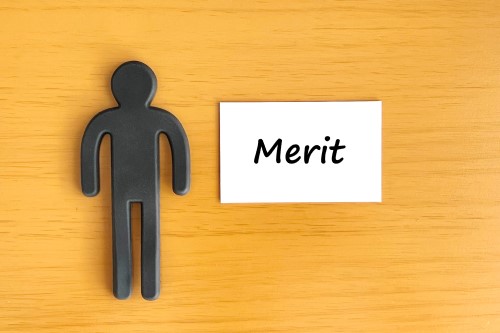
離婚後も家に住み続けることはデメリットばかりと感じるかもしれません。しかし、新たな住居探しや引越し費用などの負担を避けられるメリットもあります。
また、子どもがいる場合、環境の変化を最小限に抑えることができ、学校生活や近所付き合いなどの影響を減らせる点も魅力です。では、離婚後も家に住み続けるメリットを解説します。
生活環境を変える必要がない
現在の家に住み続ける場合、引越しをしなくて済むため、住み慣れた環境で新しい生活をスタートできます。通勤や日常の買い物などの生活リズムを変える必要がなく、離婚後の新しい生活にスムーズに適応しやすくなります。子どもにとっても学校生活や友人関係を維持できるため、離婚による精神的な負担を軽減できるでしょう。
経済的な負担を抑えられる
新たに賃貸物件を探す際、敷金・礼金、引越し費用、家具・家電の買い替えなど多くの初期費用が発生します。現在の家に住み続けることで、初期費用を抑えることができ、経済的な負担を軽減できます。住宅ローンの返済が今の家賃相場と比べて安い場合は、住み続けるほうがコストを抑えられる可能性が高いでしょう。
新生活の準備に余裕を持てる
離婚は精神的にも経済的にも大きな負担をともなうため、すぐに新しい住まいを見つけて引越しすることは難しいでしょう。現在の家に住み続けることで、住居探しや引越しの準備に追われることなく、仕事や子育てなど生活の基盤を安定させる時間を確保できます。精神的にも落ち着いた状態で次のステップを考えられる点は魅力です。
まとめ
離婚後も住宅ローンが残る家に妻が住み続ける場合、住宅ローンの名義変更や返済方法など、慎重に確認すべきポイントが多くあります。メリットやリスクを十分に理解し、トラブルを防ぐために公正証書を作成するなど、対策も欠かせません。本記事で紹介したポイントを参考にしながら、安心して新生活をスタートできるよう準備を進めましょう。
物件を探す
注文住宅を建てる

執筆者
民辻 伸也
宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。
株式会社クレア・ライフ・パートナーズ







